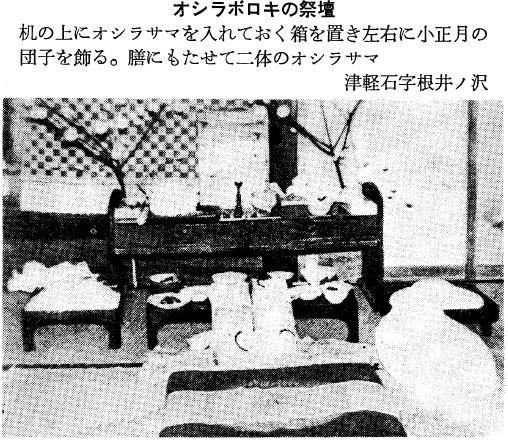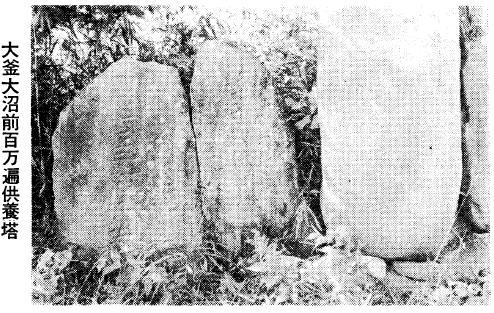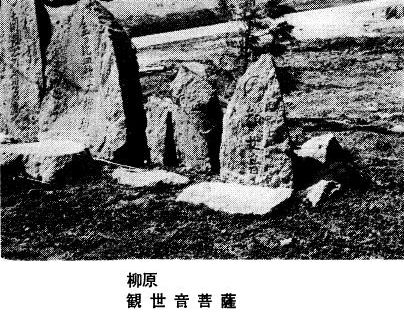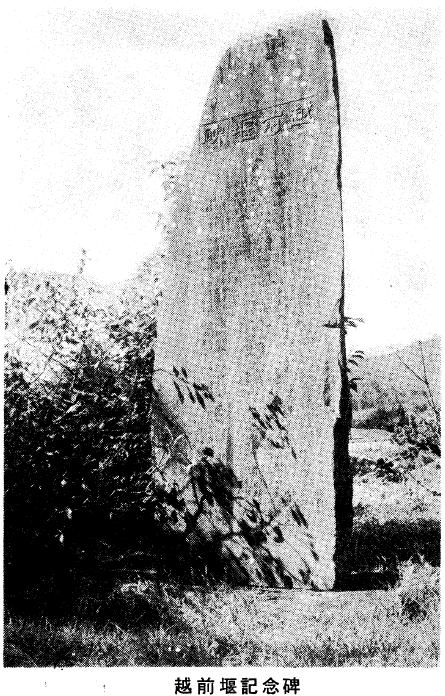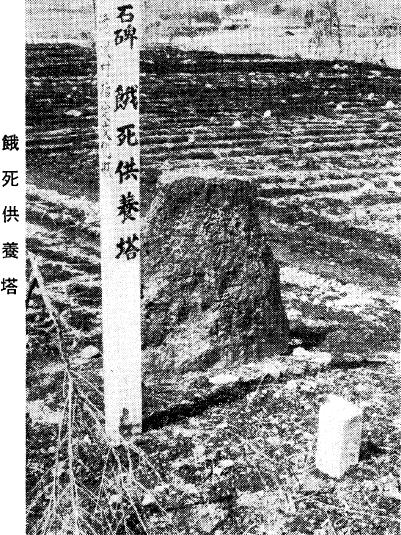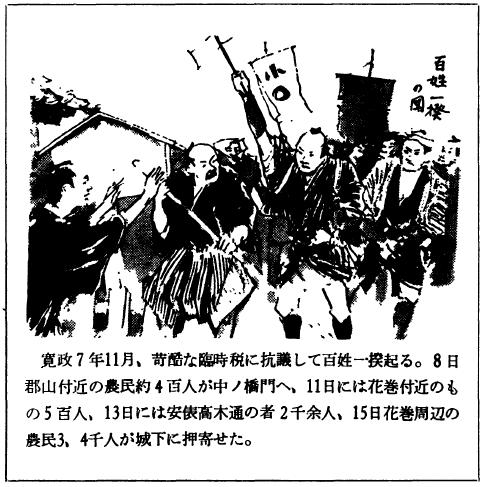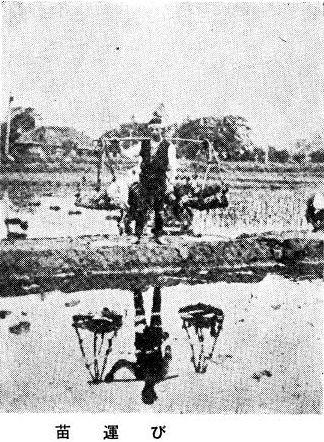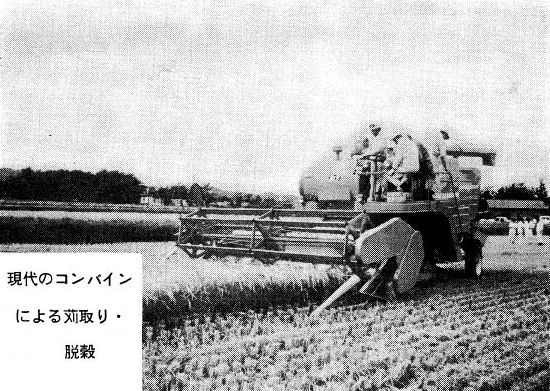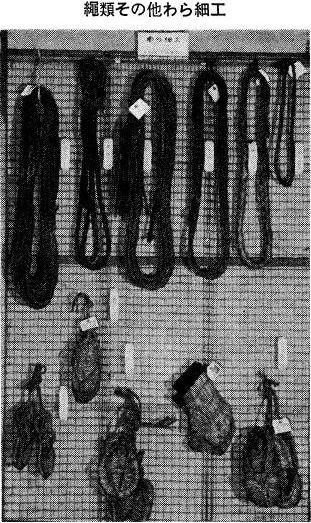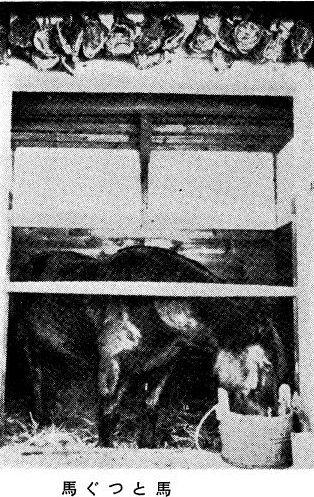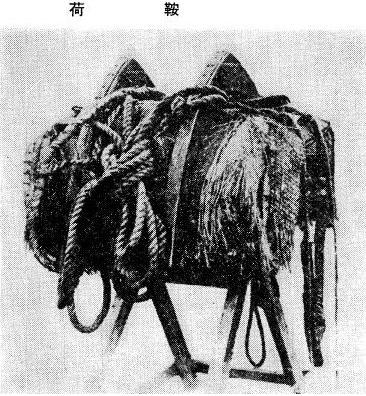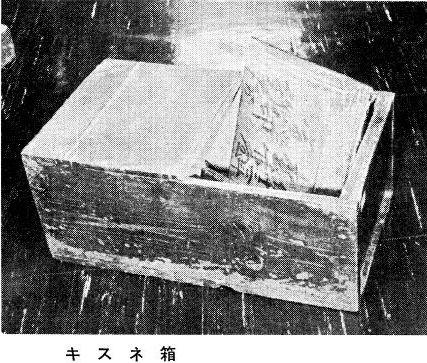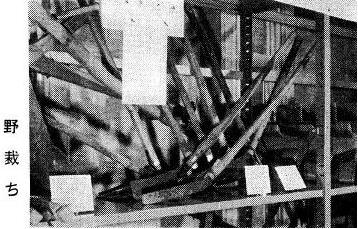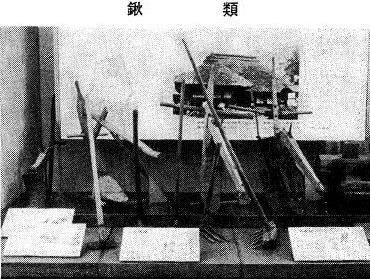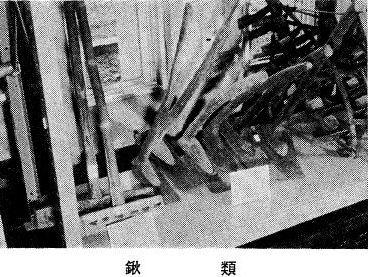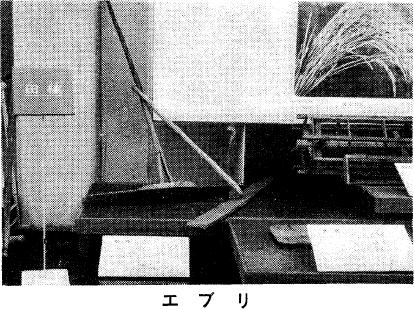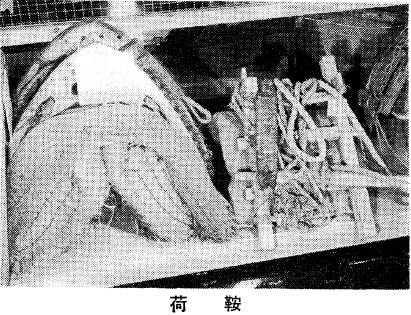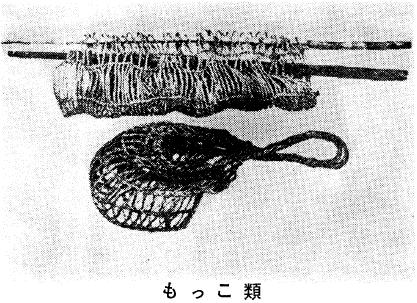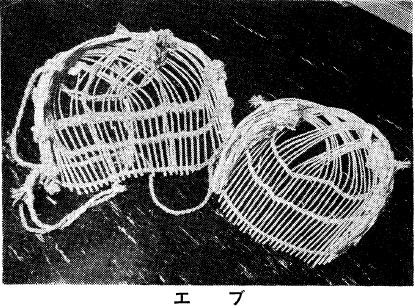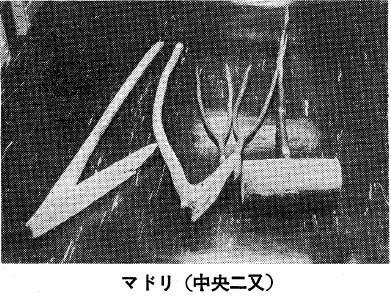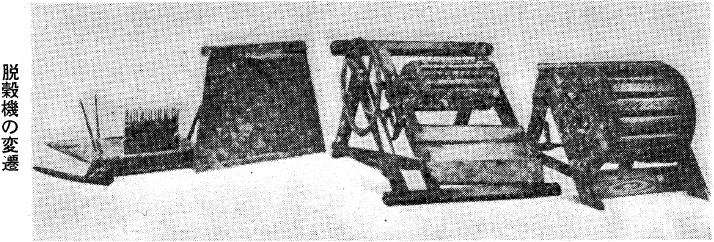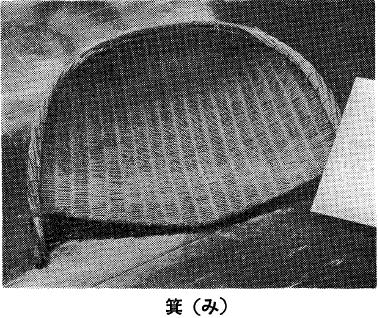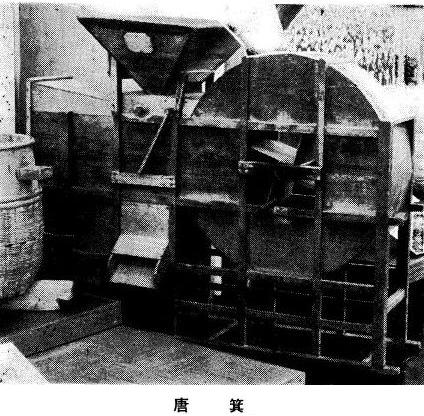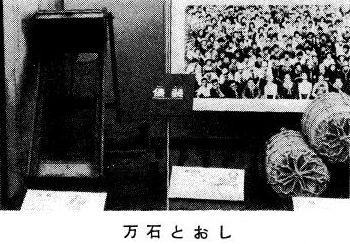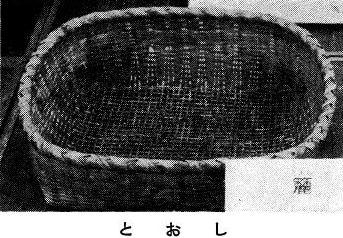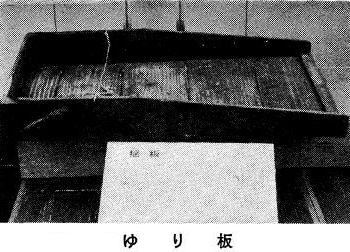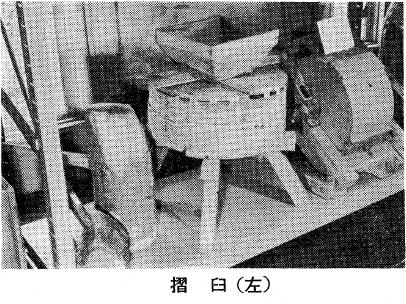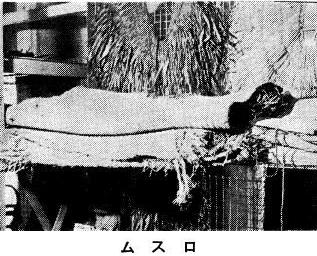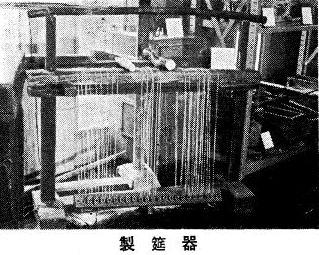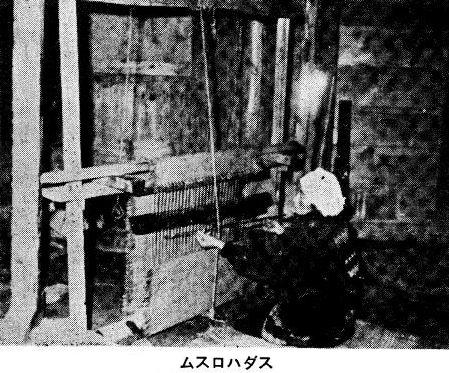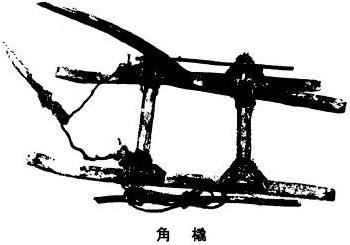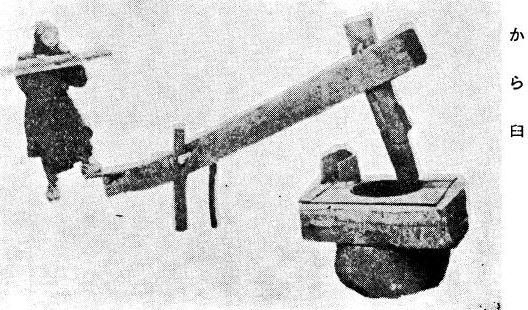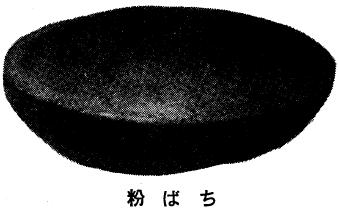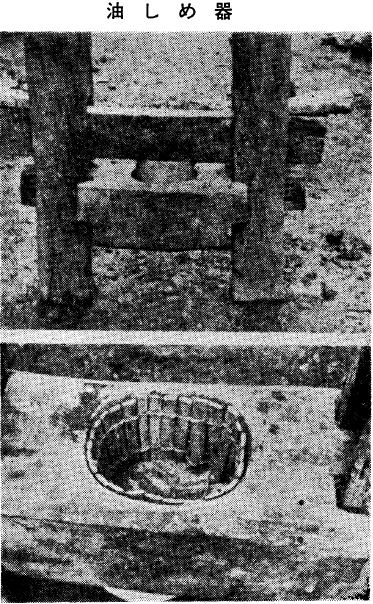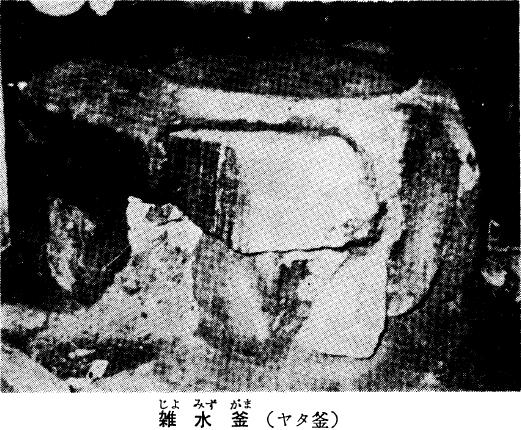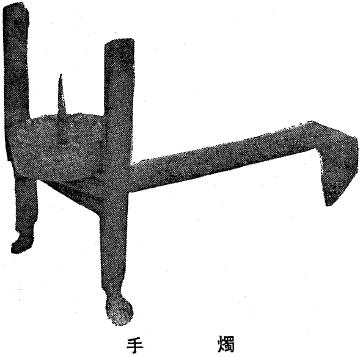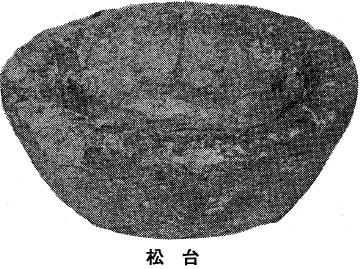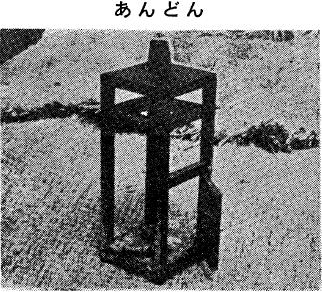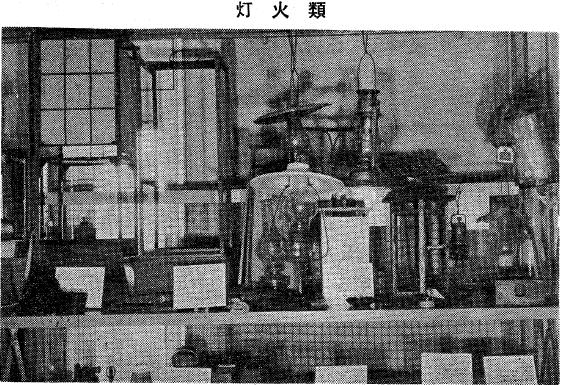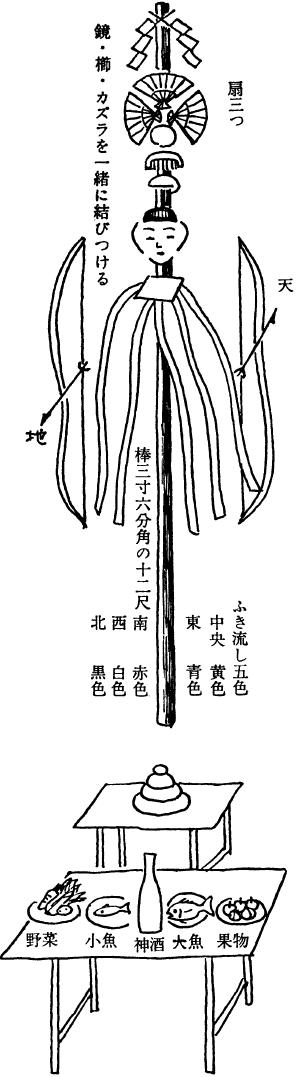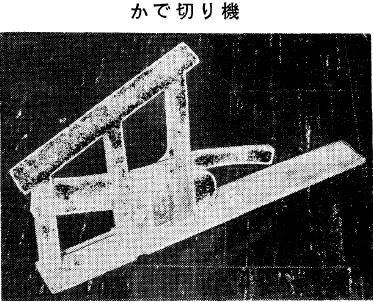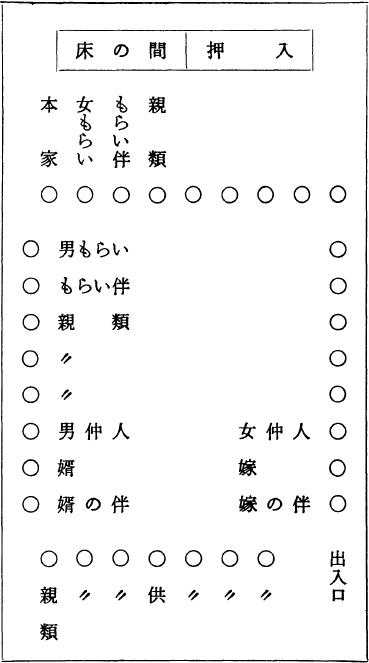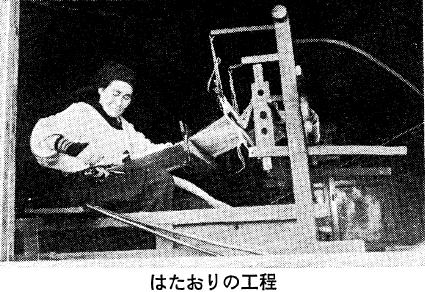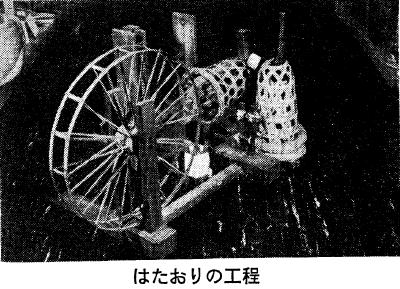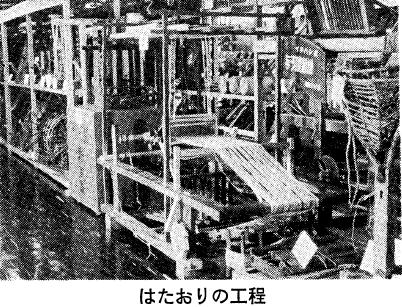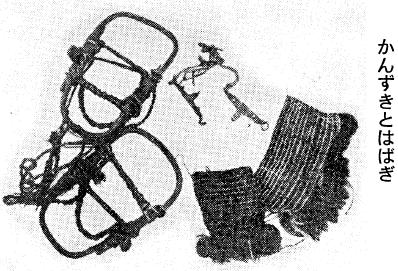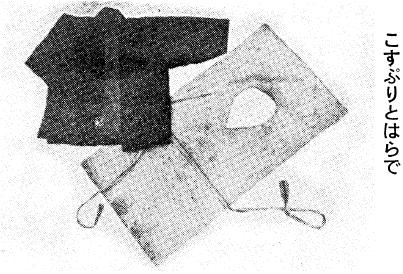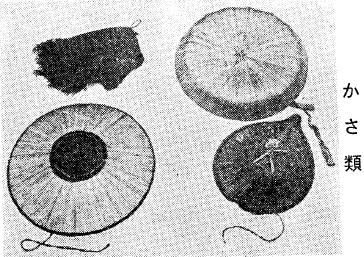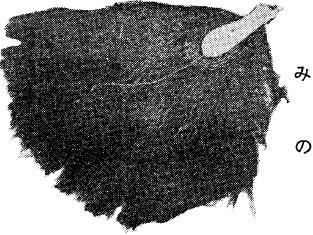第一節 信仰
一 伊勢参宮
学友沢内勇三氏の『お伊勢参り』から抜粋して述べれば、「参宮が組織化し、神都の性格が現れたのは、天正のころからであった。庶民の参詣が行われたのは鎌倉幕府が神馬幣帛を献じてからで、室町時代になると、京都を中心に参宮目的の信仰団体が生まれるようになった。これが“伊勢講”である。江戸時代になって参宮が流行し始めたのである。
参宮には季節がなく、年間を通して参詣する者が絶えない。
昔は旧二月から四月にかけての農閑期に“お伊勢参り”の幟を立てて馬の鈴音勇しく、幾組もの団体が列をなして参拝したのが江戸時代であった。
近代では太平洋戦争中、武運長久祈願のための参拝が盛んで、ことに、昭和十六年の皇紀二千六百年の元旦の大混雑は未曽有であった。
敗戦後、軍国主義、敬神思想の衰微から、参宮熱がうすれたが、最近、次第に国民感情が甦り、信仰と観光とで戦前に復活をして賑わいを見せている。
思えば、今昔を通じて日本人の心に不変に存在するふるさとはお伊勢さまなのだ」とある。
古代において、自分の家の屋敷神を信仰しても、天災地変や貢租や凶作や疫病等の苦脳から脱出が出来ず、氏神・郷神にお願いしても成就せず、これが岩手山・早池峯山を始め、遠方の有名な霊山・名刹・聖地をたずねることになり、伊勢・金毘羅参りとなったものであろう。これがいつとはなしに日本民族の血の中に流れて「人間一生に一度は伊勢に参るべし」と唯一の念願になったのであろう。
また、沢内氏は述べている。
町人・百姓の参宮旅装は、菅笠(三度笠)、雨合羽(引廻し)かゴザ、股引・脚絆に足袋で草鞋はき、手甲かけて着物の裾を尻端折っての軽快な和服、女は、小袖、打掛(浴衣)姿に菅笠、白紅の脚絆をつけ、結付草履という出立であった。長い旅路であるから、身廻品も細々と身につけたのである。
江戸時代、男は三尺手拭、頭巾・下帯・湯手拭・胴巻(大金入れ)、財布(中銭入れて首にかける)、小銭入れの巾着を腰に下げる。外に風呂敷、タバコ入、火打袋(マッチや懐中電灯の役)、弁当入、万金丹、磁石、矢立、髪結道具、道中記等、細々しい小道具を手行李(こうり)や風呂敷包にして、手拭で二つに荷を分けてつなぎ、肩にかけて歩くいわゆる振分け姿であった。
女は、巡礼姿をするものが多く、笈摺(おいずる)を背に菅笠をかぶった装束で、手甲、脚絆をつけ、白足袋に草鞋か草履はき、手に数珠、振鈴、杖など持って、ご詠歌を唱えながら旅を続けたものであった。
お伊勢参りの立振舞には銭別として金銭はもちろん、米・餅・豆腐・魚・菓子・野菜から日用品まで、親類が広いとその品物も数多かった。殊に、酒樽は昔二升五合入の十ぱい樽が多く使われ、次いで、一升樽も山に積まれた。
金銭は、今から百二十余年前の弘化のころで、村内六十軒から二百文、他村親類知人の七十軒から三百文、計五百文貰い受けたところがあり、立振舞のために一日が四人、二日が五人、三日が四人、五日が一人、六日が三人で延人員十七人で数日にわたって手伝いを要するほどの盛大さてあった。
明治三十一年の記録で、親類の多い富裕なある家の祝金の最低五銭が二戸、拾銭四十八戸、拾五銭五戸、弐拾銭四十八戸、参拾銭十五戸、四拾銭二戸、五拾銭十戸、六拾銭二戸、壱円が十戸で最高。当時一般の交際費は拾銭か弐拾銭が普通であった。その総額は何と参拾六円七十五銭の家もあった。
この立振舞は結婚式同様で、床の間に天照皇太神の掛軸を飾り、酒肴、餅を三方に供えて主人を正座に迎え、雄蝶雌蝶の酌により神酒を三三九度注いで門出を祝福し、同席の家族、親戚、知人等の酒盃を交わして道中の無事を祈り、留守を頼み、宴が終ると、一同庭に下り、用意された馬に参宮人をのせ、親戚の若者が馬方とし手綱をとって庭を三廻りした。この馬はチャグチャグ馬コの飾立てと同様であった。後「旅兄弟仲間祝」が行われた。
いよいよ出立の乗馬が馬首を南に向けると、見送りの黒山は騒然となり、馬に走り寄って挨拶をする者が続き、馬上の参宮人は一々これに応えて振り返り、群衆のどよめきが最高潮に達して盛大な見送りの光景が展開された。一行が遠のくまで手を振り大声で激励をした。見送り人もやがて退散する。
何十日後、一行が皆無事で帰宅出来るよう、村をあげてのお祭りさわぎは、参宮ならでは見られない昔ながらの行事で、村人の美しい心の交流が、お伊勢さまの信仰を通してなされたものであった。
このころは交通が不便であり、往来には辻斬り、追いはぎがしばしば現われた。出発するに当っては、未知の土地へのあこがれで心が踊りながらも、他面他郷における万一を思い、旅立つときには家族と水盃の宴を催し、切火を切って出発をした。そして、村人と、家族は村境まで見送りに行きその姿が見えるうちはのびあがり、立ち上がって見送った。従って一人や二人の旅は不可能であった。しかも旅人は、前述のごとく、食料や炊事道具を持参し、野に臥し、山に寝ることをいとわず、道端の草木を切りたおして一夜のイオリを設けてそこに眠り、自然の洞窟があればその中に入って眠ることもあった。旅行中病気にかかることもあり(後述)、そんなときの難儀は誠に痛々しい位であった。そこで旅人は道中の安全祈念のため、辻や峠に道祖神を祭り、そこを通過する旅人は手にした柴枝を折り道端に棄てて道中難をさけようと祈ったり、また餓鬼共がその辺をうろずくから、その餓鬼共への布施の意味で、持っている飯を与えてもいる。
ところが藩から文久二年(1862年)十月のような達しが度々出されている。「御領分内の御百姓共、伊勢参宮をする者は、前々から農業に差支えないようにといっていたのであるが、近年に至り数十人にのぼっている。数多の中には参詣して被いが終ると、見物同様国廻りをし、年を越して帰郷する者もあるやに聞いているが、以っての外のことである。つまりこれは代官の吟味等閑によるのであるが甚だ勝手な事で宜しくない。以後一官所より五人宛参宮致させ、先年御沙汰の通り、三月より九月迄は控えるようにし、十月より翌年春二月迄の間に往来するように致せ。此度の御沙汰があった上はよくよく心得て今後一ヶ村宛相改めるから、心得違いのないように強く達しをしておく」とある。このように、純なる農民の信仰心をはばんでいたのであった。
本村における石塔を調査したところ、他国を旅行した記念碑と思われるものを部落別に列記すれば、次の通りである。
大釜、西国三十三所観世音(明治十五年)・古峯神社(昭和四年)・西国三十三番供養(文政六年)。
棟木、冨士浅間大神・湯殿山。
大沢、湯殿山・古峯神社(昭和三年)・西国三拾三所。
谷地上、湯殿山(明治三十五年)。
鵜飼、湯殿山(明治十六年)・湯殿三山(大正八年)・善光寺如来(昭和三年)・湯殿三山。
滝沢、金毘羅山(文政二年)・湯殿三山(明治十九年)。
一本木、金毘羅大権現(明治二十三年)・十八西観音(大正十三年)・三峯山神社。
以上の石塔から、西国三十三所の観世音のみをひろってみれば、三基ある。西国三十三所めぐりの最初は、伊勢神宮を参拝した後、第一番は那智、第二番は紀の国の三井寺、第三番は粉河寺……を廻るようになっていた。従って、伊勢神宮参拝後に西国三十三所を礼拝したものと思われる。なお金毘羅山の石塔が二基あるから、途中伊勢参宮をしたであろう。後述の通り、伊勢参宮をした記録が残されているから、伊勢の神官のみを対象とした石塔がなくとも、伊勢神宮を参拝したことは明らかである。参拝した一行が、帰村すると脛巾脱ぎをなし、再び金品が届けられ、盛大に行われたのであった。その後、参加者は期日を選んで集まり、遥拝をして当時を偲んだのであった。
大字大沢の屋号長坪と称する大坪家に伝わる文書中に、第二十代清吉は正徳六年(1716年)二月三日に高野山へ姑供養、第二十一代長四郎は享保二十年(1735年)三月十六日同じく高野山へ妻供養、第二十二代半助は明和二年(1765年)一月七日同じく高野山へ父母供養、第二十五代三五郎は文政十二年(1829年)一月に伊勢参宮、第二十六代春松は嘉永元年(1848年)九~十月東北・関東・中部・近畿の神社・仏閣を拝礼したことが記録され、同家に保存されている。
約百三十年間に、五代が供養のため命がけで参拝をしている。
また、大森弥三郎氏は、寛政十年(1798年)ころ、大森弥蔵と駿河長松、三上長右ェ門の三人が、伊勢・金毘羅を百余日かゝって参拝したといっている。その外年代が不明なるも、元村の大坊守衛、鵜飼の工藤伝七、篠木の堰口の三人も伊勢参宮している。この三人をお上り兄弟と称していた。
天明三年(一七八三年)正月二十六日の『南部城事務日記』に病死のことが記述してある。
厨川通御代官所の内滝沢村肝煎与兵ェ子三之亟と申す者伊勢参宮とて旧冬十一月九日出立罷り登り候処善光寺辺より庖瘡相煩ひ旧猟十六日信州佐久郡小諸(こもろ)牧野遠江守様御城下迄罷り越し候処遠江守様にて薬用等仰せ付けられ候へ共病症差し重り同二十一日病死致し候に付き同所浄土宗詫応寺地内に仮埋葬致しおかせ候間人元并に親類共罷り越し見届け尤も三之亟持道具等もこれあり候間相渡させ申し度き旨遠江守様御留主居より此方御留主居迄申し来り候旨江戸より御用状をもって申し来り御役人共へこれを申し渡す。
吟味遂げさせ候処与兵ェ子三之亟持参致す物に相違これなき旨申し出候近国にもこれあり候はば人元并に親類の内見届けさせ差し登らせ始末仕らせべく候処不案内其上困窮の者にて遠路罷り登り候儀相及び難きに付き前例もこれあり候間アナタ御留主居へ此方御留主居より掛け合い何分にも御取置下され候様申し談じ世話仕り候者へ御目録遣され候様仕り度き旨御役人共申出右の趣江戸へ二十六日附御用状をもってこれを遣す。
但し遠江守御留主居槙造酒(みき)右ェ門へ此方御留主居加島判左ェ門より前文の趣を以て掛け合い済、三之亟法号井に諸始末書帳面等御役人共へ差し下し尤もこれある類これあり候共道中御奉行へ御届これあり候得共此度は遠江守様にて御届これなく候に付き此方様にても御届これなく相済し候段判左ェ門申し出て候旨六月二十四日付御用状を申し来り御役人共へこれを申し渡す。
大字大釜田沼清氏宅に道中記が十一冊保存されてある。
それは、田沼清氏の四代前の善助氏、三代前の善蔵氏、二代前の市太郎氏、親子三代にわたって伊勢参宮をなし、詳細に記録されている。
すなわち、嘉永二年(1849年)二月二十三日、田沼善助氏が仙台大町二丁目吉田屋から書きおろし、小保内・橋場を経由して日向首での里程を主として記録した『伊勢参宮道中記』がある。
末尾に武田千松、田沼栄蔵、同善助、同惣吉、吉清水竹松、仁佐瀬佐吉、武田丑太郎しめて同行七人。伊勢・熊野・金毘羅等各神社を参拝終了し、二月十六日より五月五日帰宅と記されてある。
次の善蔵氏は明治七年十一月十五日付『道中控帳』を残している。
それによれば、盛岡より書出し、前記同様次の宿までの里程を主としてはいるが、前記と相達し、印象づけられた個所を詳細に記述されてある。
帰路は前記に相達して南畑より仁佐瀬を経由し三月七日に帰宅していて、同行者は一行五名とある。
さらに『道中小遣覚帳』として別冊にし詳細記載され三月七日までに惣〆三百六十三文とある。
伊勢参宮ではないが、明治二十六年善蔵氏妻ヤエ氏が善光寺参りをした道中記がある。
それは盛岡を旧八月十五日汽車を利用し、東京上野までの切符一人について二円六十銭宛とある。
道中全部列車を利用して、同月二十四日午後一時に盛岡駅に到着し、茅町の通称一の長沢長次郎商店で「はばきぬぎ」をして解散している。
一行は女性中心で八人と記載され、道中記の末尾に田沼善蔵氏が当時の村長宛に次掲の旅行届を提出している。
旅行届
岩手県岩手郡滝沢村大字大釜八拾壱番地 平民
田沼善蔵 妻
ヤエ
天保十四年五月十一日生
上の者今般下野国日光山東照権現様并に信濃国善光寺様参詣の為本月二十四日出立旅行致し候也
明治二十六年九月二十二日
上戸主 田沼善蔵 印
村長亀森影徳殿
市太郎氏は明治三十四年新十二月二十六日(旧十二月十六日)より翌年旧二月七日までの八十一日間、伊勢の国天照大神宮及び讃岐国金毘羅神社参拝の為出立、同行五人と記載後、ことこまかに道中記が縦十二㎝、横十五㎝の和紙綴裏表二百十三枚余にわたって記述されてある。
なお、宿泊料、汽車賃、その他の費用、八十一日間のかかり七十一円七銭。外に表具代一円十五銭とある。
以下参宮のみを掲載することにした。
一月二十一日、七時四十分。愛知発の汽車。伊勢山田まで金壱円三十一銭づつで購入して拝み、宇治山田町に六時十分つき、泉舘太夫様に宿泊。国元を出立してから二十七日目なり。
一金弐円を出す。一金七拾銭御玉串七拾枚代。一金拾銭寄附と灯明代。また太夫様より御土産として、天照大神の掛軸と御守札を頂戴したり。
二十二日天気上々。九時出発し、五十鈴川にかかる宇治橋を渡る。右に、明治二十八年二月に我軍大山巌が支那よりブンドリせる大砲長さ五間、次に皇太子殿下御手植の松あり。
天保四年(1833年)三月の擬宝珠十本の橋へ。五十鈴川にて清め、それより鳥居くぐるなり。代々神楽殿あり。籾種石あり。明治三十四年十月、本社建立。左に米蔵と金庫あり。裏御門荒馬取神社大蛇身体池ありて、ここで代々神楽のとき身を清める。五十鈴川橋二十四間あり。御伊勢棟に二百二十五町廻りあるという。朝熊岳(海抜千五百尺)へ登る。七十二町あり。十時半に鳥居松まで登り、六十町。前に石燈篭二つ、嘉永六年とあり。石段三十登りて、摩尼殿本地虚空蔵等なり。五重の塔あり。朱塗なり。金銅の塔四つあり。石段三十登る。石に御釈迦様の足跡あり。池に鯉いたり。橋あり。鐘ある。
伊勢国朝熊岳勝峯会金剛証禅寺本社より十町戻りて茶屋にて昼飯致し、茶代金壱銭づつ出し、十二時十分参詣終り、それより下ること二十二町。内三十町目より橋渡りて、また、五十八町行きて、二見猿田彦大神を参詣二時半。参詣終り。太夫様迄百拾六町の処、近道を安行して午後五時帰宅。二晩御世話を蒙り、御酒を二回頂戴。
二十三日八時出立。太夫様より、若者昼飯を持って、外宮まで見送り下さる。度会(わたらい)の神社詣終る。
ここで、伊勢の大神宮様のことについて簡単にふれるとして、
人皇第十代崇神天皇御即位六年までは、神武天皇より五百六十五年の間、天子の御殿に天照大神を始め、大国魂等の諸神を祭り給えるも、次第に世くだりて、天子とても御行状も行届かせられがたく、帝神慮を伺い奉れば、大神宮の御告げに、不浄の人間と同席する事我嫌うなり。この故に大和国笠縫の里に別殿を建立し結いても猶神慮隠かならず、八十四年間諸国処々に遷宮し給い、その後、丹後の国へ御移り給い、二十九か所目人皇第十一代垂仁天皇二十五年の冬十一月伊勢の国度会郡今の宇治の内容に鎮座ましましけり。即ち、五十鈴川へ移し奉る。万乗の天子様におかせなられてさえ不浄を恐れ給いて、神の御座所を別殿へ移し奉る。この故に神の御座所をヤシロという。これによって、伊勢の太夫藤原の相通(しげとう)という者の妻女、自分の部屋へ大神宮を密に安置し、信心致せし処、後に霹顕に及び太夫相通は伊豆の国へ流罪となり、妻は隠岐の国へ流罪となりたる事は、人皇第六十八代後一条院の御字長元四年八月五日の事なり。伊勢の太夫すらかくの如し。況や在俗においておや。これ迄平人常人は、伊勢参りという事はなさざる処、後一条院の御字より始め、抜(ぬけ)参りという事を御免なしおかる。
御遷宮については、天武天皇の御代勅して、二十年をもって正遷宮の期と定め給い、持統天皇の四年、始めて遷御の大礼を行い給う。
伊勢大神宮内宮祭神については、天照大神。左に天手力男命、右に万播(はた)姫の神。八十末社。第十一代垂仁天皇二十五年御鎮座。
外宮祭神は豊受皇大神。東、天津彦火瓊々杵等。西、天児屋根命なり、四十末社。第二十一代雄略天皇二十一年御鎮座。
京より三十五里。大阪より四十三里。江戸より百十四里。
内宮外宮の間に、天照皇山大神宮寺あり。
なお、外宮は内宮より四百八十二年後祭る。
ここから別れて、下中の郷町宮川橋を渡り、多気郡城田村を経て田丸扇屋仙蔵にて、三銭づつ吸物代昼飯。
それより道筋左に三十三観音あり。
次に小遣帳より列記すれば、
一月二十一日(旧十二月十二日)。名古屋市名古屋区本町七丁目銭屋所治右ェ門へ泊る。一金三十銭宿泊料。一金一円三十一銭名古屋笹島より伊勢宇治山田迄汽車賃。一金拾弐銭これは弥富より津島迄片道汽車賃。一金壱銭津島で絵紙一枚買。一金四銭食代。〆一円七拾八銭也。
一月二十二日。伊勢の国泉館太夫様に泊る。一金弐円を出す下等のおどしもの。一金弐拾銭莨(たばこ)入一つ。一金拾弐銭掛図五本。一金参銭絵紙八枚。一金九銭ガラスの盃三つ。一金拾銭寄附。一金弐拾六銭五厘帯三本二丈四尺。一金壱銭朝熊岳茶代。一金壱銭二見浦拝観料。一金弐銭二見絵紙代。一金弐銭瓦代として寄附。一金拾六銭掛図三本。一金六拾五銭五厘ハサミ五枚。一金拾六銭剃刀一丁。一金七拾銭御札代。〆四円五拾四銭也。
一月二十三日。泉館太夫楼を八時出立。一金弐拾弐銭伊勢より送り物代。一金参銭田丸扇屋仙蔵にて吸物代。一金参銭弐厘手紙代。一金弐銭八厘わらじ弐足代。〆参拾壱銭也とある。
明治四十五年にも田沼市太郎氏以下十一人三月八日盛岡駅を出発し、松島、日光、名古屋、伊勢、奈良、高野山、大阪、金毘羅、京都、江の島、鎌倉、東京、成田、水戸、小牛田迄記述後、東京遊覧案内に終り、帰宅は三十一日と道中記に記述され、妻と二人分〆て百二十四円九拾四銭とある。
大釜の武田斉氏宅に残されている伊勢参宮等の記録によると、日向喜太郎・武田善三郎・武田重兵衛の三人が、明治三十三年十二月五日に大釜を出発し、汽車・舟を利用し、主に徒歩で三十七日目の二月十一日に帰宅している。その目的はいうまでもなく、先祖代々の供養と家内安全・五穀豊穣で、いただいた神社・仏閣の御札が風呂敷に包みきれず、名古屋と京都で竹行李を七十五銭宛とはさみ一円四銭を購入している。
コースは大釜、盛岡、金華山、松島、仙台、岩沼、日光、鹿島香取、成田、東京、鎌倉、箱根、名古屋、伊勢(一月一日に参拝)、熊野、奈良、大阪、金比羅、神戸、京都、大津、善光寺(三十三の札所めぐり)、新潟、本荘、角館、生保内、橋場、大釜となっている。
伊勢の御札料は八十銭、御祈祷二十銭、日光の拝観料五十銭で、案内料八銭一人前三厘三毛とある。
旅費の最高は伊勢で世話料として二円、次は東京の一円、その他は二十二銭から四十五銭までで、多いのは三十五銭であった。昼めしの最高は八銭四厘、次は七銭、六銭二厘、五銭、三銭、二銭五厘、最低は一銭とある。白米は最高十六銭、十五銭、十四銭五厘、十四銭、十三銭五厘、十三銭で最低は十二銭五厘とあり、多いのは十四銭前後である。
汽車賃は盛岡から一の関まで七十九銭、品川から横浜まで二十三銭、わらじは一足二銭五厘から三銭、舟賃は近距離で五銭、一銭、五厘、湯銭は一銭とある。
しかし、この参拝の裏に、農事視察を兼ね、各地から種子を持参して来ていることは、亨保二十年(1735年)の穀物品種書上に稲は百三十八種、粟は三百七十一種、稗は百四種、麦は九十八種、豆類は百三十種となっていることからもうかがわれる。
なお、明治の初めより戦時中まで皇大神宮の大麻が各戸に配られ、これを尊崇していた。まず役場に各部落の区長が礼服で参集し、恭しく村長から拝受して各々部落に持帰った。こうして各戸の神棚に納められ、毎年十二月の末にはまた新しい大麻が交付され、古い方は鎮守の社殿に納めるか、あるいは不浄を避ける意味で「焼き申す」といって始末するのが慣習となっていた。
二 高山崇拝
高山の神秘を霊感するのは、何れの地方においても見られることで御山かけと称して、岩手山、あるいは早池峯山に登り、山篭りをなした習慣は、従来多かったが、近時は、この山篭りをするものが殆どなくなった。往時お山掛は「もの前に」という慣習があった。すなわち結婚前しかも十四、五歳の年少のうちに実行せしめた。これは一つには高山崇拝の神秘を味あせることゝ結びつけて、身体の鍛錬に資するための方便であったかのようでもある。殊にお山かけには岩手山を先とし、早池峯山を後にする風習があった。またお山かけには身体を清浄にするため、水垢離をとり魚肉の食用を絶ち、また男一度は必ず実行せねば一つの恥としていた。山形県最上郡の月山、羽黒山、湯殿山等の登山等往時は相当に行われ、村内にも石塔がある。
御山かけをする者は、山に登り始めれば往時は一同揃って祈祷の詞を述べたものである。中には南無阿弥佗仏を唱えるものもあり、登山中所々拝礼をして唱える祈祷の詞もある。柳沢口より岩手山へのお山かけの詞に次のようなものがある。
一王子・新山・受取坂・笠結・小立場・御蔵・鉾立・不動平・不 動清水・虚空蔵・妙光岳・薬師岳・御本社等山頂に至る途中の名称 であり、そこでそれぞれ礼拝をする。岩手山は二千四十一㍍の典形 的な重複火山であるが、早暁に登り詰め、太陽の御来迎を拝すを吉 相とし、帰路は、這松の梢を折って持ち帰り、自分の家はもちろん 「御山かけ」の出来なかった隣家や親戚にも配って、祈祷札と共 に、田圃や畑に細竹で吊るして、害虫除けの「まじない」とするほ ど山獄に対する深い信仰があった。
三 修験(しゅけん)と山岳の信仰
修験宗の名は明治五年(1872年)に廃止になったが、明治二十五年に至って天台宗の統轄の下に再び修行を始めることとなった。修験道とは役小角(えんのおずの)行者の開かれたもので、この宗では教理の研究をせず、山岳に起臥して心を清浄に持ち仏性の験得に努めるのである。すなわち荒業を専らにするからで、山伏とは野に伏し、山に臥すという意味であるともいわれている。
現在岩手郡における天台宗に属する寺院はわずかに二ヵ寺に過ぎないが、昔は相当数あった。明治初年まで岩手山とか早池峯山等にお山かけをするときに唱える詞に「南無帰命頂礼懺悔々々六根罪消云々」のあるのは、修験者の登山信者より出たものとされている。高山の信仰は実に、彼らに依って勧奨されたのであった。
四 大正月と小正月の行事
年中行事の一月の行事参照。
五 農神祭り
春の農神祭りは三月の十六日の早朝であって、団子を十六個拵えて農神様に供えると共に家族もいただく。この日山の神様が山に帰り、代って農神様が里にお出ましになり、農作を保護なさるので、各家々共朝早く起床して火を焚き、煙が空高くあがることを吉相としている。秋の農神祭りは九月十六日に一般に行われるが、仕事の都合や閏年等で翌月に延びることもある。
なお、第十編教育の変遷、第五章、第二節、二の百姓春始之祝を参照せられたい。
六 山の神
木挽その他山小舎にあって、山の作業に従事する者は、毎朝毎晩新しい御飯の出来た度ごとに山の神様へこの炊きたての御飯を献饌する。ただ簡単に飯を少し許り鍋から取り分けて後神棚に供えるだけのことであるが、食事の始まる前柏手して供えるので、一同の者に同じく敬虔の念を起こさせる。その他酒宴のあるときは必ず山の神様に御神酒を供え、それを撤して一同に御神酒を頒ち、後酒宴に移る。御神酒を神前に供えるは小舎頭で、低頭柏手をする。ボタ餅を作ったときでも多くは山の祭祀であるから、まず神前に供えてから一同の者は食べるのである。また悪い天候が続く荒日で、小舎に篭っているときは山の神に晴天を祈願する。
また山小舎にあるものでなくとも、旧九月十二日には盛んに山の神を祀る。神酒を用意しボタ餅を作り、肴を煮たりして神様に供える等山の神様の信仰は盛んであった。
なお、第十編教育の変遷、第五章、第二節、二の百姓春始之祝を参照せられたい。
七 馬神
路傍に、あるいは神社の境内に馬頭観世音の碑が建てられてあるのをよく見る。これはいうまでもなく、馬の霊を祀ったものである。多年自家で仔馬を産んだ馬や、あるいは多年飼育し農耕に従った馬の斃れたものなどの供養塔であって、お盆にはその碑にお墓同様赤飯等を供えて拝礼をした。馬産地として本村はかように馬に関係した行事は少なくない。これらは単に迷信といい去るべきでなく、一面家畜愛護の美俗涵養上にも資することは疑いのないことである。
馬頭観世音として崇仰するものゝ著しいものとして、木村篠木綾織の清雲院門前に木像の観世音が祀られている。
また、五月の節句には、馬に装飾して蒼前様や馬頭観音様に参詣する風習がある。いわゆるチャグチャグ馬コで『郷土読本』から抄録すれば、次のようなものがある。
『東の空はようく白み、夜はほのぼのと明けかゝって来た。馬を厩からひき出し、二重腹帯でしっかりと鞍を着け、鼻輪や轡を施し、沢山鈴のついた「きずな・むながい・しりがい」を順序にかけ、鳴輪を吊し、飾紐を垂れ、馬の仕度が出来上がると、紺の絆纒に紺の股引、豆絞りの手拭に昔ながらの菅笠を被りひらりと鞍の上に跨った。
口笛の合図で鐙を踏張り一鞭当てると馬は駈け出した。馴れない装束を着けたせいか、どうも窮屈である。
国道へ出ると、前に一頭、後に一頭、都合三頭連れとなった。夜は殆ど明け放れて、南昌・東根の山々は紫紺色の姿を現し、岩手片富士だけは頂を雲の上に隠している。この時朝日が姫神山の右手から昇り、山も草木も生々と輝いて来た。疲れた馬の足を谷川に冷やし、一鞭又一鞭、(中略)爪先上がりの山道を進み、間もなく目ざす鬼越の蒼前社についた。
社頭の松に馬をつなぎ、用意の賽銭と洗米をさゝげ、拝殿の前に額ずいて一年中の我愛馬の息災を祈った。それから静かに馬を社前に進めて軽くその頸筋をなでてやると馬は嬉しげに首を上げ、頻りりに尾を振り動かしている』
なお、第五編社寺の変遷、第三章、第一節、五駒形神社、1のチャグチャグ馬コを参照せられたい。
八 盆行事
浄土宗や禅宗が民衆の宗教として普及するようになってから、急に盛んになったものに盆行事がある。盆行事は仏教の行事である。だから仏教の輸入と共に行われたと思われるが、国史に最初に見えるのは、推古天皇の十四年(606年)の七月十五日に設斎を設けて仏を供養した記事がある。これを盂蘭盆会というようになったのは、それから五十年ばかり後の斎明天皇の三年(657年)に飛鳥寺で盂蘭盃を設けたときからであるから随分古い。これから千三百年も続いており、その間色々な変遷があり、地方的にいろいろ変って来ているが、一年の中で最も重要な行事として、これ程古く広く行われている行事も少ない。しかし奈良平安の遠い昔には仏教がまだ民衆化せず、主に上流貴族に行われていたので、民衆の行事としてはあまり関係をもたなかった。従ってその行事も貴族的な冥想的なものであった。
ところが平安末期になって空也上人の念仏宗が行われ、浄土思想が普及し、真宗や禅宗が民衆の信仰を深めるようになったので、御盆は民衆の行事として重要な意味をもつようになった。殊に迎火が万灯会によって行われるようになると、いままで家庭内で行われていた盆行事が急に社会的になり、部落の行事になり、この日は部落全体が生産を休んで仏を迎えるようになった。
万灯会を行うようになったのは頼朝が勝長寿院を起し、祖先の霊を祀り、源平紛争の戦没者の黄泉を照すために大規模な万灯会をしてから急に流行し、だんだん民衆にも普及するようになったといわれている。藤原定家の『明月記』に「近年民家に於て十五日の夜長竿を立て、その先に鋒をつけ、張紙の灯篭物を掲げることを遠近盛になり、その状流星に似、人魂錦を着たり」と、盆灯篭の情景を述べている。岩手県では(本村においても)昭和の始めごろまでは新仏のある家で杉の葉で棒の先端を十文字型、鋒の型に作り、紙張りの灯篭を吊していた。空を往来する精霊には誠に便りとなる霊標であったろうが、生きた人にはこれほどものさびしいものはなかった。
鎌倉幕府が万灯会をするとき、七・八歳位の少女に灯篭を持たせ灯篭流しをしてからいわゆる「舟こ流し」が流行するようになった。
盂蘭盆ということは、餓鬼道に落ちた仏を救う盆の意味である。だから盂蘭盆会は施餓鬼を中心に行われるものである。仏説によれば仏弟子目連という人が、初めて六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)を得て亡き母の在所を見ることが出来た。ところがその母はどうした訳か餓鬼道に落ちて、何か食べようとすると、それが火となって食べられず苦しんでいるのを見て目連は非常に悲しみ、釈尊におすがりをした。釈尊は七月十五日に自恣の僧を供養せば解脱すると説かれた。そこで目連は色々と供物を供えて供食したところ、初めて亡き母が極楽往生を遂げることが出来た。これから御盆には必ず施餓鬼を行うようになったという。
御盆には精霊棚を作り、その年に出来たあらゆる作物を仏前に供え、仏を供養し、これがすむと川か海に流してしまうのだ。舎利供養として百物をおき、百物を供えるのだが、その作物は地方によって異るので、施餓鬼の内容も地方ごとに違ってくる。けれども出来るだけ多くの供物を供えなければならないし、また供えるのが人情だ。だからだんだん栽培する作物も殖える。従って生仏様も功徳にあずかるのだ。ところが信仰が薄れてくると、生仏様が主で仏様をだしに使う不心得者も出てくる。仏様は別に文句もいうまいというやからは、すでに餓鬼道に落ちているのだ。
御盆には盆踊りがなくてはならないものになっていた。これは灯篭流しと、当時流行していた念仏踊りとが一緒になって発祥したものだ。だから初期の盆踊りは宗教的色彩の強いものであった。舞踊人は色々なあでやかな異形の仮装をして、歴史にちなんだ戦記もの壇浦合戦だとか、新田の四郎猪退治だとかの作り人形を大勢の仮装人が引き、その仮装人の一団が堂塔の庭とか、貴人の庭で念仏を唱えながら踊ったのである。丁度今の神社の祭礼に引く「出し物」と盆踊りを一緒にしたようなものがお盆に行われた。今は分裂して仮装人形は祭礼の「出し物」となり、音頭をあげるだけになり、御盆には盆踊りだけになって、わずかにヒヨットコとかオカメの面で仮装したものが二三人入る程度に変ってしまった。個人的な宗教的な風流の要素が強く、踊りはむしろ従属的だったが、時代の下るに従って個人的な風流さはなくなり、揃いの服装をし、円陣を作りながら、総合的な律動で踊る集団的な舞踊に変っていった。だから宗教的な色彩も薄れ、ただ盆に踊るから盆踊りだという感じになってしまった。
近世になって村落制度が確立し、村落共同体的な生活が強くなると、部落ごとに集団的な盆踊りが行われるようになったのである。殊に盆は丁度一年の収穫の峠で、一年の作柄も盆までゞ決るようになったので、その年の苦心の成果も一応見通しのつく時期であったから、盆には作業を休んで先祖の精霊を祀ると共に、作柄を祝いながら踊りぬいたのである。だから盆踊歌にも
そろたそろた、踊り子はそろた。稲の出穂よりなおそろた。
盆の十六日踊らぬやつは、ねこかしゃくしか花よめか。
盆の十六日かしの葉も踊る。子持ち女も出ておどれ。
盆よ盆よと待つのが盆だ、盆が過ぎれば夢のようだ。
と農村の人々の熱情を歌い、町の人々も盆踊りの太鼓の音で、農村の作柄が分るとさえいうのである。天明の大飢饉のときは盆前に大凶作が確定的だったので、盆中でも踊りに出る者もなく「近年稀なる淋しい世中である」と武士の日記に記されたほどであった。これと反対に文化年中には連年の大豊作なので盆踊りの太鼓の音もさわやかに華美な行事が色々行われた。南部藩は頻りに盆灯篭の竿の長さを制限したり、盆の小唄、辻踊り、相撲、花火まで禁止したり、盆踊りの歌詞まで認可制をとったり、迎火の真木(杉や桧)を制限したり、ついこの間行なったようなことをしているが、なかなか行われがたいと嘆じている者もあった位だ。町の人々は今年は盆踊りが三十も出たから豊年だとか、三つしか出ないからと言っては暗い顔をしていた。従って近世になると盆踊りはむしろ豊年踊りと同じようになってしまった。精霊を迎える迎火も鎌倉時代には色々な形を造り、大規模なものだったが、だんだん小規模になり、部落全体が同じように迎火を焚くように変った。筆者(森博士)が子供のころには何処の迎火が一番大きいか見て歩いたものだが、近世の中ごろからこれも色々制限され、特別な古風なものはすたれていった。
盆行事はこのように発祥当時から見れば随分変った。中にはその意味さえ解らなくなったものもあるが、本筋だけは現代人にも怠ることの出来ない行事となっている。
御盆が何故このように深い行事とし国民の習慣になったのだろうか。それは供養に対する信仰である。仏教が日本国民に与えた最も大きな功徳をあげるならば、それは死者を愛することを教えたことである。人にとって最も恐しい苦悩は死である。この死を苦悩のない死とすることを教えたものは仏教である。生者にとっては悟りによって、死者に対してはこれを愛することによって死者を安心せしめ、己れも安心することを教えたのである。供養さえすれば幽霊さえこわくはない。供養さえすれば地獄に落ちた人も極楽に行けると知ったとき、人々は癘(れい)鬼悪霊を呪(じゅ)服し、駆逐することを止めて季節を定めて人々の魂を迎え、これを供養することによって、その精霊は極楽に安住すると信ずるようになった。これは生きている人々にとって何よりも大きな安心である。人々にこれほど大きな安心を与えた宗教は他になかった。だから仏教は大きな力で古い民間信仰に代ったのである。(以上盆行事は『岩手を作る人々』から引用した。)
九 オシラ様
オシラの神は特に社殿を設けて奉斎する向はなく、多くは箱に収めて神柵に、あるいは座敷の床前などに安置されるのが通例である。桑の木で粗雑に作られ、稍丸味を持っている。頭・胴・手足等判然とした区別がなく、丈は普通一尺以内で多いのは六、七寸位のものである。これに頭面の形が刻まれてある。
オシラ神の由来には色々あるが、第五十八代光孝天皇(884-7)の御字に道仏といっていたと姉体の歴史はいうが『岩手県史』には、心棒の墨書記年を信ずれは永禄(1558-70)、天正(1573-91)、慶長(1596-1615)のものが最古であると述べている。
神体は二個を以って一組とするものもある。毎年衣帛を新調して被い重ねてある。従って重ねられた衣裳からその時代の衣服を推定することが可能となる。これを毎月十六日に拝むのであるが、正月と盆の十六日には一般の希望者に拝ませる。
この神は養蚕の神ともいわれ、また農業の神、あるいは火の神、眼病の神、婦人病を祷る神、子供の神等定説がない。この神は不浄を忌むこと甚しく、それを持つ家では、畜類、鳥類等を煮焼し、あるいは食えば直に罰があたるといい、四足二足を食わぬという俗言は、決して珍しくないことである。
この神は性荒々しく乱暴を好む放、子供に乱暴にもてあそばれることを喜ぶ。よって付近の幼童集い人形をもて遊ぶことが屡ある。遊び終ると元の処へ安置をする。その時逆に、または後向に入れると必ず夜歩き出し、踏みならし、障子をゆすぶるという。
大沢の堰合茂富氏宅においては、毎年旧十月十四日名号の掛軸の前に御神体二個を並べ御供餅三個をあげて拝んでいる。
また、元村の大野秀友氏宅にもあるという。
十 氏神様
社寺の変遷、氏子を参照せられたい。
十一 お七夜
十一月二十二日から二十八日までをお七夜と称して一週間精進料理をし、魚獣肉を断ち菜食を主とし、夕食後毎晩集合して仏前にぬかずきお念仏をし、最後の二十八日には七日間の慰労を兼ねて祝宴を催す。なお浄土真宗の寺において七日間説教があるのでききに出る者もあった。
十二 馬作り
年末から春先の農閑期の吉日を選んで、部落の各戸の男性が集り馬作りをやった。芝草が生えた広い場所が馬作り場になる。牡馬は二歳の秋に売られるから別として、三歳以上は役畜農馬であったから、夏と晩秋二回、蹄を削り、悪血をとるという慣習があった。数人がかりで一頭宛馬を転ばし、左右の前足と後足を交叉するように結い、頭と結んだ足には枕をかい、動けないようにして蹄を削り、足首に針を刺して悪血をとったものである。馬を転ばすのは身のきく青年でないと蹴飛ばされる危険があった。三歳牡馬の口から「やせ歯」と称する替り歯を金具で叩いて抜き、伯楽は御祈祷をし、呪文を唱えて白紙に血で鳥居を描く。馬主はそれを大事に持ち帰り、馬屋の梁に張る。また当日使用した藁や縄、縄口輪に血痕のついたものおば他に使用せず、門口の生垣等にかけられ雨ざらしにされる。
全部の馬が終ると、馬をめいめい家に連れて帰り、一戸一人宛順番の宿に集り、準備してある祝宴につくのである。主賓は当日の伯楽様を中心に、お蒼前様に御神酒を捧げ、一同飲食するのである。牡馬は馬作りすることによって健康になると考えられていた。
十三 講中その他
過去の村民一般は、石塔によって明らかなように、神仏に対して信仰心厚く、信仰により神仏にたよって安心立命のいわゆる帰依の人が多かったから、部落民は礼拝供養によって、日常生活は密接な関係に結ばれていた。ところが今日では一般には因襲的な信仰で、真実の自己の内面的な葛藤を解決する熱烈な信仰は稀になったように見うけられる。
その因襲的信仰の一つとして、今に行われているものに「講中」がある。例えば、火難退けの古峯講が現在大釜の日向通中心に行われている。
1 古峯講
明治四十年より毎年かゝさず代表者を古峯神社に参拝せしめている。記録せる帳簿に下のような記述(抜粋)がある。
明治四十年二月二十五日弐円宛持参して二十五名参拝し、翌年より代表者五名宛とし、大正二年からは代表者一名について十円宛に値上げをし、大正三年には大釜のみならず篠木・大沢からも参加して八十名に及ぶも、日向通りの代表者は五名で昭和四年迄継続されている。同五年には掛金一人弐円、講員八十人で総計百六十円、代表者一人について七円二十銭、御札開き酒代二十四円、五名の代参者は配当金より二円宛御守札料に出金。同三十一年より一人当り千円の掛金になり、一人四千五百円八名代参している。年々物価騰貴につれて増額し、同四十三年には前年度産米政府買上価格三等米壱袋七千七百四十八円、これより袋代百七十円、検査料三十円差引手取金七千五百四十八円、壱斗分の代金は千八百八十七円となる。この壱斗代金一千八百八十円を掛金としている。講員七十五名、掛金合計十四万一千円、これより御札開きの費用として一人百五十円宛を差引き、代参者一人当り八千六百五十円を十五名に三月十日手渡し、二十二日盛岡を出発し、四月三日御札開をしている。
大釜と大沢に各一基宛石塔がたっている。
2 二十三夜講
旧正月・五月・九月・十一月の二十三日の、いわゆる二十三夜を信仰する講中の者若干名集り、午後七時ごろより精進料理で酒宴を催し、午前二時ごろ月の出を拝してから一同解散をする。会場は講員の者交互に当る。
3 庚申講
庚申の信仰は道教にその源を発し、庚申(かのえさる)の夜、仏家では帝釈天及び青面金剛を、神道では猿田彦を祭り徹夜をする。その夜眠ると、人身にいる人の命を短くする三尸(し)が人の眠りに乗じ、その罪を上帝に告げるという。もと武士間に信仰されていたものが、平安時代以後、一般庶民間にも信仰されることになる。庚申を信仰する講中の者若干名午後から集り、羽織を着、中には袴をつける者もあった。とにかく礼装で一同座につき、庚申の掛物に向って祈願詞を唱え、礼拝して後精進料理で酒宴を催す。会場は講員のもの交互に行うを例としていた。
4 甲子講
鼡を大黒の使者とみなして甲子の日に信仰する者若干名当日の午後から集り、甲子を礼拝して後、子の刻(午前一時)まで起きて、大豆・黒豆・二股大根を食膳に供し酒宴を催する。会場は講員交互に当る。
5 馬頭講
毎年一月か三月、あるいは七月か九月かの十九日、講中の者集り、馬頭観音を礼拝し、後酒宴を催す。会場は講員交互に当るを例とする。
6 念仏講
農閑期になると、毎月適宜に日を決めて十人乃至二十人位集り、仏前において名号を唱え現当二世の安穏を祈る。
7 観音講・十和田講
前者は毎年三月十七日か九月十七日の御縁日に講中より代表者一・二名を選定し、稗貫石鳥谷の土仏の観音へ参詣し、後者は講員で無尽を始め、当籖者数名は青森県の十和田神社へ参詣し、いずれも帰村後御札開きの酒宴を催し、講中の者へ御札を配布する。会場は交互に当る。
8 百万遍
仏に対する供養のため、部落民は年二回位定められた家に集合して百万遍を唱える。これはたゞ仏に対する供養に止らず部落民の融合を図る。
9 厄病祭
田植が終った後、各部落で厄病祭の日を定め、各家ごとに日本紙に大きく「悪病退散」または「悪魔退散」またはのぼりには「奉納天照大神官・春日大明神・豊受大神・家運長久・五穀成就」等と書いたものを中心にして御神酒・餅を供えて厄病の退散を祈願する。後にこれらを棒につるして旗の様にし、一家の代表者達が全部それを持って部落の一ヵ所に集合し、部落の境におさめて悪病を部落外へ追い出したものとした。
厄病祭りについて、昭和三十四年の朝日新聞に『としよりの心のふるさと』と題して、雫石の高橋与郎氏が寄稿している。本村のそれも大同小異であるから次掲することにする。
「ドロシコ、ドロシコ、ドントコドン、ドント、ドロシコ、ドントコドン」と太鼓の音に調子を合せて、夕やみの中に「ナアニナアニ祭りよ、厄病祭り、祭りよ」とカン高い子供たちの声が聞える。六月も下旬、田植も終り、農家ではほっと息をつく早苗振り休みに、雫石町では厄病祭が行われる。農家の人々はこの厄病祭りで早苗振り休みも終ったなと思い、再び田の草とりの激しい労働を始めようとするのだ。
全く素朴な行事だ。年と共にすたれては来ているが、それだけに老人達の郷愁を伴って、捨てきれないままに町の山手よりの部落では今でも行われている。
祭りの由来を古老にきくと、昔中国から伝わったというこの行事は、何時どのようにしてこの地で行われるようになったかははっきりしないが、天保年間の大キキンに悪疫が流行し、悪鬼、野盗の類に苦しんだ時、農家の人々の夢まくらに立ったショウキさんが神通力をもってこれらを退散せしめたことに始まるという。
厄病祭りは、ことさら祭日として決められた日どりはないのだが、その年の当番となった人の申し合せにより、町の上手からはじまり、次の部落へ、次の部落へと伝え送られて、町の外まで送り出されるのである。
祭りの当日は「奉納鍾馗大神悪魔祓」とか「悪魔悪疫退散家内安全祭納」などと思い思いの祈願の紙のぼりをおしたててショウキを形どったワラ人形と、木で作った剣に「鍾馗大神祭神」と書き、太鼓、笛の調子に合せて行列は部落の上手端から行進を始める。
各戸では家族の数のダンゴやセンベイを糸やナワでつりさげて行列の人にたくして祭神に奉納する。行列が部落をまわるに従って子供の数がまし「ナアニナアニ祭り……」の声も部落にひびきわたるようになる。このあとから重箱に御馳走を入れお神酒持参の年より達が従うのである。
部落の下手端には、老木がある。行列はそこまでたどりつくと、ここで祭り納めの宴にうつる。夏の夜はすっかりくれて、水田にはカワズの音がしきり。ホタルが静かにとび交う中で、かゞり火をたいて野宴をはじめる。それはそのまま昔のわれわれの祖先の姿である。たゞ二、三年前から農薬を使うせいか、ホタルの数が目立って少なくなったのに、私は時の流れを思うのである。
この町には、厄病祭りと並んで人形祭りというのもある。部落内で窃盗などの事件があった時、ワラ人形を仮想者にしたて、これをのろうことによって制裁の道具にしたものである。このワラ人形は、若い人にになわれて各戸でくしざしにされ、部落のはずれまでくるころになると見る影もなくなり、子供心にもその悲惨な姿は生あるものゝ如く、あわれなものに思われ、おそろしさにかられたものだ。その後、しばらくは、そこを通ることも夜の便所行きも一人では出来なかったことを記憶している。
悪疫、悪鬼と共にこうした不心得者を追放し平和な村をと願った気持に変りはあるまい。だが、人権尊重をとなえられる昨今、人形祭りの方がさすがに全く見られないようになった。
厄病祭りの方も、今では信仰を別として、子供らの行事となり、若い人達の懇親会となり、情趣ある野宴もお座敷での宴会にと変りはじめた。祭り自体も簡素となり、年と共に消えゆく運命にあるのではなかろうか。部落の団結をはかり、悪疫悪鬼を追放して平和な村をと祈った祖先の願いが、この若い人達の懇親から生み出されたとしたら、祖先の霊、又、ショウキさまにも満足してもらえるのではなかろうか。
日ごろ無信仰な私も、子供の健康と、今年も連続豊作で部落に平和がおとずれるよう静かに祈りたい気特で一杯になる。
10 虫祭
田植がすみ、早苗振り休みが終ると、田の草とりの一番除草に取りつくころ、虫祭りの「ふれこと」が流れてくる。順番制によって「何日は虫祭り、宿は某の家」と指示される。御祭りの日は朝仕事を休み、村の各戸から主人と男の子が祭りの宿に集り、細長く切った白紙に「奉納鳥海山大権現悪虫退治」と書いた細竹か葦に吊り、一同御神酒、子供らには甘酒等飲食後、夕方になって太鼓を打ちながら宿を出、口々に「田の虫祭りよ、稲虫祭りよ、虫祭り祭りよ」と唱え、害虫駆除を祈願して、田圃をねり歩き、村外に害虫を追い出すのである。藩政時代に郷役として虫祭り銭を撤収した処もある。昭和の初めのころまで本村においては、子供らのみが部落の上から下の部落境までねり歩いたのである。
11 二百十日の風祭り
二百十日を風祭りと称して休日とする慣習があった。二百十日の前後の天候は、日本列島は台風の季節であって、古来からその被害に苦しめられたのである。その被害を免れようとして二百十日を休日とし、風祭りをしてきたのである。紫波郡煙山の高橋重平氏に残る文書中に「二百十日にて風祭りだんごなり、朝食二朝分なり、休みなり」とある。潅漑用水の水を止め、魚をとって風祭り祝いに用いていた。
第二節 石塔類
過去の村人は、次掲のように、神仏に関する石塔を百基以上村内にたてている。村人は、各家庭内の神仏を拝む外に、屋敷神と氏神との中間に石塔をたてて、村よりも狭い地域の住民が、期日を定めて礼拝したのであったから、ここの住民は石塔を通じて団結を固ていたように思われる。
一 小岩井
開田記念碑(大清水)昭和四十一年。
二 大釜
西国三十三所観世音(大沼前)明治十五年、南無阿弥陀仏(同)嘉永三年、百万遍供養塔(同)嘉永三年、良檀禅定門・念仏供養塔(同)明治二十一年、皇太子殿下小憩記念碑(日向)明治四十一年、馬頭観世音(同)大正八年、庚申祭(同)大正十二年、庚申供養塔(同)寛政元年、庚申供養塔(同)天明六年、吉清水神(八幡宮)大正八年、古峯神社(同)昭和四年、馬櫪神(土井尻善徳氏宅)嘉永七年、西国三十三番供養(東林寺)文政六年、接待茶供養(同)寛政八年、南無阿弥陀仏(同)明治元年、二十三夜(同)明治十三年、百万遍(同)嘉永七年。
三 篠木
剣舞供養塔・三界万霊塔(清雲院)、庚申塔(同)、剣舞供養塔(同)昭和十七年、剣舞供養塔(同)大正十年、庚申供養(同)、庚申塔(同)、冨士浅間大神(同)、越前堰記念碑(同)明治二十三年、馬魂碑(同)昭和十二年、開道記念(篠木坂)昭和四十一年、南無阿弥陀仏(下通)、湯殿山(同)、田村神社(同)、農地整備記念(土地改艮区)昭和四十三年。
四 大沢
乾坤一如(熊野神社)大正十三年、皇運無窮・社殿改築(同)昭和九年、慰霊碑(同)昭三十九年、山神社(同)大正九年、南無阿弥陀仏(割田)、岩手山(同)明治三十一年、百万遍供養塔(同)、南無阿弥陀仏(同)、馬頭観世音(同)、湯殿山(同)、二十三夜(長坪)明治四十一年、雷公神之塔(同)大正十一年、古峯神社(同)昭和三年、南無阿弥陀仏(徳左ェ門)弘化四年、南無阿弥陀仏(同)、馬頭観音(同)、西国三十三所(同)。
五 谷地上
岩鷲山(局附近)嘉永九年、湯殿山(同)明治三十五年、三十三夜(同)明治十六年。
六 鵜飼
忠魂碑(駒形神社)大正九年、馬頭観世音(同附近)大正十五年、馬頭観世音(同)昭和十五年、湯殿山(清水沢)明治十六年、南無阿弥陀仏・観世音菩薩・寒念仏供養塔(外久保)、二十三夜(公民館附近)昭和六年、田村大明神・庚申塔・熊野山(同)文政八年、寒念仏供養塔(同)、南無阿弥陀仏(同)安政五年、剣舞供養塔(同)大正二年、湯殿三山(同)大正八年、善光寺如来(同)昭和二年、湯殿山・月山・羽黒山(同)、餓死供養塔(一本柳)寛政十三年、餓死供養塔(孤洞)文化十二年、餓死供養塔(笹森)天保三年、鬼越道路開さく記念昭和二十三年。
七 元村
南無阿弥陀仏(平蔵択)嘉永五年、南無阿弥陀仏(耳取)嘉永五年、念仏供養塔(土沢)嘉永二年、金毘羅山(禰宜屋敷)文政二年、南無阿弥陀仏供養塔(同)明治九年、馬頭観世音(牧野林)、湯殿山・月山・羽黒山(同)明治十九年、駒形神社(同)明治三十九年、庚申供養塔(根堀坂)、開田記念碑(牧野林)昭和三十九年、餓死供養塔(高屋敷)安政二年、五穀成就(松原前)天保二年。
八 巣子
山の神昭和十五年。
九 分れ
岩手山麓開墾功労者代表像柳村兼吉氏昭和四十三年、岩鷲山安政三年、正一位田村大明神文化四年。
十 川前
三田義正翁造林頌徳碑(駅前)昭和十三年。
十一 一本木
田村神社(柳原)昭和五年、金毘羅大権現(同)明治二十三年、南無阿弥陀仏・観世音菩薩・大勢至菩薩(同)嘉永七年、馬頭観世音(同)明治十四年、馬頭社(同)、馬鹿観世音(同)、大明神(同)大正十二年、観世音大士(同)昭和十四年、馬頭観世音(柳原阿弥陀様隣)昭和九年、十八両観音(同)大正十三年、三峯山神社(同)、馬頭観世音(留ケ森)、馬頭観世音(同)、二十三夜供養(同)文久元年、金毘羅神社(同)明治二十年、南無阿弥陀仏(同)安政四年、岩手山・田村大明神・馬鎮観音(同)、湯殿山・月山・羽黒山(同)、馬頭観音(同)大正四年、馬頭観音(同)。
十二 一王子
岩鷲山、庚申供養塔寛政十二年。
第三節 年中行事
一 一月の行事
1 大正月(自一日至七日)
『元旦に一家の主(男子)が未明に起きて若水を汲み、天照大神か歳徳神の神前に供え、一年中の邪気を除く風があった。古は立春の早旦に汲んで用いたところから立春水ともいっていた。元朝誇りといって元日早朝に起きて四方の神々に詣で、祖霊を迎えた神前に飯米あるいは賽銭を捧げ柏手礼拝して、国家安康、家内安全・子孫繁栄等を祈願し、併せて火難・水難・病難・盗賊難等を除去される様に祈り、産土神より付近の神詣でをなすのであるが、他人よりも自ら早くお詣りするをよしとしていた。老若男女の別なく、朝早く起きて競って参拝をなす風があった。この風が大東亜戦争のとき最盛であった。歳神には二重または三重の鏡餅を供え、外に月餅十二お供えをあげる。その年が若し閏年であれは十三になる。また仏壇には、歳神のお供餅より小さいが三重の鏡餅を供え、膳には平年であれば十二、閏年であれば十三箇の白米のにぎり飯をあげる。これは農繁期に心がけていても、つい神仏を拝むことが出来ないことがあるので、年頭に当り一年分をあげて拝んでおくとの意である。朝食前、朝日の見える処に、二重の鏡餅を供え、戸主から朝日を拝み、その年の天候の順調を祈願し、終って、神棚に神酒神灯をも供え、家族礼拝の後各人の膳にも田作りを供え、雑煮あるいは黄粉餅または小豆餅に御神酒をいただき、如何なる貧家も粟・稗等を雑えないいわゆる米の飯を食したのである。朝食後戸主等が本家や親類・知友を年始廻礼して飲み交すが、家族はそれら来客の応待等で家に待機する。
二日も親類縁者、あるいは地主等に廻礼をして出かけ鏡餅と称するものを年始祝の験(しるし)として差出し、これに松の小枝を添える。また新婿は夫婦連れにて晴衣を着、花嫁の家に礼のために行く。このとき夫は清酒一升入の樽を二本に塩鮭二尾、妻は鏡餅三枚を舅家に贈るのは古来よりの慣習であったが、資産の大小家柄等により、これ以上三・五・七の数まで増加し、二泊する。その半分を返すを例としている。里方では、朝早くから仕度をして待っているが、その日の御馳走は手打そばである。二泊以上長泊りすると粟粥か稗粥を食べさせられるといわれた。老人は鏡餅を寺へ持参をした。
三日、五日は三元日、五元日と称して、やはり黄粉餅か小豆餅に神酒神灯をそえて神様に供える風習があった。
五日の朝供えた神前の重ね餅を下げて、くるみ餅・ごま餅・雑煮餅、思い思いに調理をして食べる。鏡餅は供えたものばかりでなしにもらったものもある。この日に食べ残ったものは藁で編んで常居の天井に吊して乾燥をする。これを腹痛のときに焼いて白湯にとかして食べるとなおるといわれ、また、六月一日に「歯固め」と称して食べると丈夫になる等と伝えられ、その日まで保存している家もあった。なお神前に供えたものは女は食べられないものとし、その家の主婦は食べなかったという。
七日は七草粥といって小豆粥に七草を入れる。七草すなわち芹を主とするのであるが、その外ごぎよう・たびらこ・仏の座・鈴菜・すゞしろ・夏菜を俎(まないた)の上にのせれん木にて叩いた七草と、年縄に挟んだ田作り昆布を細かにきざみ、粥に入れ、供物の餅を焼いて是に入れ鏡開きと称して神前に供える。なお七草をつくるときは、その家の主人自ら早朝起床し「唐土の鳥の渡らん先に七草叩け何草叩け」と称えながら、あるいはまた「唐土の鳥と田舎の鳥と渡らぬ先に七草叩け何草叩け」と七回繰返しながら七草を叩き刻んだのである。
またこの日門松を撤し、吉凶の方角を占って納める家もある。
なお大正月の四日・五日・六日・七日の四日間天気がよければ、その年は豊年満作であるといわれている。
この七日の休みのうち、農民は朝仕事と称して、朝飯前に一定の仕事をする。すなわち、男は馬靴五足、馬の手綱七本、馬の腹帯七本、女は小縄四十廻りのもの三把、莚一前(一枚の三分の一)等である』。
八日、二十三日は山の神礼とて百姓が山に入り始めの日で年縄を明けの方の木にかけ「ポァポァ」と呼んで烏を招き餅をやる風習がある。このとき烏がよく餅を食えばその年は吉で災難なしとしている。またこの日明けの方角から柴をとり燃し、家族は濁酒などを飲んで暖をとり、その火に当れば年中蛇に咬まれることがないとし、一年間の健康を祈る。これをのさ打ちという。のさ打ちという意味は野に打ち立つことで仕事始めである。
十一日は農(の)はだず、または肥付けといって、前に樹てた門松の一本を田の中に樹て厩肥を三カ所に運び、肥つけの仕方をなす。百姓の働き始めを意味すると共に百姓と馬との密なる関係を現すものである。中休みに当っては蕎麦餅・小麦餅等の小昼を食べる風習がある。
正月中は御年始といって従来から年賀の廻礼が行われる。酒一升に手土産持参で世話になっている家、新婚者は仲人の処へ、または嫁婿の里方へ礼に行く(二日の行事参照)。
十三・十四日は終日小正月用の餅を搗く。すなわち、米の餅・粟餅・豆餅・黍餅・蓬餅・粉餅等で、いずれも二十センチ平方ぐらいの角餅である。
十五日には正月飾り、田植え祀り、年越し祝いの準備に忙殺され小正月の年越しをする。
2 小正月(自十六日至二十日)
『小正月は人間生活に付随したあらゆる必要な物の労をねぎらう意味で古くから行われ、お年越の神様はもちろんのこと、仏前・井戸・臼・鍋釜・炉・水桶・鍵等にも供餅をなし、なお牛馬鶏等の家畜にも日ごろの労を感謝していたわる良風があった。その他、仏前にはお供え餅の外「ミタマ飯」といって握り飯を作って九つ供えることを習慣としていた。また、臼に供える餅は四角に切り、その中央に白米をつみのせその上に臼をかぶせておき、後にその供物を下げるとき、その餅に成るべく多く白米の付着しているのをよしとして、その年の吉凶を試すものとしていた。その米は後で鶏に与える。神棚には松飾りをなし、年縄には幣束・昆布・田作り・蜜柑・炭などをつけて新春を寿ぐ。また松の期間が過ぎれば「ミズ木」を立て、各枝に団子をさし、なお米穂といって藁に小さく餅をちぎってつけ、数本を束ねて稲穂のように作ってこれをも吊し、また金といって竹に餅を細長くのばしたものをつけて室内に飾りつけ、見るからに一陽来福の感を起こさしめる。
また次のような飾物もあった。米の餅で作った小判型の「のべ餅」を三尺位の縄に連ねて三本下げた銭(ぜに)、笹竹か柳の枝へ米の餅をつけたもの十二本位の米の穂、笹竹か柳の枝へ粟の餅をつけたもの十二位の米の穂、ミズ木の枝に沢山の団子をつけた繭団子、二間半から三間位の神棚一杯に張った網へ一面に吊した藁のぬさに小さい餅を無数につけたはせ架等のにぎやかな飾物もあった。要するに家業繁昌を表徴したものである。
午後からは瓜・茄子を作るといって、門松の外の一本を長木に結びつけ、任意の場所に樹て、これに縄を張り廻し、その縄に蔬菜類を表徴する新しい草履、または草鞋の類を下げる。これは蔬菜類豊作を祈願することにちなんだものである。
また、農業の仕方をまね、雪の上に田を型どり、藁を早苗になぞらえて田植のまねごとをなす。農業に必要な「つまご」草鞋も出てくる。折角稔ったものを風に揉まれてはというので風切り鎌も出て来る。そのやり方が面白く、小昼と称して膳の上に小さな切り餅をのせ、その上に小豆あんをかけたものを前の田になぞらえた畔に持って行きおやつのまねまでしたのである。
夕方食前に籾糠と黄粉をとった豆の殻とを枡の中に入れ、年男がこれを持って蒔きながら「米の皮(糠)もほがほが(寿ぐ豊年の意)、豆の皮(糠)もほがほが、銭も黄金も飛んで来る。ヤラクセイ、トンノガナァ」と唱えながら家の周囲を二周する。このことは吉相を希う意味で、家族中一人でも欠けておれば行わない。従ってこの間子供は外に出ないし、若し外出中の者が帰宅しないときはこれを行わなかった。この晩はいわゆる小正月の年越で、それぞれ御馳走を用意して神前に供え、且家族一同無事越年の祝福をする。なお夕飯後は思い思いに夜烏追い(年男は「夜烏ホーイホーイ、朝烏ホーイホーイ、悪い烏が来たらば、頭割って塩つけて、エゾの島さ流せ」と唱えながら常居を三周して戸を明ける)、戸窓塞ぎ(家族一同揃ったところで木片に田作り、または鰯と餅及び昆布等を挟み年男が自分の家の周囲を廻りながら各戸の窓へ差し込む。これは盗難除けの意味である)、果樹(なりき)責め(果樹類に目をさまさせる行事で鉈を持って木の下に立ち、樹に向かって「今年はなるがならねぇが、若しならねぇば切るぞ」と三回いいながら鉈を振り上げる。このとき他の一人が大声で「なる」という。このとき鉈を収めて家に入る。これを行うと果樹大豊作疑いなしという)。また昼間実施しなかった家では田植えを行うのである。すなわち十一日に肥引した場所に家族一同揃って藁・豆殻等で田植の真似をするのであるが、この時植える人々は「五月の田植えには嵐のない様に、一本植えれば一千本、二本植えれば二千本、御年神様御願いだ」の文句を唱えながら植えたのである。
この晩はこれらの行事で非常に願う。昼は盛岡や他町村方面から入込んで来るが、夜は各部落の婦女子が幾組にも分れ、月夜に堅雪を踏んで近隣各戸に田植えに廻る。彼女等は口々に「明けの方がら田植(たえ)に来たます」または「田植こに来たます」といいながら目指す各戸を訪れる。訪れられた方は「御苦労さん」と受けて、各人に色々の切餅をお祝に出す。この餅はいわゆる「かまど」に相応した大きさで、富有階級になると大形のものも見受けられた。これは田植えの手伝いに参ったという意味で、来られた方はわざわざ来てくれて有難い。今年はきっと豊年満作で人手も多く要し、田植も「はがえぐ」であろうと感謝の意を含めて餅を出す。大どこになると、三駄・五駄入等の大きな「はんぎり」にこの田植餅を山と積んで彼女等の来参を待つ。この行事は殆ど徹夜で行われた。また、子供らも数人ずつ群をなし各戸に田植えと門口に立てば、各戸共よろこび切餅を一つずつくれる。こうした子供らが幾組も歩くのであった。
ミズ木にさした団子の煮汁を木の根にかければその木がよく成長するといい、実らぬ木の根本に注げば能く実るという。
さて、年越祝いをするに先だって、風呂に入り身体を清め、神酒神灯を供え酒や肴で年をとったのである。なおこの夜早く床につけば白髪が生えるといって、家内一同炬燵や炉の困りに集まって、四方山の話に時を過ごしておそく寝についた。
また、この夜の月に影をうつして、その影に頭のついていない者はその年の中に死ぬといい伝えられていた。
十六日、この日は地獄の釜の蓋のあく日である。その家の年長者は早朝起床して若水を汲み、神前を清掃し、家族は盆の十六日と共に朝仕事を休むことになっていた。早朝年男は家屋内をそこここと廻り、戸を叩きながら大声で「ねぶと・腫物・腹厄病そばぁ通ってへいさえげ(側を通って塀の外へ行け)、病神(やめえ)外さえげ、福の神(がみあ)こっちゃこ、福の神様おへぇれぇんしぇ」と唱え終って玄関に座っておじぎをした。これが根太追いの行事で、家内安全を祈る一種の祈祷である。また前夜おこなった夜烏追いの行事を、朝鳥追いといってこの朝に行う家もあったが、やり方は前者と同じである。また、この朝神棚に若水をあげ、豆殻で家の中を掃き清め、その豆殻で炉に火を焚き、炉の鈎に前夜供えておいた三角形の餅を焼き、一人で食べ鈎に鍋をかける。若しこのとき年長者が炉に火を焚かないうちに起き、炉に足を入れゝば、強くその足を叩かれる。それは早く足をおろせば種蒔のとき苗代に烏がおりて種子をたぺるからだという。なお、この日はなるべく鍋釜や日用の諸道具をねぎらう意味でつとめて使用しないで休ませるようにしていた。この日一家の主人は墓参をし、家族は仏画名号の掛図を床の間にかけて黄粉餅を供え念仏をなす処もあった。また、この日はオシラ仏として、オシラ様のある家に集って拝む集会があった。
十七日は大正月に実施しなかった新婚の夫婦相携えて舅殿(ど)へ年始に行く。共々二晩宿って十九日に帰宅をした。
十七・十八・十九日はそれぞれ餅と酒などで祝った。
二十日になれば粟ごなしといって稲穂・粟穂になぞらえてミズ木に吊したものを鎌でかりとり、団子と共にミに入れて農作物の収穫を思わしめていた。これで小正月の終りとしてお供え開きをするのであった』。
二十三日は、二十三夜様と称し、宵待して月の出を拝む慣わしがあった。部落の有志が講を結んで、定めた宿に集り、東の空にのぼる月の模様、雲や風の具合を眺めて、その年の豊作を予知し、判断し合うので、経験を積んだ古老などが中心となっていた。
三十日は、二月の年越しで夕食を晴食とした。
二 二月の行事
二月は雪深く、寒風肌をさす冷たさ、真冬とはいえ相当多事であった。上旬、藁細工は一月から続き副業として続けられ、一年間の農事設計の作成・果樹の剪定・金肥運搬、中旬、農蚕具の修理、下旬、農蚕具及び種子の共同購入・桑樹の手入及び病害虫の駆除等なかなか多忙であった。このころ部落農談会・農事・衛生・火防・納税等の各講話会が頻々として開催された。
旧暦の二月は、一日から三日間は二月正月と称して休み日。一日は男四十二・六十一、女三十三・三十七の厄年に当る人のある家では、二月中の午の日、彼岸の中日、二月の十五日の釈迦の日、八皿の日、社日等と該当する年齢の人を除く近親を集めて年祝をした。この祝の場合招待されぬのに勝手に少量の手土産を持って祝に来てもよいことになっていて、来られた方では止むを得ず予定外の客膳を据えねばならぬのでてんてこ舞をすることがあった。なおこの祝宴には他の厄年に当る人、また、厄年の前後の年齢に当る人は、たとえ兄弟でも出席を遠慮することになっていた。年祝の祝宴も随分大袈裟で、富有であればあるほど、大規模の御馳走をする。まず家内一同神官を招いて、厳粛な潔が行われた。これがすむと大祝宴となる。これが一とまずけりがつくと後引きとなる。このときは厄年に当る人であろうが出席一向お構いなし、翌朝も婚礼同様近親をよんで朝めしの宴が催された。
二月の初辰の日、折敷膳に八つの皿をならべ、自家酒を供える慣わしがあった。これを八皿行事として重視していた。
八日は悪疫除けをまつる日とし、夕食を団子に、門口に疫病神退散のため藁人形を立てたりする家もあった。
山林にこもって、山の作業をする人々は、十二日を山の神の祭日とし、作業一切を休み、春木伐り、木材の杣取り・木挽き・搬出者木炭の山出し、山林にゆく者凡てが山の神を祀ったのである。白米飯を熱いうちにこねりつけ、ボタ餅にし、それに太い棒を串にしてその棒にまきつけ、これに味噌か、油味噌、または砂糖味噌等をぬり、焚火にあぶり、それを食べながら酒を飲み祝うたのである。酒は濁り酒、兎や雉子の味噌汁等を食べていた。
この外に二月には、初めの午の日を初午の日と称して赤飯をたいて休み、十五日は釈尊入滅の日として休日にし寺詣りをなし、精進料理でおふかし、おにしめであった。
社日は二月と三月にあるが、この日は諸神奉祀の日として、山仕事をする者のみでなく一般農家でも休日とし餅・団子で祝っていた。
彼岸には小豆餅・団子・藁麦等を作り、仏前に供えて霊をなぐさめた。大抵の家庭の中日には赤飯「いり」か「おくり」彼岸には団子を仏様のお土産なりとして作ったが、漸次彼岸の入り、中日・送り日の区別がなく作り、近親の間柄に受授の風があった。中日だけは休日とする処もあった。
以上のように、大正月は七日間、小正月は五日間、二月正月は三日間の十五日間は酒食の消費は多かったにちがいない。
冬至を過ぎると小寒となり、大寒になるが、この間約三十日を寒(かん)といい、新暦では大体一月六日から二月四日(節分)の日までゞ、この期間が最も寒い期間にあるから、暖かいものを食べるようにしていた。南瓜は冬至に食べるようになっているが、寒まで持たせて食べるところもあった。
三 三月の行事
上旬、畑地用堆肥製造、貝殻綿虫駆除。中旬、畑地土張、水田排水作業。下旬、第一回の麦の追肥踏圧土入、茄子・甘藍播種準備、味噌煮、野鼡駆除、苗代耕鋤下肥施用、諸作物種籾の選種等がこの月中に行われてしまう。
三月は雛の節句、または桃の節句といい、年間の節句中最も節句らしい節句である。一日には節句用の糯米の精白や製粉をすべて終り準備をする。二日には、女性や子供ら全家族で「雛菓子」を拵える。この雛菓子には(一)型おこし、(二)切り菓子、(三)きりしぇんしょ等がつくられ外に饅頭も白餅もつくった。
(一)型おこし。厚板に動物・山水・草花その他各種の模様をほった型に、白米粉をねったものを詰めて、その型を浮きぼりにしたものをいくつも作る。まんじゅう型のものにはあずきを入れ後に蒸す。
(二)切り菓子。米の粉に五色等の色彩を入れてしめし、それを利用して各種の模様を入れる。うずまき、いち松、稲たば、梅の花、松葉等、その人の技巧をつくす。蒸して翌朝輪切とする。
(三)切りしぇんしょ。米の粉にクルミを入れたりする。横長く、扁平につくり、上に箸形を押す市場販売品と殆ど同じ、蒸して、翌朝切って供える。
型菓子は子供にもできたが、切り菓子は出来なかった。色彩を入れて湿した塊りを色々組合せて、径二寸前後、長さ八・九寸位の棒状につくり上げるが、人により家により技術に差があった。二日はこうして餅菓子をつくり、大鍋で蒸して煮るのである。また型菓子も切りしぇんしょも蒸し煮とする。
この外、白米餅をつき、のし餅につくられ、小型のまんじゅうもつくられる。すなわち白米粉利用の餅菓子の粋をつくしておひな様を祭るのである。
三日の朝は前日の夜おそくまでかかって蒸したものを、この朝ヒナ壇に陳列するが、切り菓子はこのときうすく輪切りにされ、その切断面に、色々の模様が色彩あざやかに顕れる。美しい色彩の切り菓子・型菓子・切りしぇんしょ・三角の白い切り餅・小さな饅頭、それらが膳に陳列され、その外海苔寿し、甘酒、白酒等をおヒナ様に供えられるので、おヒナ様と共にその家族も喜びに浸るのである。
こうして作られたヒナ菓子は、三日の朝食後、隣家に配られるので、この菓子作りは、自然競争の気持ちになり、技術の練磨ともなった。また若い女性は婚家から三日の休日に生家を訪れるにも手土産として持参することもあり、家の趣向、部落の技術の交換ともなった。
この節句には、三月朔日の朝、ヒナ壇をつくり、ヒナをならべるが、ヒナは花巻産の土人形で、江戸ものや京人形は、豪商豪農以外には殆ど見られなかった。朔日の朝、正月から乾燥してあったアラレを大豆位の大きさに砕き、それを鍋で煎り、餅花にふくらませ、煎り大豆共に、おヒナ様に供える。また木版色刷の絵紙(えがみ)を後に吊って飾り、朔日の朝から三日の朝まで、おヒナ様の食膳は女の子が精をつくして供えるものとされていた。
この日近所隣りの子供らを互いに招き合って一日を楽しく過し、休日としていた。
十六日は農神様の日である。この日山の神様が山へ帰り、代って農神様が里に降臨して、その年の農作物の世話をしてくれる日になっていた。各戸未明より米の粉で餅を作り神前に供える。このころになると、雪もそろそろ消えかけ、陽炎がちらちらと燃え上がる日も間近い。このような陽気な早朝毎戸から米の粉を搗く杵の音がもれて来た。彼等は競って杵の音を一番先に立てようとする。これはその家に農神様がいるからである。農神様を迎えた家はその年豊産をもたらすからで、この日も休み日であった。
四 四月の行事
春雨の煙る日が続く。もう春である。草木は生々と躍動し、我々をも促している。水田はもちろん、木々は若芽路傍の雑草は生々と芽を吹き出している。
上旬、苗代の耕鋤施肥・温床種子蒔付・種籾の浸種・果樹桑樹の薬剤撒布・厩堆肥の運搬・畦畔の整理・豌豆播種。中旬、果樹桑樹の移植施肥・麦の土入除草・馬鈴薯・水稲種子揚水並播種・本田耕鋤・果樹桑樹の接木鋏入・同相続枝薬剤撒布・山東菜の播種・桑樹盛土の解除。下旬、陸稲採種準備・接木・苗代管理・粟稗播種準備・人蔘午蒡燕麦播種・畑地耕鋤・果桑樹の薬剤撒布等々準備完了。
旧四月朔日は山見(花見)の休みで、握飯に煮〆め、「スルミ」(どじょう等を切り叩いて白米粉とねり合せたいわゆる肉団子)に酒を携え、近親者が近くの山に半日を暮す。この日伊勢詣りをした人々のみで生きた魚をあげ皇太神を拝す。この日はすでに農繁期に入っているから休み日は少なかった。
八日は釈迦降誕日で各家お寺詣りをなし、心から感恩報謝の誠をいたし礼拝すると共に、各家の仏前にも、それぞれ供物をなし墓参していた。当日は蓬餅、または赤飯の精進料理である。農繁であるから朝仕事程度若しくは午後休んでいた。
八十八夜は蓬餅をついて神前に供え、疫病除けの祈祷をした。この夜蓬餅を食べないと中風にかゝる等色々あった。
この月に種籾を苗代にまき終ると、余った分を炒米にした。もちろん余分を見込んでおくのである。
芽の生えた種籾を床から取り出し、田植組が各戸別に分類して持ち帰り、各自の苗代に種播きをする。そこで苗床の「タナゲ」が空になるから、各戸の責任者が苗床を片付ける。これを床外しという。作神様に種の芽生を感謝する意味で神酒(にごり酒)を汲みかわし、川魚で簡単に祝うたのである。
苗代に種をまき終った余分なもみを鍋で炒り、水をとり臼でつき精白に仕上げる。これが「エレゴメ」で、甘味が強く、女性や子供に喜ばれ、甘酒の材料にもされたのである。従って菓子代りにもなり、子供らに五勺位紙袋に入れて与えると一日の間食には十分であり、これで酒を作るとうまいと伝えられていた。なお隣り近所に配る慣しがあった。
五 五月の行事
上旬、大小豆播種・陸稲播種・瓜類菜豆の播種・粟稗播種・桑樹結束解除・里芋長芋下種・間引・追肥・除草等、苗代の手入・果樹の摘花・山林地均し造林・馬の種付。中旬、苗代の間引・除草・害虫駆除・甘藍仮移植・本田鋤返し・用排水の整備・蚕具蚕室消毒整理・桑樹の定植。下旬、馬鈴薯の中耕追肥・本田施肥・荒掻・肥料配合・春蚕掃立・青刈大豆の掻種・水田畦畔塗等忙しさ日ごとに増す。
1 五月の節句
旧暦の五日は男の節句で端午の節句といい、武者人形を飾り幟を立て男児の立身出世を祈ったのである。近年は二三の旧家において武者人形を飾るのみで全く廃れたが、幟の代りに鯉幟を吊し、男児の鯉がどんな急流でも平気で勢よく昇ることが出来るように、世の中の障碍を乗り越え、立身出世を願う意味で行われるようになった。鯉幟は五月一日から五日になって終るのである。
この日は、鬼が嶽から下りて来て人間の住家を荒し廻るので、前日の夕方家の入口・窓口・戸障子等屋外に面した凡ての出入ロに、鬼にとっては一番毒になる蓬菖蒲を軒端にさし、かつて人間が悪鬼に追われたとき蓬の中に潜んで一命が助かった故事により鬼の進入を防ぎ、また菖蒲湯にひたって身の迫害から逃れたともいうことと、かい縁の者が非常に嫌い。(かい縁が妙齢の婦人を襲うて危害を加えるので)人には薬になる菖蒲や蓬を軒にさして家中に入るのを防ぎ、菖蒲湯に浴してかい縁よりのがれると共に身の健康を保つ意味合で、古くから今日に至るまで引続き行われ来たったものである。いずれも共に四日の夕に行われていた。従って夕食は酒肴による晴食となり、家族一同身心を清浄にして五日を迎えることになる。
また、なお武を競う意味で菖蒲玉とて菖蒲を手ごろの糸で束ね、糸の一端を持ち互いに叩き合い引かけ合いをして武を練る勇壮な遊びも行われた。これも四日の夕方に行われていた。
この日「ところ」をたべなければ蛆になるといい伝えられている。
新妻のあるものは、この日朝食後里帰りをしてお礼を述べ、ついで媒妁人にも廻って御礼をしてもいた。
五日には、朝食に餅をつき、神仏にものし餅を切餅として供え、家族も切餅として食べていた。大豆の煮豆を入れてのし餅にしたり、蓬を入れてのし餅にしたり、白切餅と共にきなこを作って食べることが多かった。
当日は駒形神社の祭礼で古くから蒼前詣りチャグチャグ馬コの行事があり、近郷より馬を着飾らせて鈴の音も勇ましく、朝霧を踏んで馬の安全を祈っていた。馬産南部にふさわしい光景を呈していた。この日絵馬を買い求めて各家の厩にかけるを例としていた。この日田植最中でも人馬共に休みいたわり、馬には好きな青草や精のつく豆をやる風があった。
なお、当日は虫祭り、疫病祭りがあった。
2 田植え
田植は農家で最も重大な作業であり、同時に重要な祭りが伴っていた。初日を「はつたえ」といって、赤飯・神酒を家の土間・田の畦畔で田の神様にあげて祈念をした。田植えの「ゆい」の日取りが決ると、前日からカナエ(その日に使用する苗を前日取って準備しておくこと)トリをやって早朝から田植えをしたのである。
夜明けとともに田圃に下り、夕方手元が見えるまで田植えを続行することもあった。従って食事の数も、朝食・午前の間食・昼食・午後の小昼・夕食と五回食べるのが常例となっていた。不断は粟・麦・稗・干した切り大根等をカデにしていたが田植中はカデを加えず、白米飯を用い、魚類をつかい、その他色々の御馳走を拵え、毎日自家用酒も供された。田植えには汚れを忌み、身心を清めて田の神を祭った。田植始めには赤飯をたいて握飯となし朴の葉にのせ、田の神に供え、また早乙女に振舞い隣り近所にも配っていた。
田植えには早朝の作業にもかかわらず「朝ながし」がなく、その代り朝食は割合に早く現場に運ばれる。朝食は三つ組で白米飯・汁・漬物であった。
田植え初日の小昼には、小豆飯のおにぎりに漬物で男女とも大きめなものを二箇苑くはられる。昼食には、家が近ければ家に来、遠いか十人役以上の田であれは畦や土堤を利用し、すわる場所は各自の蓑をしくことは朝食・小昼の場合と同じであった。昼食の賄は五つ組で、小豆飯・汁・漬物・焼魚・煮付となっており、そのうち煮つけは田植特有の大根・蕗・牛蒡・人蔘・豆腐を塞の目形に切り、それらにさゝげ豆・糸昆布その他山菜を入れて煮〆たもので野菜の複雑な味がして皆に喜ばれる煮物であった。さらに大豆の塩煮と甘酒が出た。午後は小昼がなく、夕方は早めに終ることが立前になっており、どんなに遅れても五時ごろには田からあがり夕食によばれた。
夕食は座敷でも行われたが、着替えが出来易い処はまだしも、遠い場合はそのままの服装で庭に莚をしいて夕食を御馳走になっている。夕食は五つ組で魚をつけ、酒は朝顔型の茶碗に一杯が普通とされていたけれどもその量はその家の主人次第であった。なおこのとき、早乙女達には「腰やみ銭」といって規定のほかにいくらかのお金をくれていた。
なお、請負制・組田植えは申合せによって不定であった。
3 さなぶり祝
森口多里氏はサナブリの語源について、サナブリのサは田の神のことで、この田の神が里へおりてこられるのを迎える稲作儀礼がサオリであり、田植えが終ってサが里を去って高いところへお送りする儀礼がサノボリで、このサノボリが東北地方ではなまってサナブリになったという。今では、サナブリを田植終了後の骨休みを兼ねた祝宴に変ってしまった。
田植組の田植えが終ると、その組の全員家族が集合して慰労を兼ね、思い出を語る祝宴、つまりサナブリの祝が開かれ、宿は順番か本家が定宿であったりした。ユイは十戸前後であるから数十人の集まりは珍しくない。酒肴を神前に捧げ、一日がかりで御馳走を調理し、盛大に祝宴が行われた。出される物には、小豆餅・ゴマ餅・クルミ餅、川魚など盛り沢山であった。
娘は里に帰り親の機嫌を伺い、神社にお参りをし、修養等二、三日を有意義に暮した。
4 岩手山神社大祭
岩手山は本県第一の高山で、頂上に岩手山神社の本社があり、古来より陸奥の霊山として知られている。その山開きは七月で、二十七日は大祭で公休日であった。山麓三方の登山口には遥拝所として新山社や篭堂があり、老若男女酒肴を持参して、裾野の新山社に集合して祝うたのである。明治以前は神仏混淆で、山伏(修験道)の先導でなければ登れず、女人禁制の厳しい山であったから、新山社境内の篭堂には一週間前から御山かけが詰めて寝泊りし、精進潔斎に励んでおり、二十七日早旦頂上に登り、日の出を拝む慣習であった。昼ごろにはすでに下山者もあり、麓の新山社は参拝する人々の群衆でにぎわった。またここまで乗馬で参詣するものもあり、郷内外の参詣者が多く、休日として祝っていた。ここを訪れた登山者や参詣者によって持参された五穀成就の祈祷札と山上の這松の梢は隣家知人にくばられ、田圃や畠のほとりに細竹に結んで立てられ、農作物の護符として秋まで大切にされていた。
六 六月の行事
旧一日は向(むけ)(脱皮)節句と称し休日となっていた。この日、桑の樹の下に行くと自分の脱皮(むけがら)が眼に見えることがある。それを見た人はその年のうちに死ぬから桑の木の下には行ってはならないとか、またこの日桑の木の下で蛇が脱皮するとかいわれてた。向はムケルで脱皮を意味したものであろう。蝉や蛇のムケガラを祖先の人々がみつめて、古いからを残して新しく生れ変ったことを人間におきかえ、人間もこの日は皮がむけると考えたらしい。この日をさかいに漸次暑さが増してくるので、身体上重要な危険を感じ、休日として歯がためを実施したものであろう。すなわち、正月から保存しておいた凍餅の干餅を神仏にも捧げ、酒肴で食べ祝うたのである。また乾餅を鬼の頭にたとえ歯堅めに一家揃ってこれをかじり食する風もあった。この干餅や寒晒し粉は、土用中貴重食品として扱われ、病人(下痢)にもお粥にして用いていた。冷凍後の乾燥であるから、殺菌の食品と考れられたのであろう。干餅を包んだ藁は火防けと称し屋根にあげる慣習も古い。延享四年(1747年)、また天明(1781年)のころにも記録が散見している。
十五日熊野神社の祭典で、前夜より夜宮(よみや)があり、おそくまでさんさ踊りを踊る。赤飯にお煮〆を作り家内中休んで参拝をしている。
二十三日には地蔵様の御縁日で休み。妊婦その他盛岡市内外の各地蔵様に参詣をしていた。途上三々五々一張羅を着飾った婦人の群にあうのであった。この日小豆飯をたいて仏前に供え家族も精進料理をつくって祝した。
六月の上旬、茄子・甘藍の定植・水田代掻・水稲秧開始・麦黒穂抜取・果樹摘果薬剤撒布・抜草。中旬、挿秧・苗代跡作・植直し・二毛作麦の刈取・果樹袋かけ。下旬、夏秋蚕用桑樹施肥・蚕室消毒・偽瓢虫駆除・春蚕上簇・水田一番除草・早生大麦刈取・馬鈴薯蔬菜類の中耕除草・粟稗の中耕除草等々愈々仕事が本格的になってくる。
六月は土用の月で酷暑の季節、夏まけをせぬように「土用の牛の日に鰻を食べると夏痩せしない」といわれていた。
七 七月の行事
上旬、大麦刈取・収繭・春蚕用刈桑採直・桑園耕鋤施肥・水田二番除草・桑樹の病害虫駆除・養蚕視察・中旬、大小豆中耕除草・夏蚕掃立・小麦燕麦刈取・結球白菜及大根播取・茄子甘藍追肥・馬鈴薯収穫・蕎麦播種・水田三番除草・山林刈払・千葉式曲取伏込・馬糧刈。下旬、粟稗中耕・秋蚕用桑園施肥・水田排水溝準備・大麦脱穀・埋根仕立及び中刈土寄せ・穀類害虫駆除・千葉式土寄施肥等々眼が廻る。
旧暦の七日は七夕で休み。といっても盆を迎える準備で男は仏壇・墓地の清掃・法会棚・棚敷・抹香材料の刈取り灯篭柱立等、女は盆用の飯米調製・衣服の準備・来客宿泊の接待準備・食品の点検で終日休む暇がない。未明に起床して墓掃除をなし、また位牌その他の仏具の清掃を初め石油を使用するランプの器具の清掃をした。赤飯か小豆ばっとか、そうめんか蕎麦切りで、朝食昼食夕食共に晴食にして魚断ち精進料理であった。この日は水泳七回、食事七度するほどの酷暑であれば豊作であるとしていた。何事も七回繰返すことをよいことにしていた。昼食には「オヒナガ」と称して素麺を食するのは八岐の大蛇の「アバラボネ」を食うの意味であると、当日を期して井戸掃除を行う処が多かった。
七夕祭り、いわゆる星祭りは六日の夕方から子供らが群をなし、農事に関係した幸よい歌を歌い各戸を訪れた。各家においては一銭から五銭位までのいくらかの礼を出していた。
盂蘭盆「オホゲェ」共に併せ行われるのは十三日から十五日までで、各戸においては施餓鬼棚を作り「ガツキ」のこもを敷き、前後の垂れをば和布であみ、棚の四周は、すゝき・桔梗・女郎花等の草花を配し、種々の果物を吊して棚を飾り、その上に位牌を安置し、赤飯・煮〆め・油揚・こん蒻・豆腐・茄子等の野菜に大豆の塩煮・青林檎・金瓜等を蓮の葉にのせて日々礼拝をした。この間連日家族連れだって墓参し前述の赤飯を初め御線香・茶・その他の供物をささげ灯をつけて心から拝んだのである。墓に焚火をすることはもちろん各自家の前においても実施をした。十四、五日は親類知己の仏様を拝み、互いに各家庭を訪問をした。新仏のある家は受けるだけで廻らない。別に周忌に当る家々にては灯篭木をたて灯をつけた。
十六日は家族全員の休養日で盆の中心日ともなっていた。その家で出生したものが生家に来て、神仏を拝み、祖先の霊に感謝するのが普通であるが、中年以上で家事の都合、または遠方の場合は、その子か孫を代理に墓参させるので出入の客の多い日であった。従って訪客には、相応の酒食を準備してもてなし、泊り客にも同様にした。主として本村は仏教徒が多いので四足二足を断って終日精進料理を用いた。この日は盆中最高の御馳走であった。戸主は寺参りをするのが例となっていた。家宝什器を家族や一族に披露するのもこの日であった。この日は一月十六日と共に地獄の釜の蓋もあく日で一家揃っての休日であった。この日仏送りをするのであるが、仏壇に供えた赤飯花等をこもにくるみ昆布で結んで川に納め流したのである。お寺においては灯篭流しいわゆる舟コ流しをなし、念仏講では念仏をして拝んだのである。またこの日は歌にも「盆の十六日正月がら待ずだ」とあるように、平素娯楽機関の少ない農村にとっては、食べることの楽しみを除いては全く年に一度の待ちこがれた日であった。夕食もそこそこ太鼓の音に文字通り誘われて家を飛び出し、盆の十六日今夜ばかりと踊りくるうて夜をあかしたのである。このさんさ踊りは十四日から十八日まで毎夜一同広場に集って行われたのである。
なお十四日から十六日までは盆の休日で、盆中の献立は赤飯と煮〆、またはそうめんが主で精進料理の凡てをつくし晴食が続く。
十七日には若夫婦の舅殿訪問、酒一升に塩釜二本持参をした。
二十日は二十日盆と称して休み日であった。
この月の二百十日を風祭りと称して休日であった。
1 盆の行事
第四編第二章第一節八の盆行事で述べたごとく、この行事は印度から、支那を経て我が国に伝えられている間に、いつしか崇祖の念に加えるのに有縁無縁を問わず亡者を浮ばせる、すなわち餓鬼に施す、換言すれば死者に施すという意味が含まれるようになり、さらに貧者に施すというところまで進んだのである。そしてこの際に僧を呼んで読経してもらうのは、僧が百日安居という夏の修行を経たばかりで、最も清浄な体であるから、それに経を読んで貰って経の功徳によって亡者を供養するのが最も利目があるというわけである。
昔は着物と寝床と食物を供えて供養したと伝えられる。併し、近来は大体食物のみとなっている。この供物は土地の事情や宗派によって異るが、要するに祖先の好んだもの、季節のもの等を飾るようである。しかし別にこれを供えねばならないということはないわけで、この際茄子に足をつけたりして飾るのは、祖先が馬に乗って来ると考えられていたことに起因する。また迎火や提灯の火は祖先の魂の来る途を明るくしようとする旧来の慣習である。一体餓鬼道におちるということは、その人の行いが悪かったために、そこに落ちてからは如何に目前に珍味がもられていても、如何に空腹であってもこれを食うことが出来ないという苦患を受けているということである。だから盆の読経の功徳によってこれに食べたいものを与えようというのである。盆の行事は十三日に始まり、当日迎火を焚き、仏前にローソクを点じ、供物を捧じて準備をなし十四日は前の日の祭り、十五日は僧を招いて本当の供養、十六日は送り火を焚いて祖先の霊の帰るのを送るのである。この際仏前に供えた食物は、仏が食うことになっているので、行事がすんでも食わぬのが建前である。
以上は仏教の方の盆に対する見方であるが、これに対して起源が不明であるが日本的なものがある。
余程古くから我が国の間には、夏が終って秋が来ると祭りを行なって、その年中に自分達の受けた凡ての汚れや罪科を洗い流し、新しい生活を始めようとする信仰が行われており、そのために我が国において「みそぎ」あるいは「はらい」等の祭りを行えばそれによって汚罪は消滅するものと考えていたのである。だから古えの「みそぎ」や「はらい」は多く川の辺りで行われたのであるが、これは何物かにその汚れや罪を転化させて、それを川に流して綺麗になろうという意味である。すなわちこれが形代、または人形(ひとがた)と称されるものである。それには主として瓜類が用いられ、現に盆には瓜や茄子を流すというのがその当時からの慣習である。なお施餓鬼棚は仏壇ではなくて、昔は社に似せて作ったもので、地方によっては盆を生(いき)盆と呼んでいるところもあるが、これは昔、親、または親に当る人、目上の人などのもとに、如何に遠い所に居ても、盆には必ず帰ってその恩を謝したものである。この際御礼を述べるのは、親やお世話になった人の生きた魂に対してなすのである。そこで生盆、またはおめでたごとといったものである。我が国では昔から正月と盆には必ずこのおめでたごとをやった慣習があったので、これが今に伝わって「やぶ入り」となり、盆礼、盆祝儀となったのである。要するに我国には古来こうした仕来りがあったところへ、仏教が伝来し、その後お盆の信仰と合して今日のようになった。
八 八月の行事
上旬、葱本植・堆肥製造・小麦脱穀・夏蚕収繭・秋蚕掃立。中旬、大根間引施肥中耕・水田落水・農事視察・果樹の収穫。下旬、水田稗抜・桑苗圃中耕除草・晩秋蚕掃立・秋蚕収繭・果樹袋取・秋蒔蔬菜紫雲英播種・漬菜類の播種。何しても八月の暑さだ。ちょっと息抜きの体。
八朔の朔日と称して神に供物をして拝み休日としていた。八朔(初作)と田の実の一日とも称し、特別な田に速成の品種を植え、その初穂(初米)をあげ、また精白にし甘酒と共に神前に感謝をするいわゆる神嘗祭であった。
またこの日は八幡様の祭典で家内一同打連れて参拝をした。
十五日は田の神を祭り、夜は「月々に見る月は多けれど月見る月は此月の月」と歌にもうたわれているように秋の澄み切った空にかかる十五夜の明月に対して、煎米・枝豆・栗・初芋等と供えて搗臼を伏せ、箕をおきローソクを立てゝ家族一同礼拝をした。
この日は朝仕事程度で休日であった。
九 九月の行事
上旬、大小麦の種選・麦奴(ばくと)の予防・稗の刈取・早生水稲刈取・青刈大豆収穫・大豆葉取生掛乾燥・堆肥製造。中旬、麦の播種・粟の収穫・水稲の刈取生掛乾燥。下旬、蕎麦の刈取・晩秋蚕の収繭・山林間伐・水稲の刈取並に生掛乾燥・桑苗圃の中耕・除草。やれ腰の痛いこと。
九日は岩手山の閉山で登山を禁ずる日となっていた。
この月の九日・十九日・二十九日を初九日・中九日・終九日と称して、餅を搗いて稲荷神社に供え、仕事を休んでたべたのである。まずその年の新米で餅をつき、神に献じて年中の御恩に対して謝意を表し、後これまで農事に従事した人々に九日餅と称して初・中・終の中の一日を期して御馳走をしたのである。
十三日は芋明月である。お月様に芋の料理を供え、家族一同これを戴きながら、団欒の一夜を送る。
十六日は秋の農神様のお祭りである。この日農神様は、里の仕事が一応終ったことを見極めて、お帰りになるので、お団子を作って農神様に供えお送りしていた。九月に出来なかった家では一ヵ月おくれの十月十六日にこの行事をやるのであった。
二十九日は刈上祝いと称し、稲荷様や田の神様に餅を捧げ、これを一般に九日餅とも称していた。
秋の彼岸は大抵この月の中に当り、行事は春の彼岸と同じである。
十 十月の行事
上旬、水稲刈取並に生掛乾燥・緑肥作物の排水溝設備・堆肥製造。中旬、二毛作麦播種・大豆収穫。下旬、麦の土入・稲の脱穀・蔬菜規の収穫・桑苗木の掘取仮植・沢庵漬用大根収穫等々寸分のゆるみない生活が続いたのである。
十月は金比羅様の御縁日で毎戸あげものをし、神酒を供えてお祝をした。殊に筏流し、木流し等に従う者は守護神として餅を供え御神酒を奉って盛大にお祝いをしたと伝えられている。
二十日は恵比寿といって一年中の最も目出度い御祝であるといって午後から休日とし、生魚を供え山海の珍味を集めて調理をなし膳部を整え神酒・神灯を献じて五穀豊穣・商売繁昌を祈願すると共に家族一同下僕女中に至るまで飲めよ歌えよの恵比寿祝を祝うたのである。この日たくさんの人々に御馳走をするので金がかゝるといっていた。
またこの月中に、秋仕舞と称し、親類知人を招待して餅をつき祝宴を催した。
十一 十一月の行事
上旬、大豆脱穀・蔬菜収穫・米の調製・苗代耕鋤施肥。中旬、大根収穫・小作米納入・屋外整頓・防寒設備・稲架(かけ)材料整理。下旬、堆肥製造等々。
二十二日から一週間お七夜と称して魚をたち精進がはじまる。
二十三日は二十三夜といって、この夜のお月様に男のみの手で作った「おすとぎ」と御神酒とを供えて拝む。二十三夜といって月を拝むは一年中の正月・五月・九月・十一月の四回としていた。
二十四日は御太子様祭といって小豆粥に団子を入れ、箸木(桃の木)で作った長い箸を三本つけてお供えをした。これを太子団子という。太子様という神様は至って家貧しく、その上子沢山故、食事のときは遠くの方に居る子供にも届くように長い箸を使用したる由。
十一月の行事食中に冬至粥がある。小豆混入の米粥を煮て食べ、この冬至粥を食べると中風にならないでいつまでも健康であると伝えられていた。
十二 十二月の行事
上旬、田畑の秋耕・果樹の剪定。中旬、藁細工・薪材伐採着手・ 農蚕具の整理・収支総計算・青年夜学会の開催等々冬篭りの仕度と 来年に備える準備をしたのである。
十二月の催しは連日故休み日ではない。祭神によって食物の種類献立が興るが白米粉を使用したおすどきをあげる習慣であった。三日は不動様の御年越。五日恵比寿といって頭尾のついた魚を必ず上げ、大黒様もお呼びするというので御膳を二人分用意して供えた。八日は薬師様(目の神)湯殿山。九日は大黒様の御年越で二股大根と穀物と豆料理を上げる。大黒様は手まめ足まめの生ずるのを苦にもせず骨身惜しまず働いたので、金銀財宝が山をなし裕福に暮した神様である。特に豆類を上げれば福が授かるというのは手に豆が出来るほど働けとの意味である。十日は金比羅様で「しとぎ」をあげ、十二日は山の神様で、屋根葺や桶屋は小豆餅を十二箇供え、妊婦がこれを食えば安産するという。十三日は虚空蔵様で、小豆飯に料理を添えて膳を上げ、十四日は阿弥陀様で盛岡の教浄寺へ詣ずる者が多かった。十五日は八幡様で共に「しとぎ」を上げ、十六日はおしら様といって生の白団子十六粒を献げ、おしら団子といって小豆団子を食うを常としていた。十七日は観音様、十八日は秋葉山、十九日は稲荷様と馬頭観音様(特に馬喰がお祝をする)、二十日は疫病神の御年越、この日はお膳を二人前にし、その家の入口に供える所もあった。二十三日は地蔵様、二十五日は天神様(手工芸品を奉納すれば上手になるといわれている神様)の御年越で諸神々様の御年越が終る。寒明けの日は節分である。昔は上下(かみしも)を着用して福は内鬼は外と声勇ましく豆をまいた。二十六、七日の両日は煤掃きといって家中の大掃除をして正月を迎える。煤掃後、その家の主人自ら豆を煎り神前にさゝげ、明の方から「天打ち地打ち福は内鬼は外、鬼の目玉ぶっつぶせ」といって豆をまく風があったが、自然にこれが節分に代るようになる。家内の者は一度に握った豆の数が自分の年と同様であれば福が来、また自分の年と同様拾い集めて息災を祈ったのである。また炉の灰をきれいにかきならし、その上に豆を十二だけ並べて十二ヵ月の月になぞらえ大豆が黒く焦げれば暗、くすぶれば雨、はじければその月は風となる等天気の予測をする風習もあった。二十八、九日は餅搗きに忙しく、種類は糯米・粉餅・粟餅・小豆餅・蓬餅、形も鏡餅、供えの重ね餅・のし餅であった。三十日には松を神棚に飾り年縄を吊し、神酒・神灯はもちろん心づくしの御馳走を上げて幸多い年を迎えようと祖霊と共に迎えた神前に額ずくのであった。魚はお頭付の焼物吸物付据膳で年神様に供え拝むのである。年越そばを食えば年中小遣銭に不自由しないといって蕎麦を食う家もあった。年越のときには昔切り取り御免といって各自手ごろの門松をきりとって一斉に門松を立てたものであった。
この門松は祖霊の寄り木であったろう。家の内外を清めて祖霊を眠らずに待ち、迎えた「みたま」の家は皆謹んで新年の挨拶をかわす。言葉も行いも丁寧であったが、現在は形式的な神参りだけが残っている。
なお農事労働慣行については、第十編教育の変遷、第五章、第二節俗言集を参照せられたい。
第四節 凶作
古記によると、仁徳天皇の三年天下の百姓不作に困窮したために、詔して三年の課役を免じたのが、わが国最初に見る凶饉であるという。ついで欽明天皇の二十八年(567年)には、これまた諸国大いに飢えて人々相食むの惨状を呈し、国郡の貯穀を出してこれを救助し、清和天皇の貞観十五年(873年)、陸奥の国一体が凶作となり、その後、永保・天永・元永・長承・寿永・正嘉・天授・応永・文安・文明・永正・大永・天文・天正等は、いずれも全国にわたっての大飢饉があり、本村もまたその惨禍を免れなかったものと思われる。
一口に飢饉とか飢渇というが、米・麦・粟・稗・豆の五穀を合した収穫が平年作に比較して飢饉とか飢渇とか凶作とかいっている。
南部藩の凶作中、最も深刻を極めたのは、元禄・宝暦・天明・天保の四大飢饉であった。当時の交通は今日のごとくならず、封建制の厳しい中で、各藩は互に殻の中にとじこもり、むしろ隣国の惨禍を機として、自国を有利に導かんとする傾向にあったので、物資の交易は思うにまかせず、草木の根をかじり、家畜を屠りつくし、壁にぬりこめた藁を洗い出し、これを煮て生命をつなぎ、甚しきに至っては人肉を食し食糧が尽きても他より求めることも出来ず、多くの金銭を貯えておっても、金を抱いて餓死を待つより外はなかった。まして金の貯えもなく、一握りの穀物を持たない者は、その上悪疫にかかり、まことに惨怛たるものであった。豪農は土蔵をつくって五穀をたくわえ飢饉に備えたが、一般の農民にはその余裕がなかった。従って一粒の穀物といえども無駄にすることを絶対に許されず、粗末にすれば目がつぶれるとか、穀菩薩様と尊称し、穀物をば神聖視していた。若し残飯が生じた時は乾飯(ほしい)にして貯蔵したりした。
そのころ飢饉がなぜ発生したか起因の前提条件は、旱魃・大雨・霖雨・洪水・大風・気候不順・蝗害・噴火等があげられている。これが今も昔も同じである。昔はこれら諸原因の外に藩領主からの年貢の取り立てがきびしく、凶年といえども容赦されることが少なかった。このようなときでも藩主は早稲を植えよ。食糧を節約せよ。祝儀のときでも一汁三菜にとどめよ。山菜を採ってたくわえよ。穀物を他領に出すな。他領の人を入国させるな。濁り酒を禁じ、飼い犬を戒め、死体はみぐるしいから埋めろ等消極策のみ。一方では、幕府にはばかって餓死者の数を半減して報告したり、天保年間には藩主利済(ただ)はぜいたくした上に津志田に遊郭を造り、重税を課したりしている。その上農民に対して食えないから訴え出たり、他領へ移住したりしてはならぬと厳禁している。
このような惨害をこうむるのはいつでも直接米を作る百姓であった。権力の前には常に無力の人達であった。しかし、この無力の百姓も積極的には百姓一揆を起して抵抗し、消極的には「子おろし、まびき」が行われた。従って実働人口が減退し、荒地が増大し、次第に藩の財政が窮迫していった。森博士は幕藩体制の崩壊原因は飢饉と間引きと百姓一揆の三事件の占める比重が相当に大きいと述べている。
明治になって、二年・三十三年・三十五年・三十八年、大正二年、昭和九年・十六年・二十年の数回に亘って災を受けている。だが、以前のような連年的冷害はなく、被害の程度も次第に軽微になってきた。それは廃藩置県によって日本全体の立場に立った政治力と、農業技術の進歩に化学肥料の発達や耐寒品種の育成等近代科学がもたらした結果に外ならない。わけても大正の末期に育成された陸奥百三十二号や、藤坂四・五号等の耐寒品種の普及と、昭和二十三年ごろから普及され始めた保温折衷苗代とは、宿命的冷害をくいとめるために重要な役割を果した。
なお、南部藩における凶作についての悲惨な記録が『南部史要』『宝暦飢饉記』、『東遊記』、『地行記』等、幾多詳細に伝えていることを添加しておく。
一 元祿の凶作
元禄元年(1688年)半作、同二年不作、同三年飢饉、同五年半作、同七年凶作、同八年にいたって稀有の大凶作、同九年凶作、以上のごとく連続の気候不順のため、農作物は殆ど稔らず、青立となり、農民は食糧に窮乏し、餓死する者が多かった。ことに元禄八年は、当初の気温もよく作物も稍々並みのごとくみえたが、七月下旬より急激に気温が低下し、同月二十三日には、丁度穂が花盛りにもかかわらず、大暴風雨がおこり、田畑とも作物を吹き散らし、一切稔りをみることが出来ず、多くの餓死者を出した。この年の春、藩においては他領より種籾を買い、農民に貸与し、窮民に対しては、二月米、五月麦、七月味噌を給与している。大坊直治氏の調査によれば、御助米として、一日男一人に二合、女一合、十四歳以下八歳以上の男女に各一合を与えたが、後に男には一合二勺、女には八勺、以下五勺ずつを給与したとある。
元禄八年十一月十五日第三十世行信は次のように幕府に届出ている。
私の領内夏中冷えて、小袖を着用した程で、土用中雨降り続き、北風強く、七月下旬に霜が降り、稲実のらず、例年は三斗七升俵十四万俵の処、漸く四万俵。このようでは、来年まで飯料続きかね心元なく存じている。ことに領内広く、人数も多く、地方によっては皆無の所があり当惑する始末。以上。
十一月二十五日幕府、南部藩の飢饉をきゝ、公に対して、来春の参覲を免じている。
十二月一日行信は次のごとく発令をする。
一、当年は思いの外の不作で、毎年の収穫米の三が一程である。諸民は、来春飯米に不足をきたし、渇命するのではないかと心元なく思召され、先頃公儀へも報告をしている。
一、上の通りではあるが、文武両道及び武具・馬具等仰せの通り油断のないようにする事。
一、先達の仰せの通り、衣類等在来りのものを着用し、住居と共に新規の美麗一切無用の事。
一、住居は仮令(たとい)古くとも繕い迄にとどめ、作事等は一切相ならぬ。
一、親類縁者其外諸傍輩の会合、たとえ祝儀がましい事でも、一汁三菜とし、用事のない会合は無用。
一、歳暮・年頭祝には肴など相止めて訪問のみとし、不断の訪問・贈答も堅く無用の事。
以下略。
十二月十日領内に令し、犬を養ってはならぬ。犬餓えれば餓死者を食う。その味よしとして害を人に及ぼさん事を恐ると藩公がいう。
元禄九年一月二十一日領内代官に対し、窮民が徒党がましい事をしないように警告し、尚伊勢参宮などと称し、大勢で農民が他領に出て行くことをも禁止している。
元禄十二年三月二十三日、公、近年不作続きで農民が困窮しているのを憐み、岩手・志和・稗貫・和賀四郡に令して年貢米を前年より一分七厘六毛を減じ、橋梁米、御鳥見米を免じ、また田地仕付米の貸付利子についても従来三割であったものを一割半に減じ、全体で従来に比べ約三割減となる。
元禄十三年五月十二日窮民救恤のため領内に令して滞納の租税を免ずる。尚租税皆納者に対しては、当年貸付米の利子を免ずることとしている。
元禄十五年、気候不順で、救助する窮民の数五万一千二百五十三人に上り、餓死者二万六千人であった。この年領内に令して造酒を禁じている。
大坊直治氏の調査によると、この年の四月、岩手郡小姓が嶽(姫神山)に笹が実りあたかも麦の如し。貧民争いとる者一日に三千余人、一人の所得二斗以上に及んでいる。ここ連年凶作が相続いたので飢餓に苦しみそれを食するようになった。市中売買一升銭十三文。藩主はこれを幕府に献じてもいる。川前元村からも採取に行ったことが古記録に見えると。
二 宝暦の凶作
宝暦飢饉記に、宝暦五年(1755年)十二月二十八日より報恩寺と久昌寺において粥施行を始めた処、飢人共両寺にかけ集る。渡されていた札を持参して昼八ツ(二時)時支給されている。べんじぇ屋に行って食い逃げするもの、家ごとに歩いて手当り次第盗み取る。誠に店々は油断がならない。盗む飢人殺さるるは幸福であると悪口をきく。遠方の者御城下へ来たが、翌正月にはその数夥しく、銘々莚菰をにない椀、または桶を持って門をかぞえて歩く。在に村の相応暮しよい所へ参り、何やかやと乞えども無慈悲なれば、その無慈悲なるものへ夜中押込み、あるいは放火をし、勝手気ままの行動である。在郷の者の話によれば、秋より五穀の類喰わず、草の実、あるいは虫を拾い食っていたが、冬になって食う物なく、干草の類を食っているから、疲れ衰え漸く鳥屋に飛上がってみるに、卵例年に比べてその数が少ない。例年であれば、寒中には獣の肉市に出商売する者があるのだが、当年は余計見えない。狩人も餓死故出ていないのだろうか。それともまた、在々で食物にし、盛岡へ余計みえないのか。ともかく例年より高価である。
この時、雫石十か村の人々が飢をしのぐため盛岡城下の非人小屋に行って食を得ようと、国道四十六号線の滝沢村境にある仁佐瀬橋と小岩井繋方面に通じる十字路の処まで来、力尽きてたおれた者多数。これら死者をとむらうために長山村の小林又右衛門という人が供養を兼ねた指導標をたてゝいるから、本村においても飢人がお助小屋で食を求めたであろう。
翌年五月一日餓死者処分についての令を下している。
先達度々仰せつけた通り、近在并に遠在共に此節飢渇に及び、山林・野道・山道・作場道の往還通りも、死者が数多くあるけれども、取片付をせず、そのままにしている。この事は他所への外聞は以の外の事で宜しくない。往還筋は申すに及ばず、山道・野道・作場道、山林等に餓死者があったならば、その場所へ埋めおき、屍等取乱す事のないよう申付つける。もちろん御城下近在は、先頃も度々仰付けたのであるが、今もって眼障りになるものがあるから、川流れが岡にあがっていたならば、その近辺に取上げ埋めおく様にする事。
この年の夏、領内疫病が大いに流行して死するもの餓死者と合せて六万余人、馬の斃れるもの二万余頭に達したという。秋の損毛高九万五千八百石に上る。かく再度の凶作について充分救済の途立ち難きを以って、各自大いに倹約するよう令を出している。
宝暦の飢饉後四年目の春に書いた橘南谿の『東遊記』に、
「東部津軽の荒凉なる誠に目もあてられぬ事ともなり(中略)。路傍に人のどくろ或は手の骨足の骨等あり。皆いと日かれたり(中略)。一里一里進み行く程に、其枯骨多く、朝の間は五つ見、昼過ぎては十四五も見え、其翌日は二三十も見られ、又翌々日は五六十もあり。猶此外路傍五六町程づつには塚の形ありて、いまだに草も繁らず、其上にあやしげなる塔婆に餓死の者幾百人埋葬などと書きたるあり。ころころとして枯骨そのままにあらはれたるは埋め残せるものと見ゆ。」
南谿が泊めてもらった宿(津軽)の者から、この村にあった事実として聞いた話がある。
「この近隣にも、家内追々餓死して、親一人むすこ一人のみになれり。隣家に行って言うよう。さてもお互いに空腹なる事なり。我家にも既に家内みなみな死に失せしに、御覧の如く今は男子一人のみ残れり。是も殊の外にかつえれば、二、三日の間には死すべし。とても死にゆくもの、いたずらにせんよりは、息ある間に打殺し、食せんとおもえとも、さすがに親の恩愛手ずから打殺すに忍びず、此故にそこもとに頼み申すなり。我子を打殺し給らば、その御礼には肉半分を贈り申すべしと。まことしやかに頼むにぞ、隣家の男大いによろこび、半分の肉をだに給らばいと安き事なりとて、やがて有合いける鉈を携え行って打ちけるに、さなきだに死せんとせしむすこ只一打に息たえぬ。かの頼みに行きし親、傍に見居たりしが、すかさず隣家の男をまさかりにてしたたかに打つ。隣家の男も餓え疲れたるところなれば、何をかもってたまるべき、そのまま息絶えたり。さて一計策を以って両人の肉を得たれば、早速に二人とも料理して塩漬けしおいて一月ばかりを凌げり。近所へは隣家のもの餓えたるあまり此の子を打殺し、喰わんとせしゆえに、仇を報ぜりと吹聴し、公然として二人の肉を甘んぜり。近所のもの、その姦計をにくめども、皆々うえつかれて、相互に親子兄弟と言えども打殺し喰う時節なれば、誰咎むるものもなかりしが、彼の男も遂に餓死し終れり。」
橘南谿の記事は、津軽藩、凶作時の悲惨極まるものであって、本村及び南部藩と関係がないように思われる。しかし、このとき東北地方全般にわたる凶作故、当時如何に惨状を極めたかこの記事で想像されるのである。そして、本村にはかかる惨怛たる記録が残されていないので、あえて記述することとした。
三 天明の凶作
「天明三年(1783年)大凶作。同四年は稍とれて、同五年は農作不熟、同六年は平年作、同七年不作、同八年は平年作、翌寛政元年(1789年)又また不作なり。中産以下は犬猫を殺して食い、馬の頭数大いに減少したと古記録にある。推して考うれば乞食になりて諸方を流浪しても腹を満たすに至らざるもの多々あり。分れ道の所に通行人を目当に風に吹き晒され、雨に濡れて哀みを乞う中冬季至り、遂に凍死せる者の為に寛政年度に供養塔を建てゝ供養せり。平蔵沢か鵜飼か不明なるも或る老爺、三歳の我が子を背負い、盛岡に出でて終日食物を乞いしも一物にも得当らず、黄昏時芦毛ヶ淵にさしかかれるに背なの子は餓を訴えて頻りに泣く。老爺今後の事を考え、如何にしても養育できずと断念し、此の子の四肢を縄にて縛り、芦毛ヶ淵に。鳴呼惨なる哉」と大坊直治氏は塵塚で述べている。
当時八戸の商人恵比須屋善六から、江戸田所町の本店井筒屋三郎兵衛に達した十一月十一日付の書状は次のようで、惨状あたかも見るがごとく、ここにその一部分のみをかかげることとする。
前略。食物は早速欠乏。在々において、蕨、野老(ところ)、葛等を掘って食べたから、幾千万と申す限りなき大山も忽ちに掘尽してしまう。葛蕨の粕あも、さゝめ(あも、さゝめというはこれらの屑をたたきさらし粉をとった粕をささめといい、細かなるをあもというよし)などと申すもの許り食事していたから、毒にあたり五体腫れ、大小便不通にして忽ちに相果て数知れず。当九月頃乞食共犬猫猿等を食べたという事をきいて肝を潰した。去月よりは、犬猫は勿論の事、牛馬を打殺し食べたのである。非人乞食等は眼前の犬猫を捕え、塩もつけず食う有様誠に鬼共というべく、おそろしとも何とも申上げようがない。それに在々は押込強盗夥しく起り、家内残らず縛りおき、穀物は申すに及ばず、家財奪い取り、其の上家を焼き、立退く等数多く、仲々書尽しがたし。毎日捕手見分の役人衆隙なく相廻ってはいるが、仲々力が及ばない。
難渋の者共の食事は、あも香煎(こうぜん)、松皮香煎、同餅、藁科香煎、豆から香煎、犬たで香煎、あざみの葉、以上の類ばかりを食物としている。さて餓死の者唯今国中半分余と相見え、来る正月より三・四月迄の内如何様になるか計り難し。乞食非人の往来市の如き有様である。この様子はたとえようがなく、顔色惟忰髪乱れ、眼星の如く色青くつかれ衰え、頬骨高く口尖り手足枯木の如く、からだ赤裸に菰まといし有様何と申しても更に人間とは見え申さず。右故に店々も差堅めている。戸口を開いておけば、非人共無体に押入食餌をあたえぬ内は立退き申さず、しかたなく白昼門戸を閉め、用事ある者は戸口より用事を足す有様である。施行等した時は、家内中立わたり世話をしたのであるが、我勝に前後を争い泣きさけび、老弱の者が貫った食物を奪い取り泣きさけぶ声身にしみ胸にこたえる。互に食を奪合い、溝へ落入り、半死半生の者数多く、食を奪合い、打合い、つかみ合い、互に傷を得、正に修羅道の有様を目前にする。火事は一夜に二ヶ処三ヶ処より出、焼死する者数多く、大熱地獄の炎に入り煙にむせび牛馬鶏犬の焼亡夥しい。世尊滅後二千八百年弥勒の出世迄は余程間があると承っているが、其期が来たのではないかと心細く少しも安心出来ず。よって御上様は飢渇の者を救ってはおられるが、打続く不熱損毛で御貯も悉く尽き、御施行も大海の一滴仲々届き申さず気の毒千万に存じている。
捨牛馬は禁止の第一であれども、此節悉く捨てている。これを乞食共引参り皮をはぎ鹿と申して売っている。馬と存じながら価安き故馬肉を買いよき鹿であると申している。値段は平生のオットセイ等のように目方で売買している。鹿に限らず、何品でも、食物は総て魚等の値段である。
御城下端の近在遠在の子供を悉く海川へ投込む者数知れず。又死に方にも色々あって、いさぎよいもの、未練なもの、又名を惜しむ者は独り深林の中へ行って首をしめ、或は淵川へ行って石を抱き沈む者数多く、計り難し。然れども子を捨てる者は沢山あれども、親を捨てるは今に承らず、最も殊勝の事と存じている。後略。
筆者不明なるも、遠野近在住人の日記『動転愁記』中、天明三年凶作の記の一節に、凶作時の農作物の収穫がよく表現されている。参考までに下記することとした。
一、田作はよい方の実り方で、一束六七合ずつ、青米・はぜ米・くびれ米多く、ひずひずと光り、米は一合の中に十四・五粒位なり。そのまま摺臼にてひけばくだけ米ばかり余計になる故、むし米にし、年貢として上納をする。
一、餅米は少し実りよく、一束について八・九合から一升位の出穀なり。田はこやし、手入れよきは、一粒なしの連立なり。不手入こやし不足は割合に実入よろし。
一、粟はよい方で一束三升位、中は二升位より六・七合迄、下畑は青立、例年の通り種栗を梨の木の枝等にかけておけば、冬の中に盗まれ、迷惑する者多し。
一、稗の実り上は、一束五・六升より一・二升位までで、悪しき方は青立、粟よりは少々実入宜し。凶作時には稗の実入り格別得をする。
一、大豆・小豆相応の実入り故、早(わ)せはいつもの位出穀あるも、飯料のかては大豆を用いる故、馬の飼料不足し、翌辰の春より死馬は余計にめだつ。小豆は凶年に多く使用する故店にも品切となる。
一、蕎麦は凶年に穀もよく、用い方も至極良好なり。
一、大根と蕪は上作で豊年と変りなく、地下へ貯えおきたる処、冬の中に盗み取られ、迷惑する者多し。
一、高きみ種なしの不作、一切出穂なしに終るもあり、諸作共に宝暦亥の凶作よりは少し実入りよろしく聞えるも、当年は箱根より東国辺り一体の不作の由、米穀高値の趣、先達て他国の穀物買方一粒も調えず帰宅をする。何程高値か図り知れず、町といわず、在は勿論畑になし得る場所に、大麦、菜種、蕪等蒔付け、諸士並に畑のない者は、屋敷内の庭の植木を掘り返して薪となし、その跡へ麦、蕪等ふり蒔き、専ら来春の助けに第一心がけ、遊山遊興は一切取やめとなる。
四 天保の凶作
天保四年(1833年)『天保癸己大飢饉萬事書記』
篠木村三右衛門 抜書
一、巳の二月二十日(二月二十日に吹く風を親風と称し、之によって一年間の気象を予測するものなりという。)の親風朝の内風なく、十時過ぎより北風大いに吹き渡り、その後南風となりて曇り、南東の巽風に変り烈しく吹募る。
一、巳の年春より毎日毎日巽風吹き曇りで雨ばかり毎日のように降り、時に北風吹くも格別なる洪水なし。
一、七月の盆中に稲穂少しもいでず誠の青盆なり。
一、此年腕豆殊の外上作なり。秋迄蔓枯れる事なく、二度花咲き実のりよし。
一、草木を始め、何物も急がぬ年なり。時ならずして所々に帰り花多し。きのこの類殊の外早く出、六月七月出盛最中なり。大秋に至りて茸いでず。
一、巳の年の二百十日は七月十九日で、稲一穂もいでず青作なり。
一、諸人皆大いに騒ぎ、五穀諸品俄に高値となる。貸し借りをつつしみ、只々飢渇を待つ居るなり。
一、九月十五日より御検見始まる。云々。
一、この年税割も高く、御年貢上納格別きびしく、更に催促され、百姓共大いに苦しむ事いうばかりなし。小百姓は逃亡、欠落等で生れ国を離れて非人乞食となり、妻子・老父を引き連れ、仙台を力(ちから)に行くものその数を知らず。居座る百姓は年貢に攻められ生きたる心地なし。
一、…命のあらん限りは諸袖乞い、遂に街道や藪に行倒れて死ぬる者多く、馬引などの小百姓等は、直々仙台へ行き、その馬を安く売払う。仙台に居住する知り合いの者を力となして、行く者昼夜やむ事なく、幾万人か相知れず。花巻往来毎日よろよろ歩く者恐しく、又、不便なる事いうばかりなし。津軽・八戸・秋田・越後から迄毎日毎日仙台を目当に行く者目にあてられぬ位なり。
一、巳の年十一月朔日より報恩寺に御救小屋が建つ。この小屋へ厨川通り山根玉か村(現在の滝沢村五大字)に燃料及び運搬を仰付られる。外の御官所よりも運搬ありたり。
一、扨、金銭何程所持していても、五穀、食べ物を売る者なく、在町ともの騒動おびたゞし。
一、諸物値段の事。
蕨の根巳の年八九月の頃一斗百文より百七十文位迄。しらげしだみ一斗八九月の頃七十二三文位、大根一本十文位より十四五文位迄、以下略す。
一、その他歩行出来る者は皆山に行き、山午蒡・あざみ・桔梗・野老・蕨の根・食べ得る物を掘り集め、山々に沢山の掘跡をのこす。最後に松の皮餅・野老製法・うるい・桔梗の根・大豆・小豆のから等の調理法あるも略す。
大坊直治氏編纂の天保の大飢饉『塵塚』から滝沢村分を抜書する。
一、青壮年は家を捨て、食を乞い諸方を彷徨し、幼老の力なきもののみ家に残る。或る家にては老爺唯一人となる。一升枡に塩を入れ、小川のほとりに座して水を飲み飲み塩をなめつつありしが、終にその川岸にてその儘往生を遂げ居たり。
一、蝦谷地にさゝやかなる小足を造り、そこに住める三人の家族あり、その長終日毎戸に食を乞い歩きしが、或日、篠木・土淵・上厨川方面を乞い歩きしも一物を得ずして耳取に進む。途中夕方寒風を冒して大久保にて土淵村某の大根畑より、生育良好なる大根を愛児に食わせたく思い見事なるもの三本をぬすみ家に持ち帰り煮沸して餓を凌ぐ。後日畑主の発見する所となりしも、盗人は誰なるか詳ならず。彼は霜四五度下り、雪のチラチラ降る日「ヤス」を携えて諸葛川に鮭突きの小屋をかける。畑主がこの小屋に住む者大根盗みなることをききつけ、この家に立寄り厳談せるも話まとまらず、赫努して全家族を「ヤス」にて突き殺せりという。
一、十歳程の少年毎戸に食を乞い、夕方とある家に一宿の恵みを乞う。主人これに応ぜずして追い返す。少年はやむなく滝沢小学校桑園の辺に夜を明さんと決心し、露の野に莚を被りて打ち伏せり。盛岡よりの用達人帰宅の途中、之を見れども、暮色既に迫り、又諸葛川の川縁には狼の群、草の陰より見えたれば、取急ぎ帰宅はしたものの、彼の少年を安じ、明くる日、少年の所に行きて見れば、少年は皆食われて、ボロの衣類のみ残存しありたり。
五 郷倉
我が国に備荒倉が出来たのは、慶安年間(1648-51年)であるが、地方に普及したのは享保(1716-36年)以後である。これには幕府のもの諸藩のもの二種があった。管理はもちろん領主が当る。主として籾・米・麦・粟・稗を等を貯蔵して凶荒に備えた。有名な元禄(1688-1704年)年間の飢饉に津軽藩では十万人の餓死者を出したが、これは古米を売払い、未だ新米を入れ替えぬ間に飢饉に襲われた結果で、遂に御倉を有しながら窮民を救えなかったと伝えられる。
民間には共同施設がなく、各自凶作に対処したが、富豪は土蔵をつくり、これに備えた。
多年の経験から稗の貯蔵は最もよく、精白した皮をも食用に供することが出来、殆ど無駄な部分がないといわれた。これが明治初年まで継続したのである。
明治六年(1873年)五日岩手県嶋権令の達しは、昨年九月備荒積立米高百石に付き、籾四石、当年より籾三石ずつ積立るように達しをしたのに積立済の届がなく不都合である。これは村のためであって、目前の利をはからず、凶荒時に苦しまぬ様、将来の備えが専一である。ついでは各区会所に、村ごとに区別して積立、封印は正副区長、並に村々正副戸長の立合に取はかるよう達しをしている。
その後凶作等あまりなく、また、凶作に遭遇しても救済施設が整い昔日のごとき痛傷を感じなかったから、何時しか真剣さを失い、終に解消され、また、倉庫もとりこわされることとなる。
昭和九年、東北の地、特に岩手県の県北地方は未曽有といわれる惨状で、この凶作の悲惨事に天皇陛下から御内帑金を賜わって恩賜郷倉組合を組織し、不幸な凶作に備えたのである。
本村内の組合は、大釜・篠木・大沢・鵜飼・元村・一本木・川前の七団体に分れ、各部落民殆どがこれに加入した。
規約については、大同小異なので、篠木郷倉組合のものを掲げる。
郷倉組合規約
第一条 本組合は篠木郷倉組合と称す。
第二条 本組合は隣保扶助の精神に基き、備荒の為穀類を積立て組合員に穀類の貸付をなすを以て目的とす。
第三条 本組合は大字篠木の区域に住所を有する農業者にして、本組合に加入したる者を以て組織し、事務所を大字篠木第八地割字荒屋十二番地におく。
第四条 本組合員は、毎年十二月迄に組合員一人籾一斗以上の標準を以て穀類を積立つる義務あるものとす。但し、稗・粟・蕎麦又は全員をもって換算納付するも妨げざるものとす。前項但書の換算率は毎年組合員の決議に依り之を定む。
第五条 郷倉には備荒の為少くとも籾五十石を貯蔵するものとす。
第六条 積立穀類は前条の限度を下るに至らざる範囲に於て之を組合員に対し貸付又は処分することを得。
第七条 次に掲ぐる場合に於ては前条の規定に拘らず組合会の決議に依り積立穀類を組合員に貸付することを得。
一、凶作に際し、その収穫期を経過したとき。
二、毎年九月以降其年の作柄に依り、貸付穀類の辨済を受くるに支障なしと認めたる時。
第八条 郷倉の開閉は役員三名以上立合の上組合長之を行う。
第九条 本会に次の役員をおき、組合員の選挙により之を定む。
組合長一名、副組合長二名、世話係八名。
役員の任期は三年とす。但し、任期満了の時と雖も後任者の就任する迄はその職務を行う。
第十条 組合長は組合に関する一切の事務を総理す。副組合長は組合長事故あるとき之を代理す。
第十一条 大字篠木の区域に住所を有するものにして、新たに本組合に加入せんとする者は組合長の承認を受け、且つ、その年度迄の各組合員貯蔵額に相当する穀類を納付することを要す。
前項の穀類納付期間は五ヶ年以内の範囲に於て組合会に於て之を定む。
第十二条 組合員は次の事由に依り脱退す。
一、脱退の届出。二、大字篠木の区域内に於ける住所の喪失。三、死亡。四、除名。除名は組合規約に違反したるもの、及び、組合の名誉を毀損したるものにして、組合総会の決議により之を行う。
前項第三号の場合に於ては、前組合員の相続人は第十一条の規約に拘らず其の地位を承継することを得。
本条第一項各号に依る脱退者に対しては、次の方法に依るものとす。
一、貸付に対しては、期限前と雖も脱退と同時に返還せしむ。
二、持分に対して、其の持分の内、各自積立数量を還付す。
第十三条 穀類の貸付は次の条件に依るものとす。但し、特別の事由に依り組合会の決議を経たるときは其限りにあらず。
貸付期日、毎年六月一日以後。
貸付額、組合員一人に付一俵(四斗入)以下。
利息、籾一俵に付籾二升。
第十四条 貸付を受けんとするものは役員の認むる組合員二人以上の保証人を立てたる借用証書を差出すべし。
第十五条 辨済期日に辨済をなさゞるときは、貸付穀類一俵に付、一か月籾一升の割合を以て、延滞利息を徴収するものとす。
但し、特別の事情ある場合は、組合会の決議に依り減免することを得。
第十六条 本組合の現金は郵便貯金か、確実なる銀行、又は、産業組合に預金するものとす。
第十七条 組合会は組合長予め日時を定めて之を招集す。
但し、会合の議長は組合長之に当る。
第十八条 組合会の決議は出席組合員三分の一以上の同意を以って之を決するものとす。
第十九条 本組合の会計年度は暦年に依る。
第二十条 本組合の予算は毎年度組合会の決議を経て之を定め、決算は其の認定に附するものとす。
本組合の経費に関する事項其の他必要なる細則は別に之を定む。
第二十一条 本組合に次の簿冊を備うべし。
一、貯穀台帳。二、貯金台帳。三、貸付台帳。四、寄託米穀台帳。五、其他必要なる台帳簿。
六 餓死供養塔
本村に餓死供養塔が四基たてられてある。
寛政十三年(1801年)四月十八日建立。鵜飼第二十四地割字笹森
文化十二年(1815年)四月十六日建立。鵜飼第十四地割字狐洞
天保三年 (1832年)四月十八日〃。 〃第二十四地割字笹森
安政二年 (1855年)七月十六日〃。 滝沢第三地割字高屋敷
昭和四十二年三月一日付で村の文化財として指定された。
本村における餓死供養塔は、南部藩時代の四大飢饉中、ただ一基のみで、他の三基は、それ以外のものである。このことから推察すれば、四大飢饉はいうに及ばずそれ以外の凶作も如何に悲惨なものであったかがこれら供養塔によってうかがい知ることが出来る。
七 凶作一覧表
下記一覧表は『岩手県史』、「岩手郡誌』、『太田村誌』をまとめたものであるが、一致せざるもそのまま記載をした。
第五節 岩手山の噴火
貞享三年(1686年)二月廿九日地震があり、岩手山の爆発があった。砂礫飛散し火を噴き、熔岩を押出し、降灰は遠方まで及び、その後も鳴動が続いた。
享保四年(1719年)正月、岩手山鳴動、その中腹より熔岩噴流したが、人畜には被害はなかった。その後、同十三年、同十六年にも噴火している。
『岩手山記』に貞享三年の爆発当時の記事がある。
岩鷲山御炎焼の事
一、貞享三年二月廿九日午前十一時より岩鷲山炎焼したので、御見使を仰せ付けられた。其節、厨川通御代官長牛(なごし)市左衛門・鵜飼村御代官金田一兵衛右の両人御城へ呼出され、岩鷲山御炎焼が如何なる有様であるか慥かに見届けるよう仰せ付けられ、早速火消(ひけし)の装束で上下十二人出立をする。大沢村肝入彦右衛門に歩行夫(かちぶ)二人、下栗谷川村肝入左兵衛に歩行夫二人、都合十四人、閏三月三日午後七時盛岡を出立する。闇の夜にて炎焼せる灰ふり続き、提灯も役に立たず、側なる者も見得ざる故、提灯持参すれども風はげしく、みの笠にて出立をする。夕顔瀬の橋より岩鷲山山頂を見渡したところ、御山の内(うち)東平(だい)らが皆焼けて見える。古館(安倍館)辺りを通うた処、生臭き北風が吹いて来る。国見峠(一本木近傍か)についた処、焼灰一尺二寸ばかり降り、山頂には稲妻甚しくて火柱二本立、一本は北の方へさり、一本は国見峠に火が移り、天上には青雲・白雲・赤雲・雷雹思の外である。五間七間程の大石に火が付いて飛び、諸木大小によらず角掛へ飛落る音は地震雷濤もかくやと申すばかりなり。煙へ灰交って降り、少しも側なる人も見得ず、互に声のみ聞え、御代官も馬より下り、上下一つに提灯をかこみひしめき乍青くなる。誰もものをいわず、其原にて夜を明し、あくる四日の朝、込(こみ)と申す坂へ七時過ぎに行った処旭も見えず。朧月より闇(くら)く山の端(は)へ下りて見たる所、土水火交り、さんざんに流れる。そだの葉に火が付き、小木大木根より押出され、硫黄に火が付き物すごく燃える。扨又八時には少々雲合よくなり、長込より見渡したる処、先年より御仮屋場と申処迄火水昇り、上下通りの家見えず、四方見渡しうる処に一軒家あるのみ。その屋根の上に人一人見え、一心に念仏を申して居る。不審に思い肝入彦右衛門出むいて、声をかければ、此人漸く声を出していうには、私は右衛門三郎なる者と返答する。重ねて尋ねたるに右衛門三郎夢心地にて、誠に有難き次第なり。地獄で仏様の御尋ねにあい申した思いで、限りない悦びの趣きなり。何とて右衛門三郎一人残りたるやと尋問えば、留谷(とや)森へ家族皆引越し、只拙者一人居残ると一々申す。川より此方の家四軒馬一匹家財迄皆流してしまう。私もむこうへ越えるべきであったが、少々の間隙(ひま)を取る内に橋落ちたる故、立帰り屋根くしへ上り、最期と存じ念仏申して居る。家財残らず流した者共与三郎・伝治・勘作・三九郎・長七の五人である。外に二郎・左衛門・与四郎・惣治郎・右衛門三郎此人々は留谷森へ引越し、家財等を梁りの上にあげ、とかくする内に橋落ちたるにより、行く事が出来なくなる。その後は只茫然とするのみと右衛門三郎が申す。肝入彦右衛門とくと承り一々書留、夫より巣江町へ立帰り支度等をし、三日の七時の下刻より四日の朝迄御代官様に、右の趣を書いた書付を見せ、御城へ両御代官が、彦右衛門を御供にし、急ぎ上って御本丸廊下橋より御用の間へ御上り、上田多右衛門殿御取次ぎで、右の書付を御前へ御持参、早速多右衛門殿披露致した処、炎焼の事委細見届参った事を神妙に思召され、おほめの御言葉をいただき、両御代官様御城より御下り御休足される。その後十日ばかりの内御山山頂鳴り渡り焼石飛び落ち、姥屋敷辺り迄来る。実に前代未聞の事であった。
一、貞享四年三月七日より十六日迄御山霧霞鳴渡り、日々地震昼夜絶えず、五月廿七日御祭礼に導者御不動平迄参詣す。其内二三人山頂を拝み申し度いとて、御不動平坂峯に上り拝もうとなしたる内に、煙にて拝み申さず、心も定まらず、早々下向をする。同廿六日地震強しと申す。同六月地震己酉(つちのととり)の日山頂見分にかけられ、その時拝み申す処、御炎焼やまずして、炎焼灰岩鷲山の肩三十六童子の御辺り迄所々霧霞鳴渡り、さみしく心も定らずして下向する。
第六節 洪水・水害
一 北上川
小川博三博士の調査によれば、確実な記録の残り始めた元和のころから昭和二十三年のアイオン台風までの約三百年間に二百三回の洪水があった。このことは三年に二回の割合で、北上川のどこかで水があふれている計算になる。
これらの洪水の中には、部分的な浸水で終ったものもあれば、全域に及ぶ大洪水も数十年に一度は訪れた。南部藩時代の資料をもとに、死者、流失家屋、米の損失石数などを参考にして作った番付によれば、横網は享保十三年(1728年)の洪水となっていて、死者男二十人、女二人。家畜損害馬七頭、牛十五頭、家屋流出百四十一戸、同倒壊三十四戸、橋の流失四百三十五、山崩れ四百八十四ヵ所、米の損失四千五十石とある。大関は享和元年(1801年)で死者五十二人、流失家屋百七十八戸。関脇は享保七年(1722年)で、流失家屋三百八十五戸、米の損失四万石とこの番付は続いている。中には記録方法が違うために、番外になった大洪水もある。同博士は洪水の高さからみれば寛文十年(1670年)の洪水が北上川では史上最大と推定され、昭和二十二・三両年のカサリン・アイオン両台風の洪水もこれと匹敵する。享保十三年の洪水はその次位だろうという。
南部信直が不来方の地を築城と決定したのは、北上川と中津川の天然の防禦と、水陸交通上の要衝の地であったからである。頻々と起る洪水のために築城工事が中断されて、四十数年の長期にわたってようやく完成をみている。
以上のごとく度々の洪水に襲われたのに、北上川は治水工事の史実に乏しい。南部藩時代では、盛岡に不来方城が築かれたとき、材木町から杉土手に及ぶ堤防を作ったが、築城のためのものであった。藩政末期に新渡戸伝が江釣子で、治水と開田を兼ねた堤防を築き、また徳川初期に西磐井郡の日形で、木村勘助が治水を目的とした二十八町の堤防を作っている。こうしたわずかの例を除くと、北上川は暴れ放題、殆ど原始河川のまゝ後世に残されて来た。何故手つかず放置されてきたか。それは田畑の被害が大きいときでも、人畜の被害は他の川と比較して割合に少ない。これは北上川が川水が土地よりも高いところを流れている。人畜の被害は取り返しがつかないが、田畑の損害はその年は不運だったとあきらめ、治水工事にまで気持が盛上げさせなかったのだろう。花巻や江刺地方では、何年に一度訪れる洪水のため昔は無肥料地帯であった。この地方では洪水は必ずしも害ではなかったし、米は三年に一度とればよいという考えが古くからあったからだ。
昭和二十二年九月四日前から降り続いた雨が十五・十六日に三陸海岸東方を通過していったカサリン台風による集中豪雨によって、岩手山へ二日間に四百六十八ミリという東北地方においては最高の記録をするほどでもった。北上川の水は刻々と増水をする。このときの死者行方不明は八十八人、家屋の流失・倒壊四千二百を越し、田畑の被害は甚大であった。
翌二十三年九月に、これに上回るアイオン台風の集中豪雨に見舞われる。このときの死者行方不明は六百八十九人、重軽傷者千四百人、流失倒壊家屋三千六十戸と被害が余りにもひどかったが、本村の東部に位する北上川の川岸は多少の被害のみで、余り人畜にはなかった。
二年連続の大水害を起した北上川を治めることから戦後の岩手の復興が始められる。
昭和二十五年政府は国土総合開発法を制定し、五大ダムの築堤を見るに至る。この一つの四十四田ダムが昭和四十三年十月に完成した。このダムは、総工費六十五億五千万円の巨額と、昭和三十七年より六ヵ年の歳月を経た治水のみならず発電をも含む多目的ダムである。水没部落は松屋敷・楢木・楢木沢・妻の神・新田・野沢・大崎・築平で、土地は田十一町七反、畑六十二町七反、山林十三町六反、原野二十四町九反、宅地七千百三十七坪、墓地五百五十六坪の多きに達し、戸数は三十四戸に及んでいる。これらの人々の犠牲を見逃すわけには行かない。
この五大ダムの完成により、岩手県民全体が北上川からの苦しみをのがれることが出来ることになった。
二 雫石川
雫石川がいかに氾濫したかは、大釜の日向が四-五㍍の崖になっていることは、明らかにここを流れたことを物語り、大釜駅の西南方、俗に「オナペ」と称する湿田があり(もとここは沼で、鶴・雁・白鳥・鴨の数が群遊していたと大坊直治氏が述べている。)盛岡市土淵の神山神社付近及び稲荷神社から天昌寺一帯の断崖をみても明らかである。
『太田村誌』に享和元年(1801年)の六月二十日より大洪水にて穴口欠落ち、三枚橋はもちろんのこと、中太田まで暴れまわり、その年御役銭・御年貢米が免除されるほど、藩政時代も癌であったとある。
明治二十九年七月・同三十年十一月・同四十三年十月・同四十四年八月・大正三年七月・同七年七月・同八年五月・同九年六月・同十年六月・同十二年二月・同十三年四月・同十四年八月・同十五年八月・昭和六年五月に護岸工事を施行している。
昭和七年度より国庫補助県営継続事業として、護岸工事を実施することとなる。このとき多くの青年男女が働きに出て、不景気のころの現金収入を図った。
雫石川堤防護岸工事
施行区域及延長 北上川合流点より上流、左岸八千七百m、右岸八千九百m。
計画川幅 上流四百三十m、上流二百六十m。
築堤 高さ洪水位以上一m二十、堤防馬踏(表面)幅五m。
工事費総額 八十万円、内昭和七年度十五万円(盛岡市厨川村の一部)、昭和八年度二十五万円(本宮村太田村の一部)、昭和九年度二十万円(厨川村滝沢村の一部)
事業年度 昭和七年度起工五ヵ年継続
昭和三十三年十月雫石川大畑堤防決潰し、田畑に甚大な被害を受けたるも復旧をなす。その後約十年後の同四十五年五月十六日の十勝沖地震と、八月二十一日の集中豪雨で約百七十mにわたり堤防が崩壊した。村では県に早急復旧するよう強力に陳情すると共に、重要なる個所だけに建設省にまで働きかけ、二~三年を要する工事を単年度事業とし、工事費一千九百万円で県の事業として施行した。
昭和四十七年四月から総事業費約百九十四億円を投入して雫石川をせき止め、御所ダムが五十三年度末完成されることになっている。有史以来荒狂った雫石川はこの御所ダム完成によって終止符をうつことになる。
三 洪水・水害一覧表
第七節 狼害
大坊直治氏の調査による寛文三年より明治初年間に十数通の記述がある。
寛文三年(1663年)四月十七日(南部城事務日記)
鵜飼村に狼多く居り馬を取る故、鉄砲を討つ者を遣わして狼を討ちとる様、石井右ェ門から中野新十郎に申付けられ今日遣す。
元禄二年(1689年)八月廿九日(上同)
田畑人馬を荒す猪・鹿・狼を荒止まで討たせ申すべき事
文化二年(1805年)十二月十二日(上同)
厨川通御代官所の内滝沢村角掛辺り迄、当秋より子連れ狼が見えていたが、最近多くなり、往来の旅人にかかった事度々、よって鉄砲二挺拝借致したい旨の願出があったから、御目付へこれを申し渡す。
文化六年(1809年)五月八日(上同)
厨川通御代官所滝沢村・鵜飼村・土淵村・大沢村・篠木村の山根通に狼が出、野放の馬に怪我をさせている。殊に滝沢村に於ては、百姓家の厩に入っているから、鉄砲を一挺宛拝借致したい旨申出たる処、五ヶ村に三挺借す事が仰付けられる。
文政七年(1824年)十一月十六日(上同)
狼を留上た者へ御褒美銭を増す故精を出して留上する様申渡す。
一、壱貫弐百文也 女狼
一、壱貫文也 男狼
一、弐百文也 子狼
弘化(1844-48年)の頃
大坊氏の亡祖父、或る年の晩秋、夜九時頃盛岡よりの帰途、禰宜屋敷森近くにて六匹連れ(一血族群をなすの性あり)の狼に出あい、四方より包囲され、冷汗を流しつゝ大声にて叱咤し、大刀にて払い退け漸く帰宅したりと。
また、同氏は凶作悲劇二つを述べている。
十七・八歳の小娘が本覚大明神辺の「ヒキザクラ」の根元の木の中に潜み夜を明さんとする形勢なるを、某盛岡よりの帰途、之に見当り、注意して日く、其所に居りては狼害の虞あり、我家に来り泊れよと。娘年頃なれば痛く恥て「足部より狼に食われなば苦しからん。頭より食わるゝならば本望なり」とて動かざりしが、翌日行って見たれば、五臓は皆食われて四辺は赤に染みて居たりけり。
明治九年(1876年)七月の明治天皇東北御巡幸の際の記録に、勧業場内の県内物産と併せて狼の子を御覧に入れる。この頃狼による馬の被害は年に五十頭、県に於ては駆逐策として狼の買い上げを同八年の八月より開始する。一年に満たざるに四十匹に達している。天覧に供したのはその内の一匹なり。
以上のように、狼の被害は非常に大きかったが、恐れながらもこの狼を利用している。それは霙時、この皮を外套に用いれば、中まで水気が滲透しないので、多く利用されていたらしい。
第八節 虫害
「延宝七年(1679年)大殿様(第二十九代重信)三月七日御登り、若殿様(行信)十月二十五日に御下り遊ばされる。この年鼠大分余計で、野山の栃しだみ芋つるほど蔓迄も食い切り申す。しかれ共、世の中は七八分位の世中であった。八月十三日は大風で、蕎麦殊の外吹こぼし申す。粟稗迄も鼠食切り申す。
明和三年(1766年)同四年より“すいはく”と申す虫、稲の穂先へ付いたので、穂先は黒くなりて筆の穂の如く、段々藁が朽って鎌へかからず、余計付いた所は壱束に壱合もなし。
安永二年(1773年)、同三年、同四年、同五年、この年も明和四年より虫付きで甚た不作であった」
以上は『雫石歳代日記』の抜粋であるが『岩手県史』の年表によれば次の通りである。
「寛延元年(1748年)領内虫害旱魃のため凶作となる。損毛不詳。
安永二年(1773年)大雨虫害のため凶作、米作損毛七万九十石。
天保六年(1835年)春より夏にかけて気候不順、霖雨洪水相次ぎ、暑気薄く虫害ありて凶作となる。損毛高二十万石、飢饉となる。
昭和十五年(1940年)稲熱病発生。八月一日より二十日間、防除施設強制、県指導督励班を派遣する。
昭和二十年頃一町歩当りの病虫被害が四石もあった」
第九節 山火事・野火・火災
これらを『南部城事務日記』から拾いあげる。
万治四年(1661年)四月二日、不動沢部落
野火移り「ぶどう」沢山残らず焼失し、湯舟沢山半分焼けたについて、両町奉行太由縫殿助・滝沢三郎に御同心共、其外に山間太市助・船越与兵衛が付添い、御代官波岡与左衛門・遠山二郎左衛門に申し付けて之を消す。
寛文十一年(1671年)三月八日 晴 午後七時地震
昨日夜の十二時、大釜村喜左衛門の所より火事出来、家七軒焼失したる由、御代官土井弥之助・山屋三右ェ門・御横目船越弥平左ェ門を以て之を披露す。
元禄十二年(1699年)四月三日
昨暁より昨日迄、滝沢村の相・小柴立・野火通り三十間四方、同清水屋敷・小柴立百五十間四方焼けたる由御代官之を披露する。
寛政四年(1792年)三月十四日
昼二時、篠木村野火逆焼(ほそけ)より火を失して鵜飼村まで延焼し、人家三十六軒類焼の厄にあう。
篠木村弐軒 治助・清八。
大沢村拾九軒 十右ェ門・吉兵ェ・与兵ェ・太郎吉・七助・源之助・彦助・伊之助・才市・六助・喜助・福松・又六・甚七・萬太郎・甚六・孫左ェ門・佐二右ェ門・党右ェ門。
土淵村拾軒 善四郎・三十郎・万助・善之助・清吉・弥惣治・助作・徳助・久右ェ門・久左ェ門。
鵜飼村五軒 喜右ェ門・三吉・久助・外弐軒は人名不詳。
御代官栃内瀬左ェ門様と、松尾五左ェ門様が御出張されたので、大沢村肝入吉兵衛、篠木村肝入与兵衛、土淵村肝入弥作、鵜飼村肝入作右門が御案内して申し上げる。
この際熊野権現境内の杉根廻り一丈五六尺から二丈五六尺までのもの拾本焼ける。大蛇がその洞内を居所としていたが焼死して白骨となってあらわれたという。
このとき、沼宮内の御蔵から味噌何拾貫、稗三百駄御下賜になった。
第十節 納税
一 年貢の基礎
藩内に生活する大名を始め武士町人は、農民の汗と血によって生産された穀類によって維持されているのにもかかわらず、耕地のみでなく山林・原野や海浜・河川までも原則的には藩の所有であった。従って藩の財政運営に必要な諸経費は、年貢・諸課税・現物賦課など、凡て領内からの徴収によって支弁されている。農民から徴収されるその第一は藩の直轄である御蔵入する土地からの米穀であり、第二は武士や寺社に納入させる給所地からのそれであった。
耕地は稲田・稗田・畑などに分けているが、その反別については水田は三百坪をもって一反歩とし、畑は九百坪を一反歩とする特例を実施している。『邦内貢賦記』「一反というに十五間に二十間の三百坪、畑は三十間四方の九百坪、一畝とは一反の十分の一」とあり、一坪は田舎間を用い六尺五寸四方であったとある。従って畑は九十坪が一畝となる。耕地は沃瘠の度合によって差等があった。水田一反歩から収穫される米産一石三斗を最高として上田となし、以下二斗降りをもって中田・下田・下々田としており、稗田と苗代は共に七斗としている。しかし北部の米のよく出来ない野辺地通りでは、上田一石、中田八斗、下田七斗、下々田六斗となっており、上稗田七斗、中稗田六斗五升、下稗田六斗、下々稗田五斗五升としてある。
畑は九百坪が一反で上畑九斗、中畑七斗、下畑五斗、下々畑三斗としたが、これも北部においては、上畑六斗、中畑五斗、下畑四斗、下々畑三斗としている。これら等差の基準を斗代と称している。
当時北上川水系に属する耕地の南部藩領内では和賀・稗貫・志和・岩手の四郡と遠野地方は米産地であった。従って検地による反当収入の見込みも一反歩一石三斗と見做される土地が多かった。反当収入に対する税率も高く、その税率を歩付と称し、その歩合を「四つ八分六厘」というように称した。『封内貢賦記』に「〇一つは一斗、但し一石に付いて一分は一升、一厘は三合なり」としてある。たとえば上田一反歩の反当収入一石三斗に対する税率、四つ八分六厘とは四割八分六厘に当る六斗三升一合八勺が年貢になるということであった。「和賀・稗貫・紫波地方の水田地帯に於ては、坪当籾八合の生産を標準とし、二分の一摺として坪当り四合、一反歩一石二斗を標準田、すなわち中田とし」と盛岡市史税法の項にあるように地方差があった。
たとえば稗貫郡宮野目村の天保二年(1682年)、上田は七つ四分であり、一石当り七斗四升が年貢規定である。最高の水田でも一反収穫一石三斗とみなされているからその七つ四分は九斗六升二合の年貢である。この地域の上田はそのころでも反当二石は下るまいから、年貢を納めても一石三升八合は百姓所得の計算となり、その意味では五公五民に近いものとなろう。
岩手郡は慶長五年検地され、石盛制をとったと田中喜多美氏はいう。
当時に於ても村は自治体の性質を有するものであった。もちろん奉行や代官は事務を統轄したものの、村には駐在したものではなく、行政は村役人に依って治められた。諸税は村が納税義務者であって、年貢を物成(ものなり)といいいわゆる地組に該当する。これに対して小(こ)物成とは雑種税のことである。若しこれら未進のものがあれば、他の百姓が負担の増加となるから、農民は常に正面からも側面からも苛斂(れん)誅求を余儀なくされたものである。岩手郡の収穫高の割合すなわち斗代と、年貢米の賦課率である歩付とを次に表示をする。
一坪の由来について『国分翁夜話』第十話に次のようにある。
一体、耕地の面積の最下位の単位を一坪としたのはどんな根拠で、何時から行われたのであろうか?もとより、正しい文献を尋ねるに由ないのであるが、中国の殷の湯王の時代の記録が残っている。それによると、今を去る三千数百年の昔、湯王は伊尹を抜擢して、宰相の位につかせ農政を行わせ、主として井田法を布かせた。そして老若男女を平均して、一人一日の主食を供する面積を現在の六尺四方に当てたわけである。つまり、一坪の生産量は米に換算すると二合に満たない。反当りにすると、六・七斗にあたる。中国の中央部の標準田でも反当六・七斗と見なすことが出来るのである。現在の日本の進歩した技術に依れば、六尺四方で一升、あるいは一升五合位になっている。更に二毛作を合わせれば、ゆうに二升五合から三升に達する。だから、現在は一毛作、単作の上田なら一坪で三人から五人の人間を一日養うことが出来るし、九州・中国地方の精農家でしかも肥沃な土地ならば、七人から八人分の主食を供給する事が出来る。
従って、一反歩を三百六十坪としたのは、けだし一年間の食糧の基礎とする考え方からである。中国でも三百六十坪で出発し、日本では推古天皇の大宝令の時に始まり、完成したのは奈良朝の末期である。もちろん、当時のことであるから、地方によって若干の相違はあったが、それ以来今から三百年前までこの三百六十坪が続いて来たのであった。
ところが、秀吉の時に全国的に大規模な検地が行われ、特に文禄、慶長の二回の朝鮮征伐等のため財政窮乏を来し、その苦肉策として、天下の大検地を行い、一反歩の面積を三百坪にしてしまった。これを慶長(三年=1598年)の大検地と称するのであるが、この反当税額はそのまま据置いて中身を三百坪にしてしまったので、これは誠にずるい増税であった。
その後、秀吉に代った家康は、この狡滑な増税を豊臣の失政の第一に数え、爾今一反歩を三百六十坪に復元することを声明して大いに民心を収纜した。しかしながら、乱世の後を受けて財政の逼迫は容易に改まらず、遂にその公約は実行に至らなかった。却って後年、徳川幕府はこの取扱いを更に厳重にしたため、農民の負担は一層加重されたのであった。
二 租税の種類
藩財政の基礎をなす租税をおよそ五つに大きく区分した森嘉兵衛・一ノ倉則文両氏の種類は次の通りである。
租税の基礎は農業生産の貢租が主であり、現物納入と代替納入があった。
物産税は鉱産・林産・畜産・水産の外、木材伐出税・漆の実税・染色原料の移出税・牛馬移出税等があった。
夫伝馬税は陸路交通の円滑を期する公衆税とも称すべきものであった。
利用税は利用者が負担することを原則としたものである。それは、盛岡城下に年貢等を搬入するため、盛岡以南の郷村では後の明治橋である新山橋の橋料代を賦課されており、盛岡以北の郷村では夕顔瀬橋の橋料代を賦課されていた。夕顔瀬橋の橋料代を負担しているのは、雫石通・沢内通・厨川通の外、沼宮内通と上田通の一部がこれを負担している。沼宮内通の北上川河西の地がこれを通過し、沢内通は郡西に辺しているため、年貢は山伏峠を越し、雫石街道より盛岡城下に通じていたものであった。
これら貢租・役銭には多分に公約要素が濃厚で、国税とみなしてよいものがある。
上の租税と異って、ある一定の範囲内の費用に限られたものは郷役であるが、それも公約要素が一層強く、恒久的になっているものが据郷役である。郷役には代官所管内に割付するものと、その村だけに割付するものとがあった。
前者の用度の諸費用は、御使番(駅伝の使者)、伝馬を指図準備する人への給料、刑事々務を分掌している目明(めあかし)の給料、その他小走り使する者や、代官の身辺を世話する人々の宿直手当等である。
その外、御鷹餌鳥銭・御鷹部屋御用代・鶏黒尾代・御厩荒糠代・御蔵菰代等でこれらは厨川通のみならず負担をしている。
藩の統治は祭紀行政であったから、郷役中に虫祭銭・風祭り銭・岩手山神社・伊勢初穂銭等がある。虫祭銭は、田植直後やる祭紀行事で、稲や岡物に発生する害虫を防除しようとする祈願行事であり、風祭行事は二百十日ころ襲来する颱風や、あるいは農作物を損傷する暴風を、防除しようとする祈祷行事で、夏季虫祭りに次いで行なってきたものの費用と解される。
後者の村の負担は肝入の給料である。村肝入は里長であり村長でもある。この外肝入所の御帳付や諸費用をも村々で負担するのである。賦課の方法は百石単位でなされる。村肝入と月番老名で協議をし、その種目の高を示して百石当りを出し、連名捺印で代官所の承認をもとめる。当番代官がこれを決裁すると、それが御蔵肝入や知行肝入に通達される。御蔵肝入や知行肝入は、更に所管する地域の各百姓の持高に応じて割付、これを徴収し、納付するのである。
従前から課税してきた税金の外に、さらに臨時の税金が課されるようになった。藩政末期になるに従ってますます多くなった傾向がある。たとえは御献納木御高割(天保十一年=1840年)御婚礼御用御高割(天保一・二年)、御囲籾蔵高割(弘化二年=1845年)、御家督入用御高割(嘉永三年=1850年)、御入国御高割(嘉永三年)、北地御用御高剖(嘉永五年)、御蔵御普請御高割(嘉永五年)、江戸表御屋敷御普諸御入用御高割(安政元年=1854年)、本御蔵御普請御入高御高割(安政五年)という新名目の課税がぞくぞくと見えてきている。
これだけでも幕府との関係、藩主身辺の婚礼や家督、入国の費用、江戸屋敷の修理があり、それに国際関係の逼迫から、北地警備や自領の沿岸警備の問題が加わって、いよいよ財政面の多端な支出が顕れている。その皺寄せが百姓にのしかかる。
しかも領内の凶作対策としては御囲籾蔵(備荒倉であろう)の建築や、従来からあった藩の倉庫の修理もゆるがせに出来ず、領民の生活は余力のないものになったことが知られる。
太田蟹沢家に伝わる天保十一年(1840年)の『万覚帳』中の「定目飯岡通御官所諸控」から摘記をしてみる。
御定役金・定番草青引代・正五御礼金・御蔵壱歩増舫金・御蔵莚菰代・御厩荒糠代・遣番銭・肝入御礼金・馬役銭・明屋敷坪役銭・御年貢帳紙代・差紙代・検見入方・御帳附御同心拝借之節・御鷹餌鳥代・御鷹匠賄代・厨川通御鳥討宿□代・御鳥討雑用代・御普請銭・江戸詰夫銭・鶏黒尾代・雨宮初穂・伊勢初穂・熊野新宮初穂・本宮辻権太夫・岩鷲山祭礼夫伝馬。
◇
雫石川普請・中津川普請・北上川普請・築川普請・上田三堤・向中野通見前堤之内畑心南、田者向土手普請・向中野通内道明堤、小鷹堤、新堤、細工堤・湯坪堤、間渡堤、油田堤〆七ヶ所・見前通内三本柳堤・赤林堤・広沢堤・端山堤・矢継堤・北矢幅堤・南矢幅堤・又兵衛新田堤・前立堤・菖蒲堤〆拾ヶ所。厨川通滝沢・大喰・斎藤・赤袰三堤〆六ヶ所。
◇定目出人足
殿様御参勤之節、夫拾九人・馬拾四疋。八戸様同断、夫弐拾壱人・伝馬。公儀衆御通行之節、助合・伝馬。御年縄なひ、九人宛十二月十三日より晦日迄毎日。稲綱打、七人十一月十五日三の丸烏帽子石へ奉納。御門松迎拾九人・廿八日斗り。御門松立、拾九人・晦日斗り。八戸様御下向之節、助合夫、伝馬弐拾参人。馬藁並ニ飼鳥寒鳥御用稲十四把、青引同。見前通石突御普請は、見積り人足の内半分は飯岡と厨川、向中野、見前より、半分は日詰、長岡、徳由、伝法寺より出人足也。殿様御増年御門松建方人足、八人飯岡通総高より出る。御部屋方増年同断、三人。
御子様方御増年之節、藁三拾把、御門松迎三人。信州善光寺如来忌之節、飯岡厨川にて六十人、法輪院より普請御入用鍬・かっさび・持篭持参日数二日に割合法輪院へ差出す。御勘定所割合三十六人飯岡、廿四人厨川。同断御逗留中七日積り、飯岡厨川にて七十人、昼五人夜五人、人足法輸院へ差出す。御勘定所割合四拾弐人飯岡、廿八人厨川。遊行上人忌逗留中、十五日一昼夜九人づつ飛浄寺へ差出す。飯岡七拾人也。御勘定所より割合にて、上田通より小割来る。同所御出立之節送夫廿六人、馬十三疋、飯岡通より差出す。右詰所人馬割所也
◇
蓬、菖蒲、四捨三把、五尺縄にて、三把宛御武官所へ上納也。御年縄藁三百三拾把也。百石に付四把余。正荒糠六拾壱ヶ村片馬宛、下飯岡村斗り壱駄、右は御厩へ上納也。
寺請状(うけじょう)(キリシタン宗の改宗者が仏教に帰依し、その檀徒証明を奉行所に提出した書状)出候節料紙(用紙)壱人に付き三文宛帳付へ差出す。殿様御居間御普請御用正荒糠八斗俵弐俵と四斗八升也。然共只今八斗俵三俵宛御作事所へ上納、御善請之節斗り御勘定所より割合来る。
◇
御百姓共溜穀之事。惣百姓人別書上帳にて新蔵へ年々上納致置粟稗麦之類米壱人に付弐合五勺積り。
橋釣木仕様之事。橋有る場所前後へ栗植置、往来のためと申含、来春より植立候旨申付候。追々用木に相成候節は、何時にても申立橋材木に用可申事、奥寺常之助ェ夫申付。(天保十一年三月十六日)
第十一節 百姓一揆
一 寛政年中の一揆
寛政七年(1795年)暮、俄然重税・新税に対する不満が盛岡の南方農民によって火蓋が切られ、またたく間に全領に蔓延をした。
即ち、寛政七年十一月十二日に至り、厨川通の一揆が久慈町(茅町)まで押寄せて行く。これより先太田願意を許して在所に帰らしめている。夜六つ半(七時)過より徳田・伝法寺通りの百姓四百人(七八百人ともいう)ばかり仙北町まで押寄せ、城下に入ることが出来なかったため、対岸に群集して藩を罵詈雑言し不穏の形勢を示した。藩も如何ともしがたく願意全部を承認して在所に帰らしめた。
このことが早くも全領内に伝わり同様の一揆が蜂起した。藩主利敬(たか)は日々に起る喚声に不審を抱き種々実相を聞かんとしたが、家臣等これを「近在の樵夫共薪材木筏等流す」かけ声なりと称して厳秘にふしていたが、日々につのる騒擾に包みきれず、遂にその実状を言上した。ここに及んで利敬は直に一揆の根源たる新税・増税撤廃の布達を発し一揆鎮静の一日も早からんことを期した。(中略)しかし「百姓共町中に葭をしき莚をしきて握り飯抔食、誠に以て目もあてられぬ次第也。右程の大勢に月代(さかやき)そり候者一人もこれなく、乱髪はえ顔色常ならず、扨々おそろしき事ども也」という。これらの一揆が如何に必死の覚悟で城下に押寄せて来たかが窺われる。藩は直に家臣藤枝内規・太田忠助・山口瀬左衛門等をして取調べしめた。ある村に対しては十一ヵ条中五ヵ条を許し(他は昔よりの定役であったため不許)、あるいは全部を承認したものもあった。許可されたものには寸志金・馬役銭・山林冥加銭等であった。
厨川・飯岡通の百姓は諸士に貸借延期令を出したのを見て、農民にもこれを適用せしめようとして債権者に強請することを代官所に強訴した。しかし藩においては属々免税等を行えるを理由としてこれを却下し、一揆の首謀者を厳重に処罰し、一揆厳罰主義をとり、全領内に役人を急派し鎮静につとめた。
要するにかくのごとく頻々として発生したる一揆は凡て重税軽減を目的とし、秩序ある行動によってその目的を達し生活を擁護しようとしたのであったが、その動機に藩政の腐敗を批判したのであった。殊に一揆を援助し、これによって自己の生活を保護しようとした武士のあったことは特に注意しなければならない。
寛政七年十一月八日から十六日に亘る約九日間の全領内に起った百姓一揆は沈滞しきった藩政にとって将に青天のヘキレキであった。最初重臣等は一揆の勃発を藩主に秘していたが、日増に旺盛となる一揆の情勢をかくしきれず、一揆願筋は充分なる審議をなさず、認可の墨付を与えて帰村を促し炊事を与え極力慰撫に努めた。また直に全領内に対して新税の免除を布達し、遂に古より定められた定役すら免除するの周章振りであった。従ってこの結果を過信した一般農民は些末の問題にも直に一揆を起し、衆力に依って解決しようとする傾向が生じた。即ち、寛政八年十月百姓一揆に対して、例年のように一定の価格で米を買上げる。若しこの買上米に応ずることの出来ない者に肝入一人を総代として願出ずべしと布達している。このことは古よりの慣例であるにも拘らず、買上米反対を標?して旧冬のように徒党を組み村肝入・御蔵肝入を首領として代官所に強訴した。殊に沼宮内通の一揆は買上米免除を起した際、余勢で日ごろ憎悪していた同町の豪商井筒屋治助・鍵屋甚兵衛を襲撃し暴動化しており、鬼柳通の買上米反対一揆は、他村に比して価格が低廉であったから他村と同率に引上げることを目的として起り、地方代官の活動に依ってその目的を達することが出来たのにもかかわらず、その帰途肝入宅を襲撃している。前者は首領が田名部追放となり、後者は新協定価格で全村買上米となったので責任者を出さなかったが、このような団体行動の頻発はだんだん乱を含み暴動化するに至った。
藩も漸くこれを自覚し、寛政十三年(1801年)九月初旬、飯岡通・厨川通付近の百姓が、債務の年賦償還を金主に強制する目的で一揆を起し、城下久慈町材木町まで押寄せ、同通の大債権者酒造店恵比寿屋幸右衛門を襲撃し乱暴狼籍を極めてから態度を一変し、町検断の注進に依って、先奉行は直ちに首謀者二名を捕縛し、強硬なる態度を以て一揆を鎮圧し、帰村させた。よって藩はこれを契機として一揆に対する弾圧方針に改め一揆の要求を破棄し、先に捕縛した厨川通と飯岡通の二人の首謀者を断采重刑に処分することとし、且つ全領内に対して次のような厳重な布達を発した。
すなわち、理非の如何にかかわらず徒党騒訴を認めず、頭人を重刑に処することとして弾圧的方針を確定した。これより漸く領内に騒擾の跡が絶えた。しかし領内が平穏になったのはこの弾圧のみに依るものではなく、この一揆を契機として社会経済が好景気に転換したことによるものである。この弾圧は警察的効果のあらわれであろう。
二 文化・文政年中の一揆
文化・文政といえば南部藩においては最も好景気時代と称すべきときである。このときですら百姓一揆・米騒動が頻発したことは、たとえその一揆は後者のような大規模のものでなかったとはいえ、一層注意しなければならない。
文化元年(1804年)十月、岩手郡厨川通の内七ヵ村、飯岡通十一ヵ村の農民等一揆をなし数百人盛岡に押寄せ、債務年賦を強訴した事件があった。一揆は結局盛岡城下材木町で阻止され、一揆の首謀者として飯岡通上太田村与吉、厨川通上厨川十之助両人打首、飯岡通中太田喜作は田名部牛滝に、久蔵は同九石留に追放、厨川通清之助は大迫、中太田村の三助は三戸、同久米も追放となり落着したが、一揆の目的は達せられなかった。
『太田村誌』に、打首を仰せ付けられたことがのっている。
文化元年のことである。隠忍これ宿命とさえ諦めていた百姓達も、とうとう背に腹は代えられなかったものであろう。十月十三日寺に集り、とあるから、たしか大松院であろう。ここに四・五の主脳者が集り大挙陳情の儀を策した。以下当時の記録による。
文化元年十月十四日、家毎に一人も残らず館に揃い、飯岡通の御村を残らず廻り、下飯岡・飯岡新田・木杭と申す所の野原で雨にあたったが引帰えさず、翌十五日の六時頃、下飯岡肝入宅に集り、余り寒いため火をたき百姓共をあてる。御代官様白の山清左衛門様と村木周平様・帳付である十三日町の伝右衛門殿と同じく利兵衛お揃いのもとで、御代官様は百姓共何の願いで集ったのか、その理由を申出よ。「去る廿二日中太田村長助・久蔵両人が願出た通り、丙の年より田畑不作で借金多く、いか様にも致し方なく、年賦で諸上納が出来れば残らず皆納をする。そうなれば明年は田畑仕附可能となる。しかるに十一月三日より長助と久蔵は御町預りとなり、その上喜作、上太田村与吉、三助、久蔵、中太田村方八丁七之助、松の木久蔵も御町預りとなる。この事は何につけ迷惑至極の次第である。久蔵・喜作・与吉・三助は牢舎入、長助・七之助・久兵衛・万太・多蔵・源助子供藤兵衛は御村親類五人組預り、その内多蔵・藤兵衛には、つつしみを仰せつけられ、二月まで御沙汰なし。御町預りの者は一日壱人百三十文宛の賄代支払に当惑をしている。壱ヶ月程も親類組合預りにも賄を出している。何とぞ御容赦下さる様願出る」
これを要するに文化・文政年度における百姓一揆は夫伝馬過重の反対・重税軽減の歎願及び新興町人階級に対する反感等から起っているが、その規模は比較的小さく、皆部分的一揆であった。
三 天保年中の一揆
天保六年(1835年)には領内惣検地によって割出された賦課率は、同三年度の三歩引で、大凶作の折柄高率であるとの風評高く、各所に減免一揆が企てられた。殊に沼宮内通と厨川通の農民最も強硬で遂に歩引の目的を達している。
四 嘉永年中の一揆
上閉伊小本村の弥五兵衛が、天保の一揆以来領内を歩いて南部藩政を改革し、真に農民の生活の安定をはかるには、村々の小一揆を操りかえしているのでは成功はおぼつかない、全領民一致して要求し、大一揆をおこす必要があると力説して活躍するようになった。しかし和賀郡土沢で運動中、捕縛され、盛岡で牢死している。
この運動が奏功したのか、そういう機運だったのか、嘉永六年(1853年)には一揆が全領運動に拡大し、一万六千余人が南部藩政にあいそをつかしたかのように仙台領に逃散し、国運を賭する大一揆を実現するようになった。岩手郡の厨川通・雫石通・沼宮内通も参加している。一揆の中心地は安家村・野田・田野畑などの水稲生産力では最低の地帯であるが、それ故に大規模な鉄産業・漁業が振興し、産業構造に大きな変化の生じている地方に発生している。いうなれば日本の僻地から、最も大規模にして政治性の強い一揆がおこっている。
この一揆が仙台藩に提出した願ヵ条をみると、
一、南部藩主を交迭せしめること
一、三閉伊通の百姓を仙台領民とされたいこと
一、三閉伊通を幕領とされたい、若しできなければ仙台領とされたい
というのである。これは明らかに南部藩に対する絶望的不信によるものであり、政治的要求である。
水稲生産力の弱い地帯に、この不利を克服するようにおこった新産業に、これをも押しつぶすように重税をかける藩政への反対運動であったことを示している。しかもそれは単なる反対運動ではなく、藩主交迭をめぐる政治的色彩を加味したことは、藩政がもはや信頼に価しなくなったことを示している。
第十二節 娯楽
一 子供の遊びとうた
1 あそびの様々
あ 人取り
紅白両陣に分れ、各人員を前方に出し、先に出たものを後から出た者が捕えようとする。この際先に出ていた者は、敵の捕獲を極力逃れて帰陣し、味方の者は更に新手を出して敵を追うのである。かくして多く敵を捕えた方が勝ち、捕えられた者が敵陣内で互いに手をつなぎ一列になって救援を待つ。この目的が達せられれば、現役となって戦闘力を回復する。
い 国コとり
準備 のろきか棒。おはじきか扁平の小石。
図形 四角・円・楕円・提灯型等。
人員 男女を問わず二人なるも、三・四人でも可能。
方法 図形内に自分の陣地を小さく作る。「じゃんけん」で勝者が自分の陣地から敵陣へ小石で正しく入れば自分の陣地内の境界線上より親指を軸として他の指先で円を描き、自分の領地を広める。若し正しく入らなければ、相手の番となる。これを繰返し、領地の広狭によって勝負を決めるのである。
う でんでん虫
紅白偶数の人員で、大きな渦巻を描いた渦巻の中心は紅、先端は白になって向い合う。用意ドンの合図で、駈走で前進し、出合った地点で「じゃんけん」をする。勝った者はそのまま走って進み、負けた者はその組の後につき、それに代って次の者が陣地かち走って相手と出合い「じゃんけん」をする。このようにして相手の陣地に入れば一点の勝となる。
え 丸大学
二・三人位で遊ぶのである。五十㌢位の円を一円二円交互に作り、「じゃんけん」で一つか二つ、あるいは三つ勝った者が前進をし、最後の一㍍位の大円に達すれば勝となる。進む時線に接触せぬようにすることはもちろんだが、その途中の円に、相手の石があれば、そこには足を入れる事が出来ないし、跳ばなければならない。そのとき、円から脱線したり、手をついたりすれば相手の番となる。
お 三人馬コ
四人一組になって、紅白同数の組を作り、各組相互に協力しながら、弱点をねらい、騎手の帽子、あるいは鉢巻をとるか、落馬をさせ、その数の大小によって勝負を決するのである。
しかし乍各組に総大将があって、敵味方各の全体を総覧して指揮をとり、総大将の落馬によって勝負を決する場合もある。
か けけらご
二・三人でゲームをするのであるが、「じゃんけん」の結果、一つか二つあるいは三つを片足で前進し、元の場所が目的に先着するをもって勝とする。
き つぐす
直径三、四cm、長さ四、五十cmの棒の一端をとぎ、「じゃんけん」で負けた者から田圃に刺しこむ。相手はその棒を倒そうと力を入れて刺しこむのである。若し他の棒を倒すことが出来なければ、相手の番となる。相手の棒を倒そうとしながら、同時に次に倒されまいとするその辺に妙味があって流行したのである。相手の棒を倒せば一点の勝とる。
く 馬コ乗り
紅白同人数に分れ、負けた方が馬を作るのであるが、一人が壁等をバックにして立ち、味方の者が頭を側にしてその者の腰を抱く、順次に同様の姿勢となって馬を作るのである。勝った組は次ぎ次ぎに馬乗りをし、終ると負け組の立っている者と、馬乗りの先頭とで「じゃんけん」をなし、負ければ馬を作り、勝てば馬に乗るのであるがこの遊びは、冬など女子においてもなされていた。
け 釘刺し
五寸釘一本を参加者全員で使用する。図形は二人の場合は直線、三人以上はその人数と同数の角形を作る。「じゃんけん」で勝った者から自分の陣地を出発し、地面に五寸釘を刺しこみ、そこまで自分の陣地から直線を引く。若し釘を地面に打ち込む事が出来ず倒れた場合、また他人の線にふれるか越して交叉した場合は、他の番になる。出来るだけ接線を狭くして、相手の道を塞ぎ窮地に陥らしめるのである。
こ ガラス玉
出発点より負けた者から出発し、勝った者は出発点より相手のガラス玉をねらい当てればそれをとり、当らなければ、代ってその場から相手の玉に当ててとるのである。
さ 竹わり
竹巾一cm、長さ二十cm位を扁平にしたもの三本~六本位を準備し、最初右手を使用する。全部握って立て、端を床面に打って揃え、ばらばらにならないように素早く右廻転をし今までの下端が上になるようにしてそれをおさえること十回、その竹の下端を一旦下に打って揃え手前から上端を前方に廻転させておさえること十回、竹を右手で下面に打って揃えたら竹を水平に持ち上げ、右廻転を素ト早く一八〇度させてつかむこと十回、次に右手から左手に竹を立てたまま交換させること十回、後左手に竹を移し右手同様繰返すのである。若しその途中一本でも外れれば、交代をする。
し おはじき
おはじきには小石が用いられたり、小さい貝殻が用いられたり、藤の豆が用いられたりするが、必ず同数の数を出し合って、技を競う遊びである。数の計算が必要となり、勝負がつきまとうことになる。小石や貝殻では、お手びら、お握り、おいっちょ等の掴み方があり、算え方には、六個を基本とする。一六騎(ひとろき)・二(ふた)六騎・三(み)六騎等ひと、ひたからとうまでを算えていた。その遊び方は多種多様であり、その動律に合せて唄も謡われていた。しかしそれはお手玉遊びと多くは共通していた。六騎と呼び、それを基本とすることは、古い軍法から来たものであろうと『岩手県史』は述べている。
す 縄とび
これは主として女児の遊びで、次の児唄を歌いながら五・六人で遊んだのである。
〇大波小波
でぶちゃん
ころころ
スッポンポン
〇お嬢さん
今日は
じゃんけんぽん(けんをする)
まけたらサッサとおにぎなさい
いつすこ にに さんさん しいたけ
ごぼうのむきがら 七すこや こうごと とう
一つはひぇれ 二つはひぇれ 三つはひぇれ
一つぬげろ 二つぬげろ 三つぬげろ
〇大波小波
しっくりげぇすて あっはっは
ひふみつたがじいさん
ずぎんこかぶって ちょこちょこ
あるげば えつかかつか そりゃにげろ
大波小波 ねごかねごかすっぽんぽん
せ 風船つき
(これも女児の遊びである)
一(ひと)よに二(ふた)よ
三よに四よ
いずきて見ても
ななこの帯を
矢の字に結んで
九を十れ
そ かぐれかごとかご
かぐれかごとかご
とになったら
かあぐれろ
かぐれかごとかご
十になる婆様は
笠こ被ぶて
かぐれる
かぐれかご とかご
百になる婆様は
猫の皮被って
珠数かげで
かぐれろ
隠れ遊びのとき、鬼のいうことばで、「ようえ」の返事を待って鬼がさがしはじめるのである。
た 鬼けぇこ
鬼けぇこ とけぇこ
鬼こになったとて
ごしぇやぐな
まだけぇの けぇーのけぇ
このように呼びながら、鬼から遠ざかろうと逃げ廻るのである。
2 童(わらべ)のための歌
あ 呼びかけ歌
単純な呼びかけ言葉が、遊びを伴う歌となり、相手と共演し、競技するに至って、次第に律動的な遊戯となり、歌となり、立派な歌謡に成長している。これは明治・大正・昭和とすでに百年に近い。古いものは旧藩時代から謡いつがれているであろうし、時代や環境によって少しずつ変化したものであろうが、よくも伝わったものである。歌詞の中には教訓的なものが多いので、単に偶発的なものでなく、児童に社会生活をなさしめる面において効果が大きかった。
幼児がことばを話すようになってから、少年少女と成長するにつれて、遊びも変化し、歌も変って行くが、その歌は、祖母から、母から、伯叔母から、姉から、友達から習い覚えることが多かったであろう。
簡単な言葉で囃したてる童のことばは、未完成で歌のことばとなっていないが、同じ言葉の繰り返しにより、音声に調子がつき歌となっていく。
泣き泣き 別当
お山さ 猫三疋
しよって 馳しぇろ
泣ぎびちょ
きびちょ
家(え)さいって ままけ
まだごこやげねぇ
猿のけっつぁ 真赤だ
牛蒡焼いで ぶつけろ
がらがらず ちょちょず
ちょず ちょず ばばけ ばばけ
大風は吹げ
がらがらあ風は吹げ
あげぇず あげず
宿けらぁ とまぁれとまれ
くぼくぼ みすたげ
くぼくぼ ままたげ
つぶぅよ つぶよ
むきつぶ つぶぅよ
お醤油で煮つけて上(あが)らんしぇ
いやちゃかぽん
とぬげた
はぁはぁ
猿や
干物ほすて
山のばっけに
くられべぇな
べろべろの神は
尊うたい神で
あっちの方さも ぎろっと向き
こっちの方さも ぎろっとむく
男とおなごと ちょうへんこ
あんまりちょうして 泣がへるな
やれやれお寺の和尚さん 鐘はだぐ
おらもえさ行って 鍋はだく
おらほの隣りの 一人娘
いたわり娘で 桐の箱入りだ
いつか箱虫は食うて 大きな穴あいだ
向いの山で茅刈るは
太郎殿か 次郎殿か
一寸おでぇって お茶あがれ
お茶のこには何々 天下一の香炉箱
中あげて見だれば
赤い小袖十二 白い小袖十二
十二の中からお目様おでぇって
上さ向ってチッチッと 下さ向ってチッと
あんまりチョチョ早くて
鎌倉堂に火がついて
盲人が見(め)けて
きかずがきぎつけで
足ぼこがはしぇで
てぼが消した
単純な呼びかけ詞から、段々に成長して、対象物を色々に擬して歌詞となし、年齢もまたませてきて、ときには遊戯を交えるようになり、お手玉・手まりつき歌に化して行く前提がうかがわれる。
い 子守歌
子守歌は、泣く児をあやしたり、寝せつけるときに、ねんねこやーいの一連の歌謡をこむすめとか、両親とか、老婆の子守姿が目に浮かび、幼児のうたう歌ではなく大人びたものである。幼稚な歌である呼びかけ詞から、すでに脱出し、メロディーとしても完成されている。ねんねこやーいとうたうのが、懐かしい瞑想へ誘う歌である。
ねんねこやーえ ねんねこーいえー
ねこねこ ころころ ねんねこやーえ
ねんねこ山の白犬
一疋ほえれば皆吠える
ねんねこ ころころやー
ねんねこやーい ころころ
ねんねこしておきたら
ごことまんまど あげましょう
ねんねこやーえ ねんねこーやー
ねんねこして起きだら
いもこほどこ掘ってきて
煮だり焼いだりしてあげる
ねんねこやーえ ねんねこやーえ
坊やはよい子だ ねんねせなー
坊やのおもりはどごさえった
野こえ山こえ里さえった
里のみやげに何もろうた
でんでん大鼓にふり鼓
おきあがりこぼしにいぬはりこ
ねんねこやい ころころ
ねんねがもりが どこさえった
山をこえて 里さえった
里の土産に 何もらった
でんでん太鼓に ふりつゞみ
ねんねこやい ころころ
ねんねこして起きだら
小豆おまゝに ごこあしぇで
煮だり焼いだり あんげましょ
ゆきゆき桃の木
桃こなったら たもれ
お祖父さんさ 五つ
お祖母さんさ 四つ
おどっつぁさ 三つ
おがさんさ 二つ
あにさ 三つ
誰々さんさ 五つ
う 動物の歌
〇からすからす
かあらす からす
うんな 行く道さ
御堂コ 建つて
行がれねぇ程に
婆ぁもさ寄って
小豆まゝくって
お椀コ洗って 椀コも箸コも貸さねぇで
お膳コ拭いで
かぁかぁと飛んでた
〇からすからす
からすからす うな父(てであ)どごさ行った
しゃんしゃんど町さ糀買いさえた
その糀どごさやった 酒こにつぐた
その酒どごさやった 皆のんですまた
その粕どごさやった 隣りの犬こさけだ
その犬こぁどごさやった 死ですまた
その皮どごさやった 太鼓(てえご)に張った
その太鼓(てえご)どごさやった 長者殿の人達ぁ 打って打って打裂いた
〇とんび、とんび
とんびとんびおらほの家(え)の前(めえ)で
とんびとんび
おら家(ほ)の家(え)の前(めえ)で
一回(しとげえり)廻って見へろ
雄鳥(おとご)だら脇差
雌鳥(おなご)だら針箱
買ってけら
買ってけら もう一廻り(ふとまわり)廻(まわ)って見(め)へろ
〇ほたるこい
ほう ほう 螢こい
山路こい 甘水こい
行灯の光を ちょいと見てこい
螢来い
そっちの水ぁにがいぞ
こっちの水ぁあぁまいぞ
ほう ほう 螢こい
ほたるさん ほたるさん
あっちの水は にがいぞ
こっちの水は あまいぞ
ほたるさん ほたるさん
昼は草葉の露のかげ
夜は高 高 高提灯
ほたるさん ほたるさん
ほう ほう 螢来い
山路来い 行灯の光をちょいと見て来い
ほう ほう 螢来い
あっちの水は苦いぞ
こっちの水は甘いぞ
ほう ほう 螢来い
山路来い 行灯の光をちょいと見て来い
ほう ほう 螢来い
整った唄で、呼びかけ詞を脱出している。
〇熊さん熊さん
熊さん 熊さん 廻れ右
熊さん 熊さん 両手をついて
熊さん 熊さん 片足あげて
熊さん 熊さん 体操はじめ
熊さん 熊さん 勉強はじめ
熊さん 熊さん さようなら
遊び方は、歌い手と、動作する子と分れて、歌詞のような動作をして遊ぶ。
〇雀、雀
雀 雀
どの雀ようござる
何雀ようござる
何まゝかしぇる
小豆飯に鮭のよ
羽子なくて行かれねぇ
羽子けらー来え来え
雀 雀
すずぅめ 雀
どこの雀でござる
〇〇雀でござる
何まま食(か)しぇる
小豆飯さ 牛(べご)の糞
そんだば えがね
あずぎまゝさ鮭のよ
羽こなくて行がれねぇ
羽こけえら来うい来い
山あって行かれねぇ
山越えてこうえこえ
川あって行かれねぇ
川越えて来うえ来え
鬼こ居て行がれねぇ
鬼こ えねぇ間に来うえ来え
ちりんちりん
遊び方は二つに分れて、相互に呼びかけて歌う。歌が終って、他方の群から招かれた子が、それ群へ馳けて行くが、その途中鬼が居ってつかまえる遊びである。
雀と同じ遊び方に次の二つが残っている。
今日は誰を呼びましょう
可愛い〇〇さん呼びましょう
何魚(さがな)で呼びましょう
油揚・豆腐で呼びましょう
味噌摺鍋すれ一・十・百・千・万
ほうしい ほしい
どの子欲しい
〇〇子を欲しい
何を呉れる
ほんとのまんじゅう
それでも 足りねぇ
手箱・針箱みなくれる
それでも 足りねぇ
箪笥・長持 みなくれる
それでも 足りねぇ
日本国中 みなくれる。
雀々どごさ田を作った
雀々 何処さ田作った
柳のうらさ 田作った
なんぼ稲刈った
一束三把刈った
馬コに三把 牛コに三把
われぁ三把 背負って
ざんぐぼんぐといったれば
犬コにわんと 吠えられて
あどをきろっと見たれば
鎌倉林火ついて
目くらは 見つけて
きかずは 聞きつけて
足ぼこは 馳しぇで
手ぼこは 消した
〇おらどごの鼡(子守唄・毛毬唄等)
おらどごの鼠は あまりわぁる鼠で
仏の油ひぬすんで ひってぇこびさ ひなぐって
今日の町さえぐべが あしたの町さえぐべが
今日の町さえったれば 犬こにわんと吠えられで
うしろきろっと向いだれば つんきれはんきれ めつけで
洗屋で洗って 染屋で染めで 仕立屋で仕立て
太郎坊に着しぇれば次郎坊恨みる次郎坊さ着だれば太郎坊は恨みる
京から下った姫こに着しぇで
かねの足駄はがしぇでかねの杖つがしぇでかねの笠をかぶしぇで
次郎太郎送ってた 何処まで送ってた 堂の前迄送ってた
堂の前に何あっけ 箱こあっけ 箱この中に何あっけ 息子ぁあっけ 息子の名を何ともうす 八幡太郎と申します
八幡太郎の御厩に おんま何匹つなーいだ 三十六匹つないだ
どの馬の毛色ぁえ 中の馬の毛色ぁえ
つぎきれはぎきれ 見(め)付て
洗屋で 洗って 仕立屋で 仕立て
太郎坊に着せれば 次郎坊はうらみる
次郎坊に着せれば 太郎坊はうらみる
京から下った 三つ子に着せて
金の杖つがせて 金の足駄はがせて
何処まで 送てった
堂の前まで 送てった
堂の前に 何あっけ
御堂コあっけ
お堂コの中に何あっけ
箱コあっけ
箱の中に 何あっけ
かいこあっけ
かいこの中に 何あっけ
ひっこ(笛)あっけ
ひっこの中に 何あっけ
むすコあっけ
むすコの名は 何という
八幡太郎と 申します
八幡太郎のおん前に 御馬何匹つんながった
三十六匹繋がった
どの御馬の毛色え
中の御馬の毛色え
あぶらめって どろめって
貝ですった鞍おいた
錦のたずなをよりにかけて
あっちゃ 何色や およおよおよおよ
こっちゃ向いちゃ およおよおよおよ
およくらめてはやされて
油めってどろめって 貝ですった鞍おいて
綿の手綱ふりまいてのり出した藤十郎めどこまで乗ってった
幅まで乗ってった 幅の上の鼠こぁあまりわぁるい鼠で
上の方さもちょろちょろ 下の方さもちょろちょろめぎぁすぎで
百に米ぁ一石だ 十文に酒十ひやげ
え 植物の歌
友達な友達な
友達な友達な
花摘みコ行ってこない
何花摘むに
桜はな摘むに
一枝折って 引っかつぎ
二枝折って 引っかつぎ
三枝目に 日は暮れて
杣の中に 宿とって
朝に起きて みたれば
金銀のような 上臈は
一杯参れ酌とな
二杯参れ
肴なくて 参らんか
おらとこ お肴は
高い山の 竹の子
低い山の ひっこのこ
ひっこと けぇんコと 蛤貝コと 庭で踊るに
雀チリンポロンと 飛んでった
友達な友達な
友達な友達な 花折るにあんでごじぇ
何花折るに 桜花折るに
一枝折って 引っかつぎ
二枝折って 引っかつぎ
三枝目に 日は暮れて
蕎麦打つ小屋に 宿とって泊って
朝におきて みたれば
きぎの様な旦那ど
臼の様な女郎ど
一杯まいては ちゃぐどな
二杯まいては ちゃぐどな
おらほの肴は高くて参らんか
低くて 参らんか
高い山の 竹の子
低の山の ひっこのこ
庭で踊りこ雀
友達な友達な
友達なぁ友達なぁ
花摘みに行ってごじぇ
何花摘みに
一枝折って はひっかつぎ
二枝折って はひっかつぎ
三枝目に 日が暮れて
蕎麦打つ小屋さ 宿とって泊たれば
朝ま起きて見たれば
きぎのような女郎
一杯目に ひゃく((客))どな
二杯目に ひゃく((客))どな
肴なくて 参らんか
おらどごの 肴は
高いどごの 竹の子
低いどごの ひこのごひっこ
ひっこどけぇん((貝))こど蛤貝コと庭で踊コ
雀 ほろんからんとおっ飛んだァ
以上の友達なは、一定のリズムをもって歌われ、お手合せ遊戯に用いられていたが、毛毬つき等にも使われていた。
お 天然の歌
〇雪もこんこん
雪もこんこん
霰もこんこん
こんこんのお寺さ
あずぎばっととまって
小豆ァすみすみ
豆子ァころころこーろんだ
〇とうでぁさん
お月様(とであさん)お月様
赤げぇぽゝくなんしぇ
白(す)れぽゝくなんしぇ
まだ米ぁうるげぇねぇ
あさどきぁときよ
か 遊戯
〇向うの細道どこの道(拾数人二組に分かれる)
甲組(手の下を通る組)「向うの細道どこの道どこの道。」
乙組(手を上げて通す組)「天神様の細道だ細道だ。」
甲「少ぉし通して下しゃんしぇ下しゃんしぇ。」
乙「ご用のないもの通しゃせぬ。」
甲「天神様に願かけて。」
乙「通らんせ通らんせ。」
といわれて甲組が一列になり、乙組の下を通る。これを繰り返す。
〇かごめかごめ
かごめ かごめ
篭の中の鳥は
何時何時出はる
夜中のばんげ
すくらもくら やめで
誰のうすろ
誰子さんのうすろ
誰子さんのうすろで
起き上がれ
かごめ かごめ
かごの中の鳥は
いつ出て遊ぶ
夜明の晩に
鶴と亀とすべった
うしろの正面だあれ
ゴッチャゴチャ
誰の後に誰ぁえだ
かごめ かごめ
かごの中の鳥は
いついつではる
夜中のばんげ
つくらもくら やめだ
おじゃあがれーよかね
ねまじんじょ
立てじんじょ
おさえてたもれ
二つ三つ
遊び方は円陣を作り、鬼を目かくしさせて中心におき、歌いながら手をつないで廻る。歌い終ると同時に止まる。鬼は自分の背後にいる子の名を当てる。当てれば円陣に加わり、名を当てられた子が鬼になる。
〇開いた 開いた
開いた 開いた
何の花が開いた
れんげの花が開いた
開いたと思ったら
いつのまにか つぼんだ
つぼんだ つぼんだ
何の花つぼんだ
れんげの花つぼんだ
つぼんだと思ったら
いつの間にか開いた
遊び方は円陣を作り手をつないで、開いたで後進しながら大きな円をつくる。そのまゝで足踏みをして、つぼんだで円の中に歩みより小円となる。これを操り返すのである。
〇通りゃんせ
通りゃんせ 通りゃんせ
ここは どうこの細道だ
天神様の 細道だ
少し通して くなさんせ(くだしゃんしぇ)
御用のないのはとほしゃせぬ
この子の七つの お祝いに
お札をおさめに 参ります
いきはよいよい 帰りはこわい
こわいながらも 通うりゃんせ
通うりゃんせ
遊び方は門番と天神参りの行列の組を作り、門番と行列の先頭が歌で呼びかける。この子の七つのお祝いに―先頭の子が、後に並んでいる子供らの頭上をチョンチョンと指さす。門番は行列を通してやりながら「行きは……通うりゃんせ」と歌いながら、両手をつないで行列の一人一人を中に入れて、左右に外へ送り出してやる。
〇坊さん坊さん
坊さん 坊さん
どこ行くの
私は田圃の稲刈りに
そんだら 私も連れしゃんせ
お前が行(え)ぐど邪魔になる ホーホー
遊び方はかごめと同じである。
き お手玉の歌
ひーふ やーまくろくしぇしょで、一ちょかした。
ひーふ やーまくろくしぇしょで、二ちょかした。(以下十丁まで操り返す)
一どや、二どや、三どや、四(よ)いと、五つむさし、むさし、七おか八しま、九州、東京。
隣りのおばさん、時計は何時、一時、二時、三時に近い。早く御飯の仕度をしましょう。
一から、二から、三から、四からの前に、あざみの花よ、咲いたか咲かねえが、今さけよ ポーン
一つぶっけてトンヤラ、二つぶっけてトンヤラトンヤラ、三つぶっけてトンヤラ(以下同じことを繰り返す)
たのみつ、おまえの向うの、お山の雨ふり、花が咲いたか咲かねぇが、こら一ちょう ていばこぇ。(手箱へ)
たんたんたいこ、ひのたいこ、あぶらのよんなら、とってもこい、たんたらたらみず、はっきり、れんげの花びらくの、こら一ちょう手箱へ、となりのあねささ、お一つかしました。
たんたん滝の水、今日は蓮華の花見ずらの、こら一ちょてぇばこい。
向うのお山の雨ふり花が、咲いたか咲ねぇが、私知らの、こら一ちょでばこい。
向うのお山の雨ふり花が、咲いたか散れたが、私知らの、こら一ちょてぇばこい。
隣りの姉さんさ、お一つ一ちょ貸し申した。
お一つー お二つー お三つー おみんなおまくらかえして、おってんばらりん、ちょっかいなすちょっかいな、花さきはなも、おでぇすこ、おんだいびっき、びきせんびっきも、おしゃらず、おしやらず、おにぎぇすよ、おかえすよ、もんでさばった、おかえしやばった、一ぴょう二ひょう三びょう四ひょう五ひょうますたもれ、おまけぇしょ、しぃとあすたん二あすたんおみあすたん四あすたん五あすたん五つもたんたん、たんたんたいこのたいこ。
一((日にち))れつだんぱんはれつして、日露戦争はじまった。さっさとにげるはロシヤの兵、死んでもつくすは日本の兵。五万の兵をひきつれて、六人残して皆殺し、七月四日の戦には、ハルピンまでも攻入って、クロバトキンの首をとり、東郷大将ばんばんざい。十一なみこの墓参り、十二は二宮金次郎、十三たぬきの石の下、十四は四国の金毘羅さん、十五は五月の鯉のぼり、十六ろくやの女中さん、十七七やのお嬢さん、十八八十のおばあさん、十九は九十のおじいさん、二十は東京の二重橋。
向う通るは吉十郎さんではないかいな。紺の股引「びろーど」の脚胖、御前上(のぼ)るかわしゃ今下る。下り土産に何々貰うた。一分笄(かんざし)、二分の雪駄、紙にくるんで元結(より)もて〆めて、姉コぁ腰元さドッタラヤェーと投げだ。投げだ拍子に鼻緒が切れだ。鼻緒切れだら緒立ででたもれ、わたしゃならんよ、よしこに頼め。よしこに頼めば、銭百がぁあがる。銭の百ばり私しゃ進じましょう。
お手玉とり歌は、お手合せ歌と共通するが、お手玉とりが上達すると、座ってお手玉をとることになる。手のひらで天上に跳ね返していたものが、座っての遊技になると、玉を算えたり、揃えたり、はじいたり、手の上下を廻したり、などして複雑した動作に変ってくる。律動が変化するに伴って、歌も変化して複雑になり、一呼吸してから、また歌うというように千変万化し、繰返をつゞける長い歌となる。
お手玉とり歌は、まりつき歌と区別しがたく、どちらにも歌われていた。
く 手合せ歌
〇せっせせ
青山どでがら 白い蝶々三つ三つ 赤い蝶々三つ三つ
その中女の子が 袴をはいて すぽんぽん すっぽんぽん
〇ジョンキリ ジョンキリ
ジョンジョンギリギリ
細屋の裏道 オッチョコチョン
〇鳥どごさ行ぐ
薩摩の山
さつま山から谷底みれば
小さな子供が小石でござる
うちの子猫が運動場でボロボロボロボロ
その涙をお袖でふきました。ふきました。
ふいたお袖を盥で洗いましよう。洗いましよう。
洗ったお袖を二階に干しましよう。干しましよう。
干したお袖を箪笥にしまいましよう。しまいましよう。
しまったお袖を鼠にかじられたかじられた。
かじられたお袖をぼうやに売りました。売りました。
売ったお金は、一銭、二銭、三銭、四銭、五銭。
二月三月花盛り、鶯ないた春の日も、楽しい時も夢の中、五月六月実がなれば、枝から揮(ふる)い落されて、紫蘇にそまり赤くなり、七月八月暑いころ、三日三晩の土用干、思えば辛いことばかり、それも世のため人のため、皺は寄っても若い気で、小さい君等の仲間入り、運動会にもって行く。まして戦のその時は、なくてはならぬこの私。
お手合せの歌は、お手玉とり歌と区別しがたく、両方共通でうたわれることが多い。普通は二人で手の平を合せるが、三人ですることもある。のろのろしたお手合せは見ることがなく、キビキビした動作が多いから、テンポの早い歌が多い。せっせっせとうたい出すのがこの歌の特長である。
け 手毬・綾子
一かけ、二かけ、三かけて、四かけて五かけて橋をかけ、
橋の欄干に腰をかけ、遥か向うを眺むれば、
十七八のねえさんが、花や線香手に持って、
ねえさん、ねえさんどこへ行く。
わたしは九州鹿児島の、西郷隆盛娘です。
明治十年三月の、
鉄砲にうたれた父上に、
お墓詣りに参ります。
受け取った。受取った。どんなた様から受取った。
あれあれ向うの屋敷の白壁造りの
格子造りの
竹の暖簾の お蝶こさんから受取った。
シシシッカと御渡し申します。
とんのさま殿様、どごさオンデェルとんのさま
雉子のお山サ雉子捕るに
雉子はけんけん鳴くならば
早くもんどれ殿様
おれが死んだら、墓のあたりさ煙草を蒔いて
通うる和尚さん何だと云わば
筆と硯とたんばこへ煙草へ
向うの庵寺こ誰建てだ
八幡長者の小娘が、眉目(みめ)よし、鼻よし、姿よし
知るも知らぬの大道を、歩め歩めと誘われて
御暇下され旦那様、暇けるには易いども
誰と抱さて帯買て貰うた
帯にゃ短い、襷にゃ長い
江戸で晒して、大阪で染めて、大阪染は、よい染だ、良い染だ。
赤川の末々、赤川おはっこぁお猫コだまして
お茶碗ブカシてつぐにつがれず、買うに買われず
一匁ヤレーヤレー、二匁ヤレーヤレー、三匁ヤレーヤーレ
三本柳さ雀巣くうて、落ちて大鷹にさらわれた
どんどとえーど神様のここは札場の盛りどん
ヒーヤ、フーヤ、ミーイーヤ、ヨ、イツ、ムに、七八は、九つトホー
一つお前に一丁貸した、御白白白白木屋のお子様へ、三衛ざさえ、
門には条八色男。
名所名所、御国は名所。前は海なり、後は御山。後山から鶉はふげぇる。何とふげぇるや、五吹六吹、下へさがれや古屋はござる。古屋おいても育てゝごじゃれ、逢うか逢うかと七年噺し、南無釈迦ドッコイ、熊の鈍作、肩にかけたる惟子、片新所の梅の折り枝、中は五条のその橋、ソンソンそり橋渡らんものか、コキラコキラ小左衛門は何処で討れた、鹿島街道の、茶屋の小娘に討れた、うたれて面目ないとて、鴉櫓(やぐら)で身を捨てた一丁々々。
仙台の仙台の、尼は娘はよい娘、茜の小袖の茶の縮緬、裾を巻いたらしたらして、しょならしょならと行く所、親は見てさえ善いと見る。況して他人は只惚れべ、只も惚れらば晩ござれ、晩の枕はどこ枕、東枕に窓の下、窓はケッケラ窓、戸は明かず、戸の下から、そろりそろりと手を伸べて、ここは情けの金(かけ)処、親に五貫、子に五貫、況とおじ(ゆ)こに四十五貰、四十五貫の金持は、高き豆買って何にする。船に積む。船は何処船、秋田船、秋田船(ふーね)と申せども、船は沈んで死ぬならば、脇差太刀(かたな)は父(とと)様へ、葛篭(つゞら)三つは母(かか)様へ、化粧道具は姉様へ、オーラは姉さんは、髪も結わず、面(つら)も洗わず椿油でドーロドーロ。
まりつき歌・手玉とり歌には重さを扱ったものもある。物量をはかる初歩のものとして考えられたものであろう。従って庶民教育的要素が含まれて発生したものである。
一もんめぶんど
一もんめ ぶんど
二匁 はしけ
三匁 しおなめ
四匁 おかみ
五匁 なわなえ
六匁 髪ゆい
七匁 ぶんすけ
八匁 びんとれ
九匁 お手箱
十ちょうの お引出
一匁ぶんぞ
一匁 ぶんぞ ぶんすけ
二匁も はーけ はぎ
三匁 しおなめ
四匁 おーがめ おんがめ
五匁 縄なえ
六匁 髪ゆえ ぶんすけ
七匁 びんとれ 髪ゆえ
八匁 ぶんすけ ピンとれ
九匁 お手箱
十匁 お引出
まりつき歌に乙女(むすめ)を主題としたものが多い。時にはある時代に世間の評判となった実在の女性を歌詞に取り入れたこともあったらしい。しかし長くうたわれている間に、首尾一貫していた歌詞も、分断され、他の歌詞と組み合されて、訳が分らなくなり、いずれが原歌か、元歌が全くわからなくなってきている。
おらが姉さん三人ござる
おらが姉さん三人ござる
一人姉さん太鼓が上手
一人姉さん鼓が上手
一人姉さん下谷にござる
下谷一番伊達者でござる
五両で帯買て三両でくけて
くけめくけめに七総さげて
折り目折り目に口紅さして
今年初めて花見に出たら
寺の和尚に抱き止められて
よしゃれはなしゃれ帯切れしゃんす
帯の切れるのが厭いはしないが
縁の切れるは結ばれぬ
前は結んで後を締めて
締めたところへイロハと書いて
イロハ子供だちゃ伊勢々々参る
伊勢の長者の茶の木の下で
七つ小女郎は八つ子を産んだ
産むにゃ産まれぬおろすにおりぬ
向うを通るは医者ではないか
医者は医者でも薬箱持たぬ
薬用なら袂にござる
これを一服煎んじて飲ましょ
虫も下りればこの子も下りる
若しもその子が男の子なら
寺へのぼせて手習させて
京へのぼせて狂言させて
寺の和尚は道楽和尚で
高い縁から突き落されて
かんざし落し小枕おとす
お仙やお仙やお仙女郎
そなたのさしたる かんざしは
貰たか拾たか美しい
貰いも拾いも致さぬが
お仙の針箱開けてみたら
牡鶏牝鶏中よし小よし
ヒソヒソヒラノカイ ホーホーホラの貝
お目出たやお杯
おらが姉さん三人ござる
おらが姉様 三人御座る
一人姉さん 太鼓を上手
一人姉さん つつみを上手
一人姉さん お下やにござる
お下や一番 だてしゃでござる
五両の帯買って 三両でくけだ
くけ目くけ目さ 口紅指して
七つ小十郎が やつぐろ踏んで
向うを通るは 医者ではないか
医者は医者でも 薬箱持たの
よもぎ菖蒲を 細かに刻み
それを煎じて 飲ませたならば
寺へのぼせて 手習ならせ
将棋をささせら 日が暮れる
おらが師匠は 不調法な師匠で
高い縁から つき落されて
こうがい落し 小枕おとし
横丁のおしやんこ 拾った
拾ったか貰たか 美しい
誰にけるべと 持って来た
お前にけるべと 持って来た
お前は死んだら 今日おたやで
あしたは七日で 牡丹餅
弥右衛門弥右衛門
弥右衛門弥右衛門 多けれど、よこざ((町))弥右衛門 なか娘、年は十六名をおろし、あたりござん に貰われて、余り器量の 佳いままに、赤い箪笥を十二竿、白い箪笥を十二竿、是程揃えて やるからに、二度と戻るな 出て来るな、帰るまいとは 思えども、西は曇れば雨となる、東が曇れば風となる、北や南に雲あれば、忽ち嵐と現れて、千石つんだ船でさえ、万石積んだ船でさえ、風の吹き様で出てまいる。
弥右衛門弥右衛門
弥右衛門弥右衛門多けれど、よこざの弥右衛門中娘、年は十六名はおせん、あまり器量のよいまゝに、どだりこんだりもらわれて、おやというもの十二支の、十二支の手箱をさし揃い、其程揃えてやる中に、むくれて御座るはおろせども、おろすまいとは思えども、日本照らしのお日さんさえも、西に曇れば霜となり、東に曇れば雪となり、雪にまされて死んだらば、水入こそでさ山寺の、山寺くずしてどつっいて、どーのあたりまえさけしの花、つむに一枝おりにはお里にかけ、三枝四枚に日がくれて、一夜の宿を下さんせ、夕べ夢見たあなたの夢見た、金のさかずきさあーしましょう一丁一丁。
おんしょんしょん
おんしょんしょん、しょうてんのおしょうさんが、まるこいこけしをはらませて、なにをしたといったれば、男むすこの上息子、育ててみたれは赤びっき、おかさんおかさん抱いてくなんしぇ、おらはそんなもの抱いたごとねぇ、おどさんおどさん抱いてくなんしぇ、おらはそんなもの抱いだごとねぇ、お母さんが腰巻衣裳にして、お父さんがふんどし帯にして、隣りに遊びにやったれば、おらはこんなものと遊んだことはない、茣蓙さくるんでべぇっと投げだ、今日はお坊この四十九日、お墓参りに行ったれば、手ッコと足コがちょと出はった、十二支の手箱をさしそろえ、それ程揃えてやるからに、むくれてござるはおろせども、おろすまいとは思えども、日本照しのお日さんさえも、西にくもれば雨となり、東にくもれば雪となり、雪にまされて死んだらば、水入こそでさ山寺の、山寺くずしてどっへいて、どーのあたりまえさけしの花、つむに一枝おりにはおりてかけ、三枝四枝で日が暮れて、一夜の宿を下さんせ、ゆうべ夢見たあなたの夢見た、金の盃さあしましょう一丁一丁。
ここ御村の中村の
ここ御村の中村の、中村名主のなか娘、年は十六名はおせん、おせんの友達四十九人、四十九人の友達は、今朝の寒さに奥山へ、仏の信心菊の花、一分煙草に二分煙草、三分煙草に火をつけて、おせんにやろうと思たれば、おせんにいやだと振り向いて、お母さんの持つのは糸車、坊やの持つのは風車、くるくる廻って先ず先ず一貫貸しました。
手毬は座った場合は、歌いながらつき続けるが、立った場合は、手で毬をつきながら足を通してくぐらせ、交互に左右の手足を組合せ、途中失敗すれば相手に譲ることになる。
毬つき・お手玉とりは、一定のリズムに合せてうたうから、同じ歌詞が同じ調子にうたわれることが多い。従って、毬つき歌とお手玉とり歌の区別は出来ないのである。
単純なものには算え歌がある。お手玉歌で述べた「ひーふーやんま、五六せんしょで一丁かした」を十丁まで一くぎりとし、交代をしている。
手毬りにしても、手玉とりにしても、技術が進めば、歌も歌詞も長くなり物語風に発展をして行くのであった。
〇十二ヵ月の行事
正月は門に門松内には((おたちより))手掛手掛盆には萱や勝栗 ほんたわら
二月はにんに凧(はた)上げ空までとーどけ春の景色で おもしろや
三月はお雛遊びにおさどきなし((あがうきながし))ますだい様((だいりさま))の とり合せ
四月は四月八日のお釈迦の誕生お釈迦参りに 孫つれて
五月は菖蒲さすやら軒端の下で子供よりより 花いくさ
六月は女帷子(のんの)布晒(のの)清水参りに孫つれて
七月は盆に菩提のおみぎつ様は切篭灯して おもしろや
八月は米屋豆屋の姉さん達は芝居あやつり
ゆくとても小袖貸ましょうか色小袖
九月は稲の刈り初め刈りおさめ におに積んだり
はせにつんだり おもしろや
十月は雪を丸めてお玉とつーけて抱いてねたれは解けとーけて解けて流れて三島へおりて三島女郎衆の化粧水
十一月は二十四日のお大師様に小豆お粥に団子入れて
十二月は年取祝に餅を搗く餅を搗いたら祝い餅 十二ちょ十二ちょ
〇十二ヵ月の行事
正月は一にお手かけ 二に銚子 三によろこぶはさまれて
二月は二に天ばこうらまとつえて 明けてみたれや文ばかり
三月は桜咲いてし世の中に つつみたいこの音がする
四月は四月八日のお釈迦の誕生 お釈迦参りに孫つれて
五月は菖蒲さすやら 軒端の下で 子供よりより花いくさ
六月は女かたびら布さらし 清水参りに孫つれて
七月は盆の菩提のおみぎつさまは きり小とぼして おもしろや
八月は米屋豆屋の姉さん達は 小袖貸しますか色小袖
九月は稲の刈り初め刈り収めにおに積んだり はせに積んだり おもしろや
十月は雪をまろめて おだまとつけて抱いて寝たれば とけとけとーけて とけて流れて三島へお一りて みしま女郎衆の化粧の水
十一月は二十四日の 大師さまは 小豆おかゆに だごいーれて
十二月は年とり祝いに小餅を搗く 年をとったり 祝いごと
こ 祭祀・行事の唄
〇お正お正お正月
お正お正 お正月
松たって 竹たって
よろこぶものは お子供衆
いやがるものは お年寄
旦那のきらいは 大晦日
ひと夜明くれば 元日で
年始の御祝儀 いたしましょう
お茶もてこい お湯もてこい
吸物なんぞは はやもてこい
ヒーヤ フーヤ ミーヤヨ イツムにナナヤは
ココノツトオ まずまず一貫 おん貸し申した(手まり)
〇昨夜恵比須講に招かれて
正月 門松
二月 はたあげ
三月 雛様
四月 釈迦様
五月 御節句
六月 天皇様
七月 七夕
八月 八朔
九月 くねんで
十月 恵比須コ
夕べ恵比須コによばれ参ったけぁ
鯛の浜焼 雀の吸物
かねのお箸で 一杯吸いましょチュッチュッ
(この間指を口に当て二度吸う真似をする)
二杯吸いましょ……十杯吸いましょ
まずまず一貫 お貸し申した。
〇四十九日の墓参り
さとさん さとさん 何処へ行く
なんばん畠さ 草取に
犬コに吠えられて 笊かぶった
さとさんその晩 腹病んで
男息子の 上息子
育てゝ見れば 赤びっき
お父さんお母さん 抱いておくれ
俺はそな者 抱いた事ない
抱いた事ないから 茣蓙コさくるんでぶん投げろ
明日はお坊コの四十九日
お墓参りに 行ったれば
手コと足コと 出はてらけ
そこで一と泣 泣いて来た
一や二や三や四 五六で七八は九つ十
これでお前さ 一ちょ貸した
祭祀・行事は、農業を営むものにとって、その作業をすすめて行く上に誠に重大であった。従って農事暦の一面を物語るものであり、その意味では遊びの間に年間の祭祀・行事を辨えて行くことが含まれている。するとこれら歌詞は、生活上不可欠の教育資料として、村々に伝えられ、しかも子供中心のうたいものとして、庶民教育に知らず知らずに利用されていたことが知られる。
二 舞踊
1 剣舞
剣舞は仏教を普及するために、従来からあった念仏踊りの変化したものであるといわれている。
本村に伝わる剣舞については由緒は明瞭ではないが、大釜城が敵方に攻囲され、篭城。武士の守備良好なるにより、どうしても敵方が攻略することが不可能となる。一案をした敵側は、お盆を利用し、武士が念仏踊りの旅僧に扮装して刀剣を隠し、念仏踊りをなし、遂に落城せしめたる由、これを模したのが剣舞ではないかと、言い伝えられている。
太夫を始めとする一団が、往来の途中、墓地や供養塔や仏閣寺院があれば、必ず停ち止って念仏をとなえ、供養していくのが例となっていたという。
往時盛んだった剣舞の名残を止める石塔が、現在篠木に三基、鵜飼に一基剣舞供養塔として建てられている。
2 田植踊
本村を含む米を中心とした岩手県の農業は北上川を中軸として発展している。この農業中心の生活が固定して農村の習俗となり伝統となって今日に及んでいる。
田植え踊りは民衆の結束的な踊りと歌であり、神楽とは違っている。農村の習俗として年間五十日位の休日をとり、この休日は農業のお祭りが中心となっている。年の始めに野外で田作畑作を模擬し、その年の豊作を神に祈念をし、晴れ食・晴衣で祝うのである。それのみに満足せず、春の種蒔きから秋の取り入れまで一貫した踊りに仕組み、新たな年に覚悟をきめ、行く先多幸なる夢を托して表現したのがこの田植え踊りであり、その意味では神楽とも共通する。しかし、もっと砕けた大衆性の踊りであり、歌劇にも相当するもので、口上があり、応答があり、歌があり、演技があり、道化があって、農村最大の芸能といっても差支えないといわれている。
田植え踊りは、一年を更新し、覚悟をあらたにし、前途に多幸な夢を托して擬装化した表現がそれである。「稲の種まき」から「水田の代(しろ)かき」「苗取り」「田植え」「田の草取り」「鎌磨き」「稲刈り」「稲こき」「米搗き」「精白」までを芸能化したものであるから、その演出の稽古に数十日を要し、その踊りの一団の人員は三十人を越すような場合もあり、大正年代まではこのような田植え踊りの一団は、正月・二月を中心に招かれて踊り歩いたものである。
この田植え踊りの芸能一座には、少年少女から青年壮年が参加しており、演出に要する楽器・諸道具・衣裳もあって、田植え踊り一座を組織することも容易でなく、豊年が続いたような場合でなければ簡単に組織できなかった。踊りは三番叟・翁舞に始まり、農業行事を歌と踊りに仕組んで演出する外、その途中に漫才狂言や、別の舞踊を挾んで観客を楽しませるという趣向のものであった。従って村方における舞台芸能の最大なものであり、この一座を招く場合は、必ず臨時の舞台を作ったものである。そのため田植え踊りをよぶとなると、村の若衆が数日舞台作りに奉仕をしたものであり、田植え踊りを招待することの出来る家は、村でも指折りの素封家に限られていた。もちろんこの素封家では、田植え踊りの建元となり、その芸能を村の衆に公開するのである。また、その公演を、預め親類・知人に通知して招待し、公演がすむと、踊衆一行を交えて宴会に移るので、その酒宴の座は数十人という大酒宴となるのが例である。この踊り一座を招くことを「田植えを寄せる」と称した。その意味でも村の素封家草分けの本家の対外的な社交として取り上げられる面もあった。
元南部領の田植え踊りの歌は、各地とも大同小異で、踊りの演出も共通している。岩手県の田植え踊りの中心には紫波と遠野の二つに大別されている。
紫波を中心とする本村の田植え踊りの次第は、次の十二段階である。すなわち、一、口上切り、二、三番叟、三、掻田打、四、種蒔五、講釈、六、田植踊、七、笠振、八、刈上、九、扱きこなし、十漫才、十一、はやし舞、十二、狂言となっている。
滝沢村立南中学校郷土研究部第二号『滝沢の歴史』の中で、鵜飼の田植え踊りの形式について次掲のように述べている。
(1)人数とその役目
一団体 二五人~三四人
年 齢 一五歳~三五歳
楽 器 太鼓一人 この人が主に歌をうたう。横笛二人。テビラガネ二人。
踊 り 男四人→馬夫(ばふ)。馬の中に二人はいり、二人は馬方。
女四人→早乙女。一五歳~二〇歳。
人形の馬は、チャグチャグ馬コのように作る。
女型二人。男が女に化けかずらをかぶる。
ソゴソゴ(イッパツ)一人。馬夫の踊りを注意する人。
その他の人は衣裳の世話や踊りに加わる。
(2)場所と時間
民家の庭に舞台を作って踊る。昼は五~六時間。夜は夕食後夜中まで踊りつゞける。家の中では酒盛りをしながら狂言を楽しむ。
(3)衣裳・その他
太鼓打ちは、羽織・はかまの長衣裳。楽器持ちはももひき。馬夫の上着は格子模様でわきに切込みが入れてあり、色は青紫。早乙女は、じゅばん・腰帯・ほっかぶり・花笠。もみまきから脱穀までを動作であらわす。小道具には、扇・ざる・くわ・わらで作った笛。
藤倉勘蔵氏談によれば、紫波郡煙山の高橋三之助氏より、鵜飼の藤倉百松氏が伝授され、その子勝太郎氏に教授されて、鵜飼谷地上の田植え踊りとなり、更に大更方面にまで広まったという。
藤倉勝太郎氏より教示された工藤善雄氏が『田植踊狂言全集』として記録している。その中から田植えのみを拾いあげることにする。
田植えの口上
東西東西とは音高しき、高う御座りますけれど、憚りながら、拙者御免な蒙りまして、不辯舌なる口上を持って申し上げ奉ります。
偖て、天下奉平、国土安穏。万民常楽(じょらく)の御代なれば、地を吹く風は枝をならさず、雨は続けど動かさぬ御代の春。日本は遠い神代より治り、別して、御当所五穀満作祝のため遠方より愚者等の若者共寄り集まりまして、田植えの物真似御目にかけ上げまする様にて御座ります。
偖て、何を申上げましても、未熟なる拙者共の事なれば、ほんの肢(え)の真似、猿の人真似、おうむの口上真似なれども、仙人は人をそしらず、大海で釣りを致しますれば、下手は上手の鑑とやら、何事も悪と悪をばみ吉野の桜花にみ勝さるる、何とぞ御贔屓の程偏にこい願い上げ奉ります。
偖て、銘々いでまして、御礼申し上ぐる筈には御座候へ共、御覧の通り、田植踊りの外、楽屋取込みの事なれば、舌の廻らぬ不便無学の拙者におゝせつけられまして、只今御礼申し上げる様にて御座ります。
偖て、国元に始りますれば、かえだ打、代掻、植付け、刈納め、こきこなし等、暫く暫くの事なれば、御見物様方御退屈遊ばされざるよう御隣りより御隣りに申合せ、ゆるゆる御ゆっくりと御覧の程偏にこい願い上げ奉ります。
偖て、口上辯舌字の違い、仮名違い、何事も悪しき処をば、拙者共に召し下しおかれまして、何事も差しおき始りますれば、三番叟そのための口上左様。
仕付け口上
弥十郎
「おうよいよいどうしたな。これの御旦那様では、大地明けまして御目出度う御座います。あなた様方、こなた様方、惣代様にも、大地明けまして御座います。高う御座りますれ共、拙者御免な蒙りまして田植え仕付次第の口上を申上げる様にて御座ります。そもそも天御中主神より、天神七代、地神五代、終ってその後、伊弉諾尊、伊弉冉尊より人皇の御代となる。人皇に授くべき御宝には、五穀の種を思召され、有難くも、稲荷大明神様は、天竺へ御渡りなされて、五穀の種をば御求め、さあ、わが京めざして御飛びなされてござります。さあ、わが京になりければ、天神天皇に差上げ、神武天皇は御覧じて、夫々五穀の種ならば、日本にふやさんと思召し、偖て、今日天気日柄もよく相吉日にも差当り、紫宸殿には、即ち、甲子の日に御政事あり、そののち御田植えが始ったと御座ります。
さて日本国中は六十六カ国、すぐれにすぐれたで五月女(しょうとめ)、明の方へ三千人の五月女控えおきまして御座ります。
偖て、これの御旦那様の御田の田にとりましては、どこからどこまでで御座ります」
旦那
「おうようしたな弥十郎。御田の田と申すなら、田にとりては、明きの方の田をとれとれよ」
弥十郎
「さらばの御意で御座ります。明の方の田にとりましては、大和・山城・河内・和泉・摂津・伊賀・伊勢・志摩・尾張・三河・遠江・駿河・甲斐・伊豆・相模・武蔵・安房・上総・下総・常陸・近江・美濃の国より千人参りました。飛騨・信濃・上野・下野・陸奥・出羽・若狭・越前・加賀・能登・越中・越後・佐渡・丹波・但馬・丹後・因幡・伯者・出雲・石見・隠岐・播摩の国より千人参りました。美作・備前・備後・安芸・周防・長門・紀伊・淡路・阿波・讃岐・伊予・土佐・筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向・大隅・薩摩・壹岐・対馬の国より千人参りました。右三千人の五月女の嘉称と致しましては、さるこ・さんこ・あんぐりこ・おちょうに、お若に、お竹もかたり、それでもたらずんば、なんばのこ、さんしょのこ、なんとりこまでも相誘い、衣裳なんぞを見てやれば、十二単衣に色小袖、縞の前振りに、会津笠、それに花笠で、風にそよともませつゝ、あきの方へ三千人の五月女、ゆうりやちょうと控えおきまして御座ります。
さて、これの御旦那様の植る御田にとりましては、どこからどこまでで御ざりましょう」
旦那
「おうようしたな弥十郎。左様に五月女を揃えてある事ならば、旦那事は大田作の事なれば、未だにかえ田もうたんでおる。かえ田打ちは揃うてある事かな弥十郎」
弥十郎
「揃いも揃いなから揃うて御座ります」
旦那
「おうこらさえ弥十郎。なから揃うてある事ならば、若者共四五千人も差し揃えて、打ってくれないかな弥十郎」
弥十郎
「さればの御意で御座ります。乱波(らっぱ)若者にとりましては、異国他国の除かれ人にて候えは、彼の乱波で乱波ばかりわかして、中中この弥十郎のいい付にそわん事で御座ります」
旦那
「おう。汝のいい付に添わん事ならば、畔根の葦(よし)をばずんばりとも切りもせず、後小山さ朝雲、パット降ったる節、兎の奴はこうこうやはねしたりや如く(ママ)に打ち定め必定である。それよりは、そのお目先次第に申付けて、打ってもくれないか弥十郎」
弥十郎
「さればの御意で御座ります。かえ田打ちの一の名人には、ここに又、市助・二助・三之助・要助・要八に五助・権蔵・太郎・次郎・四郎・五郎で、これらはねりねり、ねんばとした者に候えば、これらに申付おきまして御座ります。さあ、右、太郎・次郎・四郎・五郎、千丁の鍬はなくてはならない。千丁の鍬を揃えてくれろ、そこでひょうしを頼む」
若者
「一鍬(ぐ)に二ぐ三ぐでゃないか。三鍬に三ぐは六ぐでゃないか。六ぐに四ぐは十ぐでゃないか。十ぐずり十は百ぐでゃないか。百ぐずり十は千ぐでゃないか。千鍬も揃えたな、はいくらさのさぁ、このよい」
弥十郎
「おう。よくも揃えてくれたなこの若者よ。千丁に足らねぇ処さば、この弥十郎・伝十郎、すでにでかけた伝三郎までも相誘うて、小金田外でも歩いてくれろ。小金田外を行く時は、ただでもなるまいまえやっこうて(舞う)参れ」
旦那
「おうこらさえ弥十郎。五月なかばの忙しき節。一人の人を、二人にも三人にもして使うべき筈、どんな奴でも役に立たないものではない。それよりは逢うて参れ」
弥十郎
「おうにとりましてはおうで御座ります。これの御旦那様の小金田表では、水口(みなくち)より十を七をかけて打ってもくれろ。さあ、そこでひょうしを頼む」
若者
「今年の世中は弥勒の世中ではいくらさのさ。秋また八重穂は、さくら八重と咲くべぇな、はえくらさのさ、このよい」
弥十郎
「おう。よくも打ってくれたな、このかえ田打ちよ。物にたとえていうならば、三月黄金、みどりは葉をただずんだるが如くにしばり、八町をも打ってくれたな。この弥十郎ばかりほめてはなるものではない。これの御旦那の御目に留めましょう」
旦那
「おうようしたな弥十郎。さほどにかえ田を打ってある事ならば、しろかき名馬を飼うてあるかな弥十朗」
弥十郎
「さればの御意に御座います。しろかき名馬にとりましては、明や二才、明や三才を千匹程も飼うて御座います」
旦那
「おう。こらさえ弥十郎。明や二才、明や三才では何の役にもたつものでなし、朝飯前に引出せば、手間だれこそすべき筈、それよりは年盛んな名馬はないかな弥十郎」
弥十郎
「さればの御意で御座います。年盛んな名馬にとりては、これ御旦那様の御厩見給えや、裏厩三十三間、表み厩三十三間、双方合せて六十六間の御み厩、くりくり廻りて、毛色なんど見てやれや、七戸、八戸、三戸育ちの野道の駒、青に青斑(はん)、栗性斑、栗毛、月作(さく)には四つ白あし毛ぶち、鹿毛班、相性班、物の見事に墨より流しの黒の駒。奥の御厩を見給えや。黒金八方の入口につなぎおかれまして、あやおそろしい鬼鹿毛など、飼料にとりては正月六日の日とて鳥の一番鳥より豆八升飼の如くにし、引出せば飛び立つ如くに飼うておきまして御座います」
旦那
「おう。ようしたな弥十郎。代かき名馬を飼うてある事なれば、馬鍬とりを申しつけてあるかな弥十郎」
弥十郎
「さればの御意で御座います。馬鍬とりの名人には、ことに又、角助・角太・角之亟・市四郎・二四郎・三四郎・万四郎・金四郎・純四郎これらはねりねりわんばとした若者に候えばこれらに申付けおきまして御座ります」
旦那
「おうようしたな弥十郎。左様に馬鍬とりを申付けてある事ならば、指取(させと)りを申付けてあるかな弥十郎」
弥十郎
「さればの御意に御座います。指取りの一の名人には、ここに、さんこにあんぐり子、おちょうに・お岩に・お竹もまじり、それでもたらずんは、なんばのこ、さんしょのこ・おつりこまでも相誘うて、自由自在のさせ竿に命ながらえの唐糸を、だいもん結びに結んで、駒をうちこんでかいてもくれろ」
若者
「ひんひんひん」(馬が出る)
弥十郎
「おう。よくもかいてくれたなこの代(しろ)かきよ。前田曲のロ曲、大沢巻に小沢巻、菱大沢巻、角大沢巻、その下の大沢巻にとりましては、ひょうたん曲に七曲り、はっそりそって丸くねり、こくねったり、大沢までもよくもかいてくれたな、物にたとえていうならば、とろり親方が昼寝したる如くにとろとろとろりや、ねりねりねんばとかいてくれたなこの弥十郎。この弥十郎ばかりしてほめてなるものではない。これの御旦那様の御目にとめましょう」
旦那
「おうようしたな弥十郎、代かきもすんでいる事なれば、えぶりすりを申付けてあるかな弥十郎」
弥十郎
「さればの御意で御座います。御えぶりすりの一の名人には、ここに又、角助・角内・角之亟・何というても角部勘三郎には御えんぶりすりを申付けておきまして御座ります」
勘三郎
「角部勘三郎とは拙者の事にて御座います。
偖て、当年にも相変らず、前年にも相変らず、拙者ばかりあがりまして、この御えんぶすりを仕る者にて御座います。
偖て、当年は、おそいか早いか一向御沙汰が御座いません。
何人やら上りまして御あい申したかと存じ居る処、今日幸弥十郎殿におあいする事が出来まして、喜びこの上なく、この御えぶりを仕る者にて御座います。
さて、この御えんぶりには一の段が御座います。
誰がすったか、彼がすったかとお尋ねなさる方があるならば、天竺へ白山金流真節聊か十七日、二十七日、三七二十一日、その合に飛弾のたくみと誰々に御立合いを以って、柳のやながらくずを以って蓋(よみがな)し、しばきおかれましたるえぶり板の如く、偖て、このえぶりには奇妙が御座います。右の方には米という字は七流れ、左の方には泉という字は七流れ、中には宝生の玉、一すりすれゃ祝の水、化粧水、二すりすれや悪魔払いの水、後へくるくる廻るは福の水、中にちんちん上るは即ち宝生の玉の如くや。東西南北隅から隅までずらりごったりともすりおさめまして御座います。あとは、弥十郎殿におめにかけ上げましょう」
弥十郎
「おうよくもすってくれたなこの御えぶりすりよ。物に例えていうならば、備後表の如くにずらりやったりともすってくれたな。この弥十郎ばかりしてほめてもなるまい。御旦那様の御目にとめてみましょう」
旦那
「おうようしたな弥十郎。左様にえぶりすりもすんである事ならば、投苗打を申付けてあるかな弥十郎」
弥十郎
「さればの御意で御座います。投苗打ちの一の名人には、ここに又、一八・二八・三八、何というても、ささら三八に投苗打を申付けおきまして御座います」
三八
「ささら三八とは拙者の事にて御座います。当年も相変らず、前年も相変らず、拙者ばかり上りまして投苗打を仕る者にて御座います。さて、当年はおそいか早いか一向御沙汰が御座いません。何人様やら上りまして御あい申したかと存じおる処、幸い、今日弥十郎殿におあいする事が出来まして喜びこの上なく、投苗打を仕るものにて御座います。さあ、稲草を改めましょう。二年早稲に、粳毛の五葉、雀しらずの早い早稲、大すね、小すね、岩手すね、岩がならべの京桜、糯と申せや赤糯・白もち・権兵衛糯、雨笠ならべの赤権兵衛、白と申せやどう白よ、苗と申せやわさぁき苗、しょうぶ苗、投げれゃしょうふりと立つが如く、西・東・北・南、隅から隅までばらばらばっと打おさめおきまして御座います。あとは弥十郎殿に御目かけ上げましょう」
弥十郎
「おうよくも打ちも打ってくれたなこの投苗打ちよ。物に例えていうならば、三月正金若芽春、四月牡丹の散る如く、ばらばらばっと打ってくれたな。この弥十郎ばかりしてはめてはなるまい。これを御旦那様の御目にとめましょう」
旦那
「おうようしたな弥十郎。左様に投苗打を申付けてある事ならば、こうなつばりも申付けてあるかな弥十郎」
弥十郎
「さればの御意の御座いで御座います。こうなつばりの一の名人には、ここに又、菊助・菊内・菊之丞。さあ何というても菊之助には、こなつばりを申付けおきまして御座います」
菊之助
「菊之助とは拙者の事にて御座います。さて、当年にも相変らず前年にも相変らず、拙者ばかり上りましてゃこなつばりを仕る者にて御座ります。さぁて、当年はおそいか早いか、一向御沙汰も御座いません。何人様やら上りましておあい申したかなど存じおる処、幸い、弥十郎殿におあい出来まして喜びこの上なく、こなつばりを仕る者にて御座います。さぁて、過賞ながら、五月女にとりましては、さる子・さん子にあんぐり子、お蝶にお岩に、お竹もかたり、それでたらずんば、なんばのこ、さんしょうのこ、おっとりこまでも相誘うて、衣裳なんどを見てやれば、十二単衣に色小袖、縞の前(めえ)ぶりに道者の帯、会津笠に花笠をば、風にそよそよもませつつ、明きの方よりゆうらりやちょうと控えおきまして御座います。
さぁて、過賞ながら、五月女にとりては、晩の上りはおそう御座います。門の脇では門四郎殿のかが様、それでもたらず川の向いでは角部勘三郎殿のかが様なんど、せきの向うでは清之助殿のかが様なんと、遠い方では藤五郎殿のかが様、向いではちかごろ殿のかが様、もっと近いは根五郎殿のかが様は、ねっこらめって、ひょっこらめって、ひょうたんがって、たなつりがって、腹と申せば、七月腹をそらかした。なれども、、畦まわしは上手とみえて、ふなつくりの廻りの如くにくりくりくりともひかえさせます。
さあ、そこで何んだりかんだりの歌でもうたって植えてもくれろ。そこでひょうしを頼む」
田植歌
神国一の お田の神
千代米(よね)をとるとて 黄金をささえたり
桀の木は作るとも とる米はへりもせず
米打つ長者も栄えたり
舞い込んだ舞い込んだ 福の神は舞いこんだ
社倉の下で 何やらのすめく
恵比須大黒福の神 俵積むにのすめく
俵持ち長者は 栄えたり
この家(や)の家柄の御門を見れば
鶴と亀が一と番い
嘴を揃え 羽を立てて 万ずよしと囀る
朝やのおりに 水口に咲きたる花は 何の花
黄金花か 米花か 咲いて長者となる花
十七八のあてたる前垂 八幡山に落した
紐ばかりも五貫五百 まして前垂八景だ
鎌倉の権五郎殿は ひいて上る糶駒
糶もせらせたな 一万五両と七ぎりだ
七ぎりをば番頭にくれた
後でその家が栄えた
朝に起きて前の堰を見れば
白き水は流るる
流るるも道理か 上で万長者が米をとぐ
一本植えれば 千本となる
街道の早稲こが飛んでくる
七穂に八升 八穂に九升
揃うた揃うたよ
ほら植手が揃うたよ
稲の出穂よりほらなおよく揃うたよ
苗はほどよく伸びてほら今日こそ田植時
田面水をひらひら飛び交うつばくらめ
ひらひらひら早苗を掠めてみのを掠めて遊ぶよ
花のお江戸の糸屋の娘
姉は二十一妹は二十
妹ほしさに五両金かけた
お前百までわしゃ九十九まで
共に白髪の生えるまで
コーレヤユーエ(祝え)今年はじめてこのや館に呼ばわれ初めて初田植
コーレヤユーエ年のナーヤエ初めにお年男は迎えて参るは若松
コーレヤユーエそのや中にお神松をば迎えて参るはお年男
コーレヤユーエ峯の若松谷の若水をむかえて参るは年男
コーレヤユーエ鎌倉のおや後谷地にな鳥と篭を忘れた
コーレヤユーエ鳥ばかりも五貫と五百だな増して篭は八貰
コーレヤユーエ十七八の女はだれよりも恋しい恋しい鳥と篭
コーレヤユーエ鎌倉のしおや御所の庭には五月衣裳の椎子
コーレヤユーエ肩と裾とによもぎ菖蒲のや中にうずらうの花
コーレヤユーエうの花は咲くや時には殿は下る約束
コーレヤユーエうのや花は咲いて散るとも殿は未だに下らず
コーレヤユーエ向いの山に光るものはな月か星か螢か
コーレヤユーエ月でなぁいし星でないしなやしのぶ男の松明
コーレヤユーエあんまり植えりゃ腰がやめるでゃ腰を休めろ五月女衆
田植桶の歌
筑波山の麓に、千年劫経たる翁は、今日は吉目鎌倉殿の種蒔き黄金の種桶御手に持ち萬の種物蒔始め恵の方へと蒔きおさめ、播いておさめし目出たさよ。
鎌倉殿のこごろ姫、五月めす帷子の肩と裾に蓬菖蒲や前にうつぎ卯の花、卯の花は莟む時は殿は下る約束、卯の花は開けどもまだ殿は下らぬ。
鎌倉の御所の庭には臼を立て、米を搗く、臼は八がら杵は十六で女の数は三十三人、三十三人のそれの中でどれが長者の嫁こだ白金の御立櫛に巻いたは長者の嫁御だ。
向山の茅刈は女に鎌をとられたこのや宿を探してもないかここに出て沙汰をしろ御町役に出せども沙汰はおら知らぬ。
このや宿の御旦那様は大田作りの事なれば、前田千刈後田千刈合せて二千刈だ。何というても前田千刈の一の水口に押し寄せろ。一の早乙女腰をおろして腕前揃えて植えてけろ。それに続いて腰をおろして腕前揃えて植えてけろ。余り植えねぇで腰を休めろでぁ。腰を休めろでぁ。押す早乙女。
種蒔の歌
はぁやら前田の池にこそ
何が池にと名付けたり
福が池に富が池
たな池なんどと名付けたり
沢々の水をばはろうと
にごりの水をばつけぬき
御福の水をばたたえて
おろすべき種には
備前早稲か
雀知らずの早(はや)早稲か
かようなる稲草
俵なんどに俵して
えんやらやとゆいて
ゆすりあげすくいあげ
白金の柵桶に
黄金の目笊をかがやかせ
明(あけ)の天よりゆうさゆらり
西の方よりゆうさゆらり
蒔け蒔け蒔け中のふもとに
まきこんで末繁昌と
お祝何よりも目出たかりけり
笠振りの歌
コレナーヤーハエ御植女(おしょどめ)に着せるとてな 紺の数は三百六反、藍引染の帷子
コレナーヤーハエ肩に菖蒲裾蓬うつぼ卯の花開いたとさ
コレナーヤーハエ一本植えれや千本になる街道(ど)の早稲こ飛んでくる
コレナーヤーハエ花と咲かせて実らせなこれで長者と呼ばれた
コレナーヤーハエあんまり植えれやお腰がやめる お腰をかけろ御植女達
コレナーヤーハエ男はおりて手をかけれや繕(より)によられてからまる
コレナーヤーハエ女がおりて手をかけりゃ元の石となる
コレナーヤーハエ鎌倉の御所の御庭に女に似た石がある
扱きこなしの歌
神釈々々の座頭の坊がひくべき三味をひきもせで、秋田の久保田の女郎の袖、そうらそうともひいたとせ
荒糠はなし歌
燕(つんばくら)がコラヨエコノサッサノサー、酒屋の売場の箒(ほき)にヨエコノ巣をかけてコラヨエコノ、夜明ければ、酒出して売れとコラヨエコノ囀る。
米搗歌
十七人、今年初めて家持った。柱は白銀、棟は黄金。窓は菱窓、銭すだれ銭すだれ、銭のめどから朝日輝くヤハカハレヤゴーホンノ
粉糖はなし歌
仙台のヨエコノ孫作様の袴腰。岩に苔、渚に千鳥ヨエコノ玉よ縁よ。
ほめ口上(観衆から)
東西東西ほに枝もめぐみ御代の松、春節の雨雲なびけば我々大道舞踏笛やしゃみ鐘太鼓あやの錦で始りますればほめ口上。東西田植をほめるには、芝居あやづり等とは違いまして樽肴とり揃えて、ほめる筈には御座候え共、拙者さる方より用事があって罷り通る者なれば、これらを持ち参らず、お子供衆や若者衆や尚々内の亭主様には憚りながら御免な蒙りまして一言葉はかりほめ申す。ほめてとがかあやまちか、ほめてとがなら一寸ひかえましょう。ほめて宜しいなら、だんだん、そろそろ峯ずくしを以ってほめ申します。これら御旦那様を見給えや、前には大門後田五千刈前田五千刈。あのや屋敷の御み厩を見給えや、数々の名馬をつなぎとめ、御台所を見給えや、数多の若者さざめき渡り、御常居を見給えや、これの御旦那様色白く、にこにこ笑う若恵比寿、かが様を見給えや、十二単衣に飾りたて、髪をば梅や桜とゆい分けて、歩む姿は八重山吹き、かよう御出なされた御田植様方、まず一にとどり(太鼓うち)をほめるなら音大将官鎌倉公月の和のかがらの節にどどりにも左も似たりけり。二番に笛吹をほめるなら、昔無官の太夫敦盛君青葉の笛をほめるなり。歌おろしをほめるならば、小松林のせみの声とほめるなり。中に立ちたる中踊、お釈迦様の弥生の桜とほめるなり。五月女をほめるならば、ぼたんしゃくやく柳女に下り藤とほめるなり。その楽屋に控えし太夫様方、昔、四天王は神のままをいたせし如く、諸神諸仏諸大浄浜は大漁、陸万作と御家無事長久御繁昌と御田植様繁昌と御祝いおさめ、太夫並に弥十郎に敬って申す。
返し口上
東西東西一寸の間、お静まり下さいませ。さて、誰どなた様やら一向存じませぬが、大勢の御中より拙者ら遊ぶ田植の物真似を御贔屓とあって、おほめ下さるる段、誠に以って有難き仕合せ、至極に存じ奉ります。
さて、銘々早速ここもとに上りまして、御礼申上べき筈には御座候えども、ごらんの通り田植盛んにて、楽屋とり込んで居りますれば、舌の廻らぬ拙者を若者総名代と仰せつけられまして、拙者ここもとにて御礼申し上げます。
花ずくし(同じく返す言葉の一種で以下同じ)
花も種々ありといえども、天の始まる始めにも、花売詞筵の水事に梅や桜と名をつけて、桃の花こそ桃とすりおうて、桜は玉つばきあうも白々白牡丹と右御礼左様。
山ずくし
山も数多ありといえども、一に富士山、二に二坂山、三に白富士、四に鳥海山、五に南部の岩手富士と御礼左様。
茸ずくし
茸のとりよう所の習い、長柄の鎌をふりたてて、所変れや品変る。一に習いのほほかむり、顔も形も白しめじ、紫しめじの振り袖に、呑まれ茸、呑より早くの紅茸(ママ)、尾の上の松茸宝菓山の高砂の白き木耳(きくらげ)と右御礼左様。
松ずくし
松も種々ありといえども、まず正月は、門に門松、しんからしの(ママ)秋の一葉松二葉松、そねの相生いの松、おつぼ前の五葉松の松と右御礼左様。
竹ずくし
竹も数々ありといえども、大竹・地竹・丸竹・にがみ竹、藪に生えたる笹竹に、鶯は初声を致し、ほほうけきょとさえずる声迄も、音高く、ほほ、右御礼左様。
車ずくし
車も数々あるとはいえども、一に女の糸より車、二に若者どもの押車、三つ、三つ子の風車、四つこうしの腰にさしたる前お車、五つ南部の水車、六つ無理な火車、七つなんでも相模の横山、照手姫の御正車と右御礼左様。
当所ずくし
明けてひろまる祝とて、三々九度の盃も、日出度目出度の若松や。豊穣豊年一が沢、福は北野か、外に見ゆる鬼が田、末々広いや地上扇の間、高砂ならぬ高保山、爺松婆松年振りて、色も変らぬ一本杉、清き流れのおかりや滝、鶴と見まちがうさんぎ沢、野ぎわに亀が集りて、福を抱くと、ほほ、敬って申す。
町ずくし
一つ二つは三つ家(や)町、二番目揃うた新田町、何というても夕顔漸橋、材木なけれど材木町、左程長くはないけれども長町、赤川近辺四つはんべ、鎚をふり上げ大工町、油とろとろ油町、和尚願いは寺の町、花のお江戸でなけれど本町、本町などと、ほほ、敬って、只今お礼左様。
田植踊りは、同じ調子なので、その間に、漫才や狂言を挿入して観衆をあきらせないで楽しませたのであった。
漫才には上方漫才・お江戸漫才・作(さく)漫才があり、狂言には金巻・箱根・八百屋お七が工藤善雄氏の全集に記録されているが、田植踊と関係がないので、漫才と狂言は省略することにした。
3 さんさ踊
さんさ踊りの発祥について『岩手県史』は次のようにのべている。
昔不来方の里に、悪鬼があらわれて里の人々を悩まして困るので、三ツ石大権現に退治を祈願したところ、権現様はたちまちあらわれて悪鬼を縛りあげた。悪鬼が罪を謝したので、これからこの村に来ないことを誓約しそこの三ツ割石に誓約の手形を捺し、赦免されて山に帰った。里の民衆は欣喜雀躍して、三ツ割の周辺をサンサ、サンサと踊りはやしたのが、このサンサ踊りであり、これから来ない意味で不来方の地名となり、岩に手の形を捺したので岩手という地名になったというのである。この解説は、三ツ石権現社の別当寺であった盛岡東顕寺の住職が、地名を解説したり、盆踊りの一つのサンサ踊りと、三ツ石権現に結びつけたところが興味深い。
盛岡の三ツ石神社周辺は、サンサ踊り発祥の地と伝えながら舞踊のテンポは、ここほど早いところはない。山手の村方には原形に近いと思われる格調の高いサンサ踊りが遺っており、村方の大衆踊りであった。揃いのゆかたを着飾って、家ごとの門前で金銭を乞うようになってからテンポが早く忙しくなった。しかし元来はこんなことをなさず、衣裳にはでな帯を結ぶこと等木綿衣料に不自由をしていた藩政時代にはなく、専ら自分で自分が楽しむ踊りであった。
このサンサ踊りは盛岡を中心に、旧南部領の北上平野の田園聚落に盛んであった。この歌は七七七五の二十六字調である。歌一首をうたい終って、その後に「サンサエー」とか「サンサヨー」という歌詞の句がつくので、さんさ踊り歌ともいうものであろう。踊りは一拍子から三十三拍子まであったというが、五拍子程度より以上解説してくれるような人は今は知られていない。太鼓うち、笛ふきは先頭になって、老若男女が、左に進みながら輪になって踊りつづくのである。踊りの手振り足踏みが、簡易なものから複雑なものへと転換してゆくが、それを記録したものが殆ど見当らず、口で教え、踊って教えるが、一晩で五つも六つも覚えられる程のもので、三十三種の踊りはあったとしても、盆中には全部習得が可能であった。二人で交互に踊り交叉する違い踊り、輪を開き縮みする開き踊り、踊の終末を示して叩頭(おじぎ)を繰り返し織り込んだ礼踊り、その外に神楽崩(かぐらくず)し、剣舞(けんばい)崩し、田植え崩し、囃(はや)し舞(まい)崩し、など、内容は多種多様であるが、踊りは種目ごとに変っても、唄には変化がなく、二十六字調のサンサエーを歌うのである。
本村のサンサ踊りの踊り方は、南北で多少相達しているように思われるほど行政区域と交際範囲がかなり影響するものと思われてならない。
当時の農民の心情をうかがう一端として『岩手郡誌』等より歌詞を次掲する。
さんさ踊の歌(草取り歌にも通用する)
青い松葉のしんそこ見れば枯れて落ちるは二人づれ
秋の出穂にも遅れ穂が御座るこのや踊にゃ遅れなし
朝の出がけに山々見ればきりのかからぬ山もない
あなた百までわしゃ九十九まで思うて通えば千里も一里
あなた百までわしゃ九十九までこれも此世の夢はなし
あなた後から私はさきに花の浄土で待っている
あねここちゃむけかんざし落ちたかんざしおちねど顔みたい
あねここっちゃむけ歯がまだ白い男泣かせのなげ島田
あねここっちゃ向けかんざし落ちるかんざしかずけに顔見たい
あねここちゃむげ後帯ぁとげだ結んで上げます伊達結び
あねこコリャコリャ泣かないでしゃべれ泣けば理もひもわけたたぬ
あねこ今夜あたり行くがも知れぬ戸をば細めに明けておげ
あねこどこさ行く油買いに茶買いに滑ってころんでお茶まけた
あねこ何処さ行ぎゃ豆の草取りに豆こくだけでよい豆こ
あねこどこさ行く赤いたる下げていとこ名のりの酒買いに
あねこどこさ行く赤い樽さげて酒はよいさけめぐり酒
あねこ抱く気なって山の腰だいた物も言わねぇでごしぇやげだ
あねこだくべと木の根こだいだ物もいわねぇでごしぇやげだ
あねこ何ぼになりゃささげのくれぇだささげ十六で花ざかり
あのや若者(あんこ)さんさ心からほれたさげた煙草入の中までほれた
雨がさらさら降るとも晴れた私の心もいつ晴れる
雨が降る降る白粉おちた傘買ってけろ虎蔵様
いくら通っても春山もみじ色のつく迄またしゃんせ
石は流れる木の葉は沈むさかさ川とはこれのこと
一夜でもよいあわせておくれ今の迷いは気のまよい
田舎田舎とやすめてくれな田舎なければ町ゃたたぬ
今に無情の節期が来たら何と言いわけしやしゃんす
いやならよすだよ無理とはいわぬなこそ変ればよそにある
色気出て来た川端柳日にち毎日水かがみ
色で死んだらもとだと思え色で堅めたこのからだ
色ですぐれたばぐじで敗けた親の勘当きるばかり
いわばいわばと岩ばのつつじ人に言われて赤くなる
唄い娘に笛吹き聟はどこさ出しても恥じゃない
唄え唄えと私(わし)ばかりせめて私が唄ったら誰せめる
唄こうたいたい唄のかず知らぬ知らせて下さいそばの人
唄こうたわばきりきりしゃんと唄の折節人がきく
唄こ出してもつんでも(続けて)けなや、つんでたもれや傍(そば)の人
唄って通ってけなおらほの前を一人娘の気をそらす
唄でどど逸女で年増花に於てがさくら花
馬の三才馬喰さんのはたち売れぁ値もよい七十五両
えんのきれはこの子が出来たほんにこの子はえんのつな
踊りおどるなら品よくおどれ品がよければ嫁にする
踊りおどるなら品よくおどれ品にほれたらさあ嫁にもらう
踊りくたびれたみごとに履物きれた切れた見事な履物五足
踊り見に来たか立見に来たかここは立見の場所じゃない
踊りはねるも三十限り三十越けたら子に渡す
踊りぁ来る来るお庭が狭いお庭広げろ太鼓打ち
踊って跳ねて来たぼださばぼだせ何処も日も照る花も咲く
踊る中に踊らぬ野郎はおがだまぶりの見物人か
踊るまいなら何しに来たよお庭狭めて邪魔になる
踊れ踊れと俺ばりせめるおれが踊ったら誰せめる
踊れ踊れと二度せめられた踊りぁ出ないで汗ばかり
踊れ踊れっても踊らぬあねこ腹に大切(じ)な子が御座る
お前あんじてこれ程やせた踊り廻る帯ぁ三重廻る
お前高燭わしゃまだローソク芯のあるうちあかされる
お前あんじてこれ程やせた三まわしある帯四まわしある
お前思えば三度の食も胸につかえて食べられぬ
お前よいならわしゃどこまでも柳しぼの枯れるまで
お前正宗わしゃさび刀お前切れてもわしゃ切れぬ
お前こおろぎわしゃほととぎす川をへだててなきくらす
お前百までわしゃ九十九までともに白髪のはえるまで
思って通えば千里も一里あわで帰りや又千里
表(おもて)さし花芯とめられて二度と咲くまい比の里さ
おらもなりたやお山の雪に溶けて流れて化粧の水
俺もおどるしなずみも踊れ二人揃うて夜明まで
親のない子は日の暮れ方に指をくわえて門に立つ
堅い定めは必ずするな石もくだけて砂となる
可哀そうだな何時来て見てもたすきなげおくひまもない
川に乗る瀬に絹機たてて波に織らせて瀬に着せる
川の向えから文(ふみ)投げられて文が流れて気が沈む
君と寝るのに枕はいらの互い違いのうで枕
君の盃なみなみつげはわしとお前の顔がめる
来るが来るがと浜に出て待ずだ浜にゃ松風音ばかり
恋という字はことばの糸よからんで解けない下心
恋は九つ情は七つ合せ十六のなげ島田
小石小川のざくざく石は波とゆられて岸による思いがらだか
来いという字を来るなと書いた筆のあやまり今くやし
肥えでおでぇる十五夜さまはあなたそわじのやみはない
声がすれども姿は見えねぇやぶにうぐいす声ばかり
声のよいのにうたせて聞けば小松林のせみの声
声の悪いのに歌わせて聞きゃざざら(やぶ)林のおほの声
声のえあしはどこにも御座る人め知らずに出すがよい
心こんじょは直せば直る顔のみだくなすぁ直されぬ
ごしぇもやくまい悋気もやめろ僅かこの娑婆かりの宿
今夜月の夜で灯(あかし)もいらぬなんぼローソクやの娘でも
今夜のお月様山の桜だいておらも抱きたい十七八
今夜の踊子は唖のよな踊り笛と太鼓の音ばかり
今夜ばかりと思えばくやし明日の晩から泣くばかり
さても目出度いこの家の座敷四方の角から黄金わく
さても珍らし馬喰さんの浴衣肩にゃ鹿毛駒裾栗毛
咲いた桜さ誰駒つねぇだ駒がいさめば花が散る
桜咲けばこそあれぁ桜山桜咲かねぇばただの山
桜三月あやめは五月盆花七月咲く花だ
桜花のよなわが妻おいて人の捨て花おりたがる
酒こ飲みてぇども酒屋でねだす銭もねぇがたす都合ぁえがた
酒このんでも酒もりしても君とねねぇごどぁ気がすまねぇ
酒は酒屋にぼだ餅ぁ茶屋に女郎はお江戸の吉原に
沢内三千石お米の出どこ殿さ御蔵米桝ではがらねぇで箕ではがる
参嗟踊らば品よく踊れ品にほれて嫁に貰る
さんさ踊らば品よく踊れ踊りゃ片手でごしょまねぐ
さんさ踊らば寺の前で踊れ踊る片手に後生招く
さんさ踊らば三十が前よ三十過ぎれば子が踊る
さんさ踊りのはじまる時はへらもしゃくしも手につかぬ
さんさやめても泣く子はだませ親でなければだまされぬ
死なはお寺さ流れらば川さどんと落ちらは岩がんくら
しゃみの糸さえ切れれば結ぶわしとあなたは結ばれぬ
白い黒いの争いするな雪という字もすみでかく
白毛かもめの片羽ほしい飛んで行きたい主のそば
十五夜お月様山の腰抱いた俺も抱きたい十七八
十七島田に問ひかけられて梅も食わのに歯がうきた
十七〆めかねた汽車に乗りかねた好きな姉さと連れかねた
女郎に情がねぇでぇめめずに目がねぇひやかし男に金がない
女郎の親切ぁねたうちばかり朝におざれは金はだる
すぎで連れない因果でつれだ結び合せた親にくし
すぎとすぎだば泥田の水も飲めば甘露の味がする
そばにいてさえこれ程よいがましてつれたらなおよかろ
そらの星さえ夜遊びなさるぬしの夜遊び見るじゃない
そろたそろたま太鼓打ちそろうた足がそろたび手がそろう
揃った揃ったと踊子が揃った秋の出穂よりなお揃った
揃った揃ったと踊子は揃った足は白足袋手はそろた
竹に節あり木に枝があり思うたあなたにゃあけがある
太鼓打つなら身をしめて打ちやれ太鼓いたいとはものいわぬ
出せと言われて出さぬも恥だ出してよいのは酒肴
高い山から谷底見ればかわいい姉さまどじょすくい
煙草畑の雨笠被り笠もこらして(見えるようにして)つらみせろ
銚子持って来い盃ぁいらのわしとおまえのくぐみ酒
蝶よ花よと育てた娘もはや他人の手にうつる
月の円さと恋路の闇は江戸も田舎も皆同じ
遠く離れてあいたい時は月は鏡となればよい
遠く離れて顔さえ見えぬ月が鏡となればよい
戸をば細めに開けとくぁよいがよその男が通います
どうせこの頃通いはうそよよそにあるのかいやなのか
豆腐嫁にえぐこんにゃく仲人きらずぁお酌でのどぁつまる
年は経だども気は若柳何時か此の気が失せるやら
どどいつ坂でころんで提灯けした私の行くさきしんの闇
飛ぶにとばれぬ飛んでも行けぬ苦労黒絵のほととぎす
なじみ見たさに朝草刈ればなじみ隠しの霧がふる
なじみ見たきに朝水くめば水は七提げまだ見えぬ
七つ八つからイロハこ習いハの字忘れてイロばかり
何をくよくよ川端柳水の流れを見てくらす
なるかなるかとならない迄もならぬささげさ手をくれた
二階で別れてはしごで泣いて思い切りますくぐり戸で
猫の嫁取りいたじの仲人酒の肴によなねずみ
ばかなことした大木捨てて今はうら木で苦労する
馬鹿にしゃんすな枯木だとても藤がからまる花もさく
橋のらんかんさ片臂かけて月の明りで文(ふみ)をよむ
橋のらんかんさちょいと足かけてホタル集めて文をよむ
二十日ねずみは五升樽下げて夏のお山に樽開き
花こたもらば蕾こたもれわしも手かけて咲かせたい
花といわれて咲かぬもくやし咲けば実がなる重くなる
花は一度咲く若さは一度若さ恋しや二度とない
花は千咲くなる実は一つ九百九十九のむだの花
人目しのんで七晩通った今度合わねぇば切れてしむ
一人娘はさくらとつけて桜咲く度咲かせたい
ほれたからとて気が許されぬ女心と秋の空
ほれたほれたと川原の柳水にうたれて根がほれた
ほれた横目は糸より細い悋気する目に角がたつ
盆が来たども浴衣を持たぬ爺買ってけろ花浴衣
盆と正月と一度に来らばあずきおごわに豆もやし
盆の十三日暗夜(やみよ)でけねぇが爺様姥様も出て踊る
盆の十六日正月から待ずた待ずた十六日今夜ばかり
盆の十六日暗夜でけねぇが嫁も姑も出て踊る
まくらの下で思うたあねさんの声がするあねこどこさえぐ
南風吹くいねのほほなびくくろを枕にそよそよと
向うに見ゆるは螢か星か可愛いお前の煙草のみ
むすめえなずまかがさまれぇさま嫁の涙でかんだず雨
目出たうれしや思うこと叶った鶴は御門に巣をつくる
目出度目出度の重なる時は天の岩戸も押開く
八百屋お七と最上の煙草色でわが身を焼きすてる
山で黒いは炭焼おかだ里で黒いのは鳥のはねよ
山で山なす畑でとなす私しゃこの町(ちょ)のみたくなし
よしゃれよしゃれとどこでもはやるまして南部でなおはやる
よそにあるなら大事にめされこんなわたしをすてしゃんせ
よその男の通よたる節は月の障りだといって戻せ
若い若いで年月暮し知らず知らずに白髪がよる
私もこれから道楽やめた藁で髪ゆって辛棒する
わたしゃ枯木で咲く花もたぬ咲いてからまる藤の花
4 よしゃれ
よしゃれの歌詞は七七七五の二十六字調で、前節七七を終って「サアーハンヨ」と付け、後節七五を終って「ヨーシャァレ、サアーハンヨ」と歌い納めるのである。前者の歌が終ると直ぐ後者は歌をつぐので、歌は切れ間なくうたわれ、一座は手拍子をもって調子をとるから、踊りがはずみ、歌も同一歌詞を繰り返さないようにつとめる。従って、歌の掛合の形となり、歌い上手で歌詞を多く知っているものがリードすることになる。よしゃれは、止しゃれであり、おかしゃれも置かしゃれの言葉の訛ったものである。尾張方言のオキャンセと共通していること二十六字調であること、屋外で、盆踊りにも利用されること、拍手型手拍子で調子を整えること、太鼓・笛を利用すること等である。
よしゃれ踊りは、室内では一人乃至二人の踊りで、即興に誰かゞ踊り、二十六字歌詞を前節で一舞を踊り終り、後節で同じ手振りを繰り返して踊るから、歌一つうたい終るまでに、踊りは二回になり、客人、すなわち上座に向って踊るのである。
語原については色々あるが、下掲の歌詞のごとく、「その手食うよなわしじゃない」つまり「およしなさいよ」との意味であろうか。
よしゃれ茶屋の嬶さエー花ぞめのたすきサーハーヨーかたにかゝらずサーエー気にかかるよしゃれサーハーヨー
よしゃれよしゃれとどこでもはやる まして南部でァ尚はやるよしゃれサーハーヨー
よしゃれおかしゃれサァその手は食わのサァハァその手食うよなサァやぼじゃないよしゃれサーハーヨー(以下はやし言葉略す)
姉と妹に紫着せて どれが姉やら妹やら
田舎たつときゃ菰着て発ったが 今でぁお江戸の男伊達。
うたいましょうか はばかり乍 歌のちがいは ご免なされ。
うたいまするぞ 声張り上げて 文句知らずの仮名違い。
太田男に雫石女ご、なりのないのは(黒いは・色の白いは・声のよいのは)厨川衆。
おしゃれおかしゃれその手は食わぬその手食うよなわしじゃない。
踊りはねるも今夜が限り、明日は遠山に葛苅りよ
お前その気で変らば変れ、私ァ変らぬ待乳山
思いかけるより、かん鍋かけろ、のんだ心持、富士の山
思うてみてけろ金こそ持たぬ、金で買われぬこの腹だ
おらもなりたい雫石の水、わかいあの娘(こ)の化粧の水
おらも若ぎぇどぎゃ、こちゃこどへわれだ、今でぇ秋の水よけられる。
義理に迫れば熊谷様も可愛い敦盛手にかける
で呼ばれの手で招ねかれの、唄の文句でさとらんせ
声のよい子に歌わせてきけや小杉林の蝉の声
今宵一夜は浦島太郎開けて口惜しい玉手箱
今宵一夜は緞子の枕明日は出船の浪枕
咲いた桜の枝折るからに情知らずの山鳥よ
酒はよいもの気を勇ませて顔は紅葉の色となる
さした盃中見てあがれ中に鶴亀五葉の松
さても目出度いこのやのやかた四つの隅から黄金湧く
さてもよい声お前さんの声よ銀で伸べたかとろとろと
覚めてくれるな少しの間覚めてあわれる身ではない
十七島田と垣根の芋はつらのよいのから先に掘る
十七島田と歯のかけ足駄どこで転ぶもあてはない
十七島田と道中かけ草鞋のれやのる程ちがのびる
十七島田とのき端のたるし堅く見せてもとけ易い
十七八はり花だと思うなわたしゃ三十九で花盛り
死んで又来る裏道あれば死んで見たい今の間に
そろたそろたと踊りこは揃た秋の出穂よりなおよくそろた
他処にあるなら私をば止めろ花も両手に持たれまい
出せよ出せよとめったなもの出すな、出してよいのは酒さかな
銚子盃座敷を廻るわたしゃ悋気で気がまわる
銚子盃中見てあがれ中にゃ鶴亀五葉の松
銚子は敦盛酒は熊谷飲んだ心は一の谷
銚子持てこい盃いらのわしとお前のくぐみ酒
亭主はお恵比須かゞ大黒ござるお客は福の神
情ァ寺の前の花売る婆様花はうらねで娘売る
のめや大黒踊れやえびす亀の座敷に鶴の声
春の初めの門松見れや花に黄金の玉のつゆ
春は花さき青山照らす座敷照らすが花嫁御
一つ歌います(出します)憚りながら、唄の違いはご免なされ
目出度目出度の重なる時は天の岩戸も押し開く
目出度目出度のこのやの座敷四つの隅から黄金わく
めでためでたの若松さまよ枝も栄える葉も繁る
やぶれ障子に鶯とめて春が張るかと待っている
よしゃれ浮かしゃれその手はくわぬその手食うよなやぼじゃない
よしゃれ茶庭のかゞ花染めの襷肩にかゞらねぇで気にかゞる
よしゃれ茶庭のかゞまでなよでそゝだ今朝も飯なべただまげだ
よしゃれ茶屋のかゞまでなよでそゝだたなに汚れたござ六つ七つ
よしゃれよしゃれとどこでもはやるまして南部でぁなおはやる
わしとお前は御門の扉朝に分れて暮にあう
私とお前は羽織の紐よ縁がなければ結ばれぬ
わしの親たちゃ邪慳な親でしんしょ譲らねでこえ譲った
わしの声だとて銀ではのべぬ親の代から譲り声
私奥山日蔭のわらび誰も取らのでほたとなる
笑わしゃんすな梅干婆様鶯なかせたこともある
5 小山こ三里
盆踊りの一つにうたわれたものに、小(お)山こ三里、往き来で六里がある。往時の青年は、夜遊びや、夜祭りに出かける範囲は、住居から半径、およそ二里であった。すなわち四里はその縄張りとなる。小山の宿に遊女町でもあったとすれば、夜道三里も、さして遠くない感じで通ったかも知れぬ。しかし、民謡の上の小山こが、いずれであったか知る由もない。
小山こ三里
三里三里と合せて六里、今の天保銭は唯八厘、ハ小山こ三里
嫌なわたしに酒飲め飲めと、酒でわたしをせめるのかハ小山こ三里
酒でおまえをせめるじゃないが、酒はこの世の愛敬じゃもの、ハ小山こ三里
酒はこの世の愛敬じゃとても、神さ願酒で飲まれないハ小山こ三里
酒さ願酒で飲まれぬとても、御神酒あがらぬ神もないハ小山こ三里
小山こ三里は何処から流行(はや)た、国の情の間からーア、ハ小山こ三里
6 はやしまい
はやし舞は、別名「サイサイ舞とも称している。このはやし舞には大黒舞・指し鳥舞・雑魚取り舞がある。これらは囃詞によって、身振り動作をリズムに合せて転換して行くが、踊り始めと舞い納めの基本は、殆ど同一で「サイサイナ」とか「サイサイサイヨイトコセ」などの囃詞を入れて操り返し踊るので、囃舞とかサイサイ舞と称するものであろう。
はやし舞
大黒の大黒の お大黒という神は
大黒という神は この国の神でない
天竺の三十三たいの
マツカタ国の 片はらの
須弥山の神なれば
この国に 渡るとて
天の川に 着き給う
折りふし風が はっと来て
めしたる笠をば 吹きとられ
おるやのぼるや 潮風に
もまれて色こそは黒いども
目もと鼻もと上々で
笑顔は しほらしや
大黒さんとも 囃された
大黒舞はみさいなみさいな
大黒の大黒のお大黒という神は
一に俵をふんまえて
二ににっこと笑って
三に杯いただいて
四で世の中よいように
五つで恵比須の若恵比須
六つで無病息災で
七つで何事もないように
八つで屋敷を平げて
九つ小倉をおっ建てて
十で宝を収めた
大黒さんとも囃された囃された
大黒の大黒の
お大黒の持物は
エンソ小袋 打出の小槌
引からがいて ひっ背負って
とんと打てば 大判に小判
これほどの御宝 誰に譲るべ
あちらさんにも いやしく
そちらさんにも いやしく
これの旦那様に まんまそろりと譲り置いた
大黒舞は見さいな見さいな
7 かっぽれ
舞踊としてのかっぽれは、律動の活発なものの一つで、宴会の座興として観迎されるが、その歌詞は一定している。その歌の緩急ある節廻しも他県と変っていない。独特のものではないが永く民衆に親しまれたものである。
かっぽれ
沖の暗いのに 白帆が見える
ヨイトコレワノサ サササッサア-
あれは紀の国 蜜柑船
ヨイトコレワノサ サササッサアー
あれは紀の国 みかんぶね
三 民謡
1 座敷神歌
本村のみならず、岩手紫波地方において、建物を新築改築したり、あるいは屋根替えをしたりした際、大工の棟梁とその部下を加え、親類を招待して酒宴を催すのである。「柱立祝い」とか「やうつり祝い」とか「建てまい振舞い」とかいわれている。茅屋根の葺替えが終ると「すみやどご」等と称して屋根屋の葺大工棟梁を加えて祝宴が催された。このとき隣り近所から「樽入れ」といって共同で酒肴が寄付の形で持ち入まれ、家主は親類を始め近所の人を招待するので大酒宴となる。
第一に御神酒が配られ、三献がすぎて、酒宴に移ると、棟梁等の式歌として、神歌が歌われ、その歌詞の切れ目に、「ハー面白ヤハー」の詞が入り、柏手(かしわで)を打って唱和する。神歌については宗教神楽の項の神歌を参照されたい。
2 婚礼の式歌
婚礼の式には第一謡(三つ)、第二ご祝(三つ)、第三なかおくに(三つ)、第四お伊勢坂(三つ)以上の四曲後は膝を崩し、よしゃれ等唱和してくつろぐのである。
あ 謡
実語教の崇流小謡で、寺小屋時代には児童の教科書の一部であった。従って盛んに謡われたものらしい。
高砂 所は高砂の尾上の松も年ふりて、老の浪も寄り来るや、木の下蔭のおち葉かくなるまで命ながらえて、なおいつまでかいきの松、それも久しき名所かな名所かな
高砂 四海浪しずかにて国も治まる時津風、枝もならさぬ御世なれや、逢いに相生の松こそめでたかりけれ、実(げ)にや仰ぎてもいうもおろかやかゝる世に、住める民とて豊かなる、君の恵みぞ有難き有難き
松竹 春毎に君を祝うや千代の松、立つや録も若竹の、繁れる宿の数々に、往来の人も豊かにて、なお万歳と祈らまし
田村 長閉けき影は有明の、天も花に酔えりゃ、面白の春辺や、あら面白の春ベや
玉の井 長き命を汲みて知る。心の底も曇りなき、月の桂の光り添う、枝をつらねて諸共に、朝夕なるゝ玉の井の、深き契りは頼もしや
浦島 契り結ぶの神ここに跡たれ、年を経る宮居幾久しさも限られず
邯鄲 花の袂を翻えして、さすも引くも光なれや、盃の影めぐる空ぞ久しき
難波 難波津に咲くやこの花冬篭り、今は春べに匂い来て、吹けども梅の風枝を鳴らさぬ御代とかや、実にや津の国の難波のことに至るまで、豊かなる代のためしこそ、実に道広き治めなれ治めなれ
鶴亀 庭の砂(いさご)は金銀の玉を連ねて敷き妙(たえ)の、五百重(いおえ)の錦やるりの枢(とぼそ)、しゃこの行桁めのうの橋、池の汀の鶴亀は、蓬莱山もよそならず、君の恵みぞ有難き有難き
養老 老おだに養わばましてさかりの人の身に、薬とならば何時までも、御寿命も尽きまじき泉ぞめでたかりける、実にや玉水の水(みな)上(かみ)澄める御代ぞとて、流れの末のわれらまで、豊かにすめるうれしさようれしさよ
謡
花咲かばつぎんといえずに山里のつかえは来たり馬のくら、くらまの山の内桜、ておりすおりをしるべにて、おくを通わす先続く、木影になみえていざいざ花をながめん
高砂やこのうら舟に帆をあげて、月もろともに、いでしおの、波もあわじの島影や遠くなるみの沖すぎて、はやすみのえにつきにけり。
い ご祝い
結婚式後「謡」の次にこのご祝いがうたわれるを常とする。
ご祝が繁ければ 御庭(つぼ)の松はそよめく
上り船に花が咲く 下り船に実がなる
まるき銭が数知れぬ 下り船に実がなる
まるき銭が数知れぬ 黄金の倉が九つ
てでっぽ鳥が山鳩に よく似た
ゆるゆるとおひかえなされ とさのとうの船が着くまで
御祝
御祝はしげければ 御つぽの松はそよめく
目出たいは庭の鳥 黄金の嘴で米を摺る
日出たいものには蕎麦の種葉は丸く実はみかどで御目出度
浜の真砂は尽きよとも泉の水は尽きまい
すゞ水は濁るとも亭主の御酒は濁るまい
御祝
御祝に呼ばれて先ず一つ祝い申す
御祝が重なれば七日七夜の御さかもり
御祝が繁くあれば御局の小松もそよめく
御祝に松植えて鶴と亀とが舞い遊ぶ
御祝は重なって今年の年は殊に目出度や
御祝
御祝はしげければ おっぽの松がそよめく
重ねるもいや重ねた二軒の世帯やい重ねた
沢の出口に黄金の倉を九つ建てた
喜びの杯九つ黄色の杯九つ
ゆるゆるだんぶりと とほさから 船がつくまで
う なかおくに
『岩手県史』に「座敷で歌う唄に“中お国節”がある。歌詞の長いのがこの唄の特長で、賑かな唄の終った後で、独唱的に歌われるのが例である。しんみりした調子のゆるやかなもので、手拍子も三味線も用いず、一人が歌えば一座がそれをききいるというものであった。一人が歌えば誰かは、また別の歌詞を歌うが、二三人以上はつゞかない。一座の賑かさが薄れてくるから、再び賑かな酒宴に移るのが普通である。民謡中こうした長い叙情詩のあることは珍しい。
その発生系統も判明しないが“ナカオクニ”という言葉も分らない。武田忠一郎著(東北の民謡)では、これを荷方節の一種としている。」とある。本村の大沢鶴子に在住する八十三歳になる高田芳太郎氏は、婚礼の式歌の三番目にこの「ナカオクニ」を歌うことになっているという。氏の記憶せる「ナカオクニ」を次に掲載する。
前の早稲田の一水口に鎌倉海老は上り来た。鎌倉海老の願いには、白米五升に銭(ぜに)五百、これを(が)あるならば、鳴子川渡(たび)湯治して、腰の曲りめを直したい。
さてもめずらし、鶯小鳥。今年初めて伊勢かける。伊勢程広いども、一夜の宿をとりかねた。もとくらさんの梅の大木、実の枝かりよせ、巣をくんで、十二の卵をなし揃え、十二は十二であれども、ふけつのこえをば御さかなととりなおし、飲めや大黒歌えや恵比寿、出でゝ客とれおかのかみ。
さても目出たいこの屋の館(やかた)、いかなる大工がたてたやら、柱々は金で巻く、差しや垂木は皆黄金。八棟作りの柿(こけら)葺き、座敷なんどを眺むれば、千畳の畳をはしらかし、大がいびるに小がいびる。一の座敷で嫁をとり、二の座敷で孫をもけ、三の座敷でおん酒盛、表なんどを眺むれは、雑穀土蔵(ぞうこくくら)とて二十や四つ、黄金土蔵とて二十や四つ、合せて四十八つのいろは土蔵、土蔵の錠前に悪魔払いの札をさげ、扇の如くに末広く、松の如くにごよ長く、柳の如くに糸長く、団扇の如くに事円く。
さてもめずらし鶯小鳥。夜陰の明神は母とみる。夜明けの明神ば父とみる。あわれなるかや、月の光でお経よむ。
坂の曲り目さ植えたる桃は、花は午前の白と咲く。桃は天地の果となる。仙台嵐に吹きおとされて、最上馬喰さんに払われた。
さてもめずらし、このやの館。前に池のぐるわに松を植え、鶴は天にて(より)飛びおり、亀は池にて舞い上がる。このや館も繁昌と舞いまわる。
なお、その外に歌われた「なかおくに」は次の通りである。
一 しまだでであれば
しまだで居ても佳(よ)いツマ持てや、宵から朝まで抱いて寝る。明けて見たれや雨が降る。
着たる羽織を蓑として、かむった手拭を笠となし、さらばと言うて、五つの時は、親の定めたツマならば、これ程雨の降る中をやりはすまい、又も御出と門に立つ。
二 君を見たさに
妾はこの丁に用はないけれど、お前見たきに逢いたさに、毎晩毎晩通えども三こう四こうの夜も更ける五更の天も明けれども、わたしに縁がないものか、ぬしに縁がないものか。とてもお前に逢いかねる、涙顔で帰りかけ、暁のからすに送られる。
三 さてもやさしい鶯は
偖もやさしい鶯は、父親のためとて高野山、母親のためとて羽黒山、我身のためとておいせさん、お伊勢の国は広けれど、一夜の宿をとりはぐれ、梅の小枝に宿をとり、花を枕に葉を御座に、天に雲なし月と星、月の明りで法華経よむ、その法華経の大ばおん一徳二しゃ三しゃおんに、四しゃ天神五しゃ如来、さても芽出たい春の空。
四 初夢
扨ても芽出たい此家の御亭主、年の始めに見たる夢こそ芽出たいや、銀の屏風の其中で、銀の盃頂いてしろ酒銚子に泉酒、ふけの具をばお肴に、況してお酒は花嫁、たんぶり注いだと夢を見た。
五 芽出たな御屋敷
扨ても芽出たい此家の屋敷、屋敷に生えたる大の松一の枝には銀がなる、二の枚には銭がなる、三の枝には米(よね)がなる。上より鶴の舞い下り、池には亀が浮び出る、鶴と亀とが舞を舞う、何を舞うと立寄りきけば、この家の子孫繁昌と舞を舞う。
六 あら玉の
あら玉の、年の始めの二日の晩に、見たる夢はよい夢だ、三つ見た夢皆同じ、四つでよろずの宝をもうけ、五つ何時までも此家の繁昌、六つ睦ましくこの家の繁昌、七つなにかに仕付は御座る、仕付ござれゃ金銭もまわる、金銭廻れや利息となる、利息はたまれや長者となる、八つやたらに蔵を立て、九つ黒金の倉を建て、十で年々この家の繁昌。
七 君を尋ねて
君を尋ねてこれ迄廻った、北は南部の果てまでも、東は松前蝦夷が島、南はくまがい薩摩だけ、西は岸打つ輪王寺、唐天竺は知らねども、虎ふす野べの果てまでも、尋ね探せど。
八 やつむね作りの
八つ棟作りのカワラ葺き、新調の畳をおし並べ、一の座敷で嫁を娶り、二の座敷で孫を抱き、三にはこれから倉を建て、お米倉とて二十や四つ、金銀倉とて二十や四つ、合せて四十八つのその倉に、東下りの札をかけ、七福神の寄合で、七日七夜のお酒盛り益益繁昌となる許り。
九 草刈り三之(さんの)
色に迷いし三之様よ、御殿に忍んで旅の粧束なさるとて、あやの脚絆に五じょうのたび、八つ緒のゴンズをしめ履いて、菅の笠で顔隠し、伴のものとて竹の枝、其節々リヨを込んで、急がせ給えや御姿、八重の桜もうつりつゝ梅の香りもその如く、枝だれ柳もその如く、遥か向うの筑紫豊後の国、マンノ長者へ忍び往き、今や草刈りの男と交りて、草の苅り様も知らぬぞや、右手に鎌を持って刈るものか、左に鎌を持って刈るものか、向うに押して刈るものか、手前に引いて刈るものか、教えて給われ朋輩達、今は京に居るなれや、君大臣と呼ばわれて、金の屏風の其中に、荒い風にも当らんず、ノーノいかにも自らよ、之も誰ゆえ玉世(たまよ)故。
十 仙台ござらば
仙台ござらば、松島ござれ、松島ござれ、五大堂の橋に腰かけて、遥か向うを眺むれば、白いかもめが睦連て又も道連れ睦ましく、長い道をば帆柱と、翼を拡げて帆柱と、翼を拡げて帆をかける、浮きつ沈みつ舟のゆれ。
十一 安倍の童子
阿倍の安那(やすな)の子訣れは辛い、のうのいかにも此のわけよ、後れし髪をばなであげて、顔と顔とを押合せ寝入りし耳にも良くきけよ、せめて汝が十歳までも育てたいとは思えども、マガキの浦のラン菊に、花に心をとらわれて、幼き汝に見敗られ、見通されるも是非もなや。母がしのだへ帰るぞや。母がないとて恨みるな、親がないとて成人して、成人したら其後は、手習い学問精出せよ、学問不学になるならば親の名まで呼び出され、道理じゃ狐の児じゃものと、人に指さし笑われる。
十二 酒呑童子
酒呑童子は、高野山に封ぜらる、丹波の山に鬼がすむ、一に頼光、二に渡辺、三に貞兎、四に季武、五番の保昌、六に金時、これら六人居るならば、如何なる鬼人も余すまい、酒呑童子は毒矢で落す、島田娘は目で落す。
十三 阿波の御島
あわの徳島十郎兵衛の娘、父母を尋ねて国廻る、旅のそうぞくには、あやの脚絆に五じょうの足袋、八つ緒のゴンズをしめ履いて、菅のお笠で顔かくし、頼みにするのは竹の杖、その節々にようを篭めて、国はいずくの名を名乗る。
十四 西行法師
扨ても扨てもの西行法師は、こんにゃくの刺を喉に立て、金銀でほれども抜けもせず、何としょうぞえ女郎さん、抜ける薬はあるまいか、随分薬はございます、土用の六月降る雪と、寒中に生える松茸と、み山に出来る蛤と、一夜造りのもろはくと、三年三月の甘酒と、それを煎じてあがらんせ、あがる間もなく抜けまする。
十五 ごまめ
よしごと、ごまめはねんごろ中よ、よしごはいやとて葉を拡げ、そこでごまめの口説くには、垣に結ばれし横柴も、雀に一夜の宿を貸す、馬にけられし路草も、螢に一夜の宿を貸す、そこでよしごはきき分けて、撚れて絡まれご豆づら。
十六 八百屋お七
頃は三月日は十五日、八百屋お七の寺詣り、髪をばほんだにくさだたみ、銀のかんざしさわやかに、五色のくぐりを八重にかけ、たびはもんぱへ見張りかけ、下女のおしげを共に連れ、塗物下駄にてしょなしょなと、横を通れば行く人来る人指をさし、あれあれこれこそ八百屋のお七かな、物によくこ肴譬えて見るならば、青田に白鳥の下りた様だ。
又も我が家を焼いたなら、可愛い吉さんと逢うとかや、コタツのオキを二つ三つ、小袖のこしまにかいくるみ、隣り知らずの箱梯ひと桁上りてホロと泣き、二けた上りてホロと泣き、三けた四けたは上り詰め、上りつめての其上で、二階の上にて四方見るに、誰知るまいとは思いしも、二階の格子に火をつけて、それ火事よと騒ぐなり。天上知るまいと思いしも、釜屋武兵衛に見つけられ、釜屋武兵エは、お七を捕れとの御沙汰にて、お七其日の粧束は、七つ重ねの振袖に、髪は島田に結い直し、銀のカンザシさわやかに、さらさら参り出す伝馬町、馬がなければ馬喰町、品川表になりぬれば、品川女郎衆は指をさし、アレアレ見さんせ見らさんせ、あれこそ八百屋の娘かな。
お七は牢の中での口説くには、鶴は千年朝顔は、一夜咲いてもみは一しょう、どうでもこの身になるならば、可愛に吉さんの妻として、ヤヤの一人も持ったなら、どうでこの身となるも是非もない。雪折れ竹にあらねどもお七の牢からあがる時、白張り提灯先に立て抜みの槍をひらめかし、江戸八百八丁引き廻し、咎の次第はこまこまに。
十七 鎌倉海老
前の早生田の一漑(ひとみな)口に、鎌倉蝦は上り来て鎌倉蝦の願には、白米五升に銭五百、此れをあるなら、鳴汀渡湯治して、腰の曲目を直したい。
十八 この館
扨ても目出度い此家の舘、柱々は金で捲き、差と桶とは皆黄金、六棟屋根はこけら葺き、お屋敷なんとも見渡せば、子丑の角には穀物倉とて二十四つ、金の倉とて二十四つ、合せて四十八つのいろは庫、庫の錠前に悪魔払いの札をかけ扇の如く末広し、器の如くに前丹く柳の如くに末長く。
十九 坂の桃
坂の曲目に植えたる桃は、下は白金中黄金、花は御殿の色と咲く、桃は天下の雅となる、仙台嵐しに吹き落されて、最上ばくろさんに拾われた。
さても珍し鶯どりは、今年初めて伊勢参り、伊勢ほど広い国もない、伊勢も難なくかけおろし、一夜の宿をとりはぐれ、梅の小枝に宿をとり、梅は枕に葉ばこざに、十人子供ば羽根に入れ、朝日拝んで、ホホーケエーチヨードオー。
さても芽出度い十三や娘、お酌に出るは恥かし、君に肴をのぞまれて、何も肴はなき故に、銚子のロに松を植え、小松の小枝に鷹をとめ、鷹に小鳥を捕わせて、これをお肴と上がらんせ。
障子あければもみじの座敷、先んず一番に先着仲どに花嫁さん、松の間までも居流れて、台の廻りに松を植え、一の枝には銀がなる、二の枝には米がなる三の枝には鶴ば舞う、亀は這うし、この家やからを末永く。
さても芽出度い この家の御亭主
心一つで エヽハア 土蔵(くら)七つ
一の座敷で 嫁取り祝い
二の座敷で 孫抱いた
三の座敷で 孫振祝い
銀の銚子で金の盃
中みてあがれ 中に鶴亀エヽハア五葉の松
これの御亭主は芽出度い御亭主、前には万年蔵お米蔵(よね)、後の御蔵を開け見れば、七福神のや御酒蔵、長柄の銚子に泉酒、黄金の盃とりいだし、御賜の盃とりいだし、大判小判のお肴で、弁財天は杓をとる、大黒恵比須は舞をまう、何と舞うやと立ちきけば、末代長者と舞い遊ぶ。
え 御伊勢坂
御伊勢坂七坂八坂九坂十坂目には鉋をかけて渡らせる。鉋も鉋すり鉋かけて渡らせる。
乙部町柳の葉より狭い町狭いけれども一夜の宿で銭を取る。銭も銭諸国を廻る宝銭。
十七八差す杯に花が咲く。花も花。黄金の花は八重に咲く。
うしろ川上や下へと漕ぎ行けば、如何なる釜も抜けるそだ。
お伊勢坂七坂八坂九坂十坂目にかんなをかけて渡らせる。鉋も鉋すり鉋かけて渡らせる。
お駒が岳、駒がた山の八重桜、吹きくる風にさそわれて、たざのかたかなじるひめ、ござの岩、鶴亀は、にぎわの松に巣をかけて、萬作よいとさいずる。
雫石、仁佐瀬の上り口、せまいども、扇の如く末広く、小岩井野原、お駒岳、岩手山とて名所どこ、銀の金網ゆるゆると。
『岩手県史』の舞踊と民謡の項に「岩手郡農民歌謡集より」として、長い御伊勢坂がのっている。これに踊りが伴うが、踊りは何れの歌詞の場合も同一であると。
きりきりと きり髪下げたは誰が嫁子
田尻町 検断が前の孫さ嫁
乙部町 柳の葉より 狭い町 狭いども
一夜の宿で 銭を取る 銭も銭
諸国を廻る まろぎ銭
祖父様 婆様 今朝のシバレに 何処さ行く
娘けるとて 帯買いに 帯を買うなら色よく
巾よく 丈長く 結ぶ所に鶴と亀
十七八 浜のみなとへ帯買いに 帯を買うなら
地よく巾よく丈長く 元に鶴亀五葉の松
結ぶ所は下がり藤
十七八 今朝の朝草 何処で苅った
心棒し長根の その下で 苅るも苅る
葛の若萠えゆるゆると
馬ここ付けてもはいはいと
久保田道 三十や三曲り 七落し
一人やるには案ずる道 妾も男なら
途の十里も送るども
女なれやそはならぬ
十三になるから 三十三までつれたども
言葉一語もかけられの 是はことばのかけ初め
岩を袴にたち縫えど 岩を袴にたち縫わば
空の浮雲糸にとり 松の落葉を針に採る
松島の 瑞巌寺程の 寺もない
前は海 後ろは末の小松山 松の葉は
色こそ変る 落もせぬ 落ちたとて
此方の世話に かけはすまい
雨垂れの 池になる迄忍んだども
今宵はならぬと文は来た その文を
月の光で読み見たば 涙許りで書いた文
十七八 差す盃に 花が咲く
花も花 黄金の花は八重に咲く
十七八 沢のみなとさ 水汲みに
ケラ着男に招ねがれた 水も汲まれの
担がれの 履いた足駄は横になり
立てた立櫛は前に落つ
かけた襷はふっと切れ
お前は それ程妾思わば 妾の屋敷を知らせます
高きあさ村高林 前にはマンサク桜花
門には さいかの色の水 今年はじめて布さらし
水の鏡でよく見れや
妾はくまだかにもよくも似た
十七八 柳の下で 芹を摘む
せりを摘めば 柳はよれて 絡みつく
仙台の 宮城の原の 萩咲き初めて
錦にまさる 萩の花
あねこきげ 後の山で 鳩が啼く
啼くじゃない 金持長者に なると呼ぶ
生保内の 三丁長根の桃の樹は 枝は久保田に
薬は佐渡に 花は大阪に白く咲き
桃は屋島に 樹は江戸に
核は四国に納めおく
なべこなかねの洞の柴 誰がきるやら薄くなる
妻にきらせて まるかせて
肥えた牛子につけさせて
十七さしたるコガイをふじとして
長く追いたい長正直
何処に下せや釜親父 前のコジカの其前に
釜は打捨出て下ろせ
なべこなかねの洞の雪 溶けて流れて三島まで
三島女郎衆の化粧の水
なべこなかねの洞の草 誰が苅るやらうすぐなる
妻にからせてまるかせて
肥えた馬につけさせて
小馬につけてもいさいさと
つばくらは 酒屋の軒に 巣をかけだ
夜明ければ 酒売れ濾せと 囀えずる
十七八は 今年始めて家を建てた
柱白銀サシ黄金
窓はつき窓 銭のシダレに 朝日は輝く
この頃は 夢にも見えぬ 来るも来ない
夢でさえ 見えないつまは なぜに来る
よべなまで 通うた道を 今朝見れや
今朝見れば 七重に桓を 結ばれたし
結ばば結べ 七重も八重も 九重も
十重も結べ 心に桓は 結ばれまい
十三才から 荒き駒をば 曳いたども
あねこ曳く手は未だ知らぬ
夜這いに行て よばいの銭を はたらえだ
まだ待じろ 親父を質に おいてやる
気仙沼の お雪に呉れた 白の中で
肩にかけ 落すなお雪
3 新穀節
座敷でうたう祝い歌の一つに、新穀というのがある。豊年萬作をうたった歌で、村方の古謡の一つであろう。シンコクを神国と書いたり、新穀と書いたりしているが、新米を神様に供え奉ること、新穀の収納は土蔵に溢れて、古米は尽くることがないというのが、歌詞の中枢をなしている。古米を多く持っているということは、村方の物持ち長者であることを意味していた。
神国
神国の宇賀の神何を捧げに参った古き米を量るとて黄金の枡を捧げた黄金の枡は尽きるとも古き米は尽きまい。
ののめぐでぁののめぐでぁ後の小蔵でののめく恵比寿大黒字賀の袖俵を積むとてののめく
是程のお客様に何を肴に上げましょう。鯛と鱸(すずき)と鎌倉蝦之を肴に上げましょう。
新穀
「めごさんだ」あれエアな、めごさんだ、こんにゃのお酌はめごさんだ、銚子の口をばしゃんと上げて、だっぷり注ぐはめごさんだ。
おら屋(や)隣の妹女郎は、みめも姿も梅のにほい、梅花のおなごだ。
千福山の沢のほらで縞の財布を見つけだ、おっとり上げて中を見だば、子持金が九つ一つ金をばお上(かみ)に上げて、八つで長者と呼ばれた。呼ぶも呼んだし呼ばれた。四十八たび呼ばれた。
朝に起きて、おもてを見れば、白い水は流れる。流れるも道理だ。上の長者で、米をとぐ、とぐもといだし、磨がせたし、千石万石とがせた。
しんこくの字賀の神は、何を先にすすいだ、古き米を計るとて、黄金の枡をすすいだ。たんと計れ宇賀の神、枡のけだは尽きよとも、ふるき米は尽きまい。
十七八を待ずるとて、小柴垣に立ち寄る、着たる衣裳は露にしめるまで、足袋に露の這入るまで。
西家どのと東家どのの、境のくねのかる梅、西の枝に七つなるし、東の枝に九つ、十七八は前垂れひろげて、ここに落ちろかる梅、落ちるにはよけれども、世間の前がおそろし、世間の前はどうでもこうでも、ここに落ちろかる梅。
このや殿のおだいどこで、十七八は酒漉す。着たる衣裳は月と燿く、緞子の帯が見事だあいそい結びに結び下げて、ざるたて染めのはじ巻。
豊年たでぇよ、豊年だでぇよ、今年の世ながが豊年だ、おくすねも、中手もなよ、畦を枕に豊年だ。
4 労働の歌
農作業は、春の田起しから始まり、苅り敷き、田掻き、田こすり、田植え、田の草取りと続き、畑作の方も、畑からみ、畑起し、うね起し、種蒔き、草とり、麦苅り、麦打ちがあり、それにつゞいて麦の精白の麦搗きがある。
初秋のころから秋仕事が開始される。萩苅り、稲苅り、つゞいて稲扱(こ)き、籾摺り、白搗き、餅つき、石臼挽きと続き、秋の収穫が多忙を極める。
これに伴う歌としては、田打・田かき・苅り敷き・田こすり・田植は重労働故歌が伴うことは無理で、田の草取り・草苅り・きすね搗き・しぃるす挽等単調さを紛らわすために自然歌が伴ったのである。
昭和に入って、農家の作業は、馬耕機を使用したり、脱穀機を使用したり、精米機等により、往時とは著しく変ってきている。従って往時の作業歌も次第に紊れ変って影を薄くしたのである。
あ 田植歌
朝の出がけに山々見れば、きりのかゝらぬ山もない。
いきな桜の一枝よりも、地味な松葉の末長く。
起きて朝火たけたくよとて小なら手柴折りくべて。
お昼も盛りの女郎は夏の衣裳で、参らしょ、夏は白き帷子に染め、わきのさしがさで入らんしょ。
俺が隣りの孫作どんは、女連れて下るとよ、女、女郎は年は何ぼだ、十三、七つ。
今日植える田の下も二千石積のによあり扱けかし小娘はサラリやサッともこえたりや。
こーなつばりにーめーがくれてなえたつところはーホーイ(別人拍子をとる)わすれた
桜三月、あやめは五月、私しゃ、秋咲く、菊の花。
桜は散れども青葉は残る、武士は死んでも名は残る。
十七八のおろす槌は八幡山に響く、なんとならす况して米はくだける。
十七八の箕吹きするには箕吹きまでもす、おらし、肩と裾とゆり合せて、中であげて、サオラヤー。
竹には雀、お松に烏、梅はうぐいす、きまりもの。
田の神の御煮物、何を入れて煮ましょ、芋の子に、かつのふしに松茸のわかいこと。
田の神の昼の休みには綾の枕をよせかけて、屏風立てて寄りましょ。
長く咲くのは、くるみの花よ、末をあんじて丸くなる。
ほれたほれたと川端やなぎ、水におされて、根が掘れた。
い 田の草取り歌
あねここちゃ向げほかぶりとげだ今度きたなら結でやる。
あのやあねさんのほかぶりうそだ結んであげましょ縁結び。
雨が降れ降れ七日八日も降らばみの笠あるからよ。
雨の降る時あみの笠いるが、雨がやめれば邪魔となる。
雨はしどろに降れども晴れる、私の心はいつはれる。
雨降る時あみの笠つける、つけれや肩腰痛くなる。
石で巾着縫ってやるけれど、砂で絹糸取っておくれ。
田舎なれども蟹沢の薬師佳麗上川原目の下に。
いやで幸い好かれて困るお気の毒だよ他方にある。
お江戸見るよな遠眼鏡あらば千両出しても求めたい。
男たちなら豊沢川の山の火花を手でとめる。
お盆前には田の草すんで盆には皆々気を休む。
川や堰などとめればとまる止めてもとまらぬ色の道。
来てはどんどと雨戸にさある私をまどわす南方。
気仙坂七坂八坂九坂十坂目にはかんなをかけてたいらめる。
恋は九つ情は七つ合せて十六のなげ島田。
声はすれども姿は見えず、藪に鶯、声ばかり。
声はよく似て来る筈ないが、わしの心のまよたのか。
今年始めてヤーハエ田の草取れば、あとに小草がそよそよと。
今年ゃよながよい穂に穂がさいた野にも山にも実がみのる。
咲いた桜の枝折るからす情知らずの小鳥。
酒はよいもの気を勇ませて顔は紅葉の色となる。
さても優しい螢の虫は通う男の先に立つ。
三度草には出穂ともなるが、出穂の黄金が歌となる。
十七島田と垣根の芋はつらのよいのを掘りたがる。
揃うた揃うたと前田の稲が秋が黄金の波を打つ。
揃うた揃うたとヤーハエ揃うた秋の出穂にはなお揃うようサンサエー
高い山から畠を見れば茄子も南瓜も花盛り。
田の草取には株だのまわり、まわりかませば稲がよい。
田の草取らわば実りが悪い取れば取る程実りよい。
どうせこうなりゃ二足の草鞋友にはかせたり我ははいたり。
平仮名くの字に「ノ」の字を入れて一の字ほしさに苦労する。
船に乗る時ふみ取り落し可愛二人の名を流す。
ほれたほれたよ川端柳水の出鼻で根が掘れた。
目出度目出度の重る時は、天の岩戸もおしひらく。
山せ吹かせて松前渡るあとは野となれ山となれ。
私とあなたは御門の扉朝に分れて暮にあう。
私ああなたに願がござる石で巾着縫っておくれ。
う 畑の草取り歌
歌もうだうべし仕事もすべし歌は仕事のなぐさみに。
男だてなら北上川の水の出花もとめて見る。
お前豆の木私豆のさや私はお前になりさがる。
お前峯の松私沢の杉見下げられるも無理はない。
朝の出がけに山々見れば霧のかからぬ山もない。
声のよいのに歌わせてきけば、小杉林の蝉の声。
今年始めて粟の草取ればどれが粟だかはぐさだか。
咲いた花より咲く花よりも咲いて実のなる花がよい。
花は千咲くなる実は一つ九百九十九は無駄の花。
娘何処さ行げぁ豆の草取りに豆は小丈こでよい豆だ。
え 草苅り歌
朝草に刈り込められたキリギリス
人目知らずの馬に乗る
甚句そそき出せ梅漬さすその葉
中の小核まで色よく真紅に染め出来た
草苅歌
家の御亭主もやんさか 出て褒める出て褒める
烏帽子長根のやんさか 蔭の沢で蔭の沢で
葛の若生やんさか 七把七把
今朝の朝草やんさか 何処で刈る何処で刈る
如何駒にもやんさが だよだよとだよだよと
村の人達やんさか 出て褒める出て褒める
お きすね搗き歌
白米作りは、炊事を司る女性の仕事であった。中世のころの豪族の城舘は、その土地の長者殿の舘でもあったから、多くの女性がそこに集まり、米搗き歌を唱和していたことは「臼は八がら、杵は十六で、女の員数は三十三人」と俚謡にあるのは、くびれ臼は八箇で、一臼二人宛の婦人がむかい合い、手杵で白米仕上げをしている有様を歌詞が残している。片手で扱える手杵で、左右両手に持ち替え持ち替え、その動作に合致したリズムに乗せて、きすね搗き歌が発生したものであろう。
きすね搗き歌
ついついと七日ついた よいこれさんやと 七日ついてお手に豆は九ツーやー ヨイコレサント ソレ ツケタカツケタカ
臼ばたで おぼこがなく よいこれさんやと おぼこ なくのやぼたんの花で べろべろと
十七八の おろしき ぎァ よいこれさんやと 山までひゞくよソレ ツケタカツケタカ
としより ばゞの おろすきねァ にわにも ひゞかないヨイコレ サンヤレ
臼搗き歌
姉コじょろじょろ呼ばれて来たか たゞ来たか
ただも来ない 秋機織りに来ましたよ
ヨエトコラサーヤーエ
来たがえが 針り箱手箱かねつけ箱まで来たは
これァ不思議 ヨエトコラサーヤーエ
か 餅つきかけ声
餅搗きは蒸した米の熱をさまさず、急いで搗かなければならない重労働である。餅をつく杵には打ち杵と手杵の二種がある。打ち杵の場合は搗きて二人以上は不可能で、手杵の場合は四・五人までは可能であった。餅を手で返す役目を相取合(いえどれえ)と称し、熟練者でなければならなかったから、搗き手に関係なく臼一がらに一人であった。
民家で屋根の葺替え、家の新築、土蔵の新築等の落成祝い、富豪の婚礼、大正月、小正月等の餅搗きは、大量の餅を搗くので、餅搗きかけ声が発生し固定化したものであろう。
よいどさっさ、よいどさっさ、よいどさっさ、よいどさっさが繰り返され、粒がくずれるころから次第に力を入れる。よいどこら、よいどこらを繰り返し、搗き上げる直前まで最初のよいどさっさ、よいどさっさに戻り、最後はよやすぇ、よやすぇ、よいよいよい。
き しぃるす搗(ふ)き歌(摺臼引き歌)
よえでゃ「しぃるす」などはやェー
まわせば落ちるでやなァー
よえでゃ「しぃるす」まわせばなァー
かんなべゃかかるでゃなァー
よえでゃ「しぃるす」なんどはなァー
まわせば落るなァー
そなだにかゝって
やまねでゃ死ようだなァー
く もんき突き歌
橋かけ替えの橋の柱つき。諸普請の際の杭つき等、木の杭や柱を土中に突き刺すには、その頭を重い木や金で打ち叩いて突く方法がある。それには重い木か重い金を吊り上げて、放して落下させ、杭か柱を土中に刺し込むのである。これをモンキつきといっている。
吊り上げる方法は、細綱で多人数が吊り上げ、揃って綱を放すと、その木か金が急に落下して杭か柱の頭を叩くことになる。綱を三尺程度一手操(ひとたぐ)りすることを「一(ひと)揚げ」、二手操(ふたたぐ)りすることを「二(ふた)揚げ」、三(み)手繰りすることを「三揚げ」といい、三揚げで九尺程度の高さから叩いたことになる。
地搗き歌
朝の出掛に、山々見れば、霧のかからぬ山もない ヨイヨイ、ヨイヨイ、アララン、コララン、ヨーイトナー。
朝にさきそめ、朝顔の花、姿やさしく百合の花 ヨイヨイ、ヨイヨイ、アララン、コララン、ヨーイトナー
朝の出掛に現場を見れば、黄金まじりの、霧が降る。以下同前。
このや屋敷は目出度い屋敷、四ツの隅から黄金湧く。以下同前。
締めろ、張り上げろ天竺までも、あまりはり上げて鼻かくな。以下同前。
この家の御亭主のアリャ名はなんと蔵は七つ蔵之助。以下同前。
この家の屋敷は目出度い屋敷、鶴と亀とは舞い遊ぶ。以下同前。
5 道中歌
あ 馬方節
鉄道も馬車も出現しないころは、盛岡から江戸の日本橋まで徒歩で十二日間を要し十一泊を必要とした。道中歌はこの時代にうたわれたものなのである。
古くから南部領は馬の産地であることから、年貢米や、薪炭、刈り萩、その他、旅の荷物などの運搬に多く馬匹が使用されたので、途中よく馬方節がうたい流された。馬方とは、駄馬を利用して荷駄運びに従事している駄賃取り仲間や、売買された馬を馬宿から次の馬宿へと泊りを重ねて往来した馬商人衆等をいい、農家や馬の飼主が荷物を馬で運んでも馬方とはいわない。従って馬方節は、節まわしはのんびりとし、悠長で、鈴・鳴輪の音律も偲ばれる。
〇馬方節
朝の出がけーにーハー 山々エー見れや
霧のーエーかからーのーぬー
山もーハーなーいー
貰った馬でも 関東に上れや 十五両二分
前に払って どんととおしかける
暗い晩だよ 誰だも知れぬ
早く名乗れや しのぶ島
可愛い馬喰さん 何処で夜を明かす
七つ長坂 七つ目で
〇馬喰歌
二両の馬買て 拾両に売たけや
八両儲けたよ 初馬喰
百に三升 豆食せて
あばねけぁできない 畜生目あいがれ
あるけ川原毛 歩めや葦毛ハイハイ
早く歩かねば 日が暮れる
うまく染めたよ 馬喰衆の浴衣
肩に鹿毛駒 裾葦毛
連銭葦毛に 虎かしけ
腰に馬沓 手に手綱
白い手拭 頬被り
七里長浜 歌って通る
丹波与作は 馬方をする
馬の手綱で 身をやつす
〇馬方節
はでに染めたる馬喰郎様の浴衣
肩に鹿毛駒すそ栗毛
雨は降れども逗留はならぬ
明日は南部の馬市
腰に馬沓手にをは手綱
七里長浜唄うて通る
可愛い馬喰郎様何処で夜が明けた
四十三坂七つ目で
南部片富士裾野の原は
西も東も馬ばかり
〇馬方節
ハー今宵一夜で名残りはつきぬよハイハイ
明日の出だしをのばしゃんせハイハイ
朝の出がけに東を見ればよ、黄金まじりの霧が降る。
馬喰さん晩のとまりはどこよときけば、つまりや秋田の本荘町。
長い道中で雨降るならば、わしの涙と思うてくれ。
よくも染めたよ馬喰のゆかた、肩に鹿毛駒裾栗毛。
可愛い馬喰さんのお上りするときは、青の三歳七はずな。
さても急げよ栗毛の駒よ、向うの長坂で日が暮れる。
かがよ今来た味噌米あるか、味噌米どころか水がない。
俺もなりたい馬喰さんのかがに、何時も栗毛の駒に乗る。
七里七はまうまうて通る、つらいものだよばくろの夜道。
い 追分節
道中歌としての追分節は、道中の峠越し、山中や裾野の茶屋、あるいは岐れ路、などを歌詞に折り込み哀愁を帯びた歌である。これは馬方節や牛方節とも通じ、さびしい道中節であるが、ともすれば、家の中でさえうたわれた。手拍子も踊りもなく、全く旅愁をそそる民謡として発達をしたのである。
〇追分節
西は追分・東は関所
せき所こえれゃ ままとなる
春の弥生に 鳴く鶯はイヤサノサ
梅が小枝にノー ホホケキョー
舟は新し 船頭さんは若い
川は新川 初のぼり
北山時雨て 江差は曇るコラサノサ
曇る江差は 花ぐもり
沖に見ゆるは 義経丸かや 為朝丸かや
乗せて来るお客は 色男
酒田に行くから まめでおれコラサノサ
逢うやら 逢わぬやら 知らねども
姉は二十一 妹は二十
妹欲しさに よやさのさ
妹欲しさに 御りょ願かけてヨヤサノサ
かけたごりょがん 恐山
お伊勢お伊勢に七度七度 熊野に三度
それでも足らなけゃ 月まいり
〇追分節
西は追分 東は関所
関所越えれば ままとなる
春の弥生に 鳴く鶯は
梅の小枝に 法々法華経
小山時雨れて 江差川溢る
船頭さん面舵 頼むぞえ
おしょろ高嶋 及びもないが
せめて歌棄 磯谷まで
松前城下の たてしのの坂で
泣いて泣かせた 事もある
花の松前 江差の紅葉
まして函館 桔梗の花
松前城下は むさしの別れ
あとは野となれ 山となれ
田舎なれども 釜石薬師
出船入船 目の下
〇江差追分
歌は国々数々あれど北の誉の海原を越えて蝦夷地のあの島に咲く江差追分身に泌みる(前唄)
蝦夷が島根の追分きけば 心澄むなる秋の月(本唄)
粋な船子が追分唄う 連れて啼くかや浜千鳥(送唄)
波は磯辺に寄せては返すヤンサノエ 沖は荒だよ船頭さん 今宵一夜で話は尽きぬネ 明日の出船を延ばしゃんせ
着いたばかりで直ぐ出る船に 逢うて話も後や先
一夜泊りの船頭衆に惚れて ついちゃ行かれず泣き別れ
川を眺めてホロリと涙 あの淵あたりは主の宿 会いたい見たいは山々なれど行くに行かれぬ篭の鳥
夕立の晴間晴間に帰ろとすれば 又も降り来る 涙雨
あれあれ 鴎が見てるじゃないか 泣くな又来る船じゃもの
蝦夷や松前 やらずの雨を ほれて別れの風が吹く 泣くも笑うも今宵が限り 明日は出船か浪の上
山せ風別れの風だよ 諦めしゃんせ 何時また逢うやら逢えるやら
心細さにホロリと涙 名残り惜しやと千鳥啼く
浮世荒波 漕ぎ出て見ればナカナカニ仇や愚かに過されぬ浮くも沈むも皆その人の 舵(かじ)の取りようと風も
荒い波でもやさしく受けて心動かぬ 沖の岩
浪に砕けし磯辺の月も もまれながらに丸くなる
主の出船を見送りながら 又の逢うせをちぎり草 蝦夷は雪国さぞ寒かろうね 早く御無事で帰らんせ
泣いてくれるな 出船の時に 沖でろかいが手につかぬ
泣くなといわれりゃ 尚せきあげて 泣かずに居らりょか浜千鳥
大島小島のあい通る船は 江差通いかなつかしや 船も新し船頭衆も若い 顔も新顔 初のぼり
忍路高島及びもないがせめて歌棄 磯谷まで
沖の鴎に潮時問えば わたしゃ立つ鳥波にきけ
尾上高砂千歳の松は 神代から 色も変らぬ深緑り主は百までわしゃ九十九まで 共に白髪の生えるまで
飲めや大黒 踊れや恵比須 亀の座敷に鶴の舞
枝も栄えて葉もまた繁る 目出度月田度の夫婦松
波に千里の思いを乗せて ろかいあやなす船頭さん 浮世の苦労も荒波育ち 月を添寝の浪まくら
ろもかいも波に取られて身は捨小舟 何処にとりつく島もない
沖の鴎が物言うならば 便りききたい聞かせたい
北山日暮れて 江差が曇る あい吹きや福山雨となる 蝦夷や松前 やらずの雨が 七日七夜も降ればよい
月夜更けて磯辺の宿に 一夜抱き寝の浜千鳥
浜の真砂に思いを書けば 憎しや来て消す夜半の月
鳥も止らぬ 枯木の枝に 主が情で花が咲く 花は咲いても実のなるまでは どうせ私も一苦労
忍路高島及びもないが せめて歌棄 磯谷まで
主は奥場所妾や中場所で 別れ別れの風が吹く
6 座敷歌
あ 角力甚句
村々の鎮守であるウブスナ様の祭典は、春祭りと秋祭りのあるのが普通である。春の祭りは祈願と希望を含めた祭りであり、秋は五穀収穫を感謝する祭りである。お祭りには神楽・芝居・手踊・角力が奉納されるのである。
奉納角力に参加した一連の人々を終了後、産土(ウブスナ)様の別当の家に招待され、鎮守社の祭典にふさわしい大酒宴が催される。最初「あゝ面白や」の神歌についで、角力甚句が唱和され豪壮な踊りが展開されたのである。
角力甚句
ハア昨夜みたみた大きな夢をねエ、アドッコイドッコイ駿河の富士をば腰にさげ、千石舟をば下駄に穿き、其の又帆柱杖につき、足柄山へと腰おろし、なにやら喉がかわくので、近江の琵琶湖一口二口飲みほせば、何やらのどにさわるので、エヘンエヘンと咳すれば、瀬田の唐橋ノホヽエ、アアアアアアはき出たねドッコイドッコイ
ハア今度此の度演習についてね、アドッコイドッコイあまた士官のある中で、私の好きなは唯一人色はお黒で背が高く口元ジンジョで歯が白くパッパとふき出す巻煙草、鳴り皮人の長靴で、アラビヤ馬へとまたがりて、サーベル抜いての御指図に、胸には金鵄勲章下げ、頸もたしかに金の筋、これほどこまごま見たれども、かんじん要の胸の中、見ないばかりが気にかゝり、尾張の国へとおもむいて、ハアも一度見たいノホヽエハア胸の中ね
角力取り唄
ハア角力をとるなら南部でとらんせしばは角しぱサア札の下
ハア昨夜の角力コは卵の性だっけお手をかければサアころころぶ
ハア角力にゃ負けたしばくちにも負けた今の楽はサア煙草ばかり
ハア角力とりとりためたる金を今夜一夜にチャチャコチャに
ハア角力になるなる何角力になる親爺泣かせのせっこきやになる
角力甚句
角力といわれりゃ名はよけれども 朝の四時から丸はだか
朝の四時から丸はだかでも 好きな角力やめられぬ
朝の四時から丸はだかでも 綾と錦に身をつゝむ
見定めた的がなければ心の弓を 何でうつかよはなさりょか
角力にゃ負けても酒さえのめば 晩の勝負に負けはせぬ
角力に負けたしバクチでとられ 親の勘当待つばかり
ないものづくしを一寸申します
そもそも日本という国は 戦に負けたためしない
お江戸に田がない畑ない 砂地に小便たまらない
何故か角力とりにはかゝがない
真中づくしをちょいと申します
日本でア東京真中で 東京でア日本橋真中で
頭でキリキリ真中で お顔でお鼻が真中で お腹でアお臍が真中で
角力になるなる何角力になる しらみたかりのせっこきなる
角力をとるならしょきりに 二枚三枚とらんせ四枚五枚は誰もとる
角力に負けたしばくちに取られ それで男がたつものか
角力といわれて名はよいけれど 朝は早くからまる裸
千秋楽とはこれ限り あすはお立ちで泣きわかれ
御当所角力も今日限り しゃじきの旦那に呑み別れ
年寄さまにはまず御免 子供衆に到るまで
長くお世話になりました まめで達者で御無事にて
わしもこれからお江戸へ上る 角力こそは重練す
御縁あってのその時は 又もや当所に演じます
その時おひいきを願ます
(仲入れ時の角力甚句)
わしほど因果な者はなし 十四の時から身を売られ
四辻のわらじに身をよせて ついた所は郵船会社の汽船にて
函館の港の蓬莱町 三階造り武蔵様を
夜は十二時おそくまで 火鉢と共に店を張り
会間に来る客嫌な客 のぼるはしごはつるぎ山
落ちる涙は血の涙 角力とらは南部のしばで
しばは角しば札のしば
角力といわれて名はよいけれど 朝の四つにはまる裸
角力とりとり世界をまわる せまい土俵で国まわる
い からめ節(金山節)
昔の東北地方は黄金の産地であって、安倍氏百年、平泉藤原氏百年の栄えたのもこの黄金であった。
南部氏が慶長三年に、領内から黄金が発見され、それを開発したので、財政に困らず豊かであった。ことにも鹿角の産金が豊富であった。時の鹿角金山奉行が、金山に働く娘達を盛岡城に連れて来て、殿様の御前でこのからめ踊をお目にかけた。これが領内に広まり今日に至っている。
からめ節の起源
尾去沢鉱山の創業は、和銅年間に始まったと伝えられており、その産銅は、天平年間に建立された奈艮東大寺の大仏にも使用されたといわれている。当時この大事業完成の際、国司が大いに喜び祝宴を催した。その時に鉱山に働く土着民の民謡が被露され、それに踊りが伴ったものがそれである。従って、からめ節は尾去沢鉱山に働いていた坑夫や手選婦の仕事の中から自然に生まれた作業歌で、別名「石からめ節」ともいわれている。歌詞には方言が多いが、卑猥ではなく、そぼくであり、舞う所作も粗野であるが、動作は活発で、郷土芸能にふさわしい情味あふれる舞踊であるため、古来から高貴の面前で披露されてきたものである。
なお盛岡地方で普及しているからめ節は明治十六年に盛岡の橘正三氏が尾去沢のからめ節を補作したものであるという。
金山踊の唄
からめからめと親爺が責める
なんぼからめても からめだてァならぬ
ハアからめてからめて からめて千貫
親爺の借金 年賦ですませ
金の牛コに 錦の手綱
おらも曳きたい 曳かせたい
ハアからめてからめて しっかりからめて
撮った手綱をうっかり離すな
田舎なれども 南部の国は
西も東も 金の山
ハアからめてからめて からめた黄金は
岩手の花だよ どんどゞ吹き出せ
からめ節
金が出る出る銀黄金(しろかねこがね) 鉄も鉛も銅もハアどっこえどっこえどっしり掘り出せ 岩手の名物
金の牛コに 錦の手綱 我(おら)も引きたい引かせたいハアからめてからめてしっかりからめて 握った手綱をうっかり放すな
田舎なれども 岩手の里は 西も東も 金の山
ハアからめてからめてからめた黄金は 皇(み)国の花だ どんどと吹き出せ
からめからめと御山の唄は 皇(み)国繁昌と 鳴りひびく
ハアからめてからめてからめた黄金は 岩手の花だ どんどと鳴き出せ
烏ア鳴く鳴く床屋の屋根で 皇国繁昌と なくからも
ハアどっこえどっこえどっこえ千両 どっこえ万両
目出た目出たの若松よりも 盛る御山の 黄金花
ハアかねつる千年 からめは万年
からめからめと親爺がせめる 何程からめても からめだてならぬ
ハアからめてからめて からめた千貫 親爺の借金一時に済ませ
直りゃ出て来る 世中は豊か 何処も彼処も 皆繁昌
ハアどっこも繁昌繁昌
直りゃ出て来る 御山が盛る上(かみ)も小(こ)前も皆盛る
ハア何処も繁昌繁昌
花が咲く咲く岩手の山は 北も南も黄金花
ハアからめてからめてからめた黄金は 皇国の花だ どんどと吹き出せ
う おいとこ節
おいとこそうだんよ
紺ののれんに 伊勢屋と書いたんよ
お梅女郎衆は 十代伝わる 粉屋の娘だよ
あの子はよい子だ あの子とそうなら
三年と三月でも なるたけ朝は早起き
上る東海道は五十と三次
裸でけらもしょいます 水も汲みます 手鍋も下げます
粉箱やっこらさとかついで 歩かにゃなるまい
おいとこそうだんよ
おいとこそうだんよ
紺ののれんに 伊勢屋の書いてだんよ
お梅女郎衆が十代伝わる 粉屋の娘だんよ
あの子はよい子だ あの子とそうなら
三年三月でも はだかで はだしで茨もしょいましょ
手鍋もさげましょ
なるたけ朝は早起き
上る東海道は 五十と三次
こな箱やこらさとかついで 歩かにゃなるまい
おいとこそうだんよ
おいとこそうだよ
紺ののれんに 伊勢屋と書いたんよ
お梅女郎衆は 十代伝わる 粉屋の娘だよ
あの子はよい子じゃ あの子と添うなら
三年三月でも 裸で茨も背負ましょ
手鍋もさげましょ 水も汲みましょ
なるたけ朝は早起
上る東海道は 五十と三次
粉箱やっこらさと担いで 歩かにゃなるまい
おいとこそうだんよ
おいとこそうだよ
西の果から 小雪さらさら飛んで来る
堤でなくのは 蝉やはたおり きりぎりす管を巻く
山でなくのは 紅葉の下で 妻を呼ぶ 鹿の声
軒端でちゃぼが鳴く 帰らにゃなるまい
おいとこそうだんよ
第十三節 農業民俗
一 「ゆい」
「ゆい」の起りは、南部藩の苛政の結果、必然的に発生したものと思料される。以下、岩手県共同研究者集団の研究物によった。
1 「ゆい」の意味
いうまでもなく農村の共同体的構造は、封建制を支える社会的な基盤となっていたのであり、「ゆい」はその共同体的構造の生産的側面における重要な一環であった。むしろ「ゆい」は農村における共同体の構造全体を支えてきた基礎的な制度の一つであった。それは労働手段の未発達な生産力の低い段階において、生産力を高める上で協業の特徴を生かすために、農家がお互いの間で労働力を交換しあうことによって労働力の調整をはかろうとする仕組みである。農家あるいは農民が組をなしてお互いの農作業を共同で行うのである。
そのやり方は、地方によってさまざまの相違がみられるが、概していえば、農村に資本主義経済が浸透してくるにつれて、崩壊して行く運命にある。それでもなおわが国の農村に残存している。
2 農作業と「ゆい」
本村において最も大きい規模で行われる「ゆい」は田植えの場合である。その外、もとはソバをまく畑の耕起、水田、麦畑、馬鈴薯、畑、稗、大豆畑の除草、麦まき、稗打ち、稲扱き、豆打ちなどの諸作業について行われた。但し、水田の一番除草は機械で行うようになってから「ゆい」は組まれていない。
また、畑作業のうち麦刈りをはじめとして牛馬の飼料とする乾草づくり、そば、稗、粟、稲などの刈取り、豆引き、大根の収穫、薪取りなど農林生産物を収穫する際には、殆ど戸ごとに個別的に行われた。
その理由は、刈りとったあと乾燥の必要から降雨等の場合迅速に処置しなければならず、また、大豆等は土から抜いて立てゝおいたところに強く霜がおり、次の日に天気がよくなると殻がはじけて、収穫が落ちるからである。もし、それが「ゆい」でなされていると、丁度作業の番が当っていて、適切な処置を皆にやってもらうことのできた農家と、そうでない農家では、収量が甚しくちがうからであった。
3 「ゆい」を組む農家の組合せ
田植えのための「ゆい」の組合せは昔からのしきたりで、主に本分家的な結合と近隣によって行われ、大体七、八戸から、二、三戸であって、同じく「ゆい」とはいっても大小さまざまである。
畑作業は、主として婦人によって行われ、従ってその際の「ゆい」は姻籍関係によるものが多く、組の人数も一般には数名にすぎず、田植えの際の「ゆい」のような旧慣は余り維持されなかった。
4 なぜ「ゆい」を組むか
供給量のかぎられた部落内の労働力の農繁期における労働能率を協業のもつ特徴を生かして高め、生産力をあげようとするのが「ゆい」である。
農作業のうち、特に田植え作業は朝早くから夜遅くまで続くので農民は非常に疲労し、田植えが終りに近づくころには、男女何れも食事の量が激減する。すなわち若い働き盛りの男は一日一升食べたが、田植えが始まり、やがて終るころには多少減じていた。
このような労働強化の中で、何らかの方法によって各自の疲労感を軽減することは、労働の能率を維持するために必要である。とくにその農業の生産力が低い水準にあって、生産力を支えるために労働強化の果す役割が大きければ大きいほど、このことが必要になってくる。部落の農民は「ゆいによって多数の者が一緒に働くと、皆でさわぎあって作業をするので、疲労が軽く感じられ、能率もあがる」といっていた。
また、「ゆい」は部落内の農家間の経営規模と労働量の不均衡を全体的に調整する役割を果している。部落における田植えの「ゆい」は、本分家の関係を中心にして組まれており、しかも本分家の間には経営する水田の規模と、その家で保有する家族労働力の量に差異がある。しかもその差異は、経営が極端に労働力を必要とする農繁期には、拡大する。そこで一概に「ゆい」は農家間における労働力交換の制度だとはいっても、その労働力の受授の量は農家間で異ってくる。
農家の間で「ゆい」に伴って生じた労働力の受授の量の差は、多くの場合その労働量を明確にし、これを所定の労働賃金で評価して決済する。また、「ゆい」の際に生じた労働力の受授の差をお互いにはっきりしておき、後日借りた側が貸した側に対し、たとえ作業は異っていても、同じ労働日数だけは働いて返すということも行なっている。
本家は多くの場合分家よりも経営規模が大きい。従って本家は、これまで「ゆい」という共同体的機構を媒介として、分家の労働力を無償で収取することによって、その農業経営を維持することができた。このことは、ひいては「ゆい」という社会的機構が部落内における本分家関係という身分制、また農家間における経済的な階層の構造、つまり支配のための構造を再生産する役割を果してきたことを意味している。
5 「ゆい」の損得
もちろん、物的な決済が、全く行われないというわけではない。「ゆい」で作業している間は、自分の水田の作業をして貰っている農家が、手伝ってくれている人達だけでなく、その家族達にも食事を提供する。また田植えの終った後に、「馬鍬洗い」と称する宴会を「ゆい」を組んだ農家の全家族が集って催す。その際、食物や貨幣をだすのは規模の大きな農家で、とくに水田の規模が大きいのに、労働力の少ない農家は率先して、他より若干多くの酒を提供する。この宴会は夜の十二時ごろまで続き、あとの三日間位は、大人も子供も皆ゆっくり休むことになる。
規模の大きな農家が、その宴会にだす食物や費用は、「ゆい」のさい提供した労働力と受取った労働力の量的な差を決済する意味も持つけれども、それは労働力が一個の商品として評価されたことに基づいての、個々の農家間での決済とは異り、「ゆい」を組んだ共同体的小集団の中での、相互扶助的な機構に付加されたものにすぎない。
この外形的な相互扶助的機構は、いうまでもなく、本分家関係など半封建的な支配関係を実質的な内容としている。宴会における大規模な農家による酒、物、金などの提供は、相互扶助的な外形をとりながら、実質は旧来の支配関係に基づくものであり、その維持存続のためのものである。
だからといって、「ゆい」に本来の意味での相互扶助的な実質がないわけではない。個々の農家にとって、時代により労働力の多い時もあれば少ない時もある。この調整を、一つの共同体として果すのが「ゆい」である。だが、すでに、耕地の所有と経営の規模の差異が、根本において存在するのであるから、「ゆい」の相互扶助的な側面は付随的なものとなり、強調される相互扶助的なイデオロギーや機能は、その小集団の中の支配体制維持の役割を果すことになる。
6 くずれて行く「ゆい」
共同体的構造をささえて来た「ゆい」が、昭和三十年ころから崩壊の傾向が現れ始めている。その理由は、「ゆい」をすることによって、最初に実施されたところはともかく、余りにも日数がかかり過ぎ、終りになった田植えでは、収量に大きな影響があることに気付いたからである。このことから個々にやってみると、色々の不便が生じて来たのである。それは経営規模の大きな農家では労働力に不足をきたして、他部落の援助を必要としたのであった。皆で一緒に作業をすると気分的にもはげみが出て能率があがるし、また長い年月のうちには、どのような農家でも不時の災害に見舞われ、労働力に不足するなど何らかの形で他の家よりの援助を必要とする場合があるから、平常から「ゆい」のような形で助け合っていることが必要だとされる。それに田植えをするのに自分の家の労働力が不足だからといって、一般的に労働力に対する需要の盛んな農繁期に、部落周辺の限られた地域で労働力を求めることも容易ではないし、また賃金労働者を雇うことも楽ではない。
こうした理由から、旧来のような大きな組織としてではなく、血のつながりの強いものがかたまるような形で、小さい規模に再編成されたのである。
しかし、この「ゆい」が平等な農家による単純な結合ではなく、その中に階層性が貫かれていた。技術の発達が田植え時期の収穫高に対する影響を大きなものにし、大きな構成の「ゆい」は、生産力の上昇に対応して、小規模なものに編成替えされることを余儀なくされたが、新たに生れた組織も農家間の平等な関係を基礎とするものではなかった。ただ従前の構成と異なる点は、生産過程における本分家関係の規制力の後退と、商品経済の浸透によって、経済的な考慮が現れてきたことである。
7 「ゆい」はなぜ分裂するか
田植えの「ゆい」が分裂する原因は、何よりも作業にあまり日数がかかり過ぎて、遅れて田植えしたものの収穫量が減少すること、早く田植えしたものでも他の家の田植えをしているうちに、他の作業が遅れるという点にあった。そして、このような問題がはっきりした形ででてきた背景には、最近の稲作技術とくに保温折衷苗代の普及があった。
今まで冷水のかかる苗代と暖水のかかる苗代とでは首の伸びの違いが著しかったし、耕地整理以前の水田への入水は、上流から順次になされ、七日から十日ほどの日数を経て、田植えが行われていた。この違いが「ゆい」によって何日もかけて田植えをすることを可能にしていた。
ところが、保温折衷苗代では苗の生育が早められ、その生長もほぼ均等になる。しかもそこで育てられた苗は、適切な時期に移植されることが必要であり、それを遅れさせることは、はっきりした減収をまねく。その上耕地整理によって一時に水田に入水可能となったので、生産力の上からいっても「ゆい」における協業の利益を大きく打ち消してしまう。
また、田植え作業に要する労働力の確保という点からすれば、賃金労働者を雇える条件が生れてくる。現に大規模な農家では「ゆい」で不足する労働力を、他町村から雇傭して補っている。
とにかく、以上のような理由で、急速に「ゆい」が崩れてきている。
二 水稲慣習
1 はじめに
『国分翁夜話』第八話「今ずり米」に稲の収穫を歴史的に述べている。
一体、稲作は鉄が使用される前から行われたのだろうか?と考えて見ると、もとより正確な資料はないが、鉄の発明以前から稲作は行われていたものと想像することが出来る。
鎌の出来ない前は、稲の穂は手で抜き取ったものだ。大嘗祭に奉る悠紀田、主基田の収穫には抜穂式がある。そこで、租税を穂のまま行政庁に差出した時代は相当永いものと思われる。神様に奉る米を初穂と称し今も神前に捧げる金銭を「初穂」といっているのはそのためである。この様に昔、租税として穂を差出したものが後世段段と籾となり、玄米となり更に現在の様に金を納める様になった。ところで金属で鎌を作る様になって初めて稲を刈り取る様になったことはもちろんである。
日本の開びゃくの神話に「うがやふきあえずの命」という神様が出て来るが、これは茅で屋根をふいたことを意味しているもので、この時代はすでに、茅を刈る鎌が出来ていたものと思われる。その後、いわゆる、飛鳥時代には「飛鳥の板ぶきの宮」というのがあった。これによって当時鋸が出来たことを想像することが出来る。つまり、それ以前は家を建てるのも、すべて丸太を用いていたが、このときは板を使ったことが判るからである。
要するに、鎌が出来て、茅ぶきの屋根が出現し、鋸が発明されて板が用いられる様になったわけである。こういうわけで、鉄が現れて稲を刈取ることとなり、収穫様式は全く一変した。
次に脱穀の方法としては、穂を指で落して籾とする作業が永い間行われたが、後に唐箸(からはし)というのが発明された。これは竹の箸を二本木の台に植えてこれを左手に支え、右手に穂を二、三本持ってしごいたのである。これは、当時にあってはかなりの発明だったので、唐箸と名づけられたのである。此の名称は、例えば「唐箕」などと同じ様に唐の字は舶来を意味し、同時に特とすぐれた便利なものの名に用いられた。
この唐箸は明治初年に「千把ごき」が発明されるまで用いられたが、この唐箸の時代には一町歩位の水田農家は旧暦の年内に収穫、脱殻を終ることが出来ず、翌年の正月まで持ち越して脱殻作業を行なったもので、中には苗代耕作期までかかっても作業が終らなかったものもあった。そこで農繁期に入っても出来上がらないものは作業を一時中止して田植え、麦刈りを済ませ、その後小康を得た時に脱穀調整を行なった。丁度六月下旬から七月上旬に、残っている籾を玄米にすったが、これを「今ずり」と呼んだのである。
前の年の内にすった玄米は年を越して入梅の時期になると湿気を受けて品質は劣化するもので、これに反して籾のまま入梅を越したものは外気の影響を受けることが少ないから、これをすって玄米にすれば新米の様な品質を維持することが出来たのである。
だから、同じ米でも品質、食味がよく、従って値が高かったもので今ずり米という特別の相場があった。そしてこの今ずり米は大正の中ごろ、脱穀調整が動力機械化されるまで続いたのであった。現在は、一町歩の水田耕作者が脱穀調整するには、最大限一時間あれば足りる。だから収穫期の天候が順調であれば、本県の場合、十月中には収穫から脱穀調整の全部が終るし、刈取後天侯不良の場合でも十一月十日ごろまでには終るはずである。普通これを庭じまいと称した。
今日では、農作業は農業土木の発達によって、耕作の日数を短縮させたが、農機具の発明によって、何よりも収穫脱穀の期間を著しく短縮した。今後も潅漑、排水の改良が盛んに行われ、農道が完備し、更に農具が進歩すると、反当労力は年を追って減少するものと思う。
現在は水田一反は三十日、五人の労力で代掻きから俵にするまでの作業をするのであるが、今後数十年経ったら二十人位に減少する可能性は充分にある。
従って、今後はこの農家の余剰労力を何に向けるかゞ重要な問題であって、大いに考究しなければならないことである。
2 堆肥ひき
年があけると、大正月(七日まで)と、小正月(十五日から二十日まで)の間、すなわち、同八日以降、小正月前にウッタツということをやるのが常例であった。ウッタツとは春の雪消えをまって屋外に出て農耕に従事することである。ノサウズ・ノハダズともいっている。薪取りを擬装したり、厩舎からコエ(堆肥)をひき出す真似をしたりする。この堆肥出しも、やがてくる小正月の田植え行事、その前の施肥行事としてみると、まことに意義深い。
実際にコエを田圃に運搬するのは、雪上を利用するので、小正月後となった。大寒以後になると、残寒の季節で、好天もつゞき、積雪もしまり、夜にはスバレて凍結をし、朝にはカダユギができるようになる。この季節を待って各家では、田圃や畑地に厩舎の堆肥を搬出するのである。これがコエフギである。
マヤコエは、田圃や畑地に一里塚のように、点々と積まれた。それを、コエズガ(堆肥塚)といった。一人役の面積に塚が一つ宛築かれ、一つの塚が十五橇程度、一橇二十貫とすると三百貫となろうか。この堆肥は春の田打ち直前まで現地に置かれ(畑地は別である)、小区分してタナギモッコで配置され、田の面に散布されるのである。水田経営の施肥中、この厩肥ほど大事なものはなく、その原料として夏草苅りが如何に重大であるかを証すると共に、正月の行事にも織り込まれているほど、マヤゴエが重要であり、その搬出作業は農業開始の第一歩であった。
3 種籾の水漬け
春彼岸の中日から十日前後には稲種を水漬けにする。俗言に「社日に種籾をつける」とか、「春の社日に籾種を浸さなければよい」と、年により家により多少の相違はあるが、一応春の社日がその目標となり、その後に種籾の水漬けが行われる。種籾を水漬けにする方法には、半切り桶を用いる場合と、種井戸を使用する場合とがある。
半切りを用いる場合には、社日を目途にその前、適当な日を選んで水を汲み入れて洗い、水の洩れなどをたしかめる。その後、日当りのよい風の吹きつけない場所を選んで据え、水を適当に汲み入れて後、新しい一斗入れの笊で種籾をその保管用器である箱、または俵から移し入れる。水に浮んだものは柄笊または平笊でこれをすくいとって、鶏の餅などにする。
また半切りを用いない場合には、タナイドや池を用いて漬けるが、その場所を選定するための条件は前者と同様であるが、要するに湧水のあるところがよいとされている。従って、初めてこの井戸を作る場合は、こうした条件のところを求めることはいうまでもないが、このような良い場所はざらにあるわけではないので、一カ所に四~五軒の農家が共同して漬けることが普通となっている。この中にはいうまでもなく、分家が含まれているのである。
種井戸に籾種をつけるようになると、あちこちで、「種井戸さらい」を行う。これは普通籾種を漬ける前日、泥でうまっている底を掘り、萱の簀子を敷いて泥が上がって来ないようにし、氏神に御神酒をあげ豊作を祈って終る。大きさは色々あるが、深さは三尺前後である。
漬け方は先ず長木二~四本宛縄で結んで十字にわたし、その上を渡って歩けるようにし、二斗入れの俵のまゝ、水をよくかぶるようにこの長木に結びつける。
こうして種籾が水漬けされるが、その期間は俗に「産人と種籾は三十日床にいるものだ」といわれているが、実際には三週間位となっている。
品種は、どの家でも早稲・なかて・晩稲(おくて)を適当に組み合わせて仕付していた。不作凶作は、夏季の冷害や、二百十日前後の颱風が多く原因するので、それに対処する考慮からのものであった。
4 苗代づくり
苗代づくりには種籾をまくまで三回手入をするのが常例であった。すなわち、あら打ち・苗代こすり・百代ならしがそれである。
あ
あらうちは、雪消えを待って好天の日、畔を塗り、その土を掘り起す、これを苗代打ちとも、また苗代拵えともいう。苗代は昨年の田植え直後苅敷を入れてから休ませているもので、泥土が厚く、氷が張っているので、普通の鍬で掘り返すのである。いわゆる万年苗代で、水は年間通してかけられている。このあら打ちが終ると、苗代を囲む苗代垣が用意された。
苗代ばかりでなく、本田も彼岸の中に畦塗りをすると動かないといわれて、谷地田や水の自由なところでは、この彼岸ごろ肥料をまいて田ごしらえに着手する。
ところが苗代選定の条件は「日当りのよい風よどの場所」といわれているので、すべて水の自由なところとは限らない。年によっては雪のあることもあるので必ずしもこのころできるとは限らず、春雪が消えるのを待って苗代打ちをし、ついで畦ぬりをする。
い
苗代こすり(苗代掻き)は苗代のあら打ちが終ってから苗代に肥料を入れ、その肥料が土中によくしみこませるため、堅苗代の場合は、馬を使用して苗代掻きをやる。この場合は堅田の田掻きと同様である。谷地苗代の場合は、人手で鍬による苗代の土の掻き廻しをしてよく肥料を混合させる。肥料は堆肥を使わず、灰・糞・尿その他を使い、苗代に繊維の残留するものを避ける。
う
種籾を床に入れる当日か、その日の前後に苗代最後の手入れをする。それを苗代ならしといった。この苗代均しは、田植組の成人達が共同で作業するのが慣習となっていた。苗代に最後の肥料を加施し、十数人あるいは二十人以上の人々は、手に鍬をもって横列に土を掻きまわし、苗代の水をドロドロにするのである。
種の湯洗いをするから、三日後には種籾が萌えて芽をふき、否応なしに種まきが迫っているので、苗代の最後の仕上げのため、組のものが集合して、甲の家の苗代をならし、次は乙へ、それから丙へと廻って作業をするのである。同じ日に種籾の湯洗いをする場合、苗代均しには青壮年、種の火入れは老壮年ということになりがちである。
え
苗代の土ならしが終ると、長さ一尺二寸~三寸の萱を二本上部を交叉させただけで土につきさす。これを苗じるしまたは萱じるしと呼んでいる。この交叉点は苗代の底面から約七寸位の高さにする。それはこの高さまで苗が成長すると田植えができるといって苗成育の基準とし、苗代一枚について二~三組がたてられる。
お
苗代ならしが終ると、その苗代を強風から保護し、水温保護のため苗代垣を取付けた。杭と長木で高さ六~七尺の垣を結び、それに萱や芦であんだ幅広い簀子を結びつける。春風が強いので、その風を避けるように垣がつくられた。従って、苗代の畦畔は概ね幅広く土堤のようであった。また屋敷近くに苗代が設定されているのも、平常苗代を保護し早苗の育成を監視できるためであった。
5 種まき前後
種池(たなげ)から引きあげられた種俵は、二三日の間横においた長木の上にならべて表面を乾かす。その後屋内の土間等に種床をつくり、その種床内で芽を崩やし、苗代にまくという順序になる。
あ
種床(たなどこ)は屋内の土間等に、適当な杭と長木で高さ五尺前後、広さ六尺に十尺程度の枠を拵え、その四面の側壁には藁などを列べて縛りつけてつくる。これがタナドコである。種床の大きさは組の田の面積に比例をする。たとえば百苅の面積を二反二畝とし、種籾の必要量を二斗二升とすると、千苅の面積は種籾量二石二斗となり、二斗入俵とすると十一俵となる。千苅を耕作する農家が五軒で田植組を結成すると五十五俵を収容する種床が必要となってくる。
い
種池から引き揚げられた種俵は、俵の表面を二日位屋外で乾かしてから、組の成人達が集って火入れをし床に入れる。火入れとは種籾を適温の湯に入れて洗うことである。湯を大量につくり、人肌の温みにし俵の口を開け籾を湯に入れて洗い温めて俵を軽く結い、湯を抜いて種床に入れ、保温のため藁で俵を包むようにして並べ積むのである。これを火を入れるとか火をけるといい、発芽の最も大切な手心としていた。従って湯の温度・種籾の温み具合は、経験の豊富な老農の指図に待つ風があった。
人肌の温度とは、温度計のなかった当時の標準で、容器内の水温を見る時は自分の脇の下に手を入れて見ながら加減したといわれている。
種床への床入れがすむと、あとを取り片付け、参加者一同が簡単な酒肴でお祝をする。神酒を作神様に供えて、発芽の順調を祈り、火入れ作業の慰労をも意味している。種俵の床入れは床に寝せるとか、床に伏せるともいう。他の作物でも床を利用して種をまき苗として育成する場合は床に伏せるというから、床起しと共に擬人的な詞からきているものであろう。
このとき使用された俵には、木片に稲の種類を記入してはさみ、また笊は種類別毎に区別をして使うか、一回ごとによくたたいて品種を誤ったり、また混合するのをさけるためである。これらの種漬けに使った容器は苗の芽が出るまで他に転用しないものとしていた。
う
苗代への種蒔きは八十八夜を中心に行われたが、早朝から日の出前までに蒔き終らなければならないものとした。朝日の出るとき水面が動き籾が寄合うことを嫌うのだといわれていた。
古老の言によると、笊に二~三升位宛入れてまくが、それでも蒔いている間に笊の中の籾種が乾燥することがある。乾燥した種は苗代の水に浮いて流れるので、日が出てからもなお蒔かねばならないときは、編笠をかぶせるよりは、笊の中の種に霧を吹きかけ吹きかけ蒔かねばならないといい、また他の老人は日の出後は風がでるもので、これを恐れるのであるといっていた。
種を蒔く人はその家の鍬頭といって普通農作業の中心をなす男子である。これに当る人が早朝起床し必ず水で顔を洗い、俵から持運びが容易にできる小さい半切に種の芽を欠かないように注意しながら移し、さらに一斗入の旅に二~三升宛入れて苗代に出て畦から一面に平均するように蒔く。その量は一反歩当り種籾の保管は約一斗であるが、蒔くときはその中約七升といい、これを苗代には九~十坪の面積に蒔く。従って、一枚の苗代に数種のものを蒔く場合には区別しなければならない。そのためには縄を用いて一方の畦から他の畦に張り、その両端を柴杭でとめこれを境縄と呼んでいる。この縄の一方の杭の左右に品種名を書いた板札をたてて区別を明確にする。なお、この札は一般には種漬けの俵につけた木片を用い早苗とりまでそのまま取らないことはいうまでもない。
これで種蒔きが終るが、もし、畦畔に種が落ちている場合には、そのままにしておかないで、新しい先の細い草箒で丁寧にはき落して、初めて朝食の膳につく。これは素蒔きの方法であるが、現在は温床苗代・保温折衷苗代が多くなっている。
え
苗代は小型のものが多く、畦畔で種を振り投げてまくのであるが、それには限度があるので、少し大型の苗代には、長木等を渡して中央に進出して播いたりした。その長木を支える小型の柱二本に横木を結っておき、それに長木を二、三本渡し、人がそれを渡りながら種をまく、それが種まきの仮橋であった。種をまき終ると、空俵を家の軒などに吊り乾して翌年に備えた。
種蒔きが終ると、その余った稲の種を臼でついて籾殻を取り去り、センバンまたは鍋で炒っていわゆる炒米を作る。
お
この炒米を約二十粒宛、三寸四万位の半紙に粉薬を包むように折って包んだものを萱の二尺位の長さのものに挟み、水口(みなくち)の処の真申にこれをさし、その両側に萱だけのものを数本適当な間隔にさし、その根本に杉の葉をそえる。そして「鳥が苗代に入らないように守って下され」といいながら、別に用意してきた炒米をその付近にまいて、首の成長と共に鳥の害から守って下さるよう手を合わせて拝む。これを水口まつりという。
今ではその形式のみを伝え、ただ水口に炒米をまいて拝むだけになっているところもある。
この祭りがすむと、氏神にもこの炒米を供えて豊作を祈念するのである。
水口まつりに使う炒米は少量で足りるが、その残余は糯・粳を区別して一緒にまとめ、そうしたものを蒸して乾燥し、臼に入れて手杵でつくか、水車でそのとり入れ水を弱くして強くなくつき、籾殻をとって蒸米を作る。強く鳴くとくだけてしまう。
こうして作った蒸米は炒米よりやわらかであり、甘みもあるのでお茶菓子の代りにも用いられ、子供達には五勺位を紙袋に入れて与えると、一日の間食には十分であり、また、これで酒を作るとうまいと伝えている。なお隣り近所にも配る習慣があった。
6 田植前
あ
水田のあら打ちは、農作業中での重労働とされていた。水田には大別して堅(かた)田と湿(ぬかり)田がある。堅田は乾田で、馬耕にも適しているが、湿田は泥土が深く、馬を入れることの出来ないところである。堅田のあら打ちには三本鍬が専用され、湿田のあら打ちには畠耕作用の普通の鍬を用いるのが常例であった。このあら打ちを総称して田打ちといった。
い
この田打ち作業には、古くからの慣習として、常人の作業規準が馬耕鋤の流行する大正年代の末まで存続していた。一人役というのがそれである。土の深さなどによって多少の相違はあるが、平均して約水田面積七畝から八畝が一人役で、それが常人一日分の作業量とされていた。従ってあら打ちには、その一人役を打って、その後は自由に休養してよく、どの村でも不文律となって実行されていた。よって若い者は早暁より田圃に出てあらくれ土を起し、達者な熟練者は十一時ごろには一人役を打ち終るので、午後はゆっくり休養出来たのである。このことは未婚者の資格試験でもあった。実働時間は六時間から七時間であった。田圃の中では、隣家の者がお互い早く一人前を打ち抜くように競い合い、田打ち中は田打競争の観を呈することとなる。まして若い者連中がゆい田打ちでもすると、競技の形となるので一層励むことになった。一番最初の一人役を起した者を一鍬(いちくわ)といった。たとえば青年十人でゆい田打ちをすると、十人役の面積すなわち十人打ちを起すことになるが、一番先に打ち終えたのは一番鍬で十番鍬までの十段階になる。最後になりたくないので朝早くから田打ちにかかる。朝の早いのは自由である。青年は十五歳以上になってから参加をする。ゆい田打ちでは一番鍬か二番に助力し、次は一番と二番が三番に助力し、十番目の者は九人から助力されることになるので、その御礼に十人分の三本鍬を洗い、その上食事のときは末座に座って九人に給仕して助力に対する感謝を示すのであった。これによって若者が訓練されたのであろう。明治中期の一ノ倉家の記録によると、五月二十五日五人で二百五十苅の田を打ち、翌日は十三人で六百五十苅を打っている。
ここで田打ちの変遷をみるに、手掘り、または手打ちといって三本鍬で打っていたものが、昭和の初期ごろから牛馬を使って馬耕打ちをし、今次大戦後からは砕土機を用いるようになった。
砕土機を用いる場合は別として、その他の作業の場合にはすべてキッケェス(切り返し)という作業が伴う。馬耕打ちの初期までは、この作業は人手で行うものとして三本鍬で行われたが、後半からはハローというものを牛馬に曳かせて砕土するようになった。
手打ちによる田打ちは昔から重労働であったから、平常食と違い白米食であった。平常食は一般に白米三分に稗、または麦等七分を普通とし、大農では半々の割合であったという。
田打ちの方法にはおし打ちと結いっこ打ちの二種がある。
う
おし打ちというのは、家人と手伝人とで田打ちをするときの方法で、一枚の田に全員が入って一方の隅から適当な間隔をおいて並んで、田のなりに従ってまわり打ちを行う方法である。従って最初に田に入って端を打つものが一番難儀をすることになるので、家人か家人がいない場合にはその家の主な親類に「どうがすけでくねぇ」と声をかけて先に田に入るものといわれていた。
え
結いっこ打ちは、いわば「わっぱか」仕事である。換言すれば、一人役分を打ち終ると帰宅することも可能なわけである。この方法による田打ちは、夜の明けないうちに起き出して行って田打ちを始め、夜が明けて間もなく朝食をとる。従って昼食も早目に食べるけれども、早い者は一人役の田を十一時に打ちあげ、昼食をもらって食べると帰るようなものもあった。しかし結いっこ田打ちの名の通り、結いなので相互に労力で償う共同作業であったが、馬耕を使うようになってからは、各家単位にその作業の仕方が変った。とにかく、この方法によると、田打ちは常に競争であり、その日一番早く打ち終った者は、夕食に招かれたときには、正座でその家の主人の側に座を占めることが出来た。
お
堅田のあらくれが乾くころあいをみて、それを砕き耕すため、再び三本鍬で前のあらくれを崩しながら土塊を打ち砕いて細かくし、粉のようにして均らす、この作業を田キケェスといっていた。家族またはゆい組の群が横に列んで、三本鍬で掘り崩したり、鍬の頭で打ち砕いたりして前進するので土煙りがもうもうとあがる。
か
堅田のきりかえしが終り、谷地田の田こすりが終ると、それぞれの水田に肥料が散布される。すでにあら打ち前に堆肥が散布済みであるから、今度の施肥は第二回目となる。これをズキ入れという。今回の肥料は液体肥料の糞尿・木灰類・魚粕・油粕・その他の有機肥料が散布される。このときの施肥の散布は重大であって、その家の主人公の指示によって按配され、散布の度合が決定された。
苗代の肥料は、化学肥料のなかった時代には草「カッツギ」といって、青草を苅り集めて用いるだけであるが、その量は一人役(八畝)の苗代に七駄(一把約四貫のもの六把)を基準とした。なお、蒔かれた種から芽が出ると、寒づくりの人糞尿を水でうすめて施した。寒づくりとは寒中に便所から桶などにとりわけておいたもののことである。
き
厳密な意味において田掻きというのは、馬鍬を用いて代掻きをすることである。馬一頭にサヘドリ一人、馬鍬押し一人を一組とし、馬十頭なれば要員二十人となる。馬で田を掻く場合はもちろん堅田に限られており、多くはゆい田掻きであり、十頭前後の田掻きは普通であった。従って、馬を使役する場合の要員は偶数であるが、外に水の加減をみたり、水口の調節をやったりする役目も必要であり、また馬糧役や田掻衆の食事役も必要であった。田掻きは、田の土に水を加えてどろどろとすること、施肥を平均にすること、耕土の厚薄を平均すること、水深を一定に保つこと等で重視された。
田掻きには水を必要とするが、そのためには水路の堰あげをしなければならない。堰あげはその水路の関係者が共同して行わなければならない。すなわち予め決めてある日に各戸から一人の割当で参加するが、終って水神に御神酒を供え、各自も飲んで解散するのであるが、このときの経費の負担額は田一反歩当りの基本金額が定まり、その水路に関係する各自の面積によって出しあうのである。
田に水がかゝると、土の深い処では田を掻きながら畦塗りをするが、土の浅い処では、浅春に畦を塗ってから田を掻く方法がとられている。
さて、田掻きであるが、その方法には次のような種々の順序がある。
田打ちをし、田キケェス後もとのように平らにならし、これに水をかけ荒代掻きといって、馬鍬(まか)を馬に曳かせて土をやわらかにすると共に、田の水かゝりを平均にするために高い方から低い方に土をよせるように注意しながら馬を廻して掻く。これが終ると、苅敷を山林から採取した新緑の若葉や、葉小柴を一面に並べるように敷き、その上に厩肥を田一面に散らす。そうした処に馬を入れ、いわゆる馬まわしを行うが、これは肥料を深く踏み込むためで、砂田のような表土の浅い処では必ず行い、馬の頭数も多いほどよいとされた。そのあとをふませ杖といって、柳やこんごう等の木の小枝を約三尺位の長さにとり、土にめり込まないようにその先が二股または三股になるように木どりしたものを持って田に入り、一列にならんで田の一隅から残った肥料を土の中に踏み込む。これをふませといい最後にえぶりをかけてあら代掻きが終る。
「えぶりすなわちいぶり(動り)は霊魂をいわいこめる呪術であって、田の代を平らにならすと同時に、田によき霊力を斎いこめる呪術であり田遊の最も重大な一要件である」と民俗学辞典に明示されている。
く
刈敷(かつつぎ)には草刈敷と木刈敷とがあり、草刈敷は水田に用いたが、木刈敷は苗代の肥料とした。
本田に用いる木刈敷は普通一反歩に付三駄乃至四駄を必要としたが、土のよいところではその半分位であったところもある。刈敷にする木は三年ばえが最もよいといわれて、三年経った若枝で薬の大きい木の軟かいものが喜ばれ、楢・栗等の雑木で特に榛(はん)の木がよいとされた。刈り取る長さは下膊の長さよりは長く刈らないものとしていた。この時期は他家でも多忙なときであり、ときもまた同じになるからこの作業にだけは「ゆい」がなく、家族でやるか、さもなければ、他から頼まなければならなかった。
刈敷を必要量だけ刈取ると、その晩に「刈敷山下り祝」といって、多忙な時でもあるので特に御馳走は作らないが、餅を搗いて山神に供え、祝は餅振舞で手間人と家族で行われ、このための特別の休日はない。
こうして刈取られた刈敷は田掻きの終った本田に施されるが、踏み込むまでにこの刈敷が浮んで田の中を流れないようにその上に厩肥を散らすが、厩肥は一反歩に付三百貫を標準とした。
尚、古老の言によると、刈敷を肥料として使っていた頃には、化学肥料を使うようになった今日より病虫害が少なく、米粒もまんまるで光沢もあったということである。
化学肥料が岩手県で使われだしたのは、明治三十年(1897年)ころで、この普及と共に山に登って刈敷を刈るものがなくなり、田掻き後の三~五日の日数は縮小されて、肥料は化学肥料の外に厩肥が主に使われ、三百貫を標準とすることには変りがないが、堆肥にしてから田に運ばれるので、以前よりは量が多くなっている。
け
堅田は田掻きをまって畔を塗るが、こうした畔をヌリグロといい、このぬり畔に大豆などが植えつけられた。畔(くろ)豆とはそれを指した名である。
7 田植
田植えには各種の作業があってそれぞれ分担が生ずる。植付を専門とする早乙女、苗代で苗取りを専門にする苗取り、植付当日田の土を掻き廻す代掻き、苗代から田に苗を運ぶ苗背負、「エブリ」で田の土を平均にならすエブリすり、早乙女に苗を配り植付を主宰するコナズバリ、休憩時の間食に野外の田園に運ぶ小昼持ち、全員の食事を準備する台所炊き等、早乙女が二十人前後になると、こうした分担が必要になってくる。
あ
苗運びは年齢が三十歳から四十歳位までの人で、一町歩について通常二人の割合となっている。苗を運ぶ容器は古くは苗背負樽または長樽というもので、苗が七十乃至八十把はいる。これを一つ宛背負って運ぶ。その後肥料樽(担い樽)に約四十把を入れた苗を天秤で一度に二箇宛を運ぶようになった。
なお、古くから使用されている苗運びの一つに苗籠がある。この苗寵には八十~百把の苗が入り、二箇を天秤で担いで運ぶ。
以上は本田と苗代とが近い場合であるが、遠い場合には馬の背を借りている。この場合には荷籠というのをその左右につけて運ぶのであるが、この荷籠には百五十把入るので一駄で三百把運ぶこととなる。その後、苗箱といってリンゴ箱を用い、馬のかわりに荷車、その後リヤカー・自動車と変ったのである。
首背負人は前日の夕方に翌朝植える分を運び、当日はまた、他の人々より一足先に仕事にかゝり、その日の夕方は翌日の準備のために苗を背負わなければならない。従って、夕方には仕事の性質上他の人々より先に御馳走になり、また、朝早く仕事にかゝるということで特別の賄がなされた。
い
俗言に「田植をする時は、早乙女の顔を水鏡にうつさない」といって、必ず柄振をかけて濁さねばならないものとした。従って、朝出かけて行くと、その最初に待っている仕事は柄振を振ることであった。それが終ると縄はりをする。これをトネェウズといった。このとう苗は一町歩について三人を普通とし、年齢は二十歳から三十歳位の者がこれに当り、これが終ると苗背負人の運んできた苗を要所要所に配布するのがその役でまわし終ると次の田に入って柄振を振る。トネェウズとは遠くへ苗を配布する意味であろう。
俗言に「五月田に使う道具を跳び越えるな」といわれている。この柄振については特に神聖視して、通路においたり、跳び越えたりしてはいけないといって、人の通らない土堤の急斜面または付近の立木にたてかけておくものとした。
夕方本田のとう苗役がすむと、その家の苗代の畦塗りをしてその日の仕事が終る。
う
コナズバリには、男性の老練者等が当り、水田の水の調節・植付の順序・品種の配置・人糞と魚粉を混合したものを木舟に入れ、それに早苗の根をくるんで早乙女へ配布・休憩食事及び仕事の取付・中止・苗代への連絡等植付全般の釆配を掌る重要な役柄である。従って、植付の家の主人か、若主人がその日のコナズバリの役目をするのが通例である。
え
田植えでは女性は植付専門に従事し、男性は苗取りその他に当るのが常例である。この植付の女性をショウドメ(早乙女)といい、少女から老婆までを指している。田植えの季節に咲くアヤメ・カキツバタを総称してショウドメ(ショドメ)と呼んでいることに関連しているであろう。女子は十三歳から早乙女に初参加するが、そこで先輩女性から苗の分け方・掴み方・植付技術・間隔のとり方・足の運び方の指導をうけ、訓練されて一人前になっていくことになる。いわば田園女性の初陣であり、その巧拙は衆目により評価されることになるので、その母親は娘の植え付け振りを一所懸命に指導したものである。
植え付けの先頭は熟練した婦人により開始される。例えば苗数を五本、その間隔を均等にし、後方に向って一直線に植え付けるという業は、老練の婦人にして容易に成し遂げられる。それをサキガゲともクロヅゲともよび、早乙女中の先登者として尊敬されるのである。
田植え作業は農業を営む者にとって最大重要事であった。新年の小正月の行事にみるように、その年の豊穣を念願して、田植えの模擬までやっているように、一年間の生命を托す生業で、米作りの第一歩はこの田植えに始まるからであり、それまではその準備にすぎないのである。
田植え後は、ひたすら天神地祗に頼むより外なく、田の神様を祀り、嶽の神霊に祈り、つゝがなく生長と豊穣を念願してやまない。そのため田植えには一家総力で植付に従い、晴れの気持で晴れの食事をとり、晴れの衣服で仕事にあたることが必要であった。晴れの気持、それは初田植えに田の神を祀り、田植えが終ってサナブリ祝いをやることでもわかるように、立派な祭祀行事であり、田植え中の食事は平常食と異り晴れ食であり、衣服装身具もまた晴れのものであった。すなわち、田植えには、男も女も新調の上着と、新調の股引(もすぎ)を準備するを常例とした。もちろん自製の麻布が原料であり、機織・染色・裁縫は十三歳以上の女性がそれに当り、男子十五歳以上の者は、蓑や雨具、履物を新調したのである。これが晴れの衣服装身具である。たとえばハギマゼ腰プリ・モスギ・編笠・クゴケラ・ミゴケラ・足半(あしなか)・手ケェス等が新調され田植えに着初め履初めとしていた。
また、苗代に入ってみて、その底が冷めたく感じられるとその年の世中はよくなく、温かければ豊作であるといわれていた。
お
田植えは古くから結い組が結ばれているので、その組の植え付け順序があらかじめ決定すると、その前日から苗取りが開始される。これには老壮年が参加をする。田打ちや田植えには未明から働くのに対して、苗取りは朝食がすんでから出かける。しかし、遅くとも午後の二時か三時には取り終るのである。最近は田植えも未明からでなく、朝食後から行われるので、苗取りも田植えのその日早目に取り始めると間に合うので、同時に行なっているところもある。
苗取りは苗代の水を深くしなければ苗がとれ難いため、その日は水を多くする。従って、中腰で作業をすることになるので、腰が疲労し、いたくなる。そこで最近はリンゴ箱を持って苗代に入り、これに腰をかけて取るものが多くなっている。苗は伸びのよい処から取るので、場合によっては田の中央部が先に取られるようなこともある。
なお、苗を取っているとき、今は病気苗といわれるものであるが、白く縞のようになっている苗がある。これを田の神様の苗であるといって、偶々これにあたると果報がさずかると喜ばれたが、これがまた田植え中、植えている早乙女が植えながら発見した場合も同様にいわれている。
取った苗はこれを投げるとその腰がおれるといって、田舟に積んで田の畦に近く運び、ここから籠または桶に細心の注意のもとにつめられてこれを本田に運ぶ。
苗取りの最初の食事は小昼といって「たばこ」であるが、このときは作業中の田の近くに焚火して、これを中心に各自の蓑を敷いて腰をおろし、普通の作業の間食より時間を多くとり、いわば昼食の略式ともいうことが出来る。三つ組(テッパズワン・オズゲワンコ・カサコ)であるが、魚をつけ酒が少々出る。なお、昼食は少し遅く午後二時ごろで、この後間もなく苗取りが終了する見当にしている。今は一枚の田に何人もの人が入って苗取りをしているが、昔は一人役に一人の割合、一人役というのは苗にして三百把から三百五十把であった。従って何人役の田があるから何把あればよいということがわかった。現在でも「苗ばわら」というのを百本宛を小束にして三把準備することは、昔と変りがないが、その日たゞちに植えるので、本田に持って行った苗の把数を数えなければ、これを知ることができない。このような苗取りの方法を「おいかけ苗」といっていた。
か
苗の植え付けは時期を失せず一斉に植え付けることが肝要である。そのために発達したのが「ゆい制度」である。田植ゆいは十戸前後が組み合ってできている労働交換の単位であって、二十戸に達するものは知られていない。通例同族が組合っており、地域が隣接しているので利害を共にすることが多い。この田植組は種籾の水漬けを共同し、種籾の湯洗い、床伏せを共同、苗代均しを共同し、代出し田掻きを共同し、田植えを共同するというのが常態である。永い年月の共同労働及び労働交換で戸数が増し、耕地が増してくると組が合議の上分裂して二組となることもあるが、従前は耕地戸数とも変化が少なかったので、田植組もあまり変化かなかった。組の中で労務を交換し、組の田植えが済まない限り、他の田植えや労務の交換ができないのが組の不文律である。
初田植えには、庭という中庭の土間に臼を伏せて、前日の夕方の中に苗三把を苗代から迎え、マガとサシェザオを添えて、翌朝、早乙女達が集って来るのを待って御神酒と小豆入の握飯三箇を盆にのせて供え、皆んなで豊作を祈念し、田の神祭をし、終って後、早乙女全員がこの苗をわけて田に持って行き水口に植えたのである。また田の中央に注連縄を張りその中へ田の神様を迎えた所もある。
早乙女を初め田植えに参加する人々は、早起きして出かけるが、よく晴れた朝などは夜の明けるのを待って起きて行った。そして遅くとも午前五時ごろにはその日植える家に集合したが、結仲間以外の手伝人で遠くから来る人などは、この時刻に間に合うためには一番鶏の声と共に起きてきたという人もあったと伝えている。またその日田植えをする家でも朝、夜の明けないうちに起きて炊事をし、早乙女達を待ったのである。今は朝食後からの田植えであり、結いも少しはあるが、賃労働が多くなっているので田の神祭りも形式的になっている。田植えが終了すると組のもの全員が集合してサナブリ祝いをする。このことについては第四編、第二章、第十五節 食物、三 非常食、3 その他の祝いに譲って、ここでは省略をする。
8 田植後
あ
田植えが終ると苗代垣を外してしまい、苗代から雑草等をとり去り、あらたに畔を塗り、その泥土を鍬で打ち返して、翌年まで一定の水深を保ったままとして休ませることになる。その上に苅敷をかけるが、この苅敷は苗代の緑肥でもあり、雑草の生えることを防ぐことにもなる。いわゆる通し苗代で苗の育成以外には使用せず、大切に来春まで保存する念慮からであった。そのあとは、苗代には田の神がいるといって苗を植えない習慣であった。これは苗代を酷使するなということにあったらしい。
い
田植えが終って四、五日するとウェナオスといって、前もって田の一隅に残しておいた苗をハギゴに入れて、生きつきの悪いものはこれを植えなおしし、浮いている場合は補植をする。
う
田植え後苅入れるまで草取りが三回ある程度でさしたることはない。
9 稲苅り・稲こき
稲の穂が結実し茎が黄色になると、田の水を切って枯渇をはかり、時期をみて一株一株苅りとる。三掴みを一把に結び六把一組として、穂先きを下にして五把を立て、上に蓋(おおい)として一把を掩いかぶせ、一束立てとして乾かす。これが第一次乾燥であった。その後、稲架(いなばせ)(ハシェ)にかけて乾かす。これが第二次の乾燥である。稲苅りには七~八畝歩を一人役とする遺制があり、三人分役を千刈りといい、一人役は三十三束二把に該当した。
稲を苅りとって、ハシェにかけ乾燥を待って暫くの後、家族をあげて稲こきに従事した。明治から大正にかけては末だシェソバゴギ(千把扱き)の全盛期であった。稲をこく・わらを片付けて積む・籾を打つ・ふるいでふるう・唐箕で塵を吹き飛ばす・籾を容器に貯蔵する。このような作業が一貫して行われるのである。
10 米の精白
米の精白も多く女性によってなされた。土間に臼を据えて手杵でついて精白する作業である。その場合、片手つきと両手つきは杵の種類にもよったが、共同でゆいするときは片手つきが多かった。歌のはずんだのもそれであるという。唐臼づき、バッタリ利用(一日に一斗位)・水車利用(一臼一日に三~五斗)と変化した。粉食用の粉つくりも殆ど女性であり、野外作業はなくとも女性の屋内作業は少なくなかった。
三 畑作慣習
1 畠からみ
雪が消えると、畑地を一定の幅で掘り起こし、横長い三角型の畝をつくる。人手で鍬を振って土中に打ち込み、土を掻き上げて後ろ向きに進行する。このことを畠からみといい、これがはじまる。
畑地をからむことは畑作の重労働であった。ことに昨年開墾したあらき畑は、昨年畝の半幅だけを掘り起しているので、今年残っている半分の幅を掘り起すことになる。その作業はまた重労働であって、おも返すといっていた。いと畠からみ・豆畠からみ・稗畠からみ・そば畠からみ・大根畠からみ・その他各種の作物を仕付けるためには畠をからまねばならない。一番からみ・二番からみは普通であるが、三番からみまで、同一の畑地を三回掘り返し、雑草の生えることを防がねばならない。このように掘り返した上で堆肥その他の施肥をすることとなる。
除草について『国分翁夜話』の第三話に次のように述べてある。
農業で一番悩むのは雑草の草取りで、私の経験だと、畑には六十五、六種の草が生える。そして畑作では六五%から七〇%までが草取り、あるいはその準備作業である。水田では三五%から四〇%までが草取り作業である。しかも草取りは農作業の一番忙しい季節にやらなければならない。いわば除草の如何が農業の根本である。こう考えて来ると、どこまでも土地を肥やすことが一番大切だ。家畜を飼って、労力のすべてを地力に投ずる。地力が肥えると雑草が生えない。そしてやさしい雑草だけが生えて、根強い雑草は枯れてしまう。畑では地力が肥えると、スキや鍬に土がつかなくなる。田も同様、機械を使っても土がつかなくなるから仕事はずっと楽になる。
2 大麻
大麻の作付は衣料を自給していた農家としては極めて重視をし、その作付けの畠も水田の苗代に比適するほど大事にしていた。苗代は万年苗代であると同様、麻畠も万年畠で、大麻作付けの専用畠であり、この畠だけがオツボまたはイトバダゲといわれた。しかもこのオツボは地味は最上で地価も苗代と同じく、他の作物の栽培には使わなかった。これは農家の衣服原料として重要なものであったからである。衣料としては、野生のカラムシ(苧麻)・アイコ(薄麻)その他があっても、大麻の生産が衣料としての原料を左右し、その他は補助的繊維でしかなかった。
麻蒔は「三月中穀雨より数えて六日目に蒔く」ことになっているが、この三月は旧暦で、穀雨というのは四月二十日か二十一日に当るので、それから六日目の四月下旬である。種子は一反歩に四升乃至六升を下種し、肥料には堆肥・搾粕・油粕・草木灰・人糞尿などを用い、近年は過燐酸石灰をも加えてこれを原肥とし、補肥は品質を損ずる恐れがあるとして与えない。間引・中耕・除草をすると八月ごろに幹が成長して花蕾を持つようになるが、このときを見はからって抜き取るか刈り取りをする。
大抵麻種を蒔いた日から昼休みができるものとし、また麻を収穫した日からは昼休みができないものとする労働慣行があった。この大麻播(いとま)きが、農作業の休養時間決定の標準とされるほど重視されていたことは、農作業と季節との関係において重要であったと知られる。
大麻が未だ生長中でも、雄麻がそろそろ花が咲き始めたころを見はからってこれを引き抜き、引き抜いてから根を切り去り、その葉を叩き切るのである。花が咲くのをハナソ(花麻)、実がなるのをミソ(実麻)といっており、大麻の種を採種するために外周の太いミソを残しておく。それをホドリソ(周辺麻)といった。
大麻の葉を叩き切るためには木製の幅ひろの木太刀を振ってその緑の葉をそぎ落した。その木太刀をハウズ(葉打ち)といった。麻の葉は堆肥として使用され切り離された大麻の根は乾燥して焼かれた。
引きとられた大麻は家の近くで蒸して乾燥される。そのため馬釜という大形の釜で蒸される。長方形の長持に似た箱か、あるいは大型の長い桶を上から掩いかぶせるかして蒸気を通し、適度に蒸して取りあげ野外で乾燥する。この大桶をカブシェといった。かぶせ桶の意味であろう。
大麻を苅り取った日から昼の休みが廃止になった。それは麻を青いうちに蒸さねばならぬこと、蒸した麻をば直ちに乾燥せねばならぬこと、雨に逢うと皮を腐らすおそれのあることなどの条件が重なり、麻畠から運んできて蒸して乾かし素早く屋内に仕舞い込むという一貫作業は、僅々二・三日中にやってのけねばならぬ。食事の時間も惜しいように機敏に立ち廻ることになり、殊に衣料衣服に全責任を持つ女性達が神経質になって立ち働くので、昼食休みなどしておれなかった。衣服原料の収穫が始まったからである。この麻畠はあらためて畝を立て、大根畠から大根を移植したり、冬期の漬物用としてたかな・たいな・さんとうな・かぶ類の青菜類が播かれたりする。この移植の大根をオツボナといい、軟かく成長するとして愛用された。
3 稗
藩政時代から明治初期は稗蒔きの準備として春分から八日目を目標として稗畑に肥料を運んだ。今でも肥料はいくらで十分ということはなく、やればやっただけのことがある、といわれている。
稗畑の畝は幅一尺五寸ではせまいので一尺七寸位とし、高さは三寸以上五寸位につくる。稗種は一反歩について二升五合から三升位で、粟に比較すると二倍位必要である。これを濃厚な下肥に混じて蒔くのであるが、煤を交ぜ合わせて蒔くと特別成長するといわれている。それが終ると軽く土をかけて終る。
稗は湿気(しけ)る年には良くて、ひでりには悪いといわれている。従って東北の冷害のようなときでも生育するので大切な雑穀の一つとされた。
粟は補植のできない作物であるが、稗は補植ができる。それで冷害のようなときには水田に補植されることがあった。食料の欠乏したときなど稗を白米に混じて食べるとその不足を補うことはいうまでもないが、夏は御飯が悪くなるのを長びかせ、冬は体を温める食物といわれた。実際稗は白米一升に一合の割合は丁度よいが、三合入れると鍋一杯になるといわれてふえるものである。
補植のできるこの稗は温床の蔬菜のように畑の隅などに蒔いておいて八十八夜前後に移植する。移植に際しては畝ができると下肥をふり土を薄くかけ、稗苗の丈一尺位のものを葉の先の倒れる部分を切って移植し、これが終ると、畦ふみといって根を踏みつけて固着させるのである。
水田に植える場合には畠の厚いところから間引いてこれを植えるか、苗代を作ってこれを育てて稲と同様一株に四・五本宛を遠めに植える。遠めとは八寸から一尺一寸位のことで、苗代作りは稲よりおそくてもよい。
従って畑に直播きをした場合にはヌギダデをするが、これを薄いところ、または水田に補植、または移植をするのである。その成長度はほぼ同じ位で、昔から稗はつきやすいもの、粟は手加減のいるものとされた。
六月の下旬中耕が行われるが、このときには人糞を水によく混合したものを追肥として施す。
昔は粟の場合と同じように土用前に草取りをし、両方から土寄せの二番あげをするが、稗には行われていない。
秋に苅り取った稗を八把一束とする。穂を上にしてたて、乾燥をまって脱穀をするのである。
4 粟
粟も主要食糧の一つとされていたのでその播き付けもまた重視されていた。粟畠に堆肥を使用することもあったが、前年の豆畠を利用する例も多かった。
粟を播く季節は八十八夜になり、山鳩がなくようになってから、田打桜が咲いたら粟をまくなどの自然界の事物の変化によって播種の季節を判断して農事の作業を推進することが多く、粟まき季節の判断もまたその一例であった。まず粟畠の一隅に径五尺前後深さ八九寸の浅い穴をつくり、その穴を踏み固めて糞尿を入れ、適当に水を加えて液体肥料をつくり、その液体肥料をゲスオゲに汲み分け、左手にその桶を提げ、右手で液体肥料をふり、粟種と共に畝ごとに散布し、鍬で土を掩い、その上を踏みつけておく。これが粟まきである。
昔は前年の秋の中に木灰に下肥をまぜ、天気のよいときを見はかり、これを乾燥しとうしにかけてとおして準備しておいたものを翌年用いたといわれている。ただ粟蒔肥料は稗の半分でよいといわれ、アグミズといって木灰に木炭のまじったものであるが、近年はよくタンタンが使われ、これを交ぜると温度がよけいつくといわれている。
畦幅は一尺八寸~二尺で、高さは三寸以上五寸位にたてる。蒔き終ると畝ふみを行う。これは畝通りを横むきになって踏むのであるが、生えた葉を平均にするためといわれる踏みまき法である。
粟は旱魃によく、しける年には悪いといわれているが、どうしたことか紫の穂の出ることがある。粟に紫が入ったといえば不作ということにしていた。
粟の抜立てといって間引きをするが、一番除草を兼ねて田植えがすむと直ちに行われる。この間引きが粟の育成上大切な仕事の一つとされている。
二番除草は土用二、三日前に終ればよいといわれその日を目標に行われるが、このときキッカゲといって作上げが行われる。その後暑さが益々加わり雑草が生えるので余暇を見て除草をするが、二番アゲといって畝の両方から土よせを行う。
出穂が成熟すれば根もとから苅って家屋の近くに運び、粟バシェにかけて乾燥後脱穀をする。
5 豆
豆類の作付けは農家にとってこれまた実に重要であった。殊に大豆の収穫は食生活に直接響くのでその作付けには念を入れていた。畝の中に堆肥を敷き、合い土を上からのせて堆肥をおし押え、その上に大豆を畝ごと等間隔に蒔き、さらに土で掩うのである。
大豆はいうまでもなく味噌の原料となり、その他、豆腐・納豆・炒豆など加工食品として日常生活に不可欠のもので重要作物として取扱われた。堆肥は厩肥を主としているので、その堆肥は冬期中、橇で運んでおくか、冬季以外は馬に荷付けて運搬し、それを豆畠に施すのである。
その外、麦の生長する畝と畝との中間に大豆をまいて、二年三毛作とする風もあった。この場合は、すでに麦畠に十分施肥してあるので、特に堆肥を施さずに大豆をまき、麦を苅ると麦畠はたちまち大豆畠に変形した。
かっこ鳥がなくと豆まき、クルミの葉が鳩の羽根位になれば豆まき等の俗言がある。
大豆には品種が多いが大別すれば三種になる。すなわち、種子の黄色であるものをシロマメ、黒いものを黒豆、緑色をしているものを青豆といっている。盆大豆は普通青大豆が多く蒔かれエダ豆といっている。
作入以外は空畠といってやすめていた畠に蒔く。栽培は極めて容易で、麦類と同じで丁寧に整地することを要しない。条間を二尺位、株間を一尺内外とし、二・三粒宛を一株にまくと一反歩に種子が三・四升の割になる。但し、青刈用の大豆の場合には多量の種子を要する。肥料には灰を用いた。
作入大豆は麦畑に蒔くが、種子の割合は前記と同様であるが、主として白大豆である。
播種後は普通の作物と同じで一・二回の除草・中耕をするのであるが、キッカゲは季節が早く草があまり生えないので草取りと一緒に行われるのが普通である。
田の畦にも豆をつけるがこれは豆蒔きといわず豆植えという。これには青大豆が多く、十五夜などには苅り取ってうで豆として食する。秋の青豆は滋養分が多いといって留守居がこの豆を五升鍋等に煮て働き手を待った。
収穫は秋大豆が十分に成熟するのを待って根ごと抜きとり、柴苅鎌を刃の方を反対にして打ち土をさり、稲架にかけて乾燥し、臼へ打ちつけて豆を脱し、篩(ふるい)や唐箕を用いて調製をする。
大豆を耕作する目的には、実の収穫を目的とする場合と、葉の収穫を目的とする場合とがある。後者はいうまでもなく馬料である。最も馬料には大豆そのものはもちろんのこと、大豆を脱したあとの豆殻を押切で八分~一寸位の長さに切ったものを萩などと混ぜて与えるのであるが、この場合は青苅りして馬料とするのであり、これを葉引きといっている。藁工品等をつけて町に馬をひいて行くときなどにはその馬の昼飯であった。
青苅りのための種子としての大豆は粒の細かいシロマメで青大豆や黒大豆も用いられた。これらを葉引豆という。
この葉引豆は青苅りするので普通の豆蒔きの時期よりおくれて蒔くし、またそれでよいのであるが、厚蒔きで黄大豆は一反歩五・六升以上、青大豆か黒大豆なら五升位である。肥料には灰を用い、キッカゲは草があまり生えない時期でもあるが一応草取りも兼ねて行われる。苅り取り時期は豆が実にならないうちであることはいうまでもない。
小豆は大豆と蒔き方は同様であるが、小豆と隣り(隣家)は遠い方がよいといってその種子の距離をはなして遠く蒔く。従って、一反歩当り大豆は四~五升必要とするが、小豆は約三升の割である。
小豆は昔からその使い方がきまっているので、売買はいうまでもなく米の相場と同じであった。
本村は馬産地であったから馬の飼料として青引き豆が畠に作付された。この豆はアオヅル豆ともいわれ、普通の大豆より粒が小さく小豆程度の粒で茎は四尺前後に成長して細く蔓の様になった。田植えが終ってから等間隔に数粒播くのが例で、肥料も捻り堆肥を用い、速成をはかり、成長の全盛期に苅り取って乾かし不時や使役時の飼料とした。
6 大根
大根の栽培法は品種によって多少の相違があるが、大きく分けると夏大根と秋大根に分けることが出来よう。その異なるところは時期で、他は大同小異である。すなわち、夏大根は三月下旬から四月上旬に蒔かれておそくとも八月には収穫され、秋大根は七月下旬から八月上旬に馬鈴薯を収穫した後に輪作として栽培されるのが普通で、十一月上旬に収穫され他の菜類と共に漬物に加工される。
畠はその条間を二尺乃至三尺とし株間を一尺二~三寸として種子を摘播するのであるが、その前に畦の上に棒で穴をあけ、その穴の中に肥料を一杯にそそぐ。大根は肥料を多く食うものといわれ、麦と同じようにやらなければならないものとされ、穴一つ宛に人糞尿をやるので、一反歩に五十貫、しかも濃厚なものをやるが、昔にやられた肥料は寒中から貯蔵してきた小糠を人糞尿に混じて肥料とする方法が行われているが、蚕糞をまぜる方法もある。蚕糞を混ずると虫がつかないという長所があるが、大根が堅いという短所がある。人糞尿は虫がつくが大根は柔らかいといわれている。またネリズギというものをよく使用している。すなわち、馬糞を蓄積しておき、それに木灰や糞尿を入れ混合して、手で掴める程度の堅さにし、それを大根穴に一杯詰めて肥料としたので多量のネリズギを必要としたのである。
肥料を注ぎ込む穴をズギアナといい、この穴つけの距離は一尺二・三寸位であるが、聖護院蕪のように横広のものはそれより遠くなる。ズギアナに肥料を注ぐと、その隣に手で穴を掘り、その土をズギ穴にかけるが、その際掘られた穴に種を蒔きズギアナの上に種をまくとやけるといわれて下種しない。下種の量は一反歩に二合程度である。
大根まけば百姓仕事は半仕事という。これはいままではちらし仕事であったが、まとめる方の仕事に移る。すなわち、作付け一方であったいままでの仕事が収穫に移るということである。
八月上旬の種子の摘播は、間もなく一株に七・八本の芽が生じるが、これを漸次間引きして一株一本とし、除草・中耕・補肥などをして育成し、十一月上旬に収穫する。秋掘りの一人当りの労働量は大根掘り一反歩といわれた。
7 油
畑作のうち食用油の原料としてジュウネ(荏胡麻)の作付が大事に行われていた。大根畠と共に乾燥する土地は不向きとされ、特に油畠として使用されることもある。大豆などの間作ともなった。五月初旬の立夏を目標に大豆が蒔かれるのであるが、この際一緒に播種する。すなわち、大豆の種子は粒で一カ所一カ所に蒔くが、同じ畦の前方か後方に種子を灰に混じて蒔く。種子の量は豆畠一反歩に一合の割合とする。中耕除草の後九月ごろその葉が黄色となり、荏胡麻の破裂するころを見はからって霜の前に苅りとるが、豆の方はおくれる。
豆類と同様荏胡麻も間引きをしない。それでも最初下草のようであった荏胡麻は豆をおいこして成長する。苅りとりは早朝未だ露の消えないうちに苅取ってこれを束とし、積み重ねて二・三日放置し、葉をとり去って乾燥し、まどりで打って採実する。それから油を搾るのであるが、霜にあたると油がないといわれている。
あぶら菜を菜種または菜種かぶといって秋早く蒔き、春先に食べることの出来るものは食べ、種子の菜種をしぼって油を作るのである。
秋早くとは秋分を目標に種をまいて春に間引きをし、五月ごろに花が咲くが、その前に中心を摘んで食用とする。中心を摘むのは枝を沢山出させ花実を多くするためである。
実が熟すと縦にわれる。採取方法は胡麻に準ずる。
8 蓋
アイの作付けについては、手製の麻布を衣料として仕上げるためには是非染めなければならなかった。従って自給用として若干の作付けを続けていた。畑に植えた藍を干して揉んでアイコガに入れ、灰汁を加えて発酵させ染料とした。
9 そば
昔岩手山麓の原野で十年近く耕作した蕎麦畠を放棄して荒地とし、再び草蕪地となった処を春に火を入れて地表の株や枯草を焼き払い、その跡を畑地に起した。それをアラギ起しといい、一年目は豆か小豆をまき、二年目から蕎麦をまき、腐蝕土で収穫の良いうち存続し、収量が不良になると放棄して荒地とする風があった。
蕎麦蒔きは七月下旬で、山地で焼畑に撒播して作る場合と、普通の畑に条播して作る場合とがある。前者には肥料として灰だけで特に施肥する必要はないが、後者には幅二尺位の畦を作り堆肥・人糞・尿などを施す。蕎麦は酸性土壌をきらうので灰を多く使う。種子は一反歩に付いて三・四升を下し、焼畑で六升位を基準として灰に種をまぜて下種し土をかるくかけた。
発芽後中耕除草共に行わなくともよいが、霜にあたると実が落ちやすい。
蕎麦は七十五日で鎌を持って行けといわれているように、播種後七十五日目には大丈夫苅取り出来る状態になっている。
苅りとりは三十五束を一人の労働基準量とするのは昔も今も変らない。その苅りとったものをその畠の中に八把宛たてて、それに笠一把をかけ、これを一束というが、こうしたものを五束を一列とする。これをソクダデという。こうして乾燥をする。乾燥後は臼ガラミをしマドリで少し打って脱穀が終る。
10 麦
麦の播種は十月初旬に行われるが、早ければ秋彼岸過ぎを目標とし、おそい場合には桃の葉が三葉ある中に蒔くといわれている。麦蒔には非常に肥料がかかるとされ、松田新五郎氏は遠野地方の大正時代における麦畑一反歩当りの肥料を参考までに記すと、堆肥一駄十貫として三百貫、人糞尿四十貫以上、コクソという蚕糞をまぜ、燐酸二~三貫、アンモニヤ一貫、灰はあり次第なるも一反に七・八貫当りとある。
麦蒔きの畦作りは、粟・稗畠のあと作であるから特に作らず、その隣りに馬肥などを施し被肥法というやり方をとる。すなわち、肥料の上に土を薄くかけ、その上に種を蒔く。特に湿気畠などはこの法による。
種子は一反歩について大麦は一斗を標準とするが、小麦は七升位とする。それでも小麦はあつくなる。
麦ふみを秋行わないところは春には是非とも必要であるとされ、雪消えを待って直ちに行う。
小麦のよい年は稲作もよいとか、春麦が出るころ風がなければ秋の作に風が当らないとかいって、麦作と稲作の関連を信じ、鴬がなくと麦のさく切りといって追肥をしてさく切りをし、八十八夜になると大豆の作入が行われるが、麦作がよいと豆が悪いといわれている。
四 農具一般
1 はじめに
稲作は紀元前二、三百年ごろ弥生式文化の時代に大陸から西日本に伝えられ、日本の農耕生活が始まった。この稲作が急速に全国に普及し、岩手県においても弥生式文化時代の後期には、沼のほとりや湿地を利用した稲作が行われていたようだ。このころは稲は穂だけ石包丁で苅り、臼でついて精米し、蒸して食べていた。しかし、まだ米は主食ではなく、木の実やけものが主食であった。
本格的な稲作が岩手に普及したのは、西暦四百年ごろの古墳文化時代で、このころは米がすでに主食になっていたことが、胆沢郡南都田の角塚古墳から発掘された「こしき」という氷を蒸す道具からうかがわれる。
平安時代にはいり、坂上田村麻呂が、東北の開発を行い胆沢城、志和城、徳丹城をつくり、先進農業技術者を集団移民させ開拓をすすめた。このころは乾田法といって、今のような田も出来ていた。こうして農民は村をつくり定住するようになり、農具も木製のくわから鉄製の鍬に代わり、稲を苅るための鎌も普及した。脱穀法では二本の棒にはさんで引きとる「からはし」という道具が使用され始めた。
一千年を過ぎたころの岩手は安倍氏の勢力のもとに栄え、農地も広がり、特産物として金、馬、漆、海産物などが豊富にできるようになった。これは次の時代の平泉の藤原氏になってくるともっとはっきり表れてくる。この特産物を京都まで運ぶため交通がより盛んになり、農業技術の交流も盛んに行われるようになった。
鎌倉時代にはいると、ますます開田、開畑がすすめられ、この工事のため、「つるはし」、「くまで」、「もみさらい」、「ふご」「もっこ」などが伝えられ、一般農民へ普及した。また潅漑用の「なげつるべ」もこのころ伝えられた。
このころ農民の間に信仰のため霊場めぐりが盛んになり、この霊場めぐりは先進地農業をみて農民は新しい農業知識を得ることに役立った。
天正十八年(1590年)に豊臣秀吉が検地を行い田畑を区分して石(こく)高制を定め、より強い年貢米を農民に強制をした。そして江戸時代にはいり、参勤交代が交通、運輸を一層便利にさせ、新しい製鉄の技術も進歩し、農具の改良がなされた。農業のための土木工事も盛んに行われ、鹿妻堰や松岡堰などが造られ、田や畑が広げられた。また、このころ紫根染め、あかね染め、たばこ、和紙漉(す)きなどの産業も中央から伝えられた。
江戸時代になってからは、ますます武士と農民の階級が区別され、農民の人権は全く無視され、税も五公五民で、一度凶作にあうと餓死者を多く出した。稲もまだまだ寒さに弱く、凶作のたびごとに農民が苦しめられた。
農具も年々改良されてきたが、江戸時代中期になってようやく「からはし」に代わって「千歯(せんば)ごき」というクシの歯にはさんでモミを取る新しい脱穀機ができ、「木のすりうす」、竹等て編んだ「とうみ」が出来た。江戸の末期になって米の大きさを選別する「万石とおし」が、また、「木のすりうす」に代わって「土ずりうす」ができ、農作業は幾分楽になったが、稲の耐寒性の品種は発見されなかった。
明治の中ごろになっても脱穀は「千歯ごき」によって行われたが、調整はバッタリや水車によってなされるようになった。また畜力を利用する馬耕具が民間に普及したのもこのころである。リンゴが明治五年(1872年)に岩手に初めて栽培され、明治三十四年(1901年)県立農事試験場が創設、同年国立盛岡高等農林学校が開校され、稲について色々研究がなされたが、明治末期で豊作の年は十一万二千五百t(七十五万石)であった。凶作になると二万八千五百t(十九万石)、大洪水や悪天候に作柄が大きく影響され、減収の危険にいつも農民が見舞われた。
大正期になると大きな変革の跡を見せている。すなわち、乾田耕作にしても、三本鍬、馬耕器、自動耕耘機に変革し、稲扱きにしても千歯扱から足踏み回転器、動力機と変転している。米の精白にしても手杵やバッタリ、水車利用から能力利用精米機に変った。
最近のように、トラクターやコンバイン、ヘリコプターの薬剤散布が行われるようになり、ライスセンターが出来たのは昭和も三十年すぎである。
各般にわたる用具の変遷を詳述することは出来ないが、かつて専用された用具のうち農作業の序列によってその一般的なもののみを抽出することにする。
農業用具の一つ一つは永い経験から生じたもので、そこには伝統に結びつく諸用具であり、民俗の一端を推察することが出来る。
水田を大別すればカタ田とヌカリ田になるが、泥の深い処をヒドロ田といっている。大小にかかわらず田の畦畔内を一枚といい、一枚の田をオサという。畑地は一区切りをヒトキレ(一切)といい、はたとよばずハタケといっている。岡穂(おがぼ)ばだげ・粟ばだげ・豆畠・稗畠・大根(でえご)畠・荒(あらす)し畠・はだげ稼(かしえ)ぎ等といっている。畑作の内、岡物などというのは水田作物に対しての対語として考えられよう。
農家にとって農業を経営することは、年間を通じて休むことがなく、休日でさえ多くは農業関係の祭祀のための休みである。大正年中の朝仕事に農具としての藁工品の製作があり、正月・二月・三月中の冬期には莚織り・叺づくり・俵あみをやり・雑多農具の手入もやった。木製や、縄類で自製のできるものはこの農閑期に修理し補給しておく。人々の使用するものゝ外、牛馬役畜の用具も修補または新しくつくられた。すなわち、繋つな(野外で馬をつなぐための網でマダ皮や麻糸を使用し、六尋程度、すなわち三十尺位の太めにつくる)、鼻づな(馬をひくとき、連行するとき馬のおもづらにつける長さ一尋半)、もと綱(馬の荷鞍に結び荷付用のもので一荷鞍に二本宛)、まるき綱(荷鞍に荷付けするため草をマルク綱で少し細めにつくる。長き一尋半)、おもづら縄(馬の頭につける面づら用のもので、コデ縄(な)・大紐・小紐の種頬がある)、うま沓(馬の蹄用のわらじで、稲わらでつくる)。この外、面(おも)がい・胸がい・尻がい(以上を三がいと呼ぶ)の整備、荷鞍の腹帯、馬鍬の引き綱、馬の堆肥づけもつこ用の並縄等馬を農耕に使役するために、このような縄や綱類が必要であった。正月の休日と雖も、農業経営のため自製をしている。しかし、どうしても自製できないものもある。それは鉄製の用具や、桶屋依頼の結(ゆ)い物、大工の手を要するものなどがそれである。
とにかく、私共の祖先が使用した農作業の器具や農家の生活用具を保存し、展示しているところは、砂込の岩手県立農業博物館と、本村の公民館をはじめ、各地にある。
2 穀物容器
あ 種もの俵
稲の種籾は早春のころセイロからとり出しタネダラに計量して入れる。この種俵は一斗五升入程度のものが多い。一人役の面積は七升程度という慣習からきたものであろう。一俵に二人役面積の水田に植え付けする早苗の種として余剰一升分は炒米用にも廻せるし、発芽不充分の場合の予備としてもよいとの考えであろう。種俵には三様式が見られた。両端にタラバシェ(俵帽子)をつけたもの、耳を外にしたケダシタラ(毛出俵)、耳を内側に編み込んだ耳折俵等である。後の二種は七升とか一斗とかの少量を入れるに適した。これらの俵は冬期中に製作され、種播きが終了すると、田植え過ぎころまで軒下などに吊って乾かし、その後翌年まで仕舞って保存し、破れるまで使用する。また同類の穀物を容れる俵には、二斗俵・三斗五升・四斗俵の各種があり、年間いつでも使用された。
い 叺
かますも穀物容れとして重要であった。かますは稲わらの莚を縫い合わせてつくる容れものである。通例四斗は十分入るようにつくられており、白米をこれに詰めて使用するので俵より貴重扱いしていた。
う キスネ箱
白米を入れておいて毎日飯を炊くごとに開閉する木箱にキスネ箱がある。臼搗きで精米することをキスネ搗きという詞に共通する古語である。キスネ箱は長方形の立体で、上部の一端が蓋となり、二斗入・五斗入・一駄入等大小いろいろある。
え シェロ
籾を貯蔵しておく大型の箱である。内側の幅二尺五寸・長さ六尺程度、高さ五尺から七尺位、厚い板で枡形につくり六段位積み重ね四斗俵十八俵入が多かった。最下部に板戸があり、籾の出口を付け開閉自在とし、最上部に蓋がしてある。これがシェロである。井楼からきた名称であろうか。このセイロには籾容れの外に豆セイロや俵入り、叺入りの雑穀類も多く貯蔵され、その中には備荒食品も貯蔵されていた。
お タメ(馬のタメ)
馬を飼養するのに秣(まぐさ)を切るためのオスギリがある。刃のある大型の包丁の両端に爪をつけ、木の台に刃を上に向けて据えつけ、刃の一端に取手をつけ、刃の上に秣をのせ、取手を下げて切る装置である。冬期は馬のジョミズという飲み水をヤダ釜や大鍋で温めるのでヤダ釜は殆ど各戸にあった。
切った秣はタメに入れて馬に与えたが、そのタメには耳があり、耳に穴があって、それにツルをつけて木のかぎに吊ったものである。馬を屋外で使用するときは、それを屋外に持ち出して使用をする。従来は丸木舟に飼料を入れて馬を飼養していたのである。これをウマブネと称した。
か ハンギリ
半切という容器は杉材を使い、たがに竹を用いて作られている。これは桶屋の製造で穀物容器に専用する。
半切という名称は桶を半分に切ったような形態をしているのでこの名が出たといわれているが、いわば盥の大きいもので、その中でも大きいものになると径五・六尺にも及ぶ。盥は手足を洗い、洗濯用に使われるのであるが、半切は決してそのようなものには使わず、種子漬け用及び味噌ふみに用いる程度で、使わないときは小屋に大切に保管する。
これに種籾を浸すと、浅いし移動も場合によってはできるので、水温を高めることが容易で、種井戸に漬けるよりは芽が出やすいといわれている。
3 開墾用具・耕作用具
あ 野裁(のだ)ちと唐鍬
ノダチは原野や荒蕪地を開墾するとき用いる大型の釶である。この大釶は巾二寸五分程度、長さ一尺五寸程もあって両刀で反(そ)りがあり、厚味にできている。それに四尺前後の柄を金輪入りで押えているので薙刀の形をしている。原野の地面を両手で振りかぶって叩きたつのに具合よくできており、これで草の根をたち切る野太刀でもあった。
また開墾用具に不可欠の唐鍬がある。唐鍬は大型機械が使用される終戦後まで土建業も常用していた。唐鍬は土掘りに重要視された用具であるが、類似用具にカッチャビがある。唐鍬には柄据穴があり、刀先きは広くなっていて土面を裁ち切ることができるが、カッチャビは柄据穴がなく金輪で据えられ、刀がなく三角形に先き尖りで、砂利を掻き廻すに都合のよい用器である。
い 鍬・三本鍬
耕作用具として鍬は極めて重要であり、基本農具の第一線に算えられるものである。
鍬は木製の柄と、柄にたいして鋭角をなし付着する木部とそれにはめこまれている鍬の刃の部分とがあり、柄を振って刃を土中に打込み土をおこす耕起用具である。鍬は田・畑両方に使用した。
修繕の必要なのは刃の部分で、鉄の質にもよるが平均隔年一回の刃渡りを修理することである。
農器具のなかった焼畑耕作時代に利用されたものは枝切れであった。それが特定の棒となり、自然木だけの鋤となり、鍬となったのであり、その後その先に鉄がつけられるようになったのは現在の鋤であり、鍬でいえばくろぬり鍬である。
次に柄と刃の接着する木造の部、鍬台とが分離するようになって、現今の畑作業の鍬となり、畦塗り鍬となった。土工用のトガは、鍬台をなくし鉄の部分に直接板をつけその先を四角にしたものである。
このトガの刃部を頑強にすると共に、その重量を減ずるために刃先を数本に分離し用途に応じて考案されたものに、二本鍬・三本鍬・備中鍬がある。
これらは鉄部に柄をさし込む方式をとっているが、さらに軽量にするため差し込む鉄の部をなくし柄を添えて鉄の輪でおさえる形式ができた。
これらがさらに小型となり片手でつかう熊手となり、畑の除草等に用いられる小型のものになったものであろう。
鍬はこのように用途が広く重要な農具となっているが、近年までこれらの鍬類の外に収穫用の鎌が数丁あれば農業が営み得たのである。
キッケェスが終ると潅漑用水が導かれるが、これに先立って堰上げといって用水路の清掃が行われる。このとき持寄る道具はシャクシとカッチャビである。
なお、耕耘農具一日の面積は、備中鍬八畝、唐鍬一畝、平鍬三~四畝、?鍬六~九畝、和犁(すき)田二~三・五反、洋犁二・五反、まんぐわ三反、方形ハロー十反だという。
草叢(むら)を切り落とすために柴刈鎌や唐鍬がある。
柴刈鎌は両刃の厚身のもので丈夫にできているため土をきりつけ芝くれの根を切るには適当なものである。
唐鍬には幅の広いものと狭いものとがある。広いものは重みもあり草の根を切ったり、狭いものは軽いから砂利を集めるのに使われる。
なお、堰の中からすくい上げるための道具には、イタミ(板箕)、エブ、モッコがある。
板箕は板で作られてある塵取のようなもので、土工用に多く使われる。ときには庭掃除用の塵取に使われることもある。
エブは竹であんだ塵取で堰上げのように水のあるところで多く使われる。
モッコは縄であんで作ったもので土・石を運び出すときに使用する。
う 田下駄
田下駄は湿田の作業専用に考案された大きな下駄である。大きさは区々でありその形状もまたまちまちである。田下駄をオオアシともいう。
このオオアシは、谷地田の足がめり込むところで農作業を行う場合に使用し、大きさは巾約七~八寸に長さ一尺二寸位である。主として杉板の小幅ものを使い、これを組立てて作ってあるが、足ののる部分には鼻緒をつける。この四隅から縄をつけて下から約一尺位の処で前方の二本の縄を一本にまとめ、後方も同様にした縄とで鍋弦状にし手に持てるようにするが、その長さは身長によって異なり、手を軽く下げて持てる程度をよしとされている。従って、人が変ればその都度長さを調節しなければならない。履き方はそうした縄の前方を僅かに短く持ってオオアシの前方を上げ、後方をするように歩くのである。そうすると、踏み込むと同時に田を平らにならすことになるので特にナラシ板をかける必要がなくなる。このオオアシの鼻緒は藁緒、または縄緒といって縄で作られてあるから田に入って足の皮膚が水でふやけると、この儘では足をすりむくので、使用する場合にはこの部分に昆布を巻いて予防していた。
え カナガギ
農耕肥料は従来殆ど堆肥を主とし、その堆肥は馬屋堆肥や馬糞であった。その堆肥を厩舎から引き出したり、運搬する際の必要具として用いられていたものにカナガギがある。熊手に似ていて三本の爪があり、先きが尖っているが、少し手前に曲っている。爪だけは三本あるが、作り方も用途も独特である。草や藁等湿気のあるものを掻きあつめるのに欠くことのできない用具であった。堆肥を掴んで田圃にまき散らすのにも使われた。こえを散らす用具としてはコエハリマツカというものを二又の木でつくり使っていた。
お 馬鍬(まが)その他
馬鍬は乾田に水を引いたあとその水田を掻き廻すため馬にひかせる農具である。横木に鉄の長さ四~五寸の角棒を三寸間隔程度に打ち込んで、人は両手で下に圧し馬にひかせる用具、それが馬鍬である。鉄の角棒をマガノコといった。
馬を操縦するため、馬の口とりが一人必要であるが、この口取は馬の歩行によって泥をかけられるので、それを除(よ)けるため、竿を馬の口下に結び、竿で馬を操縦する。この口取役をサヘドリ・サシェドリといい、この竿をサシェといった。従って田掻きにはマガオス一人、サシェドリ一人の二人が必要であった。この馬鍬は自作不可能で鍛冶屋から購入していた。田掻き馬には田掻き荷鞍・胸がい・御廻本(おましえぎ)などの付属用具がある。
か 畦畔塗(くろぬ)り杓子
堅田の場合は田掻きが終るとクロヌリをやる。畦畔に新しい泥を塗りつけ、畦畔を強固にする必要からである。その場合の専用具として使われるのが鍬の一種でシャグスというのがある。薄い鉄板の幅広い鍬で、木の柄に金輪で取りつけたものであった。この専用鍬で泥を杓(しゃく)り、畦畔の斜面に叩きつけるようにして塗りつけ、これを平均に撫でつける。これをヌリグロという。反対に塗らない畦畔、つまり草生え畦畔をケグロ(毛畦畔)という。
このクロヌリシャグスは、泥浚いに通しているので用水堰の堰浚いによく用いられた。味噌汁用のシャモジをシャクシというからそれに起因した農具であろう。
くろ塗りが終ると、次にはそのヌリグロに大豆を植える。それをクロ豆という。その際腰かごに大豆を入れて植える。それがハギゴである。毛グロの場合はクロと水田の境目の草を苅り払う。これをクロ苅りという。施肥が終り中代の中耕も終るといよいよ田植えに取りかゝる。組の場合は日取りを決め、前日から苗取りにかゝる。これを仮(か)苗取りといい酒肴を食べて予備苗をとる。
苗代から苗を抜き取る作業は多く壮年や老年の男の仕事である。先ず苗代に十分水を入れてから苗技き作業をはじめる。苗代への浸水はとった苗の泥を洗い落すためである。手に掴んだ苗は両手分を合して洗い濯ぎ、それを苗把(ないば)わらで結び束ねて一把とするのである。このナイバワラは正月中の朝仕事につくっておいたものである。
き 苗背負いモッコ
苗代からとった早苗は植え付けするため田圃に運ばれる。組ではこの苗を運ぶのは若者達である。運ぶ道具として苗ショイモッコがある。普通の背負いモッコは縄で密に編んでいるが、苗背負いモッコは目を大きく編んでいること、背中に触れるところは水漏れをさけるため板がとり付けられていること等で異っている。但し背負いモッコは底が尖っているので途中の休憩には不便であった。
く カズギモッコ
細竹・藤の蔓で輪をつくり円形の籠に早苗を積み天秤で担ぐ方法があった。早苗から落ちる水が身体にかゝらぬこと、途中で肩をかえたり休憩も可能であったが、坂道の多い斜面の歩行には困難であった。それは径約二尺から二尺五寸位のもので二箇を天秤で担いで運ぶ。その量は苗背負い樽の二倍で水分が入らないから量に比べて軽い。
苗代と本田との距離が遠い場合には馬の背をかり、根曲竹であんた籠に八〇把を入れたもの二箇を両側につけ、一駄で三〇〇把位を運んだのである。
け 代掻き用具
田植に先き立ってシロガギをやる。堅田の場合は代かき馬一頭と人二人が一組となって水田を掻き廻す。早乙女の多人数の時は二組以上となることもある。その用具は田のあら掻きの場合と全く変らない。
ぬかり田の場合は成人の男衆が鍬をもって田の泥を掻き廻すが、鍬は畠用のものである。この代かきは早苗の植え付きが速やかであるよう泥土の調整が目的であった。
こ エブリ摺り
田植用具の重要なものゝ一つに「エブリ」がある。幅六寸前後、厚さ一寸以下、長さ五~六尺位の細長い板の中央に斜丁字型に柄がついたものである。樹木の枝が幹から直角に出たものなど好んで利用された。桧・杉・朴の木などの軽い材質が選ばれた。田植組でこのエブリすり役になるのは重要な役目とされている。田の面の土を平らに均らすこと、田の水加減を巧みに調節すること、植え付けを指図すること等で中枢的な役目であった。
田植えの日早乙女が田に到着しない中に先ずこのエブリ摺りの者がエブリを押すのである。これは田の代を平らにならす目的の外に水量を調節して植えやすくするのが任務である。田は水が多いと植え難く、水が少ないと土が堅くて、これまた植えにくいものである。
田植えに使用される農具はエブリの外に、シロ縄があったが、型つけ・型おこしがあり、マネという線引もある。マネは約長さ一間半幅三寸位の杉板二枚の間に二尺三寸の割り竹を九本、八寸・一尺・一尺一寸・一尺二寸の間隔をとり得るように出来たのがそれである。
さ 草苅鎌と鎌類
田植えがすむと村方の青年男子は一斉に夏草苅りに山野に出かけた。馬をひいて野外に行き(実際は荷鞍の上に乗って行く)、草を苅り、それをつけて帰る。これが夏草苅りであり堆肥の原料となる。朝食前に近郊から苅って帰るのは朝草苅りであって、農休日には朝草を苅って休むのが普通である。
夏の草苅りは朝食後家を出て山野に行き草を苅って乾かし、夕方荷付けして帰ってくる。従って馬の放牧を兼ねることになり、放牧地の入口の木戸を開いて入り、帰りは閉じて帰ってくるのが慣例であった。草苅場に行くと、荷鞍諸道具を馬から下し、馬を自由にして夕方まで放置してやる。馬はグループ・グループに別れて草を食べる。
夏の草刈りには馬の荷鞍一式と草を束ねるマルギ綱、草苅鎌二枚乃至三枚を鞘入とし、袋入り砥石(といし)一挺、小型で二升入程度の樽(だる)、ワッパに詰めた昼食を袋入にして持参して行く。中心用具は鎌である。草苅鎌は大型で薄製であり、右から左に向って薙ぎ切るようにつくられ、片刃である。二尺五寸前後の柄を入れ、これを振って草を薙ぎかり、夕方まで乾燥をする。この夏草苅は二百十日ごろまで続くのである。
この間女子は田や畑地の草取りなどをし、畠では小型の草取り鎌を使用する。
鎌はいうまでもなく腰をかゞめて使う。柄の短い小さなのは手鎌という。農家には一戸平均五~六丁は持っていた。
鎌には、柴苅鎌・草苅鎌・作物苅鎌の三種で刃のつけ方からいうと両刃ものと片刃ものとがある。
柴苅鎌は身が厚く両刃である。これには小型と大型とがあり、小型は古く大型は新しい。しかし山の苅払いなどに使われるものはさらに大型で、柄も長くなり片刃である。
山草苅鎌は大型で両刃である。両刃ものは身が厚くできている。田の畦等の草を刈る鎌は大型で身が薄く片刃である。
作物苅鎌は幾分草苅鎌より小さ目である。片刀で薄く、粟・稗・稲などの稈(から)を苅る時に引っかけるように苅り、刃の方が凸凹になっている。これは最初からこうなっているのではなく、普通型の鎌で作業している中に仕事に教えられたものであろう。近年は鋸歯状の鎌が市販され、昭和四十年以降稲苅機械が使用されることとなる。
し 肥料容具
糞尿その他水分を含むズギを貯蔵するために大きなタメコガを作ってたくわえておく。この桶は高さが四尺~五尺、直径は上部四・五尺位、材質は桧・杉で桶屋に頼んでつくる。酒屋の酒造用の六尺桶の少し小型のものである。この貯め桶を五個も六個も備えてある農家は中堅農家といえよう。耕作面積が多い程肥料桶も多いことになる。このタメコガは後にコンクリート製に変化していく。
堅田の土を細かく砕いたところでその土面に糞尿を振りかける作業がつゞくのであるが、このことをズギバリという。タメゴガからシィヤグで汲みあげ、「人で天秤担ぎをする場合はカルグタンガに移し、二人天秤で担ぐ場合はオオタンガという馬の荷付けに用いる大型に移す。カルグは軽いに関連するしタンガは桶の意である。このタガには手桶のように木の柄がなく、二つの耳に各穴があけてある。
鏡タンガ=形はカルグタガに似ているが鏡蓋があり、栓が必ずついてある。このタガは細長く栓の大きいのが特徴である。容量は四斗入と二斗入があり、馬につける場合は両側に四斗入各一本宛、人で運ぶ場合は二人でタガの耳の縄に棒を通して一本宛運ぶ。二斗タルは背中に一本宛背負って運ぶ。
カルグタガ=二斗入が多く、子供らを相手に一箇宛棒を通して運んだり、二箇を天秤で運ぶ。
注桶=小便つぎともいう。これは木製のジョーロで、胴の部分は木製の桶で、底から一乃至二寸上がった処に竹の長い管がついている。最もこれは小便ばかりでなく、多く追肥の場合に使われる。
フルゲ=振り桶で径七寸位、高さ約五寸取手のついたものである。これは人糞を肥料樽のタガから移して畑に使うとか、灰その他の化学肥料を散布する場合に使われる。
このフルゲをゲス桶ともいう。糞尿や木灰(あぐ)、ネリズギ等を田や畠に施す際、片手に桶を提げ、片手で散らす、そのために軽い手桶を必要とした。これは水汲桶の半分位の容積しかなかったが、岡もの、播きものをするためには、是非なくてはならぬもので、一農家に数箇準備されてあった。
す 運搬具
堆肥付(こえつけ)モッコ=堆肥は主として厩堆肥であるが、冬季の蹟雪を利用して、田や畠に運び、そこに積んでおき、播種季に使用するのが例であるが、その後の堆肥や、春夏の堆肥は多く牛馬を利用して畠などに運んでいた。
馬に荷鞍を着せて運ぶ場合は堆肥を束ねて駄送することもあり、あるいは藁縄で編んだ二つの袋に入れて運ぶこともあった。この縄袋を馬モッコとも、堆肥ツケモッコともいったものである。
手提モッコ=堆肥その他の物を短距離の間を簡単に運ぶのがタナギモッコである。これは縄で編んだ一枚ものゝ両端に棒を通したもので、担架様式で二人一組で前向きに揃って前に運ぶか、向いあって横に運ぶ場合の用具である。
ハシィゴ=草とか、稲・麦・豆・稗・蕎麦などの乾燥したものを運ぶ用具として、木製の用具がある。二本の細長い木を中心とし、それに横木のサン(棧)をはめたものである。
4 稲扱・脱穀
弥生式文化時代の後期には、本県では、沼のほとりや湿地を利用して稲作が行われたらしい。このころは、稲を穂だけ石包丁で刈り、臼でついて精米し、蒸して食べていた。
坂上田村麻呂が東北を開発するころになると、乾田法が行われ、鎌で稲を刈りとると、脱穀法として、二本の棒にはさんで引きとるカラハシが使用された。このカラハシは、江戸時代の中期まで続いたのである。このカラハシは、太い火箸のような二本の鋼鉄棒である。一尺七、八寸の長さで真中が太く、元と先が少し細くなっている。この鉄棒の一方をマダ皮か麻で結び、一把を五つか六つに分け、その一つを二本の鉄棒の間に挟んでこく。また、別の方法には鉄棒を左手に握り、右手に一握りの稲を掴んで鉄棒の間に挟んで、手前に引いてしなごくのである。カラハシは唐箸であろう。千歯扱きが出来ても、明治のころまで老婆などが座って、この唐箸扱きをやったというが、なかなか手間どり非能率であった。
元禄年間にセンバゴギが発明された。千歯扱きというのは、一日に千把もこくことが出来るというところから名付けられたものであるという。
この千歯扱(せんばこ)きは細長い鉄板を沢山並べたもので、これを腰高の高さとし、立っていて、一人で扱くことが出来るようにしたもので、藁の束をとき、三回位に分けて扱いた。たとえ、手伝人があっても、一日に千把の稲を扱くことは至難であった。また、能率をあげるために、明治の末にはマンバ(万歯)というものが売り出された。これはセンバゴキ一人で扱くのを二人で扱くように歯の鉄板の部分を広くしたもので、二十枚に一枚の割合で万把売りが持ってきたという。
唐箸から千歯扱きに移りその扱く数がふえたといっても、脱穀が終るのは、年とりを越したといわれている。
さて、その後に使われたのは足踏式脱穀機で、明治末ごろからぼつぼつ使われ、大正の始めには大抵使われている。動力式が使われたのが太平洋戦争後のことである。
脱穀に使用された農具の分量は、カラ箸一日五~六升、カラオサ同一~一・五石、千歯扱五時間三~六斗、足踏式脱穀機一日十石という。
籾打ち槌 扱き落した籾は、土間の中央に集め厚く敷いて、その上を軽く木槌で打ち叩き、芒(のぎ)を折り落すのである。その時使用されるのは籾打ち槌である。一農家に各自一挺宛使用しても余分がある程であり、この木槌は粟落しや、稗落しや、その他にも使用し、用途は多いので脱穀用具として欠くことのできない農具である。
この籾打ち槌は太い木を短く玉切りにしたものへ横穴をあけ、横に長柄を入れたものである。両手で柄を握り、頭上高く振り上げて打ち叩くので割れ難い木が選ばれた。大工や土木用具の掛矢に似た槌である。この籾うち槌に似た小型のものは小豆の脱穀や掛矢用に使用されていた。
雑穀の脱穀 粟ばせから粟たばを土間に運びこみ、束のまゝ穂先を揃えるように積み重ね、上から木槌で叩き落す方法がとられた。用具は籾打ち槌であり、その後の作業には、マドリ・カスリ・トオス・箕・唐箕・ため・ムシィロ等のものが使われることは、他の脱穀と同じである。
麦は振り打ちで打って脱穀をする。振り打ちというのは長さ約六尺五寸位それに握られる程度の杉の棒の先に堅木の潅木の枝を自在に回転できるようにとりつけ、杉の方を持ち堅木の方を廻転しながら穂を打って脱穀する。
稗・蕎麦・大豆の脱穀には臼を横に倒してそれに打ちつけて実を落す方法がある。これを臼がらみという。これだけでは不十分なので、稗などは穂と穂とをつぎ合わせて、さらに振打ちをする。穂があまり多くないときはマドリ打ちといって自然木の枝でY字型のものを使うのである。このマドリは相対する枝先が心もちせばまっているもので、全長が一尺二寸位のものでイタヤ・ヤマガ・コンゴウ等の枝がえらばれる。
大豆や小豆の場合は乾燥したもの、根の土を柴刈鎌を反対に使って打ち落し、これを臼がらみし、その後マドリ打ちして脱穀をする。
臼がらみが大概終るとまどり打ちになる。まどり打ちはすべて補助的手段として利用される。畠のものゝ収穫祝いをマドリ割りといい、大豆小豆の収穫が終ると催される。昔は本当にマドリを割ったのかも知れない。この日は粟餅を搗いて小豆餅にし、親戚を招き近隣に配る習わしになっていた。
箕(み)=箕は両手で持って上下することにより風をおこして塵芥を飛ばす用具であるが、一時間に三~五斗位で、これまた重要な農具である。唐箕が普及してからも少量の穀類や、油種・菜種・大麻種等の実や、その他のものの塵芥を分離するためには、手早くできること、唐箕のような大道具を使わず済むこと、一人で簡単に操作できること等至極便利な用具であった。この箕の製造は普通人ではできなく専門の技術者に頼らねばならなかった。この箕はイタヤ等の割材の薄もの、藤の裏(うら)皮等をもって編んだもので、後方と左右に竹の枠を入れてピンと張り、前広がりに開けて浅くなっている。従って後方は最も深くなって籠型になっている。竹の枠には深山の地竹か柴木が利用されていた。
いわば編組工芸品中でも、高度の技術者が製作したものほど糠離れが良いとされていた。この箕で穀物を中央部に寄せ集め、腹部と腕で上下することによって塵芥をとり除くものである。
この箕は正月のミタマノメシ・八月十五日の十五夜の餅のとき、この箕を使用して供える。手杵で臼搗きした白米のコヌカバナシィ(米糠放し)等、その他製粉の補助具に使用した。
唐箕=農機具中、形の大きいものゝ一つである。全部木製で、無(む)ふしでよれのない材料、すなわちかまじの板張りである。旋風を起すため薄板の羽をとりつけた心棒、それを包む胴、穀類を受ける漏(じょう)斗(ご)枡、風の強弱により落下口が区別されて出てくる穀物、この唐箕の導入は、原始的な箕から一段と飛躍した。穀物調製の機械化であることを思わせる。この唐箕は唐の国、すなわち中国から伝えられたのでその名が付いたであろう。これは元禄時代に見えているが、この大工をトミ大工といい、建築には携らず専門職であったろう。
この唐箕にかけるのは殻及び土等の雑物を飛ばすことを目的とするから一応作物はこれにかゝるのであるが、これにかゝった後、籾・大豆を除いた殻をカッチャと命名している。一日に六~八石調製したという。
とおし=トオスィは芒を叩き折ってから、籾と塵や藁などを選り分けるために使用する重要な農具である。底部は籾一粒が自由に通けるように編まれた四角形の目であり、従って底部は正方形になっている。まわりは普通のカゴ編み式で丈夫に編み上げて枠となり、細竹を中軸に包んだ頑丈な縁に結びついている。すなわち、下方上円の浅い籠で、その底部は籾が抜けられるように工夫された篩をとおしというのである。底部の目の大小により、豆ドオス・籾ドオス・栗ドオス等といい、最少三箇は必要であった。大きさは両手で縁を握って、自由に左右に振り動かす程度の大きさ、つまり上部二尺なら底部一尺八寸の竹とおしということになろう。
千石とおし=とおしの底の目を竹でなく、太い糸や針金に替え、枠を薄板とし、天上から吊り下げて、使用する人は佇(ちょ)立の姿勢で篩う様式のものに改良されたものが普及された。それが竹籠式のものに比較すると飛躍的な能率を示す効果があって千石ドオスィとして普及されたらしい。太い丈夫な糸を漆やニカワで固め、それを縦横に編んでピンと張り、長方形の薄板の枠をつけて浅い箱とし、その底部に上記の網をとり付け、手前に引手をつけて停止したまま前後に動かすのである。これが千石ドオスィであり、後年それが網針金に替えられいよいよ普及した。但し天井から吊り下げて使用するので、一人は動かし一人は籾入れ運びに従うので、二人でやるとより効果的となる。この様式のとおしは、昭和期にも少しも衰えず、土建業のコンクリート用の砂とおしとして盛んに使用され、吊るかわりに丸太棒にのせて利用されている。
万石とおし=これは穀粒をふるい分けをする農具で、斜立したとおしの上部から脱皮した穀粒を流下させ、とおしの目から漏るか漏らないかによって玄米と籾とを選別するものである。従って傾斜度をどれ位にするかゞ重要である。
籾殻を脱した玄米は表皮が滑りよいので斜面を流れるうちに目をぬけて落下するが、籾は滑りが鈍く、且つ玄米より大型なので網目を貫けることがなく流れ去り、ここで網目を通り抜けた玄米と籾とが区分されるのである。箕で籾と玄米を選り分けたり、揺り板で区分していた原理を応用してそれを立体化し、玄米区分を機械化している一例であって、唐箕に次ぐ大型農機具である。上部に玄米受けの漏斗枡があり、斜めの台下とおし網を取りつけ、漏斗の口は自在に開閉や調節が出来る装置で、玄米と籾とが斜めの網の上を滑りながら下り、玄米だけは網目からぬけ落ちて二種に区分された。これが万石とおしである。
すりうす=すり臼は太い木を玉切りにしたもの二個を、上円とうの内部をくり抜いて空洞とし、下円とうは上円とうの台となって接触するよう中心に心棒をはめこみ、上円とうはそれに重なるが、下円とうは台となって動かず、上円とうだけがくるくる回転するようになっている。その接触点にギザギザの溝が彫みつけてある。上円とうは漏斗を兼ねて籾が盛られているが、籾は上円とうがくるくる廻るにつれて両円とうの間隙を通る間に籾の殻がすりとられ、その中の玄米と共に外部に転落する。米穀脱穀調製方法の一つで原始脱穀機の一形式である。これをキズルス(木摺臼)といった。後のドズルス(土摺臼)はこの木摺臼に改良をし、木製の上下円とうを籠式にして内部に木製の柾板を粘土に打ち込んで歯とし固めたものである。
揺(ゆ)り板=木摺臼によってすりむかれた籾は箕によって軽い殻を吹き飛ばしても、残った玄米と籾とは重量に大差がないから未だ混合している。それを分離するためにユリ板を用いた。このユリ板でゆさぶるか、あるいは箕でゆさぶると、スルスルした玄米が沈み、エガエガした籾が上層に浮かぶ。その上層の籾を取り去ると玄米が残る。この原理を応用して作られた容器は揺り板であった。万石とおしが考案される前の段階の籾・玄米分離の原始的な方法である。
5 その他
あ 穴あけ棒とツグス
大根は、大根畠という特定のところに設定した区域に仕付けをする。それは肥沃保持のためであるから菜もの畠の一部のこともある。また大根畠の畦の幅は普通の雑穀畠の二倍ある。大根が長大に成長するから普通の畦を二筋併せ合して盛土をするためで、高い耕土が厚くなることを知っての経験から生じた技術のあらわれであろう。
ここで忘れることの出来ないものに大根の穴あけ棒がある。大根蒔きの畦ができると、長さ二尺五寸から三尺位の径約二寸五分の杭に次の株間をしるせるように細板をつけ、下部をふと目に尖らし、上部を持ち易くしたツム型で穴をあける。最もこの穴に種を蒔くのではなく肥料を入れる穴である。
大根・牛蒡・人蔘・長芋を掘る物掘りツグスがある。末口一寸位下部径一寸五分位、長さ四尺位の細木で、下部に二股枝のあるものが利用された。
い 莚
穀物の乾燥・脱穀・糠放し、その他に是非必要で不可欠の用具として莚がある。莚は多く稲藁を原料として、農閑の冬季か春先などに織り出された。一農家に十五枚も二十枚も用意されていた。それを織る人をムスロハダスといった。
莚を作るには機(はた)で仕上がり六尺になるように縄の長さを定め、この縄を杼(ひ)(梅の木)に通して横幅三尺となるようにかける、これが縦糸になるのであって、横糸になる藁は幅一寸、厚さ三分、長さ三尺五寸位のヒトコロビという木の先に藁の先を折ってひっかけるように細工をしたもので、この杼の下の空間を右から左へ、その先に藁をつけて通し、右へ引き抜くときも他方の側から藁を通し、往復の後その上から杼でたたくように打ちつける。この運動を繰返してむしろを作るのであるが、最後に「耳をカク」といって、両側に出た藁の端をくくるのである。この莚は胡麻をはじめあぶら菜・荏胡麻など種子のこぼれ落ちるものの乾燥には欠くことの出来ないものであり、粟・稗など脱穀後の乾燥に不可欠のものである。この莚の紛失を防止するためにその家の印に布切れを織込んでいるのも一興がある。
莚の上級品にコムスロかある。玄米を盛ったり、米の精白の場合に用いたり、製粉類を盛ったり、餅を並べたり、大根カデを乾したりする貴重な莚で、川原ちがや等を原料として織られ、土間に直敷きしないように扱われていた。コムスロのコは米莚か粉莚の転じたものであろう。
う 橇
冬季の運搬用具として橇がある。人のひく橇には二つ山橇が多い。それを二つ組合せたのか一挺である。組合せるために腕木を二つ山に載せて縛りつける。その縛りつけをモヤシェルという。二つ山橇に腕木をつける場合、腕木に角(つの)をつけたのが角橇であり、積載した荷物が溢れたり、脱落しないように箱をのせた橇を箱橇といい、箱のないのは平橇である。平橇は平坦地で物資を運ぶのに適しており都市の商人もこれを利用していた。
角橇に細竹の籠を乗せたのはコエフギ橇(堆肥ひき橇)である。厩の堆肥は雪積の大寒あけのころ、田圃や畠に搬出され、塚のように積みおかれた。これをコエ塚、またはコエモリといい、春の播種季まで野晒しとしていた。また冬季の雪上を利用して、薪木は山林から村へ、村から町へと運ばれた。その他用途によって種類はあるが、要するに雪上運搬用具として貴重であった。
え 長木類と杭類
長木も杭も、稲・麦・粟などの乾燥用具であるが、その前提として殻類の一束(そく)という慣習があった。
稲は三つかみ一把、六把が一束。麦は二掴み一把で十把が一束。稗は二掴み一把、八把が一束。蕎麦は二掴み一把で、九把が一束。但し蓋用だけは三掴みである。大豆は成長の度合により不定である。
このうち稲は一束宛を田圃で暫定的に穂先を下にさか立てて乾かし、後はせで乾燥をする。はせの作り方であるが、杭を立てそれに長木を横に結いつけ、その長木に稲束を肢がせて吊り乾かす方法で、これをイナバシェといった。従って枕はハシェ杭といい、長木はハシェ長木といった。そのイナバシェの直立を補助して斜めに支える杭は突張杭である。その交叉を結びつけるため藁縄や藤蔓が用いられた。
稲を一束立てとして暫定的に田圃におくが、これは苅数制の遺例である。
稲は三掴みをもって一把をむすび、六把を一束とよんだ。これは中世・近世を通じての慣例である。古来から土地の面積を推し側るのに三十苅・五十苅・百苅等というのは、稲を三十束・五十束・百束苅り得る収穫の田で、それだけ生産し得る耕地という意味のことである。
本村では田打ちの三人分役を反苅といっていた。一人役は三十三束二把に該当した。
はせの長木には杉・桧等が利用され、杭類には栗の木が良材として使用された。これら多量の長木類・杭類の保存を重視し、雨雪のかからぬよう保存小舎を特設したり、家屋の軒下に積んで保存したりした。
稲ばせは二段に作られている。
粟を苅り終ると、粟畠から家の近くに運び、粟架(ばせ)にかけて乾かす。粟の穂はたれ曲っているので、粟架が斜立につくられ、長木を七段にすると七重がけ、九段にすると九重がけとなった。
なお、麦ばせは稲ばせと同一方法だが稲よりは段数が多く粟ばせと殆ど同段である。
蕎麦は脱穀まで一束立として乾燥しておくのが一般である。
大豆も特に乾燥用具を使用することはない。
稗も一束立として脱穀の季節まで現地で乾燥するが、五十把なり、六十把なりをまとめて現地乾燥することがある。
お 臼
木の臼 木の臼にはクビリウスとドオウスの二つが一般的である。クビリ臼は臼の外側を内側に向って少しへこましてあるもの、胴臼はクビリがなく大型が多い。
木の臼は米の精臼、麦・稗・粟の精白、あるいはそれらの製粉、さらに餅搗きなどのため貴重な家庭用品であって、農家以外の士族町民の家庭にも備えられていた。従って、木臼は食事に直接関係するので、平素でも大事にしていた。くびり臼の場合は普通手杵を片手で使用しているが、大型の胴臼は両手用のドウスキギを使用している。たとえば、麦の精白・魚粕砕き・豆粕砕き・餅つき・製粉、その他力を入れて振り上げて搗きものをする場合はこの大型臼に柄入り杵が適していた。
石の臼は大半土に埋めるように据えられているのが普通である。花崗岩で作ったものが多い。唐(から)臼に使用されたり、足を水に応用してバッタリに利用したり、さらに水車を利用した精米所の臼になったりして、石臼の利用は近代化に随伴していた。石臼は木臼に比して耐久力のあることが精白の近代化を増長したものであろう。足によって精白された唐臼利用が一段と進歩したのであったが、水車利用は更に近代化を明示していることになろう。
曳臼、石で作った製粉用具にフグス、すなわちひきうすがある。上円とうと下円とうが磨り合って中間の穀物を粉末とする装置で、作用は木摺臼同様であるが、上円とうを廻転させることによって、間隙に挟まれた物が噛み砕かれ、外部に落下する。米粉・炒粉・黄粉・蕎麦粉等ほこの曳臼でも作られた。一日に一~二石位作られたという。作った粉は粉ばちに入れられた。
豆腐製造の曳臼はこれより大型であるが人力により立って曳いた。
か 油しめ
菜種・胡麻等の油をしぼることを油しめといっている。
搾油の方法には昔油しめと胴しめの方法が採られた。これは搾油のための器具の相違で、強い圧力を加えて油脂をしぼり出すということには変りはない。即ち、
前者は原始的搾油器で、自然木の二又のものを一つは二尺五寸から三尺、他は五尺乃至六尺の二本を木取りし、長木の元に近い方にほぞ穴を掘り、短い方の元の臍をさし込み、長木の二又にわたるように横木を打ちつけ、その下に油を受ける盥がおける高さにする。さらに丸太を短い方の二又にわかれているところにはさみ、長木の横木の上を通して他の一端に縄で結えた石をぶらさげて重りとする。そして搾るべきものを麻袋に入れて横木と棒の間に挟む。こうして油を搾るのが搾油器である。
後者は楔を打って搾油をする方法で、台木は長さ五尺の幅一尺位、厚さは八寸で、その中央に搾油すべきものを麻袋に入れてしめることの出来るように深さ六寸、径八寸位の穴を掘り、その底の中央に小さな穴をあけて盥用の油受けにしたたり落ちるようにする。この高さを決めるには、この台木の四隅に近いところにほぞ穴を作り長さ四尺の三寸角もの四本を打ち込み、台下約一尺五寸位にする。その四本の中左右各二本宛、上端より五寸位のところにほぞ穴を作り横木をはめ込む。この横木の下、台木との間に上部三寸に縦五寸位長さ五尺の厚板をわたし、この上部と横木との間に楔を打ち込んで搾油をするのである。搾油するには、荒搗きといって杵で搗いてこれをくだき、蒸して麻糸を織って作った一尺五寸幅のものをおうように包み、麻糸をかけてこぼれないようにしぼるのである。
昔は大抵共同して行われたが、その後廃れてあまり行われず各戸ごとに搾られていた。加工所か出来てからはそこへ依頼するようになる。
き 度量慣習
従来量を計算するのに、一杯とか二杯、岡ものの作物の収量に一掴みとか一把とか一束、長さにも幾束、いくふせ、または尋(ひろ)計りがあった。一杯とは大椀一杯のことで二合五勺程度であろう。大椀とは一般家庭の三ツ組椀中の径三寸五分位の大椀をさしており、それをテッパズ椀ともいった。一杯爛鍋・一杯枡の容器があり、年中行事にもイッペェオロス=一杯おろし(家族五人であれば白米粉五杯で小豆団子を作って食べる)等の食習があり、仏式の葬儀にも一杯飯(いっぺえみす)は重要に扱われている。四杯が凡そ一升程度であった。
次に尋(ひろ)というのがある。これはひろげるより出たのである。従って拡げた両手の端から端までを一尋という。この単位は十進法とか十二進法とかいうものではなく、人体の腕と同じということである。になのごときは三尋カダギで三尋半あった。これは縄が短い場合の単位である。
長い場合は一尋二尋とはかる外、縄を左手に持ち、右手の親指と人差指との間と右肘をまわして一まわりする。これも一つの長さをはかる単位である。
藁縄など、普通の屋根葺用の細縄は三十尋をもって一把とし、それを単位としたり、また縄まき器具に二十二まわしをして一把としたり、自家用は四十まわしを一把とする。これをタゴといった。すなわちフトダゴ(フトダンゴ)である。
く 計量器
容量を測る器を枡とするならば、大きいものにキッツがある。これは測る器という概念の相違によって含める場合と含めない場合があろうが、俗にいわれる一斗笊・溜桶などの民俗的なものを含めることにする。
キッツにはもち米とか種もみを入れ、深さ二尺、巾三尺、長さ六尺で一〇駄人であろう。取手のあるものをテバギッツといい、ないものをキッツという。
ア 溜桶
これは丸形の桶であって、二斗人と一斗五升入の二種がある。普通は二斗入れで、桶の上の方に手かけがついている。これは肩に持ちあげて運ぶためである。
イ カスリます(掠枡)
溜桶は桶屋に作ってもらうが、掠枡は大工に依頼する。溜枡と同様、所望する大きさによって寸法が異なるが、一斗五升入と一斗入との二種である。普通は一斗入れでどちらも箱型になっている。口の上部には手かけがあり、下部は塵取りのようになっている。カスリ枡という名称がこの辺から出たのであろう。
溜桶は比較的遠くへ運ぶために用いるが、掠枡はその溜桶にはかり入れるのに用いたり、唐箕の漏斗状のところに持ち上げて入れるために用いる。従って、溜桶と掠枡は脱穀調製のための用具といった方がよいであろう。
ウ 笊
ざるには一斗用と五升用とがある。五升用は少し小さくて農作業に適さないので、一般に笊といえば一斗笊を指す。五升用のものは種蒔きなどに使う外台所用品であった。
一斗笊はその名の通り一斗入で数量が明瞭であるばかりでなく、持ち運びが便利なため農作業に広く利用された。キッツにはかり入れるのはこの笊であった。
精米されたもの及び粉をはかるとき、一時保存するために使われるものはこの一斗笊に渋紙を貼ったものが利用される。これを作るには、和紙を貼り、その上に豆柿の渋を塗って乾して使用していた。
エ 枡
枡には一杯枡・五合枡・一升枡・五升枡・一斗枡を普通とする。中には一合枡・七升五合枡等がある。
一杯枡は二合五勺で、容量は方三寸五厘、深さ一寸七分五厘ある。麦・粟・稗などの混食の場合に用いる。
五升枡は手のついた箱枡である。これには上場(うわば)に金のついてあるものと、ついていないものがある。農作業からいえばどちらでもよいわけであるが、売買する場合は鉄板のついた金枡と木枡では異なる。つまり枡の売買は石高制である。従って農作業に使用した木枡は磨損して五升入らないからである。
なお、正確に量るためにトガギをかけるといって丸棒を掠るように量ったものの上をすべらせると、余剰のものは枡の外に落ちる。こうして正確を期したのであるが、丸いものであると、円型であるから余剰のものが落ちるには落ちてもおしつめる働きをするので、米屋板を使い、上部を向うに倒して手前に引くやり方に変っている。トガギには堅木がよいとされて、サクラ・カヅラ・朴などが使われたが桐も好んで使われた。
この石高制は明治になってからも続けられてきたのであるが、目方であれば、よいものは目方がかかるし、反対に悪いものは軽いから、この目方の方が間違いないとして貫高制(メートル法に変ったが)が採られ、現在に至っている。
一斗枡は方一尺五分、深さ五寸八分八厘といわれているが、普通使われたのは、鉄の輪をめぐらし手つきである。
オ タメ・カスリ
穀類の脱穀や、精白調製の際使用する計量用具に、箱形容具があり、桶形用具にはタメと称するものがある。その容量は一斗ダメ・一斗五升ダメ・二斗ダメが通例であった。軽く薄い材質でつくり、竹の輪をはめ、片手で掴む耳(取手)が突出している桶である。このタメ桶で籾なり、蕎麦なりを計りながら出したり入れたり、運んだりの補助にも使えば、暫定的に穀物を入れて容器としておくこともある。
箱型のものではカスリというものがあり、これも五升カスリ・一斗カスリ・一斗五升カスリがある。立て箱式で、上部が口で底より広く、横ざまに穀類をしゃくり、両手で抱えたり、肩にかついだりするのに都合よく、一方の面が少し長い。短距離間の穀類運搬具にも使用された。
け その他
この外穀物を杓る直径七寸か八寸の木彫りで、椀に似ているが糸尻がなく、木杓子の柄のないものである。これは厚くつくられていて、容器から穀類を少しばかり取り出したり、日の中から穀類を杓りとるときに大変都合のよい用具である。これを「かよわんこ」という。
箕の補助具にカバミがある。手振り箕の小型のもので、木の皮一枚ものを折り曲げて作ったもので、少量の穀物を杓ったり、さらったりするのに便利な補助具である。樺・柳・さわくるみ・しなの木等の生皮を折り曲げてつくり縁をつける。生皮でないと折り曲げは出来ない。どの木の皮で作ってもカバミといった。本来は樺細工からきたものであろう。
6 農機具の発達年表
第十四節 住居
一 藩政時代の民家建築規制
東北地方全般にわたって、民家研究をされた小倉強氏は次のごとく指摘をしている。
「東北の民家建築を見ると根本的には全国共通のものが多く、ただ他の地方では既に失われた形式が東北に残存して、それが東北の特色であるかのように観察される。従って東北で発生した独自の形式であると断定することは危険の場合が多い。それがためには全国を広く見て東北のものと比較しなければならない。
建築様式の成立は風土性と人文性の相関からくるといわれるが、この二つの要素のとり入れ方が区々になっている。(中略)辺陲(すう)の地には今でも、土間に籾殻と莚を敷いた土間生活が行われ、外壁に開口部が極めて少ない古民家がある。それは防寒上有効ではあるが、むしろ藩政時代の民家建築制度の影響であると解釈したい。時代が進むに従って開放的な建方が普及して何等防寒的な措置を講じていない。これに比べて人文性の方はかなり強く表われている。例えば風土性が全く同一な地域でありながら、村境を左右に全く異った民家様式が存する事はどう解釈していいだろうか。例をあげると、南部の曲家とよんで母家の一方に直角に厩が突出してL字型をなす農家が旧南部藩内に分布している。ところが旧南部藩と境を接する旧仙台藩には曲家はない。(中略)このように劃然とした区別は藩毎に行政、経済などに差別があったからに起因していてそれが今日まで伝統を残している。」
次に掲げる民家建築規制は、ひとり南部・仙台藩領に限ったものではなく、封建社会においては全国的なものであった。
一、南部藩新家分家取締規定 和賀郡土沢 小原文書
前略
覚
別紙の通り古来より新家御停止にて、正徳五年(1715年)御沙汰があったにも拘らず、近年にいたり勝手次第に家作をなしその上御法度の既耕地迄家を相立て申す者これあるやに相聞え、甚不埒の至りである。早速取毀しを仰つけては迷惑の事故、追々取り毀し、村方のうち明屋或は野際御山裾通空地に場所を見立て引越しし、願次第吟味の上屋敷地を下さる。本屋の内名子寵(めぐみ)等にいたす事は構わないのであるが、別家については、野際並に御山裾その外空地の場所を見たてて願い出て許可をうくべし。すべて古来の御法度に相背いた場合はきびしく御沙汰に相及ぶ、以上。
二、延宝四年(1676年)三月十五日
衣類については、幼少の者でも白むく、浅黄むくの類停止の事、屋作は分限に応じてなす事。
三、元禄八年(1695年)十二月朔日
先達の達しの通り、衣類等あり来りのものを着用すべし。新規に仕立る時は絹紬でなく、軽き身分は木綿等を使用する事、又住居の粧もありきたりの通りで、これ又新規の美麗一切無用の事。
四、寛保二年(1742年)正月
御領分中に桑を沢山植えおく様仰せがあり、銘々の田屋地等囲垣畑境等にも植え、蚕飼に精を出す事。
五、天明二年(1782年)
百姓屋敷・地付屋敷・御定めの間数で相改める。廻垣等があっても、屋敷地面の外広い場合は相改め高に結ぶ。名子・子弟・別家屋敷の申しいででも、人住み申さず、明屋敷であれば吟味の上御竿入高に結ぶ。新屋敷等願いでても訳筋がなければ、決して許さず、すべて古来よりの地付、屋敷地共に一々改め、水帳の末屋敷帳へ記す事にする。親子・兄弟・知音(いん)・近付といえども、依帖贔屓なく、有体に相改める事。
天明二年三月御勘定所から検地する者へ銘々渡している。
六、寛政十一年(1799年)十二月二十五日
近年百姓ども住居等おごりをなし、障子、襖、箪笥、長持など用いる者多く相聞こえ、身分を弁えぬ処より自然と密木盗木等ためおく故、御山も剪荒し、諸用の差支えになるから、前々の住居に立戻り、以前同様の家作に致す様追々心がけ、百姓に似合ぬ家作を取り崩し、畳等を用いざる様心得る事。
七、文政三年(1820年)十二月二十二日
覚
御百姓共衣服について、別紙御沙汰の通り、きっと守るようにし、凡て近年在の者甚だ奢りの風俗に相成り、百姓の業を怠り、商人体に紛れる者もままある。大方の者は遊芸等いたし、その上雪踏塗下駄傘或は日傘等をも用い、飲食家作も身分不相応の者がある様に聞え、甚だ不埒である。家蔵小屋等の普請は耕作終る後でも、身分不相応の事は、決して致さず、凡て奪侈風儀に落入りたる者は、自然と農業を怠り勝ちになり、次第に窮民となが、諸上納等難渋になる。依って右の様な者に対しては御代官は専ら心を用いて厳しくし、此度の御沙汰の通り怠りなく相守るようになす事。万一身分不相応な心得違いの者がある場合は、その者は勿論肝入・老名・組頭共に思わざる御沙汰に及ぶからよくよく申し含みおく事。
二 屋敷
往古は沢水を飲料水及び雑用水となし、その下流を潅漑に利用し得る場所を選定して屋敷を決定した。その多くは屋敷を区切る外囲らしいものがないが、中には小堰、または低い土堤、あるいは一位の生垣をもって境をなしている家もある。
公道より屋敷までの通路は木柵で囲うが、雑木か一位の生垣を肩きりに刈込んでいるところもある。また、母屋を南東面させるため公道が裏にあっても南東より入る様につくり、この通路をいずれも「ジョグズ」と称している。
母屋の北東から隣家に通じる道を「トナリミズ」と称し、出口を北戸という。
西方には常緑樹の杉か桧・けやき・なら等を植えて冬季の寒風降雪を防ぎ、隣家が近い場合は防火のため常緑樹や栗・梅・桃等の樹木が植えられている。この屋敷林の枯葉や落枝は燃料や肥料に利用するし、屋敷の品位、家の権威の象徴にもなるので大切にされている。先祖が植えたという祖先を敬愛する念もあって、古い屋敷であればある程、誇りにもし、保存もする。屋敷の林を伐ることは零落を意味すると考えている。意味不明なるも枝垂柳は植えてはならないと忌み嫌うことである。
母屋の南側を「ツボメェ」と称し、花壇若しくは庭園として飾っている。
母屋の正面に当る南東側はおにわで「オニャ」と称し、広場をとり、馬草の乾燥・雑穀の整理等に利用をしている。この「オニャ」を最大限に利用出来るのは曲りの部分があるからである。さらに「オニャ」の東方に菜物畠としてきゅうり・ささげ・ねぎ等日常野菜の栽培に利用をしている。
屋敷神は西南方に多くあるし、墓地は不定なるも西方に多く残されている。
三 一般農家の建築様式
東北地方では旧南部藩領内に限って曲家が分布し、岩手・紫波・上閉伊の諸郡に最も多く、下閉伊・九戸がこれに次ぎ、稗貫・和賀・二戸になるとやや分布率が低いのが昭和十年ごろの実情であったという。
母屋からみて厩は前面に突出し、その仕方には左と右とがある。しかしながら、母屋に向って、母屋の背面に突出することは全くない。母屋と共に厩は日当りがよいように位置している。これは馬を出し入れする便宜上ばかりでなく、厩を持つことの誇りと、馬飼育に対する熱意と、馬そのものに対する愛着といったものの総和として表出されたのである。馬に対する愛情は、まことに麗しいものであった。このことは厩の構造にもみることが出来る。
さて旧南部藩では曲家を奨励したという史料は今のところ不明であるから、奨励したのかしないのか、奨励したとすれば、何か基準があったのか、その辺のことは今後の研究にまたなければならない。
今のところ宝暦九年(1795年)と天保年間(1830-44年)の記録があるから、十八世紀の終りから十九世紀の初めごろに出来たものであろう。
本村においては農業を本業とする家庭は主に曲家で、この曲家は全戸数の約八割をしめ、兼業農家は直家で、全戸数の約一割五分、切妻様式の家は、商業若しくは他の職業に従事し、農業は家業の一部に過ぎない家である。これは終戦前のことである。この切妻様式は、明治時代以前にはなく、大正時代以後に多く作られるようになる。
萱葺屋根は、全戸数の八割以上で、柾葺は小屋に多少あった。柾葺屋根の記録は慶安四年(1651年)と県史にある。終戦直前一時瓦を使用せるも、積雪の多い本村に於ては、氷割れから、毎年手入を必要としたので、終戦後使用する家がなくなった。南部藩で初めて瓦葺がゆるされたのは寛保元年(1741年)七月十九日であるが、農家にとって無縁であった。
萱葺屋根の修理を「サス萱」といい、全部葺きがえすることを「ヤドゴ」といった。「ヤドゴ」は二十年から三十年に一度といわれている。しかし屋根坪が広いので非常に多くの萱を必要とする。大体建坪一坪に百束以上かかるであろう。これを自分だけで負担することが困難なので相互扶助の「結い」制度が出来る。本村では五尺の縄で束ねた大束の萱を四-五十把を屋根ゆい講中の人々によって提供され、それに「ゴボナ」といって普通の縄より太い直径二・五cm位の縄を出し合う仕組になっていた。終戦後萱野に開拓者の入植と開田によって萱野がなくなり、昭和三十年ごろから思い思いの設計による新建築に伴って殆どカラートタンの屋根に変ったのである。
四 建物の配置
農家では、住いの中心となる母屋のほかに、農業経営上から多くの建物が必要である。まず、住いの中心である母屋に、日常生活上必須の便所や浴室が付属して別棟に設けられる。農機具やとり入れた収穫物を格納する倉、脱穀調整やわら仕事をする作業場、肥料や堆肥の小屋、家畜を飼う家畜小屋、これらの付属家が屋敷の中に適当に配置されて農家の構えをなしている。そのほかに墓地や屋敷神をもつ例もある。もちろん経営方式によって種頬の数や大きさが一様でない。
古い時代からの基本型では、作業場と納屋は母屋の中にある土間が兼用されていたであろう。
便所と浴室は「ヤネグルミ」になって同棟というのが県下の通則である。南部藩では分家するとき、本家から分与する建物は、母屋・馬屋・便所の三棟で、これを「一カマド」といったことから推察できるように、浴室は古くは特別の棟をなさず、母屋の土間の一隅に風呂桶を据えただけであった。近年は別棟の浴室が増えたが、それでも便所と同棟が多く、風呂の落し水を肥料に使えるようになっている。
土蔵及び小屋は、交通不便で物資の交易も不自由な時代には、周期的に襲来する凶作に備え、自給自足体制をとらざるをえなかったから、重要な備荒貯蓄の役割をもっていた。
南部藩では、曽て普通の平(ひら)百姓は、土蔵を持っているのが常例であり、土蔵を持つものは村では富裕階級に属し、肝入・検断・山肝入というような村役程度以上のものが多かった。富農などはたちまち藩庫に全穀などの寄付を強要され、一代の氏称が全認されたりして、在地の下級給人に編入された。金上げ侍の端くれに登録された人々なら土蔵をもっていた。すなわち士族階級以上には土蔵建築は常例であっても、平百姓には稀有であって富農に属したということである。
また建物配置の決定についての習俗には、家屋配置の場合、家相を占うことや、方位を決めるのに、物識りの和尚様や山伏に占って頂いたり、経験の豊かな大工の棟梁にまかせたり、あるいは「イタコ」に頼んだりすることすらあった。但し建物の新築は村方においては明治以降になる。
宅地と公道との関係が如何にあるとも、家屋の正面は鬼門(北東)と病門(南西)に面せざる様に気をつかい、厩屋も鬼門は絶対に出ない様に設計している。便所は東及び鬼門に建てはならないとし、「打物小屋(こなしごや)」は東より少し南よりを最も吉とし、また土蔵及びこれに類する建物は北を吉としている。
五 間取
農家の組形は、内庭と炉のある室から成立っていた。それから次第に寝室が別に設けられるようになり、昼と夜の生活する室に区別が生じた。炊事は、本来内庭の一部で行われたが、その一部を区別して台所とするものもできた。接客は、はじめ炉辺で行われたが、後に客を通す座敷がうまれた。
しかし、家の建築は村人の相互扶助によったために、好き勝手な間取ができなかったこと。旧藩時代には農民生活に対する建築上の規制があったこと。村には村の昔からのしきたりがあり、それが尊重される風があったこと。そんなようなことから農家の建築を分類すると七つの型になる。
民家間取りのいくつかの形式を、歴史発展段階的に理解しようとした今和次郎氏は次のごとく記述している。
東北地方の農村住宅の間取り特徴は、どんな点にあるかというと、中心となる常住の室は相当広い広間になっていて、ここに囲炉裡が切られ、広間の後方に六尺四方か六尺に九尺角の押入のような寝間が一つか二つついていることです。そしてこの広間が中心となっていて、一方に土間が、他方に座敷がついているのです。勿論これは標準的な例ですから、地方によって多少の変化があるのですが、そしてかかる造りの家の中心をなしている広間の機能は、どうして出来たのかといえば、私としてはそれを平安時代の文化、都の住居構えの流れだと考えたいのです。
大抵旧来の農家には大黒柱という太い柱があって、それが土間と床張りの室との境に立っていますが、大黒柱というのは大昔の土間住居の中心柱に当る柱だと考えられます。そしてその柱を中心として、現在の土間と広間とを含めて全部土間とした広い土間構えが大昔の状態だったと考えられるのです。そこへ都の住居の造りが入って、広い土間の半分を床張りにするようになったと解釈したいのです。当時の炉は、板の間の方に残って、そこが常住の座となった。それからもとはなかった寝所が公家の住居で既に学んだ通りに広間の北側に柱間毎に引戸でふさいで設けられた。即ち、中心柱である大黒柱と囲炉裡と、そして半分残った土間丈は大昔からの名残りで、板の間の広間が徹底しないながらも、寝殿造りをかたどったその片影だと解釈したいのです。そして広間の他方についた座敷構えは、鎌倉以後更に中央の感化をうけて、附け加わったと見るのが至当です。現に極く不便な土地の古い家には、座敷構えのついていない広間作りが見られるのです。
川本忠平氏は、母屋の畳間・板間・土間の面積とその機能について紫波郡志和村の民家八百八十八戸について調査している。本村も大同小異と思われたので次にかかげることとする。
八百八十八戸の調査数の約四割の三百五十三戸が曲家であった。母屋の内部は畳間、板間、土間の三つに区画されているが、八百八十八戸の農家につきこれら三つの区画別坪数をみると、畳間五坪以下の農家が全戸数の四割六分にあたり、五坪以上十坪以下の農家が四割三分となり両者合せて約九割を占める。従って八百八十八戸の農家の中、十坪以下の畳間所有農家が九割を占め、ことに五坪以下のそれが四割六分であるということは、当地域の農家は極めて小面積の畳間が一般的であるといえる。
板間については、二十坪から二十五坪のものが二割四分の最高率を占め、二十五坪以上三十五坪以下のそれを加えれば全農家の六割以上が、二十坪以上の板間面積をもつことになる。ことに五十坪以上の板間を有する農家があることは畳間の狭少なのに比して当地方の農家が、板間面積の広い間取を特長としていることを示している。
土間面積においては五坪から十坪を占める農家が二割六分、十坪から二十坪までのそれが約四割、二十坪以上のそれを加えると全戸数の七割九分に該当する。
そこで一戸平均各坪数を算出すると畳間八・五坪、板間二十七坪、土間十四坪となり、板間が最も広く、畳間面積の約三倍、土間の一・七倍に当っている。これに厩舎の約十五坪、小屋の十五坪、土蔵の二十五坪が入れば総建坪約百坪前後が普通農家と推定される。
以上により農家の母屋の内部利用は一般的に母屋総坪数に対して畳間が一割七分、板間が五割四分、土間が二割九分の割合を占め、板間を土間の広い居住様式を示している。
六 間取と生活
1 神座
旧南部領の曲り家における神棚を調査された田中喜多美氏は、厩や座敷の部分は「イロリ」とか神棚のある所を中核として後に付加されたものであることを論証している。曲り家は「イロリ」と神座を中核として成立しているというのであるが、これは民家全般についてもいえることであろう。同氏の神座論を次に掲げる。
台所と常居は、もともと一つの部屋であった。そこには神棚も「イロリ」も戸主の間もある。この一つの部屋が二つにわかれて台所と常居になる。そうなると「イロリ」も二ヵ所に設けられることになる。「イロリ」が二つになるにつれて、家によっては食事も二ヵ所になる。格式を重んずる家では、戸主だけが神棚のある常居で食事をとり、家族は台所で食事をとる慣行があった。
常居と台所のある家では、神棚は常居にある。神棚が常にある家では、必ず戸主の居間はその近くに占められている。
戸主が一家の主宰者としてその地位におり、家族とは別に常居で食事をとるような家では、戸主の兄弟でも戸主と同じ場所で食事は出来ないのである。身分関係からいって、戸主の座はそれほどまでに高いと考えられたからであった。
神棚は常居のない家においては、必ず台所にある。座敷には決してない。これが古俗である。この場合、神棚は煤臭い台所にある。常唐と台所を比較検討してみると、もともと常居と台所とは同一部屋であったことが明白となる。
常居
イロリを有す、鍵を吊る。
イロリに信仰が伴うし座席名もある。
神棚がある。
板敷が本来の姿である。
棚を架いている。
食事の間とすることがある。
寝室をともなう。
屋根裏を露出している。
台所
イロリがある。鍵を吊る。
イロリに信仰が伴うし座席名もある。
神棚が常居にない場合は、ここにある。
板敷になっている。
棚を架いている。
食事と炊事の間である。
寝室をともなう。
屋根裏をみせている。
このように比較してみると、特に著しい本質的差異が認められない。本来同一であったものが二つに分化したものであることが、これで明白である。伝承によれば、昔は台所と常居の間には戸障子の仕切がなく、莚や「コモ」で中仕切をする程度であったという。常居と台所とはもともと一つであったのである。ということは常居と台所の部分が原始的な母屋であったのである。
戸主が神棚に最も近い「イロリ」の部所、すなわちヨコザ(かみざ)に着座し、家族その他は相応の「イロリ」周辺の座につく。戸主の座は神棚のある方に位置している。「イロリ」着座部所は神座を規準にしているのである。家族生活は神座を中心にして秩序が保たれていたことが推測される。
家庭において食事をする場合、戸主が上座につき、家族達はそれぞれ相応の席につくのが常例である。この場合も、戸主の着するのは上座であって神棚に最も近い部所である。戸主が常居で食事する慣行の家では、神棚は台所にはなくて戸主の居る間にまつられている。
また、食事をする場合、古風な家では朝の礼拝に朝餉を献じ、戸主が神棚に向って礼拝が終ってから家族一同食事についたものであった。従って戸主の座る「ヨコザ」は何人も侵すことは出来なかった。
民家に共通していることは、戸主夫妻の寝室兼居間ともいうべ室は固定していたということである。しかも、その位置は神棚に最も近く占められているということである。その部屋から戸主が移転するのは、家督を譲り隠居する場合に限っていた。であるから、戸主夫妻の居間は、神に侍る部屋、神に奉仕する指定の部屋であったわけである。
田中喜多美氏の要旨は以上のごとくであるが、氏は結論として「私は、自分の調査した結果から見て、約五十ヶ村の民家の中二十一ヶ村は曲家以外の民家一斉を含めて、八八%(五千五百九十戸)は常居に神棚を有し、八%は台所に神棚がある実状に接している。また残る二十九ヶ村は殆ど常居である。しかして自分の神座論は、如何に建物の変革あるとも、神座は不動なりとの結論に逢着したのである」と、述べている。
2 間取と機構
座敷には床の間・押入があって常に畳を据付けない家が多く、冠婚葬祭等のときのみ敷詰めたのである。中には一枚も持たぬ家があるほど高価なことから大事にしたものであろう。縁側から直接上座敷に上がるのは僧侶のみであった。
常居は広い板床であるが、幾部に畳を据付けるもあり、周囲には箪笥・戸棚等がおいてある。ここから出入するのは神官・武士・本家の主人のみで、一般は「ニワ」に廻って台所から出入をしたのであった。
常居の奥に神棚と仏壇がある。東縁の障子を開けば、仏壇が目の前に眺めることが出来るような位置にあって、キリスト教信者でないことが一目瞭然である。
寝室は概して空気の流通良からぬ家屋が多く、掃除が行届かず、大抵一坪か二坪位である。ここは常居の後方にあって、入口は一間二枚の戸障子によって仕切られている。以前は藁屑を褥とし、いわゆる万年床が多かったが、大正の始めごろから屑布団と称する麻織物に藁屑を入れ、漸く木綿の敷布団が使用されるようになり、終戦後真冬にエバーソフトが用いられたのである。
寝室が狭く採光少なく昼なお薄暗いのは、午睡の関係もあったろうが、毎日広い天地を相手に労働する農業において、明日への計画、将来の構想を練るには薄暗く狭小なほどまとまったのではないかと推測するのである。
寝室と常居の中間に神棚と仏壇がある。ここは母屋の中心である神仏を守るため「トド」と「カガ」の主人夫妻の寝室がここにおかれている。台所の北側の寒い部屋は「アニ」と「アネコ」の若夫婦の寝室であり、下座数の日当りのよい部星には「ジ」と「バ」いわゆる隠居の寝室がある。主人夫妻の部屋には「カガサマ」専用の長持・箪笥、主人専用の重用書類等を整理する箪笥その他がおいてある。あねこ夫婦の寝室にも同様持物がおいてある。この主人の寝室には嫁が出入することがなく、嫁の寝室にも妹夫婦以外出入するものがない。すなわち「カガ」の部屋と嫁の部屋は厳然と区別されて互いに出入することがない。
ところが、嫁の長男が成長して、嫁をとり一人前になると、今までの自分達の部屋をば若夫婦に譲渡して、仏壇のある常居の寝室に移動させ、自分達は下座敷に移動をする。寝室の交替は、神仏を守って鍵を握り、「ヘラ」を握ることを意味し、一家の生計管理の移譲が伴うことである。きめられた部屋に就寝すること二十年。嫡孫を二十歳とすれば、その父は四十歳、その祖父が六十歳と推定される。
普通家族の常住するところは台所で、ここは一家団欒の場である。ここには流し元・戸棚・水桶・くど等があり、その中心は「シィブド」である。この「シィブ(ビ)ド」は四・五尺四方か三尺に六尺、または四尺に五尺位の炉で、薪を燃し、食物を煮焼して暖をとる。電灯のなかった当時は、ここで藁細工の光源ともしたのである。この炉の上には火棚を設け、生薪・灯火用の松の根、楔、鉈鎌の柄、濡れた衣類の乾燥、中には凶作時のため米をもあげている。流し元は台所の西北かまたは南方にあって、「ヤタ釜」に近い処にあるを例とした。
台所と出入口との間に「ニワ」がある。いわゆる中庭である。この中庭の広さは家屋の大小によって一様でないが、大概十坪内外で、ここに板敷がある。この板敷に「オスギリ」がおいてあって「ヤダ」すなわち馬の飼料を切り、壁で拵えた大きな「ヤタ釜」を勝手の近くに据付けて馬糧を「ショミズ」と共に煮て、馬にも冬季は人間同様暖めて与えている。「ニワ」の北側に鍬・鎌等農耕に使用する農具が蔵められてある。この「ニワ」は馬の飼料作りから、農閑期における藁細工、蓑作り、俵編み等もここで営まれるのである。また、小屋のない家では穀物の収穫物の調製も行われるため、塵埃の飛散夥しく、いわゆる屋内作業場でもあった。
「ニワ」(中庭)から外に出る所を「ジョグズ」という。ここには巾一間もある木の大戸が一枚たっている。外に出るには太い土台の敷居を飛越えねほならぬ程高い。「ニワ」の外は「オニヤ」である。
厩は「ニワ」に隣接したところに位置していたから蝿や蚊の集りが多く夏には初中終蚊ゆぶしをして防いだのである。厩の上桁をば「マゲ」といい、ここに藁及び秣が揚げられていた。
座敷及び寝室にのみ天井があり、外は殆どないのは「シィビド」の暖が家全体を暖め、最後は厩の上の「カホノグズ」から抜け出るようになっている。
小屋は柾葺か茅葺で農作物の置場となり、また調製に使用していた。
土蔵は茅葺もあるか、柾葺か瓦葺が多く、火災に耐えるよう壁を厚くして堅固に建て、重要な家具・什器・穀物等が収蔵されていたが、主に凶作に備えたものであった。
3 いろり
いろりは、住いの中心というよりも、遠い昔から生活の中心であり、農村文化とは切っても切れない関係にあった。板の間に莚敷の「おかみ」が、仕事場であり、お客があれば対客の場となり、家族にとっては休息、レジャー・ルーム、子供らの勉強場所にもなった。いろりの上には自在カギから鉄ナベがぶらさがり、グツグツと何かが煮えている。ナラ・ブナ・クリなど長さ三尺ほどに切ったタキギが燃えている。老人たちは「この明かりだけで、昔話(第四編第二章第十八節説話参照)を聞いたもんだ」と語ってくれた。採暖煮焼のほかに夜間照明の機能もあったのである。いろりばたは子供にとっては楽しい場所であった。楽しかったのは、子供だけではなかった。老人達は、「トロトロ燃える火をつつきながら話しあってみなさい。自然に心がとけ合ってくるもんだ」といっている。大人達にとっても楽しい場所であった。いろりの上は火棚になっていて、ぬれたつまご等を乾燥させた。
岩手県ではこういう場所を、旧南部領でも旧仙台領でもイロリというか、全国的にみると地方によって色々な呼び名があるという。代表的なものだけでも二十余種類にのぼるが、類別すれば「イル(居る)場所」、「火の場所」、「家の中心の場所」といった三系統の意味で表現されている。イロリ・ユルギ・ユリなどは「居る場所」から出た呼び名であり、イロリに囲炉裏や囲炉裡の文字を用いたのは当字にすぎない。インナカ・エンナカ・エンナタなどは「中心の場所」という意味で、ヒホド・ヒボド・ヒドコ・ヒビド・ヒジロ・イジロなどは「火の場所」であると解釈されている。古風ないろりは一般に大きい。四・五尺に四・五尺、あるいは三尺に六尺位もある。炉縁だけの低いものや、腰をかけて足をいろりに入れるような深いものもある。フンゴミ炉(踏込炉)といって土足のままでいろりに入れるようなのもある。
いろりの位置は一間(ひとま)だけの家では室のほゞ中央で、家が二室、三室と分化発達するにつれて、家族常住の場所であるオカミにおかれるようになる。台所から庭に板間が延びてくるとそこにいろりが設けられるようになる。現在の家は普通そうなっている。その場所でも、オカミにはいろりが残存していて、平常は使わないけれども、人寄せの時などにはそのいろりを使う。オカミが畳数になると、踏込炉でなく浅い炉に変る。オカミのを上(うわ)イロリ、台所のを下(した)イロリと区別して呼ぶところもある。-以上が小倉強氏のいろり位置変化に関する要約である。
いろりが家長権家族生活の中心となっていた封建遺制の例証として、いろりの座位置がよく引用される。本人のすわるとこがヨコザ、その横が主婦のカカザで、その向いが客座、ヨコザの正面がキジリ、これは全国的なものである。「ヨコザにすわるのは坊主か、ネコか、というように、座位は一家の長を中心に形成された農村の家族制度から決ったと考えられている。いろりの近く、普通は台所と常居の界(さかい)の中央部に大黒柱がある。大黒柱は重要な柱とみなされているので巨大な材木をつかう、構造上からみて、屋根の荷重を最も多くうける柱であり、家の中心部にあたっている。ヨコザに座った家長は大黒柱を斜めにしたような恰好になる。威容もそなわることになる。ヨコザという名称は、ここに畳かゴザが一枚横に敷いてあるからだというのが通説であるが、あるいは大黒柱のヨコの座という意味なのかも知れない。ヨコザにはウスベリを敷いてあるが、客座には来客のときウスベリを敷いて接待をする。この横座から主人が厩を眺め馬の顔を見なくては気がおさまらぬとされている。横座をば上座ともいい、普通主人の席なるも、集会等の場合は、横座に上客を据え、家人及び子供らは各隅か木尻座を充てている。客座は来客時の席であるが、常時は男の座席としているので男座ともいう。客座の向いがカカザで前には湯釜があり、炊事の際ここで鍋釜を上げ下しする。この座をおなご座、嫁座、バドゴともいう。横座の向いが木尻座で使用人の席で火たき及び小用事をするに立易い席である。目上の人が家を訪問したときは尊敬の念を持って木尻座に座るものなりとしている。明治初年ごろはこの座は「にわ」と続いていて、普通跣足で座についたという。その後板張りにしたが、浅い炉では床とほゞ同じ高さに、深い炉では床から一段低くなっている。
客座と女子(おなご)座が横座に向って正反対になっている家がある。それはその家の勝手と関係をしている。すなわち、横座の左手に勝手があれば左側が女子座になり、横座の右手に流し元があれば右側が女子座になる。炊事がスムーズに行われるように仕組まれている。しかし、多くの客座は座敷に近い横座の右側が当てられている。
炉縁に沿うて炉の中に足置板がある。石の台をおくところと、しからざる所がある。平素床板同様雑巾にて拭きおくため、土足にて炉に座る場合は敷板を裏返しにして使用をする。
鍵は自在鍵なるも昔ながらの木製を使用せるも、大正のころ?より余裕のある家では、鉄製更に真鍮製を使用するようになる。
禁圧には、地震の際、老母が新割を立てる。子供が小便などしたときには、塩を振り清めることをする。
火の神様の不動様を各戸で信仰していた。
4 燃料
薪(まき)はナラの木を最上とするも主に雑木を使用し、これを冬季男子の仕事として切り取る。それを女子が橇にて運搬をなす。春先男子は販売用として小割にし乾燥するのである。末(うら)木、杉の葉・松葉等は「やた釜」にて馬糧の湯をわかすのである。
薪の単位は、一間と称し六尺四方か九尺と四尺に積み、木の長さを三尺玉寸とし、これを一棚という。
「しぃびど」や「やた釜」には縄類及び藁は、愛馬心より使用されず、その他「ニンニク」・「ネギ」等青い物は肥料に積み重ね、燃料の中には一般に入れなかった。
梵火は昔灯明・保温・炊事の三者を兼ねたのであるけれども、灯明用には昔松の根をも使用している。灯火については明治の末まで火を照明に使用していたが、石油ランプが使用されるに至り次第に減少し、大正五年ころ本村に電灯が入り、石油ランプが漸次減少することになる。電灯の使用後、漸次ストーブによって炊事と暖をとるようになり現在に至っている。
明治三十-三十五年ごろまでは燧掘山から産する石英を火打石とし、それを火打金と摺合せて発火し、軽木の先に硫黄を塗った「つけげ」に移したのである。それまでは燧掘山の石英かたくさん移出されている。(第七編産業の変遷、第一章、第四節の二を参照せられたい)しかし安価なマッチが容易に手に入るようになると「つけぎ」を用いず直接杉の落ち葉か松の枯葉に焚付けるようになる。「キセル」による喫煙については、昭和十五年、ころまで火打石によって発火し、それを乾燥した蒲の穂に移して発火している。
火留は主婦が主としてこれに当り翌日早朝炊事が可能なるように残り火をしておかなければならぬし、火災のことをも考慮せねばならぬので、主婦の炊事権はヘラと火によって絶対的なものであった。たとえ四十歳になっても炊事権のない女は「あねこ」と呼ばれ一人前として認められなかったのである。
木炭の使用について『岩手を作る人々』(中巻)に森嘉兵衛氏が記述している。
近世になって鋳物師や鍛冶屋達は全国を移動して、砂鉄を掘り、炭を作り、ふいごを吹いて、鍋釜を作り、農具を作っていた。これを見た農民には不思議で珍しかったにちがいない。彼らが去った跡には、真黒い炭が残されていた。煙も出さずに赤々と燃え、鉄をも熔かす威力はたしかに一大驚異であった。
農民達はだんだんこの灰を作ることを覚え、家庭に取込むようになると、岡炉か利用され、炬燵が発明され、煮焼に利用されるようになって、家庭生活や炊事に大きな革命をもたらした。冬の長い岩手に木炭が暖房用として利用されたことは、冬の生活に暖かい平安を与えることになった。
木炭が重工業である鉄工業の動力として使われたばかりでなく、家庭生活にまで使われたことは近代において石炭が重工業の動力だけではなく、家庭内にまで行われた以上に大きな影響を与えた。
5 灯火
大昔には桧を摩擦して発火させ、皿型の土器に木片を入れて燃しそれを明りにしたり、多くの木片を油の中に浸し、芯の代用にして焚いたかゞり火、樹脂の多い松等を利用して携帯用とした松明(たいまつ)、これらかゞり火、松明は人質が発見した最初の火であった。
しかし、油を使用したのは一部の人々で、一般は木材を利用していたであろう。
仏教伝来と共に灯火も発達し、江戸時代になると、石灯籠が庭におかれ、灯火にふたをするようになり、「しょくだい」が出来、夜は行灯、原始的な「ろうそく」が発明される。携帯用として「ちょうちん」が利用される。その後、外国との交通が盛んになり、明治時代(1868-1912年)には石油ランプが現れ、白熱のガス灯が安政四年(1857年)に初めて島津家が使用し、明治十六年(1883年)電灯がつき、明るく便利なため上流社会に使用されたのであるが、本村においては、大正五年から使用している。
灯火について『岩手を作る人々』より抜萃する。
農仕舞がすむと山に入って松の根本に傷をつけ、漆をとるように松脂を集めさせた。これを「よらす」といっていた。これを冬の中にもって来て米糠とぬり合せ、「でっち」を作り、夜の家の光としたのである。しかし、こういうものは実に稀る方で、雪や螢を集めた昔話がある程、書物を読むだけの光を備えることは容易なことではなかったのだ。松の小割木を「キデ鉢」でもやして僅かに家の光とした時代のあったことを思うと昔の夜がいかに佗びしいものであったかを淋しく思うのである。こういう時代には家は一般に闇く、陽がおちれば寝るより外はなかったのである。そこへ松木をたいて光を与え、夜の労働に楽しみを与えたのは主婦である。松の火のあかりは、まことにかすかなものではあったが、男女の共同作業に楽しい夢を結び、若い人生をあかるくしたのである。家の明るくなるのは愉快なものである。独り夜分ばかりではない。紙の障子が自由に用いられる様になってからは窓も高くしておく必要はなくなり、闇い戸を立てゝおく必要もなくなった。南部藩では窓税というものをかけたので、南部地方の農家の窓は少ないという説をなすものがあるが、鍵役という戸数割をかけた事はあっても窓税をかけたことはない。たゞ窓が少ないのは、紙の障子を作る余裕がなかったからである。
家に光を導くか闇にするか、笑を作るか悲を呼ぶかほ、その主婦の如何にあるといったら少し大袈裟かもしれないが、実は主婦がこの矛盾した二つの性格をもっていたのだ。「嫁が姑になるの早さよ」と川柳が諷するまでもなく、嫁はやがて姑となる主婦になる候補者である。嫁は「呼びめ」で一家の主婦として呼ばれた女である。だから嫁が来たら姑は主婦権を渡して隠居すれば問題はないのだが、「私の目の黒い内はそう簡単にへらは渡されない」とかんばる姑があれば、嫁の夫の妻として、姑の娘として、夫の兄弟の姉妹として、主婦見習として、家風に従い、人倫を学ばなければならない。それがむずかしい姑であればある程、「人生とは」とトルストイにすがり、イブセンに共鳴せざるを得なくなるのである。
然し主婦は少なくとも家計の主宰者であり、家族が多ければ多い程、そのやりくりは重大であり、若い嫁にはまだまだと言いたくなるものらしい。佐渡の民謡に「添うて七年、子のある仲だ、嫁に杓子をわたしゃんせ」という歌があるが、将に嫁の心情である。「おまえ」とか、「おかた」とか、「とじ」とか、「かか」というのは主婦の古語で、任務と権能とそれに伴う尊敬のついている地位であった。それは炉の座席にはっきり定められていた。常居の炉に横座があり戸主だけがここに座るのだ。無断で他人が座れば「米一俵」出さなければならないと言われた。横座の左側が「かか座」、「へら座」で主婦の座席だ。右側が「客座」、「けぐら座」で客の接待場所だ。横座の向側が木尻で、奉公人とか「ひやめし」の座る所だ。
炉の火を管理し、これを断やさないようにするのが主婦の任務であり、同時に子と共に財産相続権をもち、相続人の選定権をもっていたのである。
家督相続は今のように長男相続となったのは近世以後のことで、中世の終り頃迄は必ずしもそうではなかった。
岩手県の人口は稀薄なため、いくらでも開拓し、分家させる土地に恵まれていたから、子供ら全部を家におき大家族制をとり、共同開墾をし、分家を起したのである。しかし土地生産力が低いから新田が熟田と同様になるためには本家の保護が必要である。従って本家を強力にする必要があり、長男相続制をとり、二・三男以下を分家せしめる慣行を作ったのである。出羽山形地方では姉家督制が行われている。これはむしろ長子相続制で、男でも女でも長子に相続させる。だから長子が女であればこれに養子を迎えて相続させるところから「姉家督」制と言われるようになったのだ。これも開拓型だ。この相続人の妻が後主婦になる嫁なのである。しかし主婦権を譲られない限り、その嫁は「おかた」でもなければ、「かか」でもなく、「あねさま」なのだ。「あねさま」が「おかた」になるまでにあまり苦労し過ぎると、「嫁が姑になるの早さよ」と目を見はられる事になる。
姑と嫁との対立は家庭を複雑な感情の坩堝と化した。然しこの紛争は決して古いことではない。古い習慣では一家に主婦の現存している間は結婚はしても嫁には来なかった。妻は生家にいて、婚家という部屋を与えられ夫の方からこの部屋に通ったのである。
夫が妻の家に通う古い習慣は部落内結婚の場合の可能だが、遠方婿になると、そうは行かないから、一家に主婦がおるのに嫁に行かざるを得ない。そこで嫁と姑の問題を生じたのである。これが一般的になると、嫁の実家に通う男を見ると事情を知らぬ者からは「夜ばい」と見えたのである。しかし実際は通う男は決っており、親も認めたものが多かったのである。「夜ばい」というと何か淫蕩な感じをもつのは想像する者の自涜だ。一家の主婦はこれを許さなかったのだし、主婦のきびしい眼が光っていたのである。「よばい」は決して「夜這い」ではなくて契りを定めた女を「呼ぼう」のである。「夜這う」も「呼ぼう」も結果は同じだというかも知れない。然し精神が違う。この差は人間か動物の差なのだ。間違ってもらいたくないのである。
主婦の力で家族中心の団欒が作られていたのである。だから家庭においては「かか天下」であるのが普通だったのである。これが異例であるかのように「かか天下」という事が亭主を軽蔑する意味になったのは後年のことで、亭主が部外でする仕事が少なくなり、家庭のあれこれを支配するようになってからのことである。男女同権は何も外国の一手販売ではなくて、古くは岩手の家々もそうだったのである。主婦が家付女中みたいになったのは、近世の変化で、家庭生活が悪く変った一例である。
七 建築慣行
1 用材慣行
用材は、旧藩時代、自分の山林でない限り、藩の公許を得て伐り出していた。歩合山の植材でもその通りであった。原則として山林なども藩主のものであった。
しかし大事で家屋が焼失したり、洪水や津浪で流失したり、地震で倒潰したりして再建を要する場合は、必要とする限度を伐り出すことができた。山林の種別によって色々の制限のあることは、南部藩の林制を参照せられたい。
柱材としては耐久性を考えて楢が古くから使用された。東北古代蝦夷征討開拓期の城柵跡で発見された柱材、例えば胆沢城跡の建物をみても栗が多かった。
家格の高い民家の接客用の座敷には杉柱が多く、そのうちでもいわゆるヒロマには杉材だけを使用した例もある。
ケヤキが使用されるようになったのは東北地方においては、藩政末から明治にかけてであるという。ケヤキの太い大黒柱はその家の自慢でもあった。屋根梁にミズキをよく使うのは火難除けの呪いの意味があったという。なお用材の樹種その他家普請については第十編教育の変遷、第五章第二節俗言集を参照せられたい。
台所の柱梁材には、よく曲材が使用される。山の立木の皮を剥いで、大面をとり、あるいは太鼓落しにするなど、あまり加工せずに使用している。
木材の使用に当って、木末と木元を重視した。立木の姿を生かし木元を下にし、逆(さわ)木は絶対に避けた。小屋組をうける桁は、木元を台所の方に向けるようにする。小屋梁は一本置に木元、木末を交互にもちいる。屋根の合掌材は、木未を上にして組み合せ、木末を下にして小屋梁にのせる構法が多い。この場合には逆木になるが、組合せ部のほぞをらくに工作できるためもあろう。社堂・墓地より出たる用材、穴を利用して巣を作った材木、落雷木は禁忌になっている。
用材には四寸四分角のごとき角材は使用せず、継ぎ方は元と末を継ぎ合せ、異名の木は継がず、さらに根元は日射を受けぬ様に注意されている。土台には栗・落葉松、柱には杉・栗・けやき、ぬきには松、桁にも松、梁には松・栗、中びきには松・杉が主に使用された。
2 工事慣行
金及び用材供給の準備が出来れば、本家に内意を告げ、精神的援助方を依頼し、しかる後用材及び設計に関して大工に相談をし、初めて本確的な建築に取りかゝるのである。
山入りと称し、用材を取る山に、主人及び木切り、本家の主人と共に行き、山に御神酒を供えて拝むのであるが、これには一定の形式がない。御馳走は漬物程度で帰宅後の御祝も普通食に洒程度である。
用材運搬には木引きと称して、近親及び隣人の奉仕により運搬をする。御馳走は普通食に酒程度で、運搬方法は昔は賑やかなもので、橇二台位に村人十人位乗せ、掛声勇しく引いたものである。もし途中日が暮れると、力酒と称して濁酒を呑ませ、その勢で勇気百倍し運搬したものだという。終戦後は一切大工に委任し、協力体制が見られなくなった。
用材運搬終了後、大工に依頼をするのであるが、これを図面とりといい、棟梁(とうりょう)が用材を見て設計することを墨うちという。
大工の仕事始めを手斧立てという。これは一定しておらぬが、親類及び近隣の人々に家を建築するから何分の御援助を願いたいという意味が含まれているので、親類近隣はもちろんのこと、職人等を招待し、嫁入程度即ち大引・五寸吸物三つ皿車つ等で七リブタなしの御馳走をする。招待を受けた親類及び隣人はこの日から用材の供給、労力の奉仕、食料の提供等精神的・物質的援助の義務を生ずるのである。
手斧立てが終れば宅地の「おはらい」を神宮に依頼して行い「地がため」になる。これを「モンキツキ」とか、「ドンズギ」とか、「亀つき」という。重さ二十貫-三十貫位の石に縄をつけ、音頭とりを中心として亀つき唄をうたい、村人十五・六人乃至三十人位の奉仕により、北の隅から東南西北の順に地がためを行うところと、戌亥の西北の隅から搗き始めて右廻りする所もある。御馳走は普通食に酒程度である。
柱を直接土台の上に建てるのが古風で、現在のように柱の下に土台を据えるようになったのは安政以後といわれている。
いよいよ柱建てになる。このときは棟梁の腕前を世間に発表する唯一の機会で最大の力量を発揮するときである。御祝は、奉仕者及び大工の御馳走は、普通食に皿一つ位多い程度のもので、それに酒がつく。しかしながら祭場は新築中最も良装飾である。
柱を建てる順序として構造上重量な柱、例えば屋根組を受けて荷重の大きい柱から建てはじめる。これは重要な柱を建てゝ、それを桁貫で固め、次ぎに小柱等を建てゝ行く。つまり家の構造上の重要な個所の枠組を始めにつくり庇(ひさし)のような部分を後からつくるという順序になる。柱間(はしらま)の寸法には六尺、六尺三寸、なかには六尺五寸もある。
祝の順序であるが、祭場の礼拝の最初は棟梁、次は家主、職人、その他となり神酒開きは家主から棟梁、大工、奉仕の順につがれる。
上棟式、つまり屋根の落成を「むねあげ」または「葺キズマイ」といっている。
祝の前に神に供える重ねの供餅、撒餅、廻し餅が準備される。葺きじまいには屋根の棟梁がこの式の主催者で屋根の上で神酒・肴・餅等を持ち、北より南・東・西と四方の神を拝み、神酒を開き、しかる後屋根職人正面より四方に餅をまき、続いて親類がまく。なお撒く餅に「ハンドメェ餅」がある。これは妊婦安産のため特に縁側より撒く奇習がある。屋根の上には木で作った鎌のようなものを十二・三個立てる。このときは老若男女隣家の人々が集り餅拾いをする。親類及び隣家奉仕者等に若者三人程に直径六寸程の廻し餅を担がせ、祝の印としてくばり、祝の招待者には同じ位の大きさの餅を二・三箇宛膳に添える。
屋根勾配は、葺材によって異なるが、萱葺の勾配は四十五度位、柾葺は三寸-五寸勾配、瓦葺は五寸-六寸勾配になっている。
萱葺は四十五度を基準とするが、本村においては梁間三-三・五間のものは下廻一尺に対し高さ一・一四尺、梁間二間位のものは高さ一・二尺の勾配とする慣習である。萱葺屋根が急勾配になっているのは、積雪よりむしろ雨の排除で、萱のような細い材料を何本も重ねて葺くのであるから、厚く、しかも急勾配に考慮されている。
萱の数量をあらわすのに一駄・一締・一把がある。一駄とは馬一頭につける数量をいう。一丈縄で大把三箇で締めたものを一締といい、二締を一駄といって馬の背の両側にのせる。大把は径三寸位の小把十個をいう。
参考までに和賀郡藤根の建坪一坪当りの萱葦の大要を詳述すれば、
〇萱葺屋根材料、大要
萱 建坪一坪当 五、五蹄 一締ハ萱根元四尺違イノ九尺五寸縄締
苧稈(おがら) 軒一間当 〇・五締 同
葭簀 屋根坪一坪当葭十分ノ一締 一締ハ葭根元四尺違イノ三尺縄締
長木 屋根坪一坪当 二通(母屋ノコト、ヤナカ)
ホケ細長木 屋根一間当 七本(タルキノコト)
ナル極細長木 屋根坪一坪当 八本(萱下地ノ細木)
荒縄ソバ縄 屋根一坪当 七尋 一尋約五尺五寸
摺縄 屋根一間当 一〇尋
水縄針縄 屋根一坪当 三〇尋
〇葺上用具
杭足代 長木 柵板 足代縄(二尋ノ極太縄)
〇葺職人用具
鈎鉈針(五尺) 鋏 手柄(木製) 差箆(へら) 突上ゲ踏鈎 萱抜鋏 砥石
〇人員
構造ニヨリ多少相違アリ、建坪一坪当所要人員大略
人夫(材料運、建築、葺上、雑用)十四人位、殆ド近隣ノ共助ニヨル
杣人 三人位
大工 六人位
屋根葺職人 一人位
である。
棟を一般にグシと呼んでいるが、本村では「やねグス」といい、棟にのせる芝土を「やねグレ」といい、厚二寸位、大きさは二尺に三尺、切取って棟にのせる。
棟には富裕を意味した奇数の千木型か、進歩した箱棟のあるのが珍しく、多くはユリ等の咲く芝草が多い。
建築は雪解期の農閑期、すなわち春二月より四月上旬に行われている。普通上棟式には新宅祝いと屋移りが兼ねられる。
分家を独立させる場合は、本家が全用材を準備し、労力は隣家から一軒三人程度の奉仕である。また分家になる者の知己関係者より柱二・三本の提供がある。本家が中流家庭の場合は全用材の四割位、親類知己による柱及び土台は残りの六割位である。食糧については米及び酒で親類の相談により「手斧だて」より落成祝いまで交互に提供をなす。労力の奉仕については、親類は約十人村付合いとしては五人位を普通とする。
屋根替の「ヤドゴ」は一代に一回は必ず出合う大役である。萱葺屋根は二十年乃至三十年程度で葺替えしなければならない。葛屋は小さくて建坪六十坪、大きいのは百二十坪前後のものが珍しくなかった。従ってその屋根の面積は、建坪が増すに従って高さを増し、面積が大きくなり、屋根葺の量を増し「ヤドゴ」無尽が出来たのである。たとえば二十戸の村で葺萱十五尺丸しめ五丸、細藁縄二十把、押え柴三十本、人足六人、白米五升とすると、葺萱は百丸、縄四百把、柴六百本、人足百二十人、白米一石が自己負担を加えて確保され、一年一戸の屋根替とすると二十年目に自己当番となって、十九年分の蓄積が還元されるので、それだけ負担が軽くなる。
家屋建築に伴うそれぞれの専門職は延宝八年(1680年)の記録に、南部領の盛岡分として大工百八十九人(上九十四人、中三十八人、下五十七人)、木挽五十三人(上四十人、中七人、下六人)、舟大工五人、桶屋三十四人(上二十人、中七人、下七人)、桧物師八人(上五人、中一人、下二人)、畳刺三十三人(上二十一人、中七人、下五人)、屋根三十人(上二十五人、中五人)、鍛冶六十四人(上十二人、中三八人、下七人)、瓦師十人(上四人、中五人、下一人)、鋳物師四人となっている。
とはいうものゝ、前記の各職人は城下における上級士族とか、商家が主であって、特に畳が一般に普及したのは元禄(1688~1704年)以後であったという。『勘定参弁記』に「畳表志和を第一の産とす。一枚凡そ九十文より百三十文位迄」としてある。これは宝暦十年(1760年)の領内相場であった。当時旦雇労賃は一日五十文であり、白米一升二十文であったから、畳表一枚は白米凡そ五升程度と交換出来たことになろう。
神仏の祭祀は新築、もしくは修理する年は春彼岸より工事中御ことわりをなし、近親はその家に代って時、時節の供養物を供え祭るのである。落成すると依頼しておった近親より神仏を移すのであるが、神仏に鏡餅を上げて拝む程度である。最初の火入に当っては塩と水を供えて礼拝の後火を燃やし、馬をば新宅の廻りを三辺廻して後入れている。
禁忌については、屋根葺替の年味噌をつけた食物を焼かぬこと位である。屋移り慣習で面白いことは、屋移り粥と称し、小豆粥を炊き、両親のある子供男女二組を常居の四隅で一椀ずつ食べさせ、食い終った者は未だ終らない者の箸を奪うことである。
新宅祝には餅を搗き、酒と肴が準備され、大工・屋根職・親類、落成当日労力提供者は皆僅かの御祝いを出し合い祝宴に加わるのである。これを樽入と称す。祝宴は大工の棟梁の神唄に始まり、うたいに移り、その後は自由に民謡が出、踊りが伴い賑かにとり行われる。
このときの御馳走は普通食に皿二つ位増す程度である。なお、第十編教育変遷、第五章、第二節の俗言集を参照せられたい。
第十五節 食物
一 往時の食習
藩政時代の町方食習慣について遠野市仲町『菅沼左衛門扣書』から拾うと次の様であるが、村方は一層粗悪であったことはいうまでもない。
天明三年(1783年)の書上に「塩・わらびのあも・粟糠・赤魚・秋生鯣・鮭」と見えており、特に粟糠及びわらびのあもについては「あわ糠あも喰する者糞つまり死す」とあり、秋生鯵については「何方ニ而喰物大ニよろし」とある。
天保四年(1833年)十一月廿一日相場
新自壱升弐百二十文、古白同弐百五拾文、糯白同弐百六拾文、古粟同弐百参拾文、新粟同弐百文、大豆同百文、新同八十文、大麦同百文、小麦同百二十文、古稗白同弐百文、黒稗同八十文より五十文迄、小麦同弐百二十文より百五拾文迄、そば同百文、ふすま同四拾文、ひえ袋同三拾文、わらびの花同百五拾文、きらず同三十文、小糠同三十二文、めの子同百文、ところかて拾七文、大根一本五拾文、干な壱釣(連)百文、鶏鹿肉大高値、鮪一本四百文、金壱両五〆八百文。右の通相場暫不相替侯
天保六年(1835年)三月六日の相場書上には油類として、荏(まめ)油〆、胡麻、粒重根油があげられ、同年五月朔日市場には「ふきかけて、うるい、牛蒡葉」が記され、また「外青物うど、わらび大ニ下値ニ相成候」とある。
天保七年十月十一日の市相場には酒類、味噌、酒粕についてもあり、最後に「濁酒御差留厳敷御用達町同心相廻り候」とある。
天保八年三月十六日の市相場にはさらに「麦つき糠が見え、最後に餅について「売物ハ根餅、ひやら餅、野老餅、大豆餅、目餅、大豆から餅、松波餅、大豆餅、申はかま餅、いろいろな物相出侯」とある。
明治維新となり、四民平等の世になって三年目『菅沼左衛門扣書』の相場書上をみると、「明治三年(1870年)二・三月中の相場白米一升壱〆四百文、糯白同壱〆六百文、粟同壱〆五百文、大豆同九百文、小豆同壱〆五百文、白ひえ同壱〆三百文、つき麦壱貫文、蕎麦同八百五十文、きらず同百二十文、ふすま同弐百文、糯粟糯粉糠同弐百文、古稗壱駄二付参拾弐貫文、味噌百文ニ三十匁、塩一升五首文、とうふ壱丁六十四文、玉砂糖百文二七匁、大工日用一日懸はなし弐貫文、但し、喰料手前ニ候ハバ一日壱〆四百文、日手間取一日懸はなし壱〆五百文、手前賄人一日五百文、日手間取懸はなし頼候時へ利方也。白米壱升壱〆四百文、酒五合九百文、二度呑セ、肴三度百五十文、味噌二度、漬物小びり入り申さず候共弐貫四百五十文余諸入用二御座候、尤も日三度ニハかて入候ても大喰故此諸懸り申すべく相違これなく候、とあり重根油、荏油については壱升に付、それぞれ壱〆弐百文、六貫文とある。
もっとも、四民平等とはいえ、村方の生活は藩政時代と異なることなく簡素で、菅沼家書上は、町方の中流以上の家庭であったろぅ。明治以降の食習慣における食物は一般に粗食で、村方においては岩手の米どころといわれる江刺、胆沢でさえ米のみを常食とせず、多くは粟、稗、麦等を混食し米・麦・粟の三穀を混ぜて常食することも少なくなかった。
維新前までは江刺地方でも、三穀飯にさらに大根・菜葉・粟・稗等を混ぜ、山間部では栗の実を食したといわれている。さらに胆沢地方でさえ、後年大正時代まで大麦を混ぜて常食とし、その後も「かて」として大根を細かに刻んだもの及び粟を混ぜて食べるのを例とした。
本村においてはこれら地方よりさらに簡素で粗食であったであろう。
二 平常食
1 主食
本村を含む北上川水系に属する米産地帯でも、年中行事の祭祀に関係する場合は、「米ノミス」と称して晴食にするが、不断日、いわゆる「ケの日」は米を食べなかったのであるが、後に白米の外に粟・稗・麦・切干し大根を混入して用いた。これを「カデ」と称し、「カデミス」を常食としていた。米の飯は、盆・正月・田植えや、休日などの行事日か、訪問客の接待用とされていた。農閑期の冬期などの家庭食は、蕎麦粉のねり粥を昼食にとった。明治七年(1874年)あたりまで地租は現穀の年貢であったこと、米は換金作物として重要であったこと、そのため米を大切にし、なるべく他の雑穀を主食に用いたことであろう。その後麦稗は馬糧として栽培され、残部は凶作時の食糧の準備として貯蔵され、麦俵・稗俵の数多いのを一家の誉としていたが、その反面日常これらを混食すむことを恥としていた。
こうした食習も、大正末期から昭和にかけて、米と雑穀の混合割合は年代が進むに従って米が多くなり、米食者の数が漸次増加してきたところに太平洋戦争当時の配給制度が布かれ、その速度をはやめた。
しかし、昭和九年の凶作時、それに戦争当時の食料難はものすごく、過去における食習慣を再現したことはいうまでもない。すなわち、しだみ・粟等の外に稗・うるい・いも・野菜の混食、わらび・葛の棍餅等が用いられた。
食事は通例一日三食であるが、春から秋にかけての農繁期には、一目五食か六食になる。すなわち朝食・コビリ・昼食・コビリ・夕食である。七月七日には、七度食べて、七度水あびすとよくいわれているが、このことは七度の食事をすることではなく、七度水泳が出来る程暑ければ豊作であることを願う意味であろう。
農作業が過重である場合、餅を搗いて間食したり、赤飯を食べたり、干し餅を間食にしたのは、食事の回数を増すより以上に、エネルギー補給になることを昔の人が考えていたらしい。
米の貯蔵には三通りで、白米は櫃か叺、玄米は俵、籾は「セロ」に入れてなされた。
その他の代用食としては
小麦餅
小麦粉を水で練り丸めて煮る。
麦切
小麦餅と同じようにこねったものをうすくのばし細く切り、そば切り同様にして食す。
ひっつみ
小麦粉を水で練り、小さく千切って汁に入れる。
そばはっと
蕎麦粉をこね、ひっつみ同様汁に入れて煮る。
そばねり
蕎麦の粉を沸騰した湯で練り、醤油等に浸して食べる。
くしやき
そば粉を熱湯でしめしてうすくのばし、握こぶし程の長円形にし、平たい木の串にさして焼き、胡桃味噌をつけて食べる。
2 野菜・山菜の食習
農家におけるエネルギーの摂取は雑穀を主とした米であったが、副食物としては、明治以前から用いられた一汁一菜であった。
味噌には糀を入れないで製造し、古いものをとうとび、早くて三・四年ころから食べ始める。中には十年目位から食い始める家もあった。従って味はよくなかったが、このような家庭は、凶作に備えて、食に不足がないことを暗にほこりとしたものであろう。昭和廿五、六年ごろから糀を入れ味噌を製造している。このころから一般に醤油が用いられたが、それ以前の代用醤油は『スマス』といって、味噌をこすか、またはたまり汁を使用していたのである。味噌の作り方は大豆を煮て踏潰したものを味噌玉にして乾燥し、一・二ヵ月吊して発酵を起させたものを水に浸して臼で搗いて塩をまぜ槽に仕込み、保存をするのである。
自家用蔬菜については第一に「さいもの畠」と称し、屋敷か屋敷の近くに設定し、手取早く採取が出来る処に栽培したのが、きゅうり・ささげ・大根・蕪・なす・ねぎ・なんばん・二度いも・里いも・とうきみ・甘藍等である。
大根について『国分翁夜話』に次のように述べてある。
大根は我が国蔬菜中、殆んど八割の栽培面積と生産高を占めている。世界には色々の蔬菜があるが日本の大根の様にその八割を占めるという様なものは全くない。欧米には日本の大根に類似した所謂二十日大根その他があるが、総野菜中では僅少の量である。
日本では野菜といえば先ず大根を連想する程広く栽培されているので、栽培技術の進んでいることや品種の多いこともまた、驚くべきものである。現在では品種の育成に努力された結果、次々に新品種が現われているが、今後も各地方の需要に応じ、多種多様な品種が作られるものと思われる。
他の野菜は部分的には食用にならない所がかなりある。例えばゴボウなどは根を食べるが茎や葉は捨てなければならない。或は、甘藍などは食用になる部分が多いのだが、それでも根や茎は食べられないから矢張り六割位しか食べられない。これに比べて大根は全量余す所なく食用に供することの出来る利点を持っている。その意味でも蔬菜中稀な存在である。
古来食物には食傷、つまり食あたりとか物あたりということがあるが、大根は一切何物を食い合わせてもあたる心配がない。だから何をやってもあたらないというので、下手な役者を大根役者と悪口をいう言葉さえ使われている。
大根は春夏秋冬の食膳には生のまま供することが出来るが、およそ半量は漬物として用いられるのである。大根の漬物には数十種あるが、当座に用うるものを朝漬といい、年を越して年中食べられるのが沢庵漬である。如何なる家庭でも大根の漬物を食べない所はない。諸外国の蔬菜の加工品中ではまさに異色のあるものである。
生大根の所謂おろしには、多量のジアスターゼを含み消化剤として働くので、消化不良の食物の薬味としては消化促進剤に用いられることは誰でも知っている通りである。又、茎葉部は乾燥して、干し菜として汁の実とすることが出来る。その味は極めて淡泊で、味噌汁に用うれば、毎朝でもあきない。だから『菜汁と月夜は飽きまい』といわれるのである。
本草綱目の中の医薬書には、大根の薬を最も薬用価値の高いものとしてあげている。例えば血を鎮め便通をととのえ、人をして健康ならしめる外、あまたの薬効を列記している。
我が国で大根の最も有名な産地は尾張であるが、その尾張大根といわれるものは、細く長く、根身六尺に及ぶ守口大根など珍しいものがある。
薩摩の桜島では巨大な円形の所請桜島大根を産する。最大なものは一果にして五貫目を越えるものがある。だからサラリーマンの住宅街では、一個を数軒で買って分けて食う様なことさえある。この大根は緻密で柔かく大根としてはけだし天下一品である。各種の分布の広いこと殆んど全国にあまねくしかも根身は久しく貯蔵に堪えて寒暑の別なく食膳に供することが出来る。
なお、大根は白菜、甘藍など各種の薬類と共に、十字花科に属する作物であるが、この十字花科の作物に万国に通じ、蔬菜の王座を占めていること、恰も穀類に於ける禾本科植物に匹敵するものである。
森口多里氏は『民俗の四季』の中で大根について述べてあるので要約する。
「ラルッス大辞典の野菜図版中に、ローマ字でダイコンと記されているから、日本を代表する野菜であるだろう。まことに日本人の食制に大根と大豆はなくてはならないものであった。今では、大根は食膳でのワキ役になっているが、もとは日常の主食であった。収穫した米の大部分は年貢にとられたので大根のカテ飯を食べなければならなかった。ある処では、畑に育てた大根の三分の二をカテにし、他の三分の一をおかずにした処もあった。また、大根をこまかく切り、これをよく煮て天日で乾煉して保存し、これをカンピョウと称していた。このカンピョウと米の外二・三種の穀物を等分量にまぜてカラ飯にした処もあった。とにかく大根は昔の主食にされていたのである。」
第二には大麻を引いた跡に、大枚の移植と、青菜や蕪をまき、越冬用漬物の材料とし、大量に収穫したのである。ここを大麻畠(おつぼ)という。ここから採取したものをおっぼなと称し米糠漬にしている。
第三には粟畠、稗畠、麦畠、大豆や小豆畠、油畠等へ若干補助としてきゅうり・片うり・縞うり・人参・牛蒡・長芋・大根・赤蕪・山東菜等本作に支障がないように、副食物の不足を補うように栽培されたのである。
とはいっても、家の近くに「さいもの畠」をもっていない家庭は、遠隔地の畠に、大豆・蕎麦・稗の類を植えるので、にんじん・ごぼう・ねぎ等を盛岡から求める状態であった。
乾燥するものには大根葉・大根の寒干・芋の茎・ぜんまい・蕗・わらび・茸頬・甘藍等。
越冬用に埋めるものには白菜・馬鈴薯・大根・にんじん・牛蒡・甘藍等があった。
山菜食用植物には・こごみ・ぜんまい・わらび・ふき・みず・うるい・やま芋・しどけ・ほんな・かんだいな・ぬのば・みつば・せり・たらぼう・うど・しょでこ・さんしょうの葉・さいかちの若芽・はし木の芽・わさび・あまどころ・にがどころ・片栗葉等が食用として採集された。
秋には、はつたけ・しめじ・ほうきもだし・こうだけ・あみのめ・とうじん・ゆきの下・うえこ・くねもだし・落葉松もだし等の茸類に、葡萄、あけび、栗、はしぱみ、木いちご、百合等があった。
3 淡水産の魚類
副食物として味噌汁と漬物の外に淡水産の魚類がある。
狩猟時代はともかく、封建時代には家畜はもちろんのこと、野外の鹿や雉子も自由に捕獲は出来なかった。野獣・野鳥は狩人でないと捕獲が出来ず、厳しい藩制でもあったし、宗教上からも二足四足は食禁で食べる機会はなかった。自家の周囲に熊・かもしか・野猿・猪がいても捕獲が出来なかったが、四民が網等によって、冬は雉子・山鳥・山鳩・鴨・雀・野兎等を食べたようである。
そこで動物蛋白は内陸の淡水魚を食用とする機会が多かった。かりに漁具がなくとも村落生活を営んでいるから、交換・贈答等で有無相通じ、村内の食生活に大差があったとは考えられない。
淡水漁業の内、鮭は明治・大正をになっても少なくなかった。雌は少なく、雄はそれに数倍上流の清水に、しかも水量の豊富な処まで遡上し、秋の中ごろから初冬にかけて産卵する習性があった。「正月の御馳走は米の飯にさけのよ」の諺の通り、貴重で高級なため塩引の干物にして保存し、贈答用にし、祭祀行事用の晴食にし、祝儀には欠くことが出来ず、使用しない婚礼は考えられぬ程まで貴重なものであった。さらに、煮肴、焙り肴としてよく、切身にして桶につめ、鮨(すし)漬にすると正月から田植えころまで保存され、高級な食品として賞用されている。
その外、ます・あゆ・やまべ・いわな・はい(はいざ・くき・まるだともいう)・かじか・こい・ふな・うなぎ・なまず・ぎんぎょ・どじょう・たにし等を食用にしている。これらを捕獲するには、夜づき、やなによったが、小堰には山椒の皮や茎を乾燥後もんで粉にし、それに灰を混ぜ袋に入れて上流から流してとったようである。夏分たくさん捕獲しておき、出来るだけ動物蛋白を補給するように、小麦の茎を利用して作ったベンケイに串焼きにした魚類を刺しこみ、いろりの上に吊してさらに燻製にし保存をした。
三 非常食
非常食には祭祀を主とした年中行事食を始め、田植食や冠婚葬祭食・出生祝食・救荒食とがある。
1 年中行事食
神仏に祈願をする年中行事には飯食が伴うので、その材料の用意調理・献供等かなりの時間を必要とするから、農作業を中止し休日となるのである。
この食習には、神仏その他に供えるものと家族用と大別すれば二通りになる。
なお、行事食と田植食については年中行事にゆずる。
晴食の餅類には米餅・粟餅・ヨモギ餅・稲キミ餅(あん・ごま・くるみ・きなこ等をまぶす)、シイトギ餅(糯(うるち)の粉を餅に作り煮る)、くし焼(そば粉あるいは粳の粉に少量の糯の粉を入れ餅を作り煮て味噌をつけて焼く)・団子(糯・粳の粉半々位にまぜて作る)・ボタ餅(粳米を半煮に炊き臼で搗く、丸めて味噌をつけてやく)・キリシェソショ(糯は粳の三分の一位の割合で作る、しめす時醤油ごま等を入れる)・花まんじゅう(粳三升糯一升の割合)・蕎麦切(そば粉を湯でしめしてこね、うすくのばして細く切る)。
飯類には白米飯・赤飯・胡麻飯・ささぎ飯・油揚飯・お茶飯・くるみ飯・さけ飯等がある。
なお祭祀の調理は主として主婦があたり、神への供饌撤饌(あげおろし)は主人、もしくは既婚の男子これにあたった。
2 冠婚葬祭食
あ 結婚
結婚は人生の重大事であるため、その式も比較的荘重に行われるを常としている。しかし現今は、長持担ぎの歌も少なくなり、また婚儀の列をなす風習も少なくなった。
配偶者の選定については、当事者間の意思も多少は考慮されたが大方両親において選定をした。中には見合をなすもある。後媒妁人をたて、媒妁人は双方の意を通じて愈々結婚と決定せば手打酒、または極(きめ)酒と称して婚約決定の祝酒(酒一升肴二本)を相手方に媒妁人が持参し、饗応し、日取等を決定、式に関する諸般の打合せをする。先方に仕度または将来の準備として式服一式、または反物表地裏地とりまぜ七反を買求め吉日を選んで「祝儀物立」と称し媒妁人は洒二升、頭付の魚二尾と共に持参結納をなす。日時決定すれば各々結婚衣裳の購入饗応万端整え、当日に至れば嫁迎えに行列を作り、家族近親九人迎えに行く。婿は礼もせず座敷の緑より入り、帰宅の際もまた一人だけ縁側より出る。俗にこれを婿の食逃げと称す。このとき嫁方では「見立て」と称して近親のもの及び近隣の人を特に招待して饗応するを普通とする。
嫁方においては、親戚一同を招待して婿方一行の到着を待つ。一行到着し、酒宴に移るが、多くは婿方全部座敷を去り「中宿(なかやど)」と称し、別室でまた酒の饗応を受け酒宴となる。婿方一行適当の時機を見計い帰途につく。このとき嫁の荷物を婿方に渡すのである。
花嫁が持参するものには、紋付一枚・小袖一重・帯一筋・紺無地木綿・角巻・単衣地等を入れた箪笥、仕事着を入れた長持、下駄箱、盥、洗面器、下駄、傘等であったが時代と共に変化を見るに至る。
この嫁の荷物を「目出度目出度の若松様よ。枝も栄える葉も繁る。鶴は千年亀は万年栄えるものだアハ御渡し申すぞナーヨー」など歌いながら、仲人の連れて行った若衆に渡す。若衆はまた「鶴よりもナー亀より松竹よりも高砂の爺婆(ぢさまばさま)で受取り申すぞナーヨー」など歌いながら、これる受けとり門口を出る時またこのや家柄(やから)は目度い家柄サス(合掌)は地金板は黄金ナーヨー」と節面白くうたいながらこれを担ぎ帰る。
いよいよ嫁迎えの行列になるが、普通は嫁方からは婿方より二・三人多く付添うのである。行列は媒妁人男、婿、もらい方の主人、その伴(とも)、もらい方の母、その伴、仲介人の女、嫁、嫁の後追女、両方の近親者、箪笥、長持の順序となり、持物の多少によってちがいはあるが、普通は荷物運びとして婿方から二人、嫁方から四人位出、道のりの約半分位のところまで来ると一休みして長持歌をうたい、嫁方の荷運搬は婿方の荷運び達へ渡すことになる。だんだん婚家に近づくとまた休んで長持歌をうたう。この時近迎が来る。近週は男一人にて荷物さぞ重いであろうと、迎えに行くのである。
長持ち歌には「ハァコレナァハァお長持 受取りまする二度とナァハァ 帰すまいぞ向うのナァハァ 宝によハァ なれ~ナァエー。ハァコレナァ ハァお長持 受取りまする二度とナァハァ-帰えさぬよハァ 親元にナァエー。ハァコレノナァハァお長持よ思うたより重い 金のナァハァ 千両もよハァはいった様だナァエー。ハァ辛苦ナァハァ 尽してよ、育てた子供、今はナァハァ 他人のよハァ手にわたすナァエー。ハァ目出度ナァハァ 物にはよ、くるみの花よ、長くナァハァ 咲いてもよハァ実がまろいナァエー」がある。
一行婿方に到着すれば、中庭の入口で花嫁に酒を饗し、そこから介添人(あいてのぼ)につき添われて、指定の寝室に入る。
着席順は右図の通りである。
床の間には高砂の翁の掛物を飾り、座敷には席順の札をつけて一の膳が備付けてある。酒が三回位つぎ終ると、三々九度の盃事がはじまる。これは三つ組盃二組を本家の指図により婿方の両親に各一組宛を配す。婿方の父から本家または座頭に、右二種の盃は本家及び座頭より仲人夫妻に、仲人夫妻より花婿に、花婿より花嫁に、その後は当日の来客両方より廻すのである。
本膳には、往時猫足膳の黒塗物が使用されたが、その後朱膳・朱椀が用いられた。本宴の本膳には二の膳が添えられる。
本膳の内容は、飯付、一の汁(醤油汁で豆腐とカキ等)、二の汁(豆腐四分の一に魚の切身にねぎ等の醤油)、五寸(さがかたいの大身)、皿(さけの切身)、小皿は数の子・豆類・たこ・青物等の三・五・七種頬、酢の物(きゅうりとほや等)、にやこ(煮合せであまに、にんじん・いも・れんこん・きの子・竹の子・牛蒡等五色か七色)、さしみ(まぐろ)等である。
二の膳は、二の椀(魚の切身、葱かせり等)、大(だい)引(鮭一本か赤魚三本、または木綿一反位)、壷(とろろ)、お茶椀(ほたて、やきふ、椎茸、春さめ)等になっている。
その外にロとりとしてかまぼこ類がつく。さらに「しちりぶた」といって五色、七あるいは九色の御馳走も出るが余裕のある家である。
婚儀の献立にはすべて蕎麦、麺類のように切ったものを使うことは忌まれている。
口取、しちりぶたが出ると嫁は里方の紋付に着換えお酌をする。
最後に至って、高砂の爺婆、鶴亀松竹梅を配した蓬莱山の島台を出し、招者人は謡曲「所は高砂の尾上の松も年古りて、老の波も寄り来るや、木の下蔭に落葉かく、なお何時までか生きの松、是も久しき名所かな」など歌い、引続き「御祝」と称する歌をうたうを普通とする。「御祝は繁ければ、おんつぼの松もそよめく」のごとく歌い終ると「ゆるゆるとお控えなされ土佐の舟の着くまでも」が出、後思い思いの目出度い歌が出、夜のふけるのも忘れて祝宴が続くのである。盃のやりとりには決して返すということばを使用せず「差上げます」「頂戴いたします」と気を使った。
婚礼祝いのあった翌日、第二次披露宴を催うし、前日招待しなかった、親しい知人、新郎の友人等を招待する。料理は前日より簡素であるが、酒もりは却って当日より盛大で、酒量も多く消費された。これを「朝めし」とか「コガアレェ」とも称した。泊客には朝めしであるが、新来客には婚礼用に準備した酒造桶の酒を飲んで、その桶洗いを手伝って欲しいとの意味の招待語で「コガ」は酒桶のことである。
最近は盛岡を会場にして式及び披露の宴が行われるようになる。
い 婚礼と慣習
ア 式見
嫁を見ようとして仕事を早目に片づけて行列の来るのを待受け、行列と共にその家までついて行き、座敷の縁側に入りこんで、式が終るまで見物をするのである。これをスキミと称し、当事者は見物人に酒をふるまうのである。しかもその人数の多いのを誇りとしている。
イ 樽投
焼麩に葦を通し、麩々中葦(夫婦仲よし)の意を込め、または末広を表す扇を添えて、樽に酒半分を入れ、長い竿の先に樽を結びつけ、お祝最中に座敷の真中に投込むのである。これに対して、直ちに受酒を二倍にして返すのである。
ウ 式後の慣習
(一) 床入
媒妁人は新郎新婦の床入までを以て媒妁の責任として世話をなしたるも近来は余り立入らず。
(二) 式後の披露
結婚当日は親類、その翌日は知人、その翌日は花婿の友人、四日目は下僕、女中等の順序に招待してお祝いをなす。
(三) 里帰り
結婚式の翌日若しくは翌々日、新夫婦相携えて、清酒一樽、肴一折を配偶者の実家に持参して謝礼をなす。
(四) 媒妁人への礼
嫁の里帰りの次の日、嫁が一人で酒一升に手土産持参で礼をなし、その外正月の年始をもなす。
(五) 舅礼
結婚後三年間、旧正月一日乃至二日、及び十五日乃至十六日の両度鏡餅五枚、塩鮭二尾、清酒一樽(通常三升)、白米若干(通常二升)宛を携え、配偶者を伴って嫁の実家に謝礼をなす。これを舅礼、若しくは正月礼と称す。なお、五月の節句と盆にも酒一升に手土産持参で礼に行くのである。
(六) 春団子と秋餅
夫婦は嫁の実家から春と秋招待される慣習がある。春の招待を春団子、秋をば秋餅と称して歓待を受けるのである。
う 出生祝
ア 出産慣行
妊娠をし、やがて「つわり」になる。それを「クシェヤミ」といっている。五ヵ月目の犬の日には腹帯をなす。初産であれば里方の母を招待し、お赤飯を作り産婆を呼び腹帯をなし祝ってやるのが例であるが、経産婦はこの限りにあらず。妊婦が比較的苦しそうな場合は男であるという。
性別の予知としていい伝えられていることは、妊婦の後から呼びかけ、妊婦が右方からふりかえれば女の子、左からふりかえれば男の子が生れるとか、また、母が妊娠したとき一番小さい子にへラと杓子をおいてどちらを取るかを見、へラを取れば必ず男の子、杓子は女の子が生れるとか、または、一番小さい子の太股の付根の皺を後から見皺が一つなれば次に生れる子は男で、二つの場合は女の子が生れるといわれている。
また禁忌についてはこんなのがある。
女が菷をまたげば難産するし、男をはねても同様である。妊婦が南瓜をたくさん食べると、胎盤が大きくなって難産をする。妊婦が兎肉を食べると三ツ口の子が生れる。鉄瓶や片口のような口のある器物の口から吸うと三ツ口の子が生れる。妊婦が臼に腰掛けると包茎の男の子が生れる。旧暦の正月・五月・九月・十一月の三日・十七日・二十三日には鬼子が生れるといってこの日の出産を嫌う等がある。
産気づいた妊婦を床につかせ、産婆(コナサシェ)を招寄せ、生母に通知し、立合で出産させるが座った姿勢が多かった。かますや俵で周囲をかこむか、藁等を利用した、枕と称する肩の高さの大束のものに、産婦を背後と両側面から寄りかからせるかである。山の神様や子安地蔵様にも灯明をあげその加護で安産するよう拝んだりするが、山の作業に働く男は産室に入ってはいけないといわれている。余り産婦が苦しむときは後から腰抱きと称し、抱きかかえる様にして助け、産み終ってからも悪血が下さないといって枕を三尺も高くし膝を曲げさせて寝せるのが古来からの習慣であった。
産湯は古来乾葉湯、白米のとぎ水を温めて使用した。
エナ(胎盤)または後産の処置は普通便所の土台の下に埋めている。臍をば繃帯し、一週間位で剥(はく)離されたものをへソの緒と称し、大切に保存し、その子のお守にしている。
分娩すると、クルミや鶏卵を与えたりする。産婦への食事は、白米粥に味噌漬大根や梅漬であるが、寒晒し粉をといて与えたりもする。日を経るに従って、白米食を普通に与える。
イ 肥立(ひだち)祝い
三日湯と六日目には赤坊にお湯を使わせ産婆に出産の労をねぎらう意味で酒肴をふるまう。七日目の一枕下げのお祝いのとき産婆はお祝いとして子供に名を贈る。とりあげ礼として昭和十五年ごろは三・四円出している。稀に二十一日間隔日または三日隔位に産婆を招いて子供に湯を使わせる家もあるが、普通は一枕下げで切上げてしまう。一枕もとれたころから親類、隣り、近所から産婦に適当な食物として白煎餅持参で見舞に来る。七日目を一枕、二週間目を二枕、三週間目を三枕と称し、枕を撤去する。これを枕あげと称し、内輪の祝いとし、三枕が終ると産婦は、床を離れ屋内の軽い作業に従事するが、冷水に手足を入れることは禁じられている。またこんな事もいわれたのである。日数のくれない産婦に近より田畑に出て働けば、作物が悪くなると言い伝えられているところから日数が立ってから見舞するようになったといわれている。
肥立が順調であると、孫祝いと肥立祝いが枕のうちに行われる。
ウ 孫祝い
孫祝いは、一面初産婦の出産祝いでもある。普通その家の息子の新嫁が出産した際、その肥立を見計って行う祝儀で、男児であろうと、女児であろうと、区別なく行われる風があった。初生児が女児で、次に男児が生れると、家督が生れたと称して喜び、改めて祝うところもあった。一週二週と産婦の身体が健康体になって行くことを肥立がよいと称し、三枕から起き立つこと、歩行すること、縫い針程度の軽い労務は差支ないとされており、三枕中は自分の床の中にいて、食事を給仕してもらう。その食事の給仕は産婦扱いで、女性がこれに当っていた。産婦は最低三十日を休養し、その休養中に出産祝い、孫祝いには産婆を始め本家親類が招かれる。実家よりは産着、ねんねこ、「フタデコ」、帽子、胸掛まで一揃いを贈り、祖父母も産着一重ね、親類は産着にする反物を持参して招きに応ずるのである。
お祝いの席順の女座は本家、近親がつづき、下座は産婆に孫であり男座の上は嫁の里親、近親、下座は知人となっている。
孫の出生祝いがすむと姑が嫁につきそい、初孫をつれて嫁の実家に送って行く。嫁が実家に帰って休養するためである。これを肥立休みとも称している。姑に代って嫁の亭主が送って行くこともある。そのとき、酒樽や肴、土産などを持参するが、里に暫時の間保養を依頼する意味が含まれている。期間は十日から二週間程度、それがすむと嫁の生母がつき添うて送り返す。その都度軽い祝いがあり、有合せの御馳走がつくられる。
エ 宮詣り
三十三日目に産土様へお詣りをするといって、氏神様へ子供を背負って参詣をする。外出を初めてさせるときは、魔除けと称して、子供の顔にチョット墨をつける風習があった。
オ その他の行事
出生後男児は百十日、女児は百日になると、「食い初め」と称して祝うのである。尾頭の魚をつけ膳立し、神棚にも供え、家族一同揃った食膳にその子供の分もこしらえてあてがい、ごはん粒を三粒食べさせる。家中よろこびあい、ひたすら子の成長を祝うのである。
出生後満一年の誕生日前に、丈夫な子供は立って歩くようになる。「ムガレドギ」というが、誕生日にこうした子供があれば特に一升餅を搗いて丸め、風呂敷に包んで背負わせて歩かせるのである。もし、ころばずに歩いたときは、わざと側から突いてころはすようにしている。この餅を「立ったら餅」といっている。また、この「立ったら餅」を投げつけてころばすところもある。
胎内にあること同一年の場合は一年児といい、胎内で越年し、二カ年にまたがった場合は二年児といっている。
え 厄年祝い
厄年、男は十五・十九・二十五・四十二・六十一(あるいは六十二)で、女は十三・三十三・三十七・四十五等となっているが、最も人生生活の変転期に当る厄年は男四十二・女三十三とされている。この年に、親類や知人、その家の出身者や子孫、兄弟姉妹等の一親等を招待し、酒食を饗して祝宴を張り、これをもって「厄払い」としている。餅をつき、酒を供え、厄年のものを主賓として座席を組み、祝宴にうつる。個人対象の祝いとしては珍しい。
招待された人は酒一升に金子若干を添えて祝いとする。
この厄被いの祝いは、二月正月と称せられている。すなわち、二月一日から三日までの間に実施されるが、二月二日は特に多かった。
厄被い祝儀の場合は、個人対象の祝いであるから、父子・兄弟姉妹・近親者と当人の親友が中心となる故、婚礼や葬儀のように一戸一人宛が配列の膳に着席すると異なり、参会者全員着席するのが特例である。
お 葬儀
ア 葬前
(一) 死亡通知
人が死ぬと北枕にし逆さ屏風を立て胸に手を組ませ仰臥させる。また、死人の枕もとに香をたき、死花を立てる。葬式については宗旨によって異なるが、本村においてながらく行われた行事は、次の通りである。
知らせの一番先は本家、次は嫁婿の実家・兄弟・子供・近親で、これらの人々によって、葬儀の日取、通知先の範囲、法要、膳部の調理等について相談の上決定をする。菩提寺への通知、親類への通知平素相互に手伝い助け合っている村方への通知をそれぞれ分担をする。その死亡通知を「報知(すらしえ)」といい、一人で使者になることを不吉とし、男性二人宛を出している。一人であれば魔にあって頓死することがあるから、その使いを果し得ないので、二人と伝えられている。報知の使いを依頼した人には、酒肴を副え食事を出して、その労を謝するが無報酬で手伝う。
(二) 死者の処置
死者生前の知己、及び臨終に間に合わなかった人には、死水(半紙に水をふくませて口唇を拭くこと)をとらせる。
次に目・口を閉じさせて北枕に寝せ、合掌させ、顔に白布をかけておく。枕もとに机か台の上に線香一本・花一本・水・灯明一本・洗米等を供える。次には一杯飯を供える。一杯飯は碗に一杯の米を炊き、三つの小さな握飯を作り、残ったもの全部一つの碗に盛り、碗の真中に箸を一膳真直に立て一枚の紙を三角に折畳み三角の頂点が上になるように碗に巻付け三角を前方に向けて供える。死人の側には決して猫を近づけない。
(三) 入棺
棺桶はむらびとの奉仕によって作られる。棺桶が出来れば入棺(にっかん)をする。入棺に当る人は兄弟のうち一人と子供二人がこれに当るが、該当者がない場合は近親者がこれに代る。人が揃うと、三人が縄帯・縄襷にし、他人と死者を清めるための水汲みに出る。家人声高く三回その名をせきたてて呼び寄せ、呼ばれた者も声高に返事を三回なし、帰りを待って盥にその水を入れる。その後水に湯を汲み入れる。このときのヒシャクの使い方は普通のときと逆で、さかさ水・さかさシィヤグといい、平常このような使方をすることを忌む。清めの水の用意が出れば、三合酒を三人が独酌で三回飲み塩をなめる。次に死人を盥に入れて洗い清める。男なら散髪をし、女なら化粧をさせるのである。
死者の装束は全部白着用である。順序は足袋・脚絆・うでさし・手甲・白衣(経(きょう)帷子)を着せて帯をしめさせ、頭に白の三角、最後に白頭巾を被せる。これらは近親の人々で新調する。銭六文と穀物入れの袋を持たせる。手を合わさせ珠数を受けさせる。
入棺の前後には念仏を唱える。
棺は通常竪棺の御輿形で(人夫四人で担う。この人夫を六尺という。六尺は近親の者でなす)、座棺である。予め死人の膝を折曲げてあるからそのまま座らせ、紙袋に糠を入れて作り、死人が動かぬ様に周りにつめ込み、姿勢を整え、膝の上に鏡を立て合掌に珠数をかけさせ、前に一杯飯の時用意しておいたお握り一つは「ソズガのバサマ(三途河(しょうずか)の婆(ばば))」への土産、二つは犬に吠えられたときの用意にとて持たせる。その外におかね米といって碗の糸底で二石一斗一升三合を量り、お握りと同じ袋に入れて持たせる。棺の中には草鞋一足半、下駄一足、菅笠、うつぎの杖等を入れる。忘れ物のないようにと注意し、全部用意がすめば棺に釘を打ち頭に当る方へ三角の紙を貼る。
夜詰は仏の供養と死なれた家人の淋しさを慰めるために、葬儀出発前及び葬儀後七日忌明まで毎晩行う。集る者は近親者はもちろん、知己・近所の人々が寄集って念仏をする。念仏後、午後十時ごろになると、一同に膳を据え、酒や素麺等精進料理の夜食をふるまうのである。
イ 葬儀
村内の人々の奉仕で御飾りを作り葬具運び、穴掘り、縄、草鞋等を作る。穴掘りは三人で三尺四方四・五尺の深さに掘る。穴掘りには穴掘り酒といって、酒一升に赤飯等を饗す。
出棺一時間前に僧侶を招き近親者と共にオチツキといい、僧侶を主賓として近親その他の人々に膳が出る。以前は黒膳、黒椀が使われ、吸物・小皿・五寸三つ盛の皿・飯・汁でそれに少量の酒が出、素麺を食べ、棺を真中にして大数珠で大円を作り、親類一同念仏をする。それは南無阿弥陀仏の音頭とりと鐘打ちにより三十三回数珠をまわす。その間僧侶は読経をなす。
行列出発に先立ち六堂アカシを家の前につける。六堂アカシは竹六本にローソクをつけたものである。また仮門を葦(よし)三本でコの字形に門を作り家の前に立てておく。
行列であるが、屋外に藁を円形に敷き、その上を三回廻り、後棺を中央におき読経及び焼香をし、菩提寺に墓地がある場合は本葬後埋没し、ない場合は自宅本葬後、墓地に埋葬し、後菩提寺詣りをする。
葬列が寺若しくは斎場に向う途中、世のため、人のための布施の意味で、米と銭を振りまくのが常である。列順はだいたい一列で、ローソク・台・灯籠・赤旗二・日月・大蓮花(ひらき・つぼみ)二・龍四(緑・白・赤・黒・青・黄・赤・白)・花二・煎餅・干菓子・団子・盛花二・お茶二・ローソク二・香ろう・死花・写真・野飯・位牌・先綱・棺・後綱・側に黒龍・線綱・死木・消灯龍の順序になる。
ガンコの中を通した一反の漂木綿の前先を先綱といい本家が持ち、ガンコの前に立って歩き、後の方は子や近親者が二列になって布に手をふれながらガンコに従う。ガンコの側にはザイ米撒がつき添い念仏を唱え、ガンコの屋根にザイ米を撒き、死人に一々途中の説明を生ける人に話すようにして(死者の思い出を呼びおこす親しい人の家や場所等)寺に到着をする。ガンコ担ぎの六尺は死者の孫甥に当る近親者四人が草鞋ばきでこれに当る。
昔死人が生前使用した器物を焼却したように、出棺と同時に使用したものを破棄焼却をする。
禁忌については、妊娠者は夫婦共、死者の処置、または葬式参列を忌むとか、葬儀参列者は途中決して後をふりかえってはならないとか、悔人に対ししては送りをしないし、またおいで下さいとか、悔みに行った人が、また上がります等の言葉を使ってはならないとか、葬儀に参加した人、悔みに行った人は一週間位田畑に出ることを忌むとか、近親者に死人が出た場合百ヵ日前にお宮に行けば必ず不吉なことがあるといって参拝を控える等がある。
部落民は農繁期といえども葬儀当日は一家より必ず一人は奉仕し、またおくやみとして米一升、昭和の始め弐拾銭位持参して協力をした。受ける方は一人一人に酒と赤飯一包をふるまう風があった。
ウ 墓地
土葬の場合穴の中に死人が後向き、または倒れぬように正しく入れ、その上に地極穐・草鞋・笠及び杖を入れ土を盛り上げる。墓標に三本、木を結び鎌の柄をさし立てる。鎌を立てることは、古来新墓を狼が山から下りて一夜の中に掘りかえしたところから、狼をさけるためになされたといい伝えられている。墓標は三十五日目か一周忌等に石碑をたてる。
放香には濡米をまき、お茶を注ぎ、ローソクを灯し、線香とお花を銘々たて、親等(しんとう)の順序に焼香をする。
エ 葬後
埋葬帰りは門口で、用意してある塩をまき身体を清め、手とロを洗い全身を清めてのち家の中に入る。留守宅では葬儀参加者の帰宅の時刻前に炭火・塩・水を揃え門口に出しておく。
死んだ日から一週間の中は親演家人共に朝は焼香、夕方は焚火の墓詣りをなし、夜は念仏をする。
忌あけの座席順は仏者に対する親等によるもので、ひどく厳格に詮議されて決められる。献立も資産に応じて上下の別がある。一例は次のようである。
本膳には、飯、汁(こんにゃく・豆腐・大根・人参・油揚の細々汁・味噌)、つぼ(油揚・こんにゃく・人参・椎茸)、五寸(牛蒡・人参・油揚・椎茸)、皿(大根・天ぷら・きのこ・よせもの・羨煉)<五ツ盛という>がつく。
二の膳には、にの椀(麩・椎茸・こんにゃく)、つけあげ(油揚もの三種)、ちょく(菓子小型のもの)、菓子(落雁五枚)、盆(饅頭三箇または雪餅三箇)がつく。
酒は本膳の時に用いる。
法要は普通七日目に行うが、五日目または三日目、あるいは葬式の当日行うこともある。
その後二過日、三週目、四・五週目、四十九日、百ヵ日、一年、三年、七年、十三年、十七年、二十三年、三十三年には仏書きといって法事をし、僧侶を案内して膳をこしらえ親戚を招待して行われる。料理は凡て精進料理で魚類を全然用いていない。さらに団子はつくるけれども餅は作らない。切麦・切蕎麦を使う。ただ祝事でないのに赤飯を用いることは他地方と異る。
三十五日と四十九日に巫女を招き近親集い「クチヨセ」といって仏の代りに語らしめている。
新仏のある家では、初盆といい、その年のお盆に寺へ灯龍を飾ったり家にイタコを招き口寄せをし親類を集め仏の言葉として慎しみきくのである。
なお、イタコの言葉に戸主を弓取り、妻をへらとり、子供を目下、残った妻をば愛の枕の弓取り、残った夫は愛の枕の弓取り、目上の人を百万様という。
藩政時代における百姓の野辺送りは台笠をつけることが出来なかったといわれる。台笠をつけることはむずかしいことではないが、その後の七日の焼香墓参に馳走しなければならない定めになっており、その方が経済的に行うことが出来なかったので、ブラリにして野辺送りを終えたということである。
神葬祭では、仏教のような精進料理ではなく、魚類を不(ふん)断に使用しての晴食である。死んだ故人は人間の世から神に移動し、その招魂はすでに神様を慰める祭祀であるとの意味であろう。降神・昇神をなし、柏手で礼拝し、酒肴をもって直会(なおらい)にのぞみ、五十年条・百年祭も行われることになる。柏手といっても、この時は音なしである。
3 その他の祝い
あ 普請祝い
家屋の新築・増築・屋根替等の場合は近親・知己の人々手伝人として互いに出動するはもちろん、茅・木材・縄等をも互いに持寄って補助をなし、落成の日には酒を御祝いとして送りスミヤドコといって盛んに酒宴を催した。
い 早苗振(さなぶり)
毎年田植えの終了後、早苗振といって田植え組の人々が集って酒宴を催し、田植え中の労苦を慰め豊作を祝う。会場は結いの人々交番に行う。
う 田植祝い
田植え踊りを始めると毎年旧正月十五日の夜、田植え祝いといって、田植え組の人々が集。酒宴を催し、当年の豊年を祈る。会場はその組の人々交番に行う。
え 秋餅
毎年秋期農作物の取入れ後秋餅といって、近親知己手伝い人等を招待して餅及び酒肴を振るまう。
お 釜祝
毎年麻糸調製後釜祝いといって人々集り酒宴を催す。会場は人々交番に行うを例としている。
か 寄合酒
一般的ではないが、毎年春秋の二季に部落ごとに各戸で米五合乃至一升及び酒代を持寄って酒宴を開く。これは部落民の親睦を図ることと且重要な相談事をする。会場は大きな家の持ちまわりが多い。
き おわりに
細越広人氏は『研究紀要』第五号の「山村の生活」の中で、次のように指摘している。
「同族社会的な村の構成は他の社会との交渉が余り行われず、そのために余計部落内での交渉が緊密に行われ、それを遵守することが要求されて来るという結果になっていることを知ることが出来ると思われる。
行動半径の狭い封鎖的な生活は外界からの知識の必要が余り意識させなかったであろうし、知識の不足が一層封鎖的な生活を助長し、この悪循環の中にあって、交際費がかさみ、交際が飲食を伴い、飲食が唯一の娯楽に通じたものであろう。」
4 救荒食
「春は火事、夏はすずしく、秋出水、冬はききんとかねて知るべし」という歌もあるように、昔からききんは東北に多かった。南部氏が盛岡築城より明治維新までの二百五十年間に七十二回、その中、ひどいもの凡そ四十回、このひどかったものだけで六年に一回の割である。さらに明治元年(1868年)から昭和九年(1934年)までの六十七年間に八回の凶作があった。凡そ八年に一回の割である。明治以前の封建体制下にあっては他藩は国外であるから、その国が食料不足になると餓死者が出たのである。
天明の凶作の状況が『動転愁記』に、下のごとく記されている。
盛岡御家中四戸覚右衛門殿知行三戸在にて、実子二人食殺し侯女これあり、捕人遣わせられ侯ところ山に駆け入り、漸く尋ねさがし鉄砲にて打留め候由。
何処の女にて候や、早瀬川原へ七・八歳の娘を召連れ、石を枕にさせ、初めは髪の虫など取りくれ候ていに見え候ところ、手ごろの石を振り上げ力に任せて頭を一打うち付ければ、わっと泣出し、以来は喰いたい喰いたいと言わぬ故ゆるせゆるせと詫びすれども、めった打に頭を微塵に打ひしぎ、息絶えもせぬに川に押入れ、その身は目をすりながら行方知らずになり侯。諸人見聞の人落涙せぬはなし。
これらの凶作の原因は冷害・霜害・作物の病害等であり、その中冷害がその最たるものであった。これらの原因が二重三重になることが多く、しかも、二年、三年と続くことがあったから大凶作となり、「死屍累々川をせきとむ」の惨状を屡々出現したのである。従って農民はこの凶作に対応して生きぬくため、次のような予知についての俗言を残し、救荒食物を準備しなければならなかった。
それは、古籾・古稗の貯蔵の外に、寒中に大根を刻んで乾燥したカンピョウを貯蔵した。貯蔵の方法は、セイロという大きな箱の中か、藁俵や叺に詰めてマゲに積み、虫をさけながら貯蔵するのであった。梁上(まげ)は焚火の煙によって害虫を駆除したのである。これらの食物は栄養価は問題でなく、食べて害がない程度の粗末なものであった。
天保四年(1833年)の救荒食物に「わらび・牛蒡葉・ところ・かれ芥(からし)・うるい・松の皮」などが掲げられている。次に主食として用いたもの、山菜、その他食用とされたものを記すことにする。
とちの実であるが、これは救荒食物の重要なもので、水づけして干すと、何十年貯蔵しても虫がつくことなく、また変質がなく豊年にこれを拾い集めて貯え、凶作時に食べたものである。従って宅地にも植えたが、山にあるものについても、官民ともに保護を加えて育てたのでいたるところにあり、拾うことが出来た。これを食べるには、そのままを水づけにして皮をとりさり、水ごしして後木灰の上ずみの水を加えて一、二日放置するとにが味がなくなるが、その後二、三日水がえをして煮て食べる。
しだみをどんぐりともいい、楢の木の実である。そのままでは渋くて苦く食べられないが、皮をとり去り、木灰の上ずみ水、またはソーダを加えて煮て清水にさらし、あくをぬくと食べられる。簡単な方法としては、皮をとり実を細かく砕いて幾度も水を替えて煮水にさらして食べる。食べ方は小麦粉等を混ぜて団子にしたり、小豆等と一緒にして餡(あん)にもする。独特の風味のあるもので嗜好食品としても賞美される。
わらびの花またはわらびの根花はわらびの地下茎の澱粉である。これは盛夏の外は年中ほられるし、肥えたわらびより瘠せたわらびの方から「ハナ」が多く採れると言われて、瘠せたわらびのある山にわらび掘りが集った。掘る道具は鍵・鍬があった。『菅沼藤左衛門扣書』によると、天保五年(1834年)五月朔日のころに「毎日山山江小屋懸わらび掘能キ働キ者一日分四十盃不働者ハ十四・五盃、女子も子供も花掘りこ相出何れかセき次第云々」とある。何盃とは木椀でのことであろうが、古老の談によると、「明治三十五年(1902年)の凶作には一人で二駄位掘った。一駄というのは四把である」といっている。この掘ったわらびの根を「くまさらい」という木製で巾七・八寸位の熊手で掻きまわしながら洗って土をおとし、これを径二寸五分位の藁打ち槌のような木槌で打ちつぶす。この方法にはわらび石と厚板を使う場合がある。「わらび石」は、内庭の片隅に据えられた石で、ここで打ちつぶすのであるが、厚板の場合は持ち運びが自由なので、家族中で打ちつぶす場合には外庭に持ち出されて作業が行われる。荒つぶしがすむと、麺棒をもって打つ。麺棒はイタヤ・ヤマ等の堅木で作った長さ三尺位のものである。この場合薄くのばすとわらびの花が出てしまうので、まるめながら打つのである。一晩おく場合には挨がつくので網代をかけておく、また臼でつく家もある。別の方法では最初から水流ししたものを丸太舟の中で打ち潰すところもある。丸太舟とは栃の木等の雑木をくりぬいて作ったもので、この外味噌ふみ等にも使われる。味噌ふみの場合、味噌玉を作るときだけで、塩・麹を混ぜるときには用いない。若し塩けがあれば、根花がどろどろとよらないからである。従って根花をとるために使われる全ての容器に注意が払われたのである。潰されたわらびの根を槽(かいばおけ)に入れ、水を注いで流し出し袋でこし、これを桶などの容器に入れて沈澱させ、出来たのが澱粉、すなわちわらびの花である。これをさらに漂白するには何べんも水替えをする。こうして出来たどろどろの根花を水花という。水を切るには箱などに入れて乾燥するが、灰の上に布片か日本紙をしいてその上におくと水が早く切れる。水花は持ち運びに困難な上保管に困るが、ネモチなどを作ることが出来、量的にいっても、水花八合は乾燥花一升位に相当するから、水花のままが望まれた。根餅というのは、水花であっても、これを湯または水でゆるく煉ったものを鍋に入れ、火にかけて煉り固めたもので、きなこ等をまぶして食べるのであるが、これもない貧家では漬物汁で食べたところもあった。一般にはこれだけでなく米の粉や小麦粉、大根の干葉などが混ぜられた。飢饉の場合には、このわらびの根花も貴重品となり、雑草などの粗悪なものに混じての食糧として重用された。最も、平年に食べても珍味であったので、凶作の時のみならず、量的に多かったから毎年掘られて市場に出されたのである。
大坊直治氏の調査による天保四年の大凶作の糧食として左記のように四十余あげられている。
一、飴のしぼりかす。二、茄荷の茎を干したもの。三、こづき葉共に、(葉芋里芋、干し、糧とした)四、小麦のひきかす(但ししようふをとらぬもの)五、米の糠。六、たんぽぽ。七、沙参(しゃじん)(俗にヌノバといい煮て食べる)八、菖の根をいせて団子とする。九、稲の根を搗いて食べる。十、米の籾糠剪粉(せんこ)として食う。十一、莠(はぐさ)(えのころ草と粟をたべる)十二、女郎花(おみなえし)(根茎共に干煮して糧とする)十三、牛蒡の茎葉。十四、天瓜(からすうり)(根をいせて団子とする)十五、荊蕀葉(いばらの)(若芽をつんでひたしとす)十六、山女(あけび)(あけび花芽を食用とする)十七、山吹の芽。十八、藤の花(菜もあえものにして食う)十九、牡丹芍葉(花をしたして食う)二十、野老(ところ)(根茎をにて食う)二十一、そば葉実を食う。二十二、めのこ(若芽葉を製して糧とする)二十三、南瓜の茎のひたしもの。二十四、商陸(やまごぼう)(山牛蒡をいせて団子にして食う)二十五、くるみの花(あえもの)二十六、つつじの花(あえもの)二十七、草そてつ(葉を春の出初あえて食す)二十八、藻草(よもぎ)(よもぎのあえもの)二十九、蓮の葉(茎根葉を干して煮茎をあえものとす)三十、くこの葉(あえもの)三十一、栃・しだみ(ならの実)。三十二、忍冬(すいかずら)の葉。三十三、うるい。三十四、松の皮。三十五、ぶどうの葉(干し煮て食煮)三十六、胡瓜の葉茎。三十七、すぎな。三十八、夕顔の葉や茎(ひたしものとする)三十九、五加(うこぎ)(浸しもの干して茶にする)四十、あざみ。その外やたがらの粉、小豆からの粉、のぬかご? 枯れ蓬等。
なお、第四編第一章第四節、同編第二章第四節各の凶作を参照せられたい。
四 調理と調味及び清物
1 調理
調理の方法としては、生で食べるもの、焙(あぶ)って食べるもの、煮て食べるものに大別される。
果物や瓜類は別として生食は少ないが、白米や稗の生粉を団子にしオシトギとして供える風があるのみである。殆どは焚火や木炭火にかざして生気(なまぎ)を除いて食べるものと、主食や汁頬のように煮て食べるものが多い。
火にかざして焼くことをアブルという。たとえば肴をあぶる。餅をあぶるが実態である。魚類の干物や塩びき類は加工品であるから、あぶるにしても焼くまでではない。
煮る方法は飯・汁の外に桶に焼石を入れて煮ることや、蕗の葉などに食物を入れて包み土中に埋め、上から火を焚いて蒸し焼きにする原始法が知られている。
主婦は毎日の食事の外に酒、味噌、精白、納豆、豆腐、醤油、漬物を作らなければならなかった。よく農村において調理講習が行われるとき、農村の調理が単純で栄養を無視しているという非難をきくが、農村の調理は実は味噌、醤油、豆腐、納豆、殊に米麦を粉に挽くことそれ自体が調理であったのだ。生の米麦の粉で何か作る前に粉にすることが主婦の大きな辛い労働であり、調理だったのであると『岩手を作る人々』上巻の「主婦と家風」に述べてある。
2 調味
あ 塩
往古調味料といえば塩一色であった。これは加里分を多量に含む植物性食品に偏しているための自然の要求であると思われる。
ことに海辺より遠い本村においては流したり捨てたりしないのが原則で、漬物をつけ込んだときに上がる塩水でわらびの花の味をとったり、別の桶に保存しておいて、味噌作りのときの塩に使ったり、野菜を煮たり、牛馬の飼料にするなど極めて大切に扱ったものである。
終戦後塩一升に米一升という交換率があったが、これは藩政時代からいいならわせられてきたことであった。
飢饉に人が死ぬのは、塩の有無によるといわれ、塩を買うことは健康を買うことであった。
い 味噌の利用
調味料としての味噌の利用範囲は、日常生活の味噌汁を始めとして、最重要な必需品であって、同一の方法でつくっても、各戸とも悉く味を異にするといわれるほどである。醤油の利用者は都市に偏していて、村方にはあまり普及されていなかった。これは醤油を利用することが出来ない生活状態であった。農家の冠婚葬祭のときは味噌からスマス液を臨時に製造して用いた。味噌を水に解かして煮、それを麻袋で絞りとり、その液を桶に入れて沈澱物を分離し、上部の透明分の液を利用するのである。透明度・色合・味共は醤油と区別が出来ないものもあった。従って、いずれの家にもスマス台とスマス桶とスマス袋があった。スマス台は洗面器に似て底に小穴のある木製品である。木彫りの大皿に穴をあけた用具である。スマス液を受ける桶は、縁に手のないものであれば、間に合ったが、スマス袋は無染の麻布(ぬの)が用いられた。一幅ものを合わせてつくるので、二幅の大口の袋となった。この袋に味噌を入れ、絞って醤油としたのである。この代用醤油のスマス液は、目濾しをして一番スマスとなし、これを重視し、再度煮て絞った液を二番スマスといって雑用にする風があった。一級品・並品の区別になる。
味噌ごがの中味の一方に小穴をあけ、そこから味噌液を汲みとることがあった。これを味噌の「たまりこ」ともいい、最重要の調味液として貴重視した。味噌漬大根も貴重な調味料で、産婦・病人・昼食の握り飯の中味に利用されていた。
う 甘味
甘味の砂糖が生産されず、輸入品であって、南蛮貿易を通してキリシタンに伴う文物の一つである。砂糖は都市以外には普及されなかった。最も多く用いられたのは小豆で農家の常用作物であった。今日でも農家では小豆餅が出ることによって晴食と心得ており、祭祀行事にも、冠婚葬祭にも使われている現状である。葬儀の荷役の赤飯を菓子といい、夜食赤飯を夜菓子とさえ呼んでいる。甘味として使われた小豆は古くから用いられていたのである。
麦糀を利用して飴を作ったり、炒り米や、大豆粉を応用して、アメ・オコシ・タンキリ類の菓子になった。
その他、アマドコロ・蜜蜂の飴・大豆の煮液なども甘味料として利用された。
甘味と酸味を兼ねるものに野生葡萄があった。大粒のぶどうを採取し、その甘味の厚い粒を桶に漬けおくと、自然酸酵して、紅色の葡萄酒が出来ることを知っていた。
え その他
酒は調味料といえないが、甘酒・白酒・清酒・濁酒の粕は調理に多く用いられ、肴頬の粕漬は並品以上の高級品であった。
酢は売品の外は知られていない村方では稀にしか使用しなかった。酸味としては魚類の鮨(すし)漬が自然に酸味を呈し、漬物類も同様であった。冠婚葬祭時には酢のもの調理は少なかった。
油類とクルミの利用については省略をする。
3 漬物
今日ではどんな漬物でも食料品店で販売しているが、昔はなかなか漬物についてはやかましく、その味わいは家風でもあり、その家の個性でもあった。従って、新嫁がその家の味を仕込まれるのであるが、姑からその要領を教わり、主婦となってからも、季節の漬物を間違いなく仕込むことに、常に心遣いを怠らなかった。
もともと、漬物は野菜を長期に保存する手段として発明されたものである。
山菜のワラビ・ゼンマイ・フキ・ミズ・ウルイ・竹の子・きのこのあみのめ・落葉・畑作の大根・ニンジン・ゴボウ・瓜類・ナス・タカナ・ヘラナ・山東菜・白菜・甘藍等、これに野生のもの。畑作ものに季節があるので、年中食膳にだすことが出来なかった。従って塩漬にして貯蔵し、長い冬期間の重要な副食の一つであった。
魚類の塩漬等は滅多に食べるものでなく、正月や節句等の年中行事のハレ食であった。これに比べる野菜類の漬物は四季を問わず食膳に供することが出来るので、長期間保たせる塩づけが発明されたのである。そこで塩がいかに大切であるかが問題になる。大釜の沼袋に塩の森という地名がある。ここで塩が購入されたのであろう。
この野菜の塩漬が、特別な風味を帯びるようになり、その家の工夫の積み上げによって、前年秋に漬けた野菜を、翌年の秋まで食べられるように、その時々によって分量の少ない野菜に、塩の外米糠か糠味噌等による当座漬け、分量のやゝ多い浅漬け、年を越す分量の多い囲い漬け等計画的に漬けこまれ、消費されたのである。
漬物は蔬菜の塩漬けに止らず、多量の米糠をまぜて、醗酵させながら色あいのよい沢庵和尚の発明にかかる沢庵漬は、漬物の歴史にとって革命的なことであった。
作業時の一升入ワッパの弁当のおかずには、梅漬とか、大根の味噌漬とか、味噌そのもの等、一種類入れられて持参したのである。
後には塩のみでなしに、酢・酒粕・焼酎を利用し、色々な野菜の外にニシン等の魚頬や麹等いろいろ工夫され、糠味噌くさい女房といわれるほど、主婦は漬物に精を出したのである。この漬物は、毎日の三度々々の食事に欠かすことが出来なかったし三食以外のお茶飲み時、来客のときなどの食べものには必ず自慢げに出されたのである。
第十六節 衣服
一 藩政時代の衣料価格
木綿の移入はすでに慶長(1596-1615年)のころで、そのとき砂金と木綿四反と交換したというから高価であった。天和(1681-84年)のころは一反一貫二百五十文で、元禄十二年(1699年)ごろは上染一反五百文であった。
盛岡の商人村井甚助の書き残した『勘定考弁記』によると、宝暦十年(1760年)ごろの盛岡における労働賃銀と諸物価が記されている。それによると、日雇は一日五十文、飛脚に雇われた場合は百文であったという。物価は白米は一石二貫文とあり一升二十文となる。塩一升は二十二文で、白米一升より一割方高いが、盛岡地方では白米一升は塩一升と交換される例は後世まであった。
衣料関係の反物は、京阪地方から移入されてきているせいもあって、都茜(あかね)一反は四百八十文で最低、その他は五百五十文以上、中には七百文のものもあった。七百文の綿布一反を購入するには、日雇の者なら十四日の労働に値し、職人でも七日間の労賃に値した(石工は二百文、大工、木挽は一日百文が定法であり、上大工は百二十文の定めはあるが極めて稀であるという。旦展賃銀の二倍、白米五升というのが職人一日の賃銀)。また、白米と交換するには、白米三斗五升で綿布一反という計算になる。木炭十貫目は二百五十文の相場とある。五貫目俵の木炭なら五俵を売って綿布買入ができることとなる。以上のごとく衣料綿布一反を買入れるためには常人は十二日から十四日の労賃、または白米三斗から三斗五升、木炭なら五俵、塩にして三斗を必要とした。
従って、衣料綿布を購入する階層は、富裕な者や上級武士であり、一般農民には容易でなかった。
二 衣服
衣服を着物と同義語とみて大別すれば、和服と洋服になるが、ここでは和服に絞り洋服を除外したのである。
身体に着ける物の中で、頭を被う被り物、足脚につける脛巾(はゞき)・脚絆・足袋・履物・手や腕に当てる腕貫・手甲類・腰にまきつける帯・紐・前掛等はもとより、間接的な物には蓑・合羽等がある。
本村においては、着物を「きかゞり」、「きるもの」、「せんだぐ」といい、「きもの」といえば綿入だけに限られている。
明治の初年ごろまでは、男女共に主婦の作った麻布を用い、ノノカダビラ、またはヌノカダビラ・ヌノコスプリ・ヌノフゴミ等といって単衣・平常衣・股引を着用している。最も藩政時代は木綿着用を許されてはいるが、近世になって近江商人がフルデ(古手)を販売するようになってからである。しかしながら呉服屋を古着屋と呼んだように、新しい反物はそう売れなく、ボロまでも含めた古着であった。
福岡町図書館長の高橋九一氏の論文『雪国の女と麻』の中で、南部藩では、しばしば農民は木綿に限ると達示を出し規制したが、農民は木綿を着るような暮らしが出来なかった。赤児のおしめから、男女の下着、労働着、腰巻、前掛、脚絆、手拭、帯、布団、蚊帳等、身につける物のすべてが麻であり、これが明治の終りごろまで続いた。
一部の階層は明治の中ごろから晴れ着に木綿を着るようになったが、農民の中には大正にはいって初めて木綿の着物を着ている。麻は被服を自給自足するために作付していた。農村では七・八歳のころから麻糸をつむぐ作業をし、七歳になれば七反分、八歳になれば八反分の麻糸をつむいだという。幼少の指先でつむぐことはできないので、ひざの上でやったようだ。この仕事は、秋の農作業が終ってからだった。十三歳ごろになると母や姉に教えられて、はた織りをし、嫁になる十六・七歳までにひとりで働き着を作るように励んだ。嫁入りのときは上流家庭で長持、一般家庭では木びつに働き着三枚、股引二、三枚持参する程度であった。機が織れることが嫁の第一資格で、嫁入道具の第一の物であった。
一家で収穫した麻の数量が、家族の員数に平等に配分されるのが常例であり、収穫された麻は女性によって処理される風があった。それはせんだくの受持ちでその配分を処理するからである。三夫婦十人家族の場合、婆様は爺様と自分の二人分、嬶様は主人と子供二人として自分を加えて四人分、嬶様はそれぞれ子供一人に自分を加えて三人分、嬶に十三歳以上の娘がある場合、独立自習のため一人分を配分されるのである。
「せんだぐ」をするということは、衣服全般を自分の責任において行うことで、水漬け、剥皮、糸拵え、糸縮み、糸おみ、糸撚(よ)り、がわ返し、筬(おさ)がけ、くだとり、機織り、麻布晒し、染上げ、裁縫と進み自分の受持の人員分の衣服の責任をとることで、平常の修理や洗濯も「せんだく」の中に入るのである。
本村でも「せんだぐ」ということばを使用し、農閑期を利用して、嫁は実家に帰って晴衣を作ることを「せんだぐすに行(え)ぐ」といっている。以前は手機を備えていて、冬期はみなどこでも衣服を始め布団までの調製に努めたのである。だから嫁入道具に手機がかくべからざる調度の一つだった。
麻は大正十年(1921年)ごろまで盛んに栽培され、股引・布カダビラ・蚊張等作っていたが年々減少し、昭和の始めごろまで水田作業用の股引にする位栽培されたようである。麻の魅力は木綿と違って、田に入っても水が浸みこまず、茨等にも強く、急に裂けるようなことがなかったから、特に股引だけに、ゴムの長靴が出来る前まで使用されたのである。
麻糸を造るには、晴天の日を選び、麻を根こそぎ引きぬいて根を切り、「葉打ち」を使用して麻の葉を払い除き、多ぐ野外に臨時に窯を築き、小束に束ねた麻を大束とし、縦に立て、三尺に六尺の大桶を被せてむし、後広げて乾燥をする。「白そ」にするものは三晩位、「たゞそ」にするものは一晩位水に浸した後、「たゞそ」は一本ずつ、「白そ」は二・三本ずつ皮をはぐのである。皮の外側についた糸屑を取るには、「おひこ板」の上に乗せて「おひこ」で粕を取り除き夜ざらしにする。白く晒した糸を細くさき、糸をつなぎ合せ、「おぼけ」の中に入れる。紡いだ麻糸を「へそ」に巻き、後紡ぎ車とかけて糸によりをかけ織機(はたす)にかける。製麻の経は綿糸で緯は麻糸である。織機の道具には糸をまきつける「オマキ」があり、織物をしめる「ヒ」(中に糸が入っている)があり、糸が通してある「オサ」があり、糸がもつれたとき使用する「ヒモチダケ」があり、巾を整える「伸子」があり、紡いだ糸をまく「ガワ」があり、木の管に金属の棒が通っている「ツム」等がある。
麻の外にシナの皮をマダといい、作業服や縄、こだし等を作って使っていた。縄やこだしならまだしも、マダ皮の衣服は木綿と比較にならないほど硬く、麻と同じように染付が悪いから、衣服は一般に暗い感じであった。
木綿の特長は暖いこと、水分を吸い易いことである。身体から絶えず汗が出るが、水分をすわない麻は水をはじき出す。冬は寒いが、麻より木綿を喜んだのは、このような特長があったからで、そのうえ肌ざわりもよく、それに染色は自由にできることである。だが、木綿はいたみやすい点があったから、木綿ができても容易にうつれなかった。麻の着物は二代もきられる特長があり、労働する村の人達によって、いくらよいといっても痛みやすい木綿に容易にうつれなかった。つまり村の人達にとって木綿は仕事着でなく、正月や祭り、または儀礼などに用いられる特別のものであった。
染色については、紺屋(大釜に屋号紺屋がある。おそらく明治十年の末ごろ唐糸が入り、紡績工業が盛んになるにつれ、綿屋も紺屋も潰れているから、そのころ廃業したと思われる)を利用している。
衣服は男女共に四種類備え、いわゆる冠婚葬祭・物見遊山の外出着・日常着・労働着とその服装を異にしている。
冠婚葬祭等に着用するものは、トットギとかエッソウヨウとかエッチェラといい、その大部分は結婚の際購入をする。その後多少の補充をなす者があるけれども、着用の回数が少ないため本人一代これを用うるようである。明治十八年(1885年)ごろまで婚礼のときは脇着を用いたとか伝えられている。喪服について禁忌めいた制約があったらしい。
戦後都市と農村との開きがなく、男子より女子の服装が華美に過ぎる。従って結婚衣裳購入のため多額の金を投ずるものも少なくない。一月十五日の成人式の女子の服装は年を追うて贅沢になる。
物見遊山に着用するものをチェットギといい、平常着より体裁のよいものを用い、外出着として用いた物を、着古して家庭の平常着とする。外出着の夏冬を区別して示せば次のようである。
夏の男着はミズカ、コスプリ、モズリ(むじり)、ワッパリ、ハッピ、テッポ、テッポムズリ、ナカミズカ、サスコ、モスギ(股引)から漸次ジャンパー、洋服、乗馬ズボン、ズボンと変化し、女着は袖の細いむじりに股引かフゴミを用い終戦後は洋装か多くなっている。
冬の男着は手製のシャツの上に、綿入みじか、細入むじり、印半天、袷股引、乗馬ズボン、スボンで女着は夏物に綿を入れる程度である。外出時には終戦後とくに和服が多くなり、都市と大差がない。
平常着はフダギといい、膝の辺まで下がる筒袖の左右側下端を約五・六寸位開き、女子用には肩の部分はカダツギ、裾の部分にスソツギといい、別柄の布を着けるもある。年齢によりその種類を異にす。このハギアワセは、ぼろぼろになったありぎれ、ハギアワセるのとは違い、女人の美意識によるもので、郷土的な美しきを持っていた。これをコスブリという。このような上衣を着用し、紺無地の麻布、または木綿の股引を穿つ。これをモスギといい、前と後を六・七寸開いて前後の二つとなし、共に紐をつけて別々に腰に結びつけるのが女子用で、男子用は右側の部分を少し開いて用便をなすに備えている。冬は股引に裏をつけ綿入を重ね着用するを普通とするが、労働する場合は、長衣装にフゴミといい、股引の上部を広めたものをはき、衣服の下部は全部この中に押込むのである。
子供は上張(わっぱ)り・チャンチャンコ(袖なし着物の下着)・メエブリ・洋服。
産着は赤いものか黄色、模様には麻の葉が多く、背中の後襟の下に色糸で水の文字のよう縫いつける。
労働服については、男女共家庭着とほゞ同じてあるが、比較的粗末なものをこれにあてる。
男子は上着にはむじり・みじか・胸当・胸掛・腹掛・肌着(ネルか木綿で製作せる物)等を着用し、下着には脚部の細い股引・乗馬ズボン・半股引・モンぺ式のもの(帯の上からはき、脚部のやゝ太いもの)、ふごみ等を着用し、頭部には手拭・すげ笠・麦稈帽子・風呂敷・モンパ、手にはテッケェス・ウデヌキ・軍手・手袋・足には地下足袋・ゴム靴・草履・草鞋・藁のミゴまたはマダ皮のハバギ・巻脚絆、背中にはケラを着用する。
女子の上着には、ハダギ・チッポコ・ムズリパンチャ・ミズカ・布かたびらに前掛かメェブリを着用し、下着には股引かフゴミを着用し、頭部に手拭・あみ笠・すげ笠・風呂敷・手にはテッケェス・うでぬき・手袋・軍手、足には男子同様ハバギ・脚絆・ツマゴ・草鞋・ゴム靴等である。
田植え時の野良着については、男子もほゞ同様であるが、主として女子の服装を述べるならば、下半身にコスマギをしてその上にモンスギをはき、上半身には、ハダギ・コスプリ・スゴギ・メェブリ、被りものには、手ヌゲ・スハンコ・あみがさ、雨降りはみの・おどこやま、はきものにはあしだか(あしなが)を穿つのである。夏の田の草取りには下半身は田植え時と同じであるが、上半身には「ハダギ」またはハラデ・テッボ・ミズカ・スゴギ・メェブリ・手ぬき、被りものは手ヌゲ・スハンコ・目アデ・あみがさ、日除けに「ひごも」かマダケラを背負い、はきものはあしだかである。
以上の野良着の組合せは無駄なくよく考えられている。すなわち田植時の下半身には、丈の短い腰巻をしめて、その上にモンスギをはく。上半身には肌着の上に袷仕立てのみじかを着、紐帯のしごきでしめ、メェブリをつける。手には手うえ(手甲)をあて、頭にはテヌゲで髪を押えてスハンコをかぶり、その上に飾りをつけた編笠をかぶる。七・八月ごろの田の草取りのときには、みじかは半袖の単衣になる。これをテッポミズカという。二つの腕には「てぬき」をはめるが、泥をかくから「てうえ」をしない。目を保護するために風当をかけ、スハンコにかさは田植えと同じであるが、背中には日除けの「ひごも」をつける。男はメェブリも「ひごも」も着用しない。
森嘉兵衛氏は『岩手を作る人々』のなかで次のように述べている。
「日本の古い服は大体西洋の服装に似ているが、室町時代になると、不断服や晴着がすこぶる悠長な形に変化した。丸で四角な着物である。丸い身体を四角な着物でつゝむ民族はあまりない。この原因は日本は季節風地帯にあって湿気が多いためこういう着物はたしかに衛生的である。然しもっと大切なことは生活の安定のことである。服装というものは大体平和になると、上衣がズボンの上になり、だんだん上衣が長くなる。非常時になると、反対に上衣が短くなってズボンの中に入り、それが極端になると、工人の着る作業着のように上下が一枚にくっついてしまう。日本人の和服が四角な着物になったのは徳川時代の平和な時代からで、上衣が異常に発達したためではないだろうか。」
野外に出て抱えて運ぶ時は、丈一尺八寸位の三巾で作った前当を使用し、木炭・薪等を担うときはケラという藁かマダ皮等で造ったものを用い、その頂の部分をケラクビというがそこには、二寸幅位に矢の羽の形等編み出して、これを飾りとし、特に稲穂の部分のみを取り、これをミゴといい、水に晒して色素を去り、柔らかに打ち、それで頂に色々の模様を編みし、その周囲には葡萄皮をつけ、その外、全部にわたり皮を下げたものをミゴケラといい、旧正月の休日にこれを作り、新妻に着用させることを誉れとする風かあった。
外出防寒用として、古来蓑(みの)という草製のものを用いたが、その後他所行きにはカッパという飛白縞等の地に油紙を入れたものを男女共に着用するに至る。大正の始めごろまで使用したケット(毛布)・モンパ・ドンブグ(綿入むじり)・目出し・雪帽子・昭和の姶めごろまでマント・合羽・トンビ・カブリ(大巾四尺位のフランネル)・女子の脚絆等を身につけ、終戦前までムズリ外套・角巻を着用していたが、現在は男女共外出着にオーバーコート・室内着ハッピ・ワッパリを着用している。育児用には綿入のネンネコ・フタデコ(掛着物)・ハッピ(袖無し)等がある。
森口多里氏は『民俗の四季』の中で手拭の使用法を述べている。
現代のニュースにしばしば現れるのはストやデモのときのハチマキだが、その人たちがハチマキをして集団行動に移ったせつなに、神がかりといっては大げさかもしれないが、ともかく心機一変して、たとえ背広姿でも、事務室や教室にいるときとは全くちがった人格に変わる。けんかをするとき勇ましくネジリハチマキをしたせつなにも、気持ちは一段緊張するらしい。頭に手ぬぐいを巻いてかたく結ぶことが、精神的に常ならぬ変化をもたらすことは、決して珍しい現象ではない。それを利用したのは戦時中の勤労報国隊で、戦後の民主主義時代にそれを適用したのが、背広姿のスト隊やデモ隊であった。
女の人の手拭の使い方に三通りあったと高齢者がいう。即ち、全部の髪をおうて頬かぶりすること、後ろで結ぶこと、前で結ぶことであるが、第三のヒタイの上で結ぶ型は働くときのかぶり方であった。
働くときには前で結び、剣道のときのように後ろで結ぶのは貴族的であって、労働者でないしるしであった。
しかし、ハチマキは決して働くときだけのものではなかった。ハチマキは信仰行事にたずさわるときの重要な身なりでもあった。神楽の天の岩戸開きで舞うウズメノミコトが後ろ結びのハチマキをしているのは、神事舞の姿であった。
田植踊のシヨトメは、手拭を横の方に結んでいるが、それは、働く姿と神霊に奉仕する姿との折衷であろう。
古来四季を問わず男女共に手拭を被り、冬季に至れば、男子はモンパを、女子はスハンコという正方形の布を対角線に沿うて打直し三角形としたものを防寒用として使用した。このスハンコは年齢に応じて色物を用い、大体三十歳位まで自分の好む色を使用している。四十歳以上と男子老人は三巾で接ぎ合せた暗い色の風呂敷を使用していた。その後若者は無帽となり、厳寒には、目出し帽・スキー帽・毛糸帽並に襟巻を使用している。
頭髪については、明治十八年(1885年)ごろを境にしてチョンマゲから角刈に変り、女子の未婿者はモモワレ、既婚者はイチョウガエシに結い、後頭部に巻くワッカテガラは大正の末ごろまであった。終戦後女子はパーマネントに代る。
履物の草鞋は、大正十年ごろまで使用し、これに代るにゴム靴が登場する。皮靴は高価故他所行のみに使用している。草鞋は長い間、田畑はもちろんのこと、長途旅行登山には常に用いている。草履には室内用と室外用と区別されている。足だか草履は葬式のときのみ用い、ツマゴ・スンベ・アグドモンコ・アグドゴンべ・みそふみ等の藁製品の外、こま下駄・下駄・はしぱ下駄・足駄・地下足袋が使用された。
雨具には、スゲ笠・編笠をかぶり、ミゴやヤツ草で作ったミノを使用し、雪降りのときには藁で編んだ藁帽子を被った。
物を背負うときは、ネコやマダケラを使用した。このマダケラをヤドゴケラとも称した。ヤドゴケラは、情愛のこもった相手が襟元に赤・緑・白・紫・黒等の色糸で美しい矢がすりの模様を織りこんでいた。早春の屋根ふきがえに手伝う嫁や娘が背中の矢がすりと、前身の手甲の縁を赤色でつゞり、左右の腰ぶりのさけ目の縫い込みが暗色の衣服に調和して一層その美しきをましていた。これがヤドゴケラと称するようになったものであろう。
中屋弘子氏は『東北地方の農民服飾』の「寛政二年(1790年)の北行日記」の中に「蓆を着て寝て侍る」、「畳をとて、身の上に置いて寝ねける」、「今夜寝るに草をあみたるものをきる」、「寝わけるに今夜も夜具なし、畳をきる。風すき間より吹き入りて寒し」、「寝るにも畳を一つ着るのみ寒くぞありける」、「今夜蓆もあらで丸寝にいね待る、寒し」と、述べている。
村方で用いた衣科と染色の一端を示すものに、オシラ様の着ている布片がある。オシラ様は毎年三月十六日オシラあそぴをして、新しい衣裳を着せられるから、その衣裳が村方の衣料の沿革や、染色の変革にも関連することになる。オシラ様の御神体である芯木の墨書に古いものは天正(1573-91年)・慶長(1596-1615年)年代のものを見かけるが、着ている衣裳は二百枚以上はなく、精々百数十枚止まりであった。そのうち布地質では麻布・マダ布・絹地(縦細 横太)・絹薄地・木綿手紡織・金巾(かなきん)・木綿機織等が見られるが、内綿布が大量を占めている。その綿布の染色模様は、木綿縞・手織木綿茶地・緑無地・藍無地・紫草染無地・手織木綿更紗・木綿友禅模様・赤根染模様であり、徳川中期以降に岩手県に移入された綿巾と、染色の沿革を立記している。けだし婦人の衣服に使用されたものゝ断片と解される。
本村の大沢部落の堰合茂富氏宅と元村の太野秀吉氏宅にオシラ様が保存されている。
第十七節 言語
第十八節 説話
一 岩鷲山
往昔草昧の代、岩手山付近に人民の棲む者なかった時代、すでに八戸地方は開拓せられておった。ある年八戸地方に一羽の鷲現われ苗代を荒したので人民は大いに迷惑した。偶々(たまたま)仙台より一人の乞食が来たので、それに頼んで苗代の番をさせた。然るにもかかわらず鷲はなお盛んに苗代を荒し剰え四方の小児を浚(さら)ったので、乞食は大いに驚き藁はばきを結んで鷲を追いかけた。鷲は一気に遠くへは飛ばずあやうく捕えられんとしては飛び、捕えられんとしては飛びそのうちに遂に岩手山まで追いかけて来た。鷲は山腹の一巨岩にとどまるよと見るや忽ち変じて神の姿と化し乞食に向って言うよう「余鷲にあらず実はこの山の神霊なり、この山の開かれんことを望み汝をここまで誘い来れるなり。希くはこの山を開き祭祀せよ。汝にノギノ王子という名を与えん」とて小児と共に掻き消す如く姿を消し失せた。
ノギノ王子これより八戸に帰ったところ、前に荒されたと見えた苗代は神霊の力にて実は何等の異状もなく、苗が充分に成長していた。ノギノ王子事の由を詳かに里人に伝え里人と共に力を合せて遂に路を拓いて神霊を祝ったという。
崇敬登山者の御本社にて唱うる旧来の祈祷詞は「南無岩手大権現シソノゴウ御峯は三十六童子御宮本社は三社の権現田村明神ノギノ王子一時に御本尊ワラハバキの一時礼拝」にてすなわち能気王子藁はばきを作って奉納する風習今なお残っている。因に能気の王子は征夷将軍田村麻呂が東夷征伐に際し、仙台に生れたる将軍の落胤であると云い伝えられる。
二 岩手山と姫神山
岩手山は、昔この地方の主宰者であった。そして姫神山はその妻であった。けれども彼女の容貌があまり美しくなかったので、岩手山は同棲を嫌がり、遂にお前は俺の目のとどかない所にいけといって、彼女を追い出すことになった。そしてその送り役にはオクリセンという家来に申付け、もし首尾能く使命を果さないときは、お前の首はないものと心得よとの厳命をした。姫は泣く泣くオクリセンを伴って出ていったが、翌朝、岩手山が目を覚して東の方を見るとこれ如何に姫神山は悠然と眼前に聳えているので、非常に怒って、口から盛んに火を噴いたために、谷は鳴り渡り、山は震いどよめいて凄惨を極めた。岩手山と姫神山の間にある送瀬山(おくりせん)の頭が欠けてないのは、その岩手山が憤怒の余り、彼の首を落したためであり、その首をば自分の傍においたのが、今右裾に見える岩手山の瘤であるし、また送瀬山の近くに五百森と呼ばれる青草で蔽われた多くの丘のあるのは姫が後の形見にと手に持った巻子(えそ)を散らしたものだといい、赤い小石の多い赤川は、やはり記念に姫がお歯黒を流した跡だということである。
三 山の夫婦
雫石郷の南にあたって男助山(おすけ)と女助山(めすけ)という二つの山を挟んで対立している。昔この二つの山は夫婦であった。また岩手山と姫神山も昔は夫婦であったが、岩手山は姫神山を醜いといって嫌って離縁をし早池峯を妻としたので三山は三角恋愛で仲が悪かった。一方が晴れると、一方が曇って顔をかくしたのである。岩手山は姫神を遠くへ行けといって離縁をしたはずだが、姫神山は遠くへ行き難く、北上川を挟んで直き傍にいた。岩手山は赤くなって怒って火をはいた。姫神は名残りを惜んで形見の臍(へそ)を蒔き散らしたが、それは今の五百森だという。
四 鬼古里
昔、わが東北の地は山河到る所に多く、随所に夷族が穴居して互いに掠奪闘争をし、達谷窟には高丸、すなわち悪路王が暴威を振い北には岩手山麓に大武丸が頑張り、相呼応して奥羽征討将軍田村麻呂を挟撃したので、さすが鬼神のような将軍も度々敗戦の憂目を見たのであった。野戦数年辛じて悪路王兄弟を誅戦したのであったが大武丸は多くの部下がおり、勢い甚だ盛んなので、さすがの将軍も生檎にされようとしたが、かろうじて免れ米内の名乗坂の陰に隠れたこともあった程である。大武丸は岩手郡を根拠として遠く紫波、稗貫、下閉伊地方までも土民の親分を配置し、各子分を付属させて掠奪をしていたが、身体は偉大、頭髪は赫土のようで、顔面極めて醜く性慓悼(ひょうかん)、臂(ひ)力七八人力に拮抗し、山木を矯めず削りもしない強弩を引き、戦術はまた頗る老巧で大酒を好み、婦女を近く侍らせ、あたかも大江山の酒呑童子のようであった。姥屋敷の南方の長者館は大武丸の猛威を振った居館の跡で、ここがすなわち鬼古畳である。
西山の西根に篠崎八郎という土豪がおった。将軍の東道をし、各所に転戦したので、大武丸も鬼古里にとどまることが出来ず、岩手山の九合目の鬼ガ城にたてこもり、縄の梯子を用いて上下し、坑内を居所と定めた。密かにこれを捕えようとしたとこそ彼は坑外に逃れ出で、かねてから知っていた雫石御神(おみ)坂を走り下り、配下の良民を掠め、盗人森より彼の旧館の辺を通り、火燧山の北側を下り、安倍館の方向さして逃げ走った。将軍の部下が待ち構えていた耳取川原に大武丸が逃げて来たので、難なく捕え首を討ちとり、ここに平安を告げたのであった。
当時の習に従い、耳のみせ切り取り、これを塩漬とし、悪路王兄弟の分と共に京都へ送って復命をした。
五 参郷の森
篠木と大釜の境にある小山で、前九年の役に安倍貞任が厨川柵にほろぼされると、貞任の女がこの森によったのである。折からその身臨月であったが、やがてこの地で出産した処から産後の森というようになった。森の中からは蝦夷の土器を発見することがあったという。
六 北上川(その一)
御堂観音は、平泉の中尊寺の末寺で、田村麻呂がエゾ征伐に来た時にここに建てたといわれ、旧御堂村はこの話にちなんでいる。
その後、源頼義が安倍頼時征伐の勅命を受け、ここにおいて両軍が戦を交えた。時はたまたま六月でカンカンと日が照り、よろい、かぶとを焼くがごとく、その上、数十日も雨が降らず、沢の水も殆どかれてしまった。源氏の軍はのどがかわき苦しんで、力を発揮することが出来ず戦は不利になっていた。『前太平記』の叙述に『将軍はるかに本国の方を伏し拝み観世音を至心に念じ、擁護の手をたれさせ給えと願って、しばらく礼拝恭敬あり、自ら弓筈(ゆはず)をもって岩をうがち給いしかば、真に大悲の感応にや、岩の角より冷水にわかに湧き出てとうとうとして初めて流る。古今希有の瑞験重り、この水の流れ、加美川に落ち入りたるほどに、このところを北加美川と名づけたり……」源氏の軍は、この清水を飲んで大いに息を吹き返し、安倍氏の軍を打ち破った。
療養の子八幡太郎義家はこれを多として、山頂に観音堂を改築し自分のもとどりの中に入れてあった黄金の観音小像を安置し、この寺を新通寺と名づけた。初め北加美川と呼ばれたこの川は、後に上川と呼び直されるようになり、北上というようになったというのである。
北上川(その二)
八幡太郎義家の納めたという仏像は金製で、重さ三〇グラム、長さは三・六センチという千手観音で、十一面観音の腹の中に納めてあった。ところがあるとき、四国の六部(巡礼)がこの小像を盗み出して姿をくらましてしまった。長く行方不明だったところ、南部三十二世利幹(としもと)公が、徳島藩蜂須賀家から夫人をめとったとき、その夫人がこし入れの時、観音堂から盗まれた千手観音を嫁入り道具の一つとして持参したというのである。百余年にして再び戻ったということは実に不思議なことである。
なお、この寺には、当時源氏の軍が炊事用に使ったという鉄の大釜が、木の箱にたいせつにしまわれている。
北上川と白ヒゲ水(その三)
寛元のころ大洪水があり、稗貫郡や花巻地方の平地一帯が海と化し、東は胡四王山のふもと、西は花巻城のからめ門のきわまで水に没したことがあったが、このときの洪水を白ヒゲ水と語り伝えられる。
そのころ早池峯山のふもとに川原坊という坊主が住んでいた。あるとき白い餅を焼いて食べていると、真白い髪をした山ウバが来て、それをじっと見ていたので、すっかり恐しくなってすくんでしまった。そのすきにその山ウバは、その餅をとって食べ、そばにあった酒を飲んで行ってしまった。それが毎晩続いたので、坊主は一計を安じて餅の形をした白い石を真赤に焼き、洒びんに油を入れておいた。山ウバはその日もいつもの通りやって来て、真赤に焼けた石を食い油を飲んだところ、たちまち口から火を吹き、苦しそうに空に飛び上がり消えてしまった。ところが、その後七日七晩大雨が続き、山は崩れて、その辺一帯が大洪水になった。またある大洪水の夜、大水の中を黒いものが流れて行くのが見えた。稲妻の光でその正体を見ると、なんとそれは大きな竜で、背には白ヒゲの老人と美しい娘が乗っていた。そこでこの洪水を白ヒゲ水という言い伝えがある。
北上川と白ヒゲ水(その四)
寛文のころ盛岡地方に洪水があり、中津川の三つの橋と夕顔瀬橋が流されたが、そのとき水上に白髪白ヒゲの老人が現われた。これより五十年後の享保四年夏にも、北上川と中津川があふれて三橋が流れ落ち、馬場丁・鷹匠小路は水の深さ五尺にも達し、舟で往き来ができたほどで、このときにもやはり白ヒゲの老人が水上に現われたという。
七 諸葛川
源義家が安倍貞任を征伐したときのこと、貞任は敗戦となり谷地館まで退却し、義家がよる攻め入ることを予知して、数多くの籾屑を集めて夕食時からこの川に投げ込み、水面が見えなくなるまで詰め込み後川を挟んで対陣し、盛んに交戦に努め、とてもかなわぬ気配を見せて逃げ去った。義家ここぞとばかり突込んだが、この用意に備えた川であるから深さも相当、義家らの兵士は何れも水中に身を投じ、遂に溺死する者数百に及んだという。この籾屑川は何時しか諸葛川と呼ぶ様になったという。
八 春子谷地
大昔、鞍掛森の南口に夫婦と娘一人の三人暮らしの炭焼きがいて何不足なく一人の愛娘を労りつゝ、最も睦しく職にいそしんでいた。光陰矢のごとく過ぎ去り娘の春は十八の春を迎えたが、その容姿実に美しく絵に見るような花の顔ばせ、月の眉、柳の腰に、立てば筍薬座れば牡丹、歩む姿は白合の花的美人で炭焼の家におかれぬ美しさであった。
夏の苛烈な炎暑も去り、月清く尾花が招く秋のこと、九月も暮れようとするある日、家の囲りにおるべきはずの春子の可愛い姿は見あたらない。何処をさがしても影も形も見えなかった。大声疾呼したけれども答えるものは麓の楢林の山彦のみであった。母親は狂気のようになって駈け巡り、疲れきって炉ばたにぐったりしていた。とかくする中、夕日も西山に傾くころ、何処からともなく春は帰って来て、つくねんと入口に立っていた。両親は驚き、見、喜んで何処に行って来たかを尋ねたが、ただうつむいて息を殺しているばかり、後は両親も強いて問わず、そのまゝにしておいた。
その後十日程経て、また春子の姿が見えなくなった。前のように心配したけれども、ただ噂のみをして夕方を待っていた。七ッ時というのに、春子は漸く帰って来たが、腰から下は濡れて見る影もない。母はその訳を尋ねたが、春子は口を開かず、言を発せず、肩から息をつくのみで、うなだれていたが、唯一言、逢の沢に行って来たと洩らしたのであった。その後は変ったこともなかったが、ある草木も眠る丑満時、春子はうなされて「吉さん、吉さん」と大声で叫んだ。両親は可笑しく、また怪しく思ったが、ねごとだと思い、余り気にも止めずにいた。その後、春子はねごとを屡々繰り返し、精神に異状をきたしたことに両親が気付き、また春子がしばしば家から抜け出す様になったから、母は無断で行くべからざることを諭す。されど憧れの吉さんは、毎日この逢の沢に来いと言うたとて、母の諭しも諌めもきかなかった。春子はその後、父母の寝息をうかがい、真夜中に脱け出て、しばしば逢の沢へ行き続けていた。
吉さんというのは、春子谷地の主で、何時のまにかこれと恋におちていたのであった。
岩手山に二、三回雪が降って、四方の山々は綿帽子を被り、家々では冬仕度に忙しかった。春子の家でも冬囲い、冬仕事の準備に日もなお足らずという忙しさ。ある日のこと、それはそれは怖しく空曇り真黒く、雪さえ交え疾風の大嵐、木をゆるがし木の葉を巻き上げるものすごい夜のことであった。春子の家では宵の口から戸張を締めて床についたのであった。この嵐の真夜中に春子は、この夜限り慈愛深い父母の膝下を離れて恋人の吉さんが誘うがままに永久にこの沼に入って行って主になった。どっとはれえ。
九 底なし沼(ごまうなぎ)
土沢の細谷地に底なし沼と称する沼がある。その辺りは、柳・さんなし・芦・がま等叢生して水面をおおい、また二十間程南に北方傾斜地の畑の西隅の小杉立には、狐穴数洞あって、白昼も狐が彷徨するという気味の悪い所があった。鮒はたくさんすんでいても、人気のない所、釣をしようとも一人ではいやな場所、盆には青年連が申合せて、山椒の皮をおしもんで、鮒や鯰などを捕える位のもので甚だ淋しい所であった。
ある年の盆に、一人の旅僧が瓢然と土沢に現れた。時に平蔵沢・土沢の青年等六・七人で盛んに山椒の木の皮を、日盛りの天日で乾していた。僧は一青年に向い何をするのかと問うた。青年答えて、この皮の粉と木灰とをまぜ、それを流せば、水中の雑魚はみな死ぬこれから盆の休日に雑魚捕りをするのだという。僧曰く、その雑魚とりを何処でするや。青年曰く、細谷地の沼でとると。僧曰く、何ものか生を欲せざる。一草一木みな生を遂げて子孫繁栄を願っている、況や動物においておや。生物を愛し、慈しみ、育み育て、決して之を苦しめたり、殺したりするものでないと言葉をつくして戒めた。
血気にはやる青年らは耳にも入れず、やかましき小言を並べるなまぐさ坊主。この土沢で餓死されては甚だ迷惑、この赤飯でも食べて腹をこしらえここから去って死ねといった。旅僧は止むなく退去、山椒の皮は乾燥し終っていた。
明日は地獄の釜の蓋もあくという七月十五日、空は朝からからりと晴れ一点の雲なき好天気、昨日の青年ら旅僧の言をきかずに底なし沼にかけつけ、山椒の皮と木灰とを上流からもみ流した。鮒・すずもろこ・果ては鯰・銀魚など背負いきれぬ程とれた。青年共これに力をえて粉のあらん限りもんだら、その辛味に堪えかねて大きさ五尺ほどの「ごまうなぎ」半身を現わして泥中を泳ぐ。青年らは力を合せ半時ほどもかかって漸くこれを陸に引上げた。喜び勇んで持ち帰り、平蔵沢の人々にも分配せんと料理にとりかかる。ところが人間の鮮血そっくりのものがとめどもなく流れ出るのにいささか面食いたるも勇をふるって切断したるに、これいかに臓腑中より昨日の赤飯色も変らず出たのには一同顔を見合せた。強いて元気を出し之を焼き、あるいは煮、舌鼓を打って食べたが、中には病気にかゝり永々苦悶せしもあり、あるいは養生叶わで死せるもあった。あの旅僧は人間ではなく古鰻で、今日殺されることを予感し、しばし人間の姿に替えて慈悲を説いたものであろう。
十 猿さ嫁こになった話
昔あったどさ。一番娘二番娘三番娘と三人の娘を持ったとゞ様があった。春になっても田に水がかからなかった。その父さまが困ってしまった。「誰でもえだす、田さ水こかげてけだら俺の娘一人けらよ。」といった。それをきいた山の猿は田に水をかけてやった。
とゞ様は大変喜んだが、翌日になって、猿との約束を思い出すと心配で心配でたまらなかった。飯も食わずに青くなって奥にねていると、一番娘が起しに来た「おどおど飯(みす)かねえが」といった。「かねえでぁ。」「なすてよ」「俺昨日(きな)猿さ娘けるて約束すただす心配(すんぺえ)で食(か)れねえでぁ。うな行ってけねえが」とおどがいった。一番娘はびっくりして「誰あな、猿さなど行ぐだずぁ」と、ぷんぷんふくれて行ってしまった。今度は二番娘が来た。「おどおど飯食(か)ねぇが」「食ねでぁ」と父は元気なくいった。「なすてかねぇ」「娘、娘。おれえ昨日(きな)猿さ娘けるて約束すただす心配で心配でかれねえであ。うなえつてけねぇが」とまた二番娘にたのんでみた。二番娘は顔色をかえて、「ほうえど、おどにかてぇ、だれぇ猿さなど嫁にえぐ人(ふとあ)あんだず」ぶんぶんふくれて行ってしまった。お父さまが死んだようになっていた所へ三番娘がきた「おどおど飯かねぇが」「おら食ねぇ」「なすて食ねぇであ、身体悪ぐなれば俺(おれえ)こどなだす食(く)てけろでぁ」「へなだす、俺昨日(きな)猿さ娘ける約束すて田さ水ふっぱってもらたども、あねも行(え)がねずす二番(ば)めもやんた、俺なじょにすたらえがど思(お)めば飯(みす)も何も喉(のど)通(と)らねぇでや」というと気立のやさしい末子は「お父(ど)おど姉達(あねえだ)行(え)がねぇくても俺行ぐだす苦さねぇで飯食(みすけ)でぁ」といったので、お父さまは喜んで飯をうんと食った。
猿は次の日娘を貰いに来た。末娘は猿について、だんたん山へ行った。ある谷の路を通ると、高い崖の上に一本の柿がうまそうな赤い実をならせていた。あまりうまそうなので、娘は欲しがって「あの柿食てぇな」「すたらは俺とって来てけら」と猿は木に登る。「この枝の実が」「もっと上」「この枝の実が」「もっと上」というので猿はだんだんに上へ登って木のてっぺんに来た。「この枝の実が」「もっと上」すると細い枝がぼっきり折れて猿は、落ちて死んでしまったとさ。
十一 三人の姉妹
昔々その昔、ある所に三人の姉妹と爺様と婆様と五人で暮らしてらどさ。ある冬の大雪の時、爺様と婆様が朝早く起きて火をたいていると、そこへ一匹の猿が「今朝はずんぶさびなす」といって入って来た。そして爺様に「今日俺は爺様のえずげだ仕事をなんでもすだす娘一人けでくねぇ」といった。爺様は「うん、え、え。」といって猿に仕事をいいつけて、「山さ薪とりにいってこ、そすたら娘けでやる」といった。
猿は大層喜んで、山へ行って木の上の枯枝をたくさんかいて汗を流し流し背おって来た。猿は早く娘を貰いたいと思って、「爺様早ぐけでくねぇ」といった。婆様は一番目娘の「へんこ」にお前を猿にくれてやるといったから行ってくれ。「へんこ」はだれが猿などにもらわれて行くものがあるかといって大変きかなくなった。今度は二番目の「まんこ」に、そんならばお前が猿にもらわれていってくれというと、だれが猿などにもらわれて行くやつがあるかといって悪態(あくでえ)をついた。そこで仕方なく三番目の「さんこ」に、お前が行ってくれと頼むと、「さんこ」は「行(え)ぐます」といって、荷物を持って出て行った。猿は非常に喜んで爺様と婆様の方に頭をベコベコさげて出て行った。
ある池の所までくると、そこに大きな枯木があって、それにきれいな藤の花がからまって咲いていた。「さんこ」はその花がほしいから取ってきてくれと頼むと、猿は木に上がって行って「この花が」という。「さんこ」は「うんにゃ、もっと上(うえ)かの方」という。「こごが」「うんにゃもっと上かの方」といってる中に猿は段々上の方に登って行った。
そのとき、上の方の枯枝がぽきっと折れて、猿はまっさかさまに落ちて死んでしまった。そして「さんこ」は無事に家に帰ったとさ。
十二 山山の屁(へっ)ぴりおんず
長老どんの林に行って、木をだんぎりだんぎりと伐っていた。長者が出て来て、誰だ、おらほの林で木を切るやつは、と省めた。「はい。私は山々の屁ぴりおんずでござんす。」それでは、「ここさ来て屁をひって見ろ。」「はい」といって爺は長者どんの庭前へ行って、尻をひったくって、「にしきさらさら、ごようのまつをもってまいれ、ぴっかっぽん」とならした。さてもこれは面白い屁である。もう一つ所望所望。「はい」「にしきさらさら五葉の松を持って参れ。ぴっかっぽん」これは目出度い屁である。「これゃこれゃ、酒を持ってこう。」座敷の縁側で爺はうまい酒を頂戴した。帰りにはお金を貰って、それを頭巾に入れて喜んで家に帰った。そして婆様と二人で酒を買ったり、肴を買ったりして酒盛をしていた。そこへ隣の慾たがり婆が来て、「こつで何すてるどえ」という。爺様は長者どんに行って屁をひって、お金を貰ってきたから、酒買って、こうして酒盛をしていたというと、それでは、「俺も爺に長老どんの林にいって木を切らしぇべ」といって帰った。隣の爺は長者どんの林に行って、だんぎりだんぎりと木を伐っていると長者どんは「誰だおらほの山さ来て木を伐るやつは」というから、ここだと思って「はい、はい。山々の屁ぴりおんずでごわんす」と答えた。「そんだらこごさ来て屁をひって見ろ。」「はい」といって爺は長者どんの庭前に行って馬こになり、尻をまくって、うんとえきばったが、どうしても屁が出なかった。赤くなってうんといきばると屁ではなく糞がびりびりと出た。長老どんは顔をそむけて、これは大変なことになった。若者達そんなに笑ってないで、早く、この爺を門の外さ引張り出せといった。若者達は四・五人で爺を門の外へ突き出して、茨をもってからんで顔だの、手だの、足だのを疵だらけにした。着物はぼろぼろに破れて、体からは血が流れた。爺はおいおいと泣きながら家に帰った。婆は遠くからそれを聞いて、あれあれ、おらほの爺は、長者どんからお金をたくさん貰って喜んであんな唄を歌って来た。「どれ出はって見べ」といって出て見ると、爺は真赤になって来たので、「あれやあんな赤い着物着て来た。」「こんたなぼろ着物焼いてしまえ」といって、炉にくべてしまった。
十三 上の爺と下の爺
上の爺と下の爺と二人で川に梁をかけた。上の爺はまだ夜の明けぬ中に行ってみると自分の梁には箱が入っており、下の爺の梁には雑魚がたくさん入っていた。そこで自分の梁の箱をば、下の爺の梁に投げ入れ、下の爺の梁の雑魚をば自分の「はきご」に入れて持ってきた。夜が明けてから、下の爺が行って見ると、自分の梁に箱が入ってあったから持って来て日向に干しておいた。いいかげんに乾いたから、その箱を割ると、中から「爺静かに割れ」といった。静かに割ると小犬が出た。それを大切に養っていた。その小犬が椀こで一杯食わせると一杯だけ、二杯食わせると二杯だけ、三杯食わせると三杯だけ、大きくおがっていった。ある日その犬が爺に、握飯をつけて、「爺なはその上(うえ)かさ乗はでごじぇ」といってすすめるのである。爺は乗ると、ぶんぐらぶんぐらと、走せて奥山に行った。そして彼方の鹿も此方さこう。此方の鹿もこっちさこうと呼ぶと、彼方の山の鹿も、此方の山の鹿も、みんなぶんぐらぶんぐらと駈けて来た。爺はそれを斧で一々叩き、犬につけて家に持って来、その晩爺の家では、鹿汁をして食っていると、上の婆がやって来た。「何してるどえ」といった。おらほの爺な犬と鹿狩りに行って、鹿をとって来て、鹿汁を食ってる所だがら入って鹿汁食ってごじぇと、上の婆はお笑止だども、「へでぁ入(へえ)って食がなあ」といって上がって食った。いい加減食ってから後、椀の汁を家の爺さ持って行って食わせべなあといった。いやいや、爺那さば、こっちからやるから、すぇずば食ってごじぇと言って、別に重箱に入れて婆にあずけた。すると婆は、それも馬舎の隅こき行って肉(みどこ)をみんな食ってから、その汁(すたずこ)に馬の糞を入れて爺那のもとに持って行った。そして、「爺那爺那、今おりぇ隣りさえったば鹿汁食ってらだす爺さ食(か)しぇべと思って貰って来たがら食ってごじぇ」といって出した。爺はこれは少し馬の糞臭(くす)ぇども、うまい、うまい、といってそれをみな食った。婆は隣りの爺は鹿を取って来るときおらほの爺は何もなねぇと爺にいった。
その次の日上の爺は、下の爺の所に行って、「今日はおれも鹿打にえきてぇだすお前達の犬貸して給れや」という。下の爺は、「あえます。つれでてくねぇ」といって貸してやった。上の爺は、犬がつけろと言わぬのに、握飯だの斧をつけ、乗されともいわぬのに、自分が乗って山に行った。犬はごせやいて、彼方の蜂もこっちさ来う。こっちの蜂もこっちさ来う、爺のきんたま刺してけろといった。すると彼方の蜂も此方の蜂も皆飛んで来て「じかほき、じかほき」と爺のきんたま刺しつけた。爺のきんたまはひどく腫れ上がった。爺は怒って犬を殺して土にほうり込んだ。そしてその上にこめの木を挿して家さ帰った。下の爺は、上の爺が貸した犬を返さぬので、不思議に思って取りに行くと、上の爺はうんうん唸って寝ていて犬も糞もあったもんでねぇ。「お前達(めいだず)の犬のために俺はこんなにきんたま蜂にさされてしまった。あんまりえらすぐねぇだすぶず殺して、土さ掘っ込んでこめの木の枝を挿しておいて来た。慾かったら行って兄でごじぇ」といった下の爺は山に行って見るとそのこめの木があったからその枝を家に持って来て、仏壇にあげて拝み、米なれざくざく、金なれざくざくといって拝んだところが銭や米がたくさん落ちた。
そのことを上の爺は聞いて、己(おら)家(ほ)さもその米の木を貸してくねぇといって来た。借りて行って仏様に上げて拝み、米なれざぁくざぁく金なれざぁくざぁくというのを間違って牛(べご)の糞べたくた、馬の糞べたくたといって枝をほろったら、午の糞だの馬の糞だのがたくさん落ちた。皆がけつな米の木だといって、その木を切り割って釜の口にくべてしまった。下の爺は貸した米の木をあまり返きぬので、取りに行くと糞が落ちたから火にくべてしまったという。ほんだらその灰でもよいからといって灰を枡に入れて持って来た。秋になって雁がギアグギアグと鳴いて屋根の上を飛んで行くから、下の爺は屋根に登ってその灰を「雁の眼さ灰入れ、雁の眼さ灰入れ」といって灰を撒くと雁の眼さ灰が入って、下に落ちたから、それを捕って雁汁にして食っていた。するとまた上の婆は火こけて給れでぁといって来て、「こちで何してるどえ」「雁汁食ってらだす入って食(あが)れ」というと、「へでぁお笑止だども入ってくがな」といって上がって食った。そして前のときのように椀に少し残して、それは爺那に持って行って食(か)せべと言ったので爺様にはこちからやるから、それは食ってごじぇといって重箱に入れて、持たせた。するとまた婆は馬舎に入って肉を食ってから汁に馬の糞を入れ爺にもって行った。下の家で雁汁食ってだがら爺なに食せべと思って貰って来た。さめないうちにあがってごじぇ。爺はこれは少々馬の糞くすぇどもうまう御座るといってみんな食ってしまった。それから己(おら)家(ほ)でも灰を貰って来て雁を捕って雁汁するべと、上の爺は下の爺から残りの灰を貰っていった。雁の飛ぶとき屋根に登り、雁はグエクグエクと鳴いて飛んで来た。爺は雁の眼さ灰入れというのを間違って爺郡の眼さ灰入れといった。すると爺なの眼さ灰が一杯入って屋根からごろごろ転げ落ちた。下には婆だの嫁だのがもみ打ち槌を持って待っていたが、ごろごろと落ちて来たのを雁と思って爺を槌で叩き殺してしまった。
十四 正直なお爺さん
昔あるところに、お爺さんとお婆さんがあった。その家は大変貧乏で、寒い時でも薪をたいてあたることが出来なかった。そこで爺さんは山へ薪を取りに行った。山へ行って腰から鉈をとって木を切っていると山の奥の方から「だれだ、俺の家の木を切る者は、」という声がするので、誰かと思って立っているとまた、「誰だ、俺の家の木を切る者は―」というので、お爺さんは俺だというと、「そんなら、ここに来い」というので、行くと何のため薪を取るかときかれた。そこでお爺さんは、正直に自分の家は貧乏で何とも仕方なく、ここに来てこのようなことになった。どうか切っただけの薪を下さいというと、薪はくれるが、別なものもくれるから一緒について来い。というので、ついて行った。すると籠を二つだして、重い方が慾しいか、軽い方を慾しいかというので、正直なお爺さんは軽い方の籠をもらって帰った。家に帰って籠をあけて見ると、立派な着物がたくさん入っておった。そこで正直なお爺さんとお婆さんは急に金持ちになった。ところがこれを聞いた心の悪いお爺さんは正直なお爺さんの真似をして山に薪を取りに行った。そして正直なお爺さんと同じように薪を取っていると、山の方で「誰だ、俺の家の薪を切る者は」という声がしたので「俺だ」というと、取った薪は全部やるし、その外に別なものもやるからついて来いというので、ついて行って見ると、やはり、二つの籠を出して、重い方がほしいか、軽い方がほしいか。心の悪いお爺さんは重い方の籠を持って帰った。家に帰って籠をあけて見ると、中から、馬の生首や犬の骨や猫の頭などたくさん入っておった。
十五 瓜子姫子
とし寄った爺と婆とあって、爺は山に行った。その留守中に婆は川さ行ったらば、川上から瓜子が一つ、ちんぼかんぼと流れて来た。それを拾って爺が山から帰ったら一緒に食(く)べなと思って、戸棚に入れてとっておいた。夕方爺が山から帰って来て、ああ喉がかわいた婆様水を一杯たもれというと、婆は爺様爺様水よりもええもの己拾っておいたから、それを二人して、食うべすといって、戸棚から瓜を出してきて庖丁で二つに割った。すると中から美しい「おなごぼっこ」が生まれた。瓜から生まれたので瓜子姫子と名をつけて爺婆は大事に育て上げた。
瓜子姫子はとしごろになると益々美しくなった。ある日瓜子姫子に留守をさせておいて爺婆は山へ九年子(ほどこ)を掘りに行った。爺婆は山に行くとき瓜子姫子に瓜子姫子、瓜子姫子、爺婆が留守中に誰が来ても戸を開けてはならないぞ。このごろ奥山から、おっかない山姥が出て来て子供を取って食うずがらなといってきかせた。あい、あい、そう言って瓜子姫子は戸をしっかり締切って、中で、きこばとん、きこばとんと機を織っていた。すると奥山から山姥が来て「瓜子姫子、ここの戸(とっこ)少し開げでけろ」といった。瓜子姫子はおら爺様や婆様に叱られるから開けられないといった。山姥は僅かでいいから此所を開けろと言った。
余りにもせめられるので、瓜子姫子は僅か爪のかかる分の隙を開けたら外の山姥はもう少し指の入るだけ開けないかと言った。瓜子姫子は言う通りにしたら、今度はどうせこうせ手の入るだけ開けろと言った。仕方がないから、いわれるままに開けると、山姥はいきなりがらりと戸を開けて家の中に躍り込んだ。そして瓜子姫子、瓜子姫子、小豆はないかといった。あるという。「そんなら早く出して鍋で煮ろ。」瓜子姫子は鍋を出して小豆を鍋に入れて煮ると、今度は「瓜子姫子庖丁と俎を出せ。」瓜子姫子はそれを持って来ると「お前はこの上にねろ。」瓜子姫子は仕方なく俎の上にねると、それを庖丁で切って小豆鍋に入れて、グツグツと煮て食べてしまった。そして瓜子姫子の骨をば根太の下に入れて、自分は瓜子姫子の顔の皮を顔に当てて、すっかり瓜子姫子に化けて機を織っていた。
爺と婆は山から家で瓜子姫子が待っているだろうと思って、ホドコをたくさん掘って来た。「今来たぞ、誰も来なかったか。」偽の瓜子姫子は、「はい、誰も来なかったます。」と言って中から出て来た。爺と婆はこんなにホドコをたくさん掘って来たから、これを川に持って行って洗って来うといったら、そのホドコを笊に入れて持って川に行った。大きいのを皆食べて小さいものばかり爺婆のところへ持ってきた。これはどうしたことかと思っていると、あとは川へ流してしまったという。爺婆はめごい瓜子姫子のことだから「よい、よい。」といった。すると瓜子姫子は「あ」忘れていた。さっき隣の家から小豆餅貰ったから食(く)べといって、瓜子姫子を煮た小豆鍋を出して爺婆に食わせた。爺婆は喜んでこれは瓜子姫子臭いが甘いといって、みんな食ってしまった。
ところが偽の瓜子姫子の顔に血がついているので、爺婆はどうしたのかお前の顔に血がついているから洗って来いというと、偽の瓜子姫子は湯を汲んで顔を「ぽろん、ぽろん」と洗うと、生皮がはげ取れ本当の山姥になった。そして爺婆にお前達は瓜子姫子の小豆汁を食った食ったという。爺婆は山姥に瓜子姫子が食われたことを知って、そこにあった木の尻や木割を持って追うたら山姥は山へ逃げて行った。爺婆は瓜子姫子がおらないので、それから淋しい日ばかり送るようになった。
十六 狐と犬
昔あるところに狐と犬がいて一緒に町に行った。町に行く途中「ぞっぱりくら」をした。狐が言うにはお前がどんなことをしても俺は絶対に負けないぞといった。すると犬がいうには、お前がそんなことをいっても、その通りになるものではない。だまっておれ。俺が勝って見せるから。そのうちに二人は町についた。町で用をたし途中二人は別れた。犬は帰る途中に大きな池があったので、その池の藪にかくれていると、狐が辺りをみながら帰って来た。藪の所までくると、犬が「わん」と吠えると、狐がびっくりして、池の中に入って死んでしまった。犬はそれ見ろ、どんなことをしても負けないといった狐が負けたではないか。今でも狐と犬の仲の悪いのはこの時からだとさ。
十七 牡丹餅を食った阿弥陀様
和尚様と小僧がある山寺に住んでいた。和尚様は大層けちん坊であった。何を檀家から貰っても、小僧には一向分けてやらない。あるときお寺で檀家から牡丹餅を貰った。小僧は食べたくて食べたくて仕方がなかった。その内に和尚様は檀家へ出かけた。小僧はその留守に、そっと牡丹餅を盗んで食い、残った餌を本堂の阿弥陀様の口の周りに一杯つけて、知らない振りをしていた。やがて和尚様が帰って来た。そして、牡丹餅を食べようと思って、急いで重箱の蓋をとって見ると、中には何にもはいっていなかった。「小僧、小僧うな牡丹餅食わねぇが」ときくと、「おら何も食わねぇ」という。「嘘つぐな。」「本当に食(か)ねぇます。すたども阿弥陀様食ったがも知れねぇ。」「なすてよ。」「阿弥陀様の口さ餡こつでらます。」小僧は牡丹餅を食った罪を仏様になすりつけた。和尚様は「本当にが」といって阿弥陀様の所へ行って見ると、小僧のいった通りに口の周りに一杯餡をつけすましていた。和尚様はそれを見ると、「けずな阿弥陀様だな。なすて餅盗んで食たべ」といきなり叩きつけると「くわん」と鳴った。和尚様はそれをきくと小僧に「なあ、小僧阿弥陀様食わねぇてらべぇ。」「すたらば、釜さ入れて煮て見てねぇすか、そしぇばきっと喋べら。」和尚様は阿弥陀様を釜の湯の中に入れた。すると阿弥陀様は、「くた、くた」と泡をふきだした。「俺言った通り食ったとへってらべぇすか。」「本当だなぁ。」と和尚様がいった。
十八 親棄て山
昔、年寄りを大嫌いな殿様があった。六十になると親棄て山へ棄てさせた。そのころ二人の兄弟があった。二人に六十になる父親があったので、どうしても山へ捨てて来なければならない。二人は仕方がないので、父親を輿に乗せて山へ捨てに行った。愈々山の上についたので、「爺様、爺様。へでゃ達者で居ろや。俺達ぁ爺様を家さおきてぇども、殿様の言うごどきがねえばねぇだすよ。悪ぐ思わねぇでけろ」と二人でいう。「兄、兄。何てもねぇでぁ、うなだ家さ行ぐ時、道迷わねぇよに、俺来た道々さ芥子の種蒔いて来たはだけぇ、その芥子たよりにして迷わねぇよに戻れでぁ」という。二人が山を下るとき、芥子の種は青く芽を出していたから、二人は山道を迷わず家に帰ることが出来た。
「兄、兄。親ずもな、ずんぷ有難でぇもんだな」と弟がいった。「うん、あんたに心配(すんぺえ)すてける親をすてるのいだみたな。連れで来べすよ」と相談し、父親を山から連れて戻った。そして座敷の下に穴蔵を作り、そこに隠しておいて、三度の飯を運んで養っていた。
十九 せっとこ
舅家(ど)では聟(むこ)と娘を招んだ。聟は初めて団子というものを食(く)って、ひどくうまかったので、とても忘れられなかった。自分ばかり一人先に帰って来ながら、団子という名前を忘れないようにして、早く家に帰って母親にこしらえて貰って食べようと思って、舅家を出ると、一生懸命に団子団子と口の中でいいながら帰って来た。自分の家が間近くなったとき、堰を跳ね越す拍子に「せっとこ」と声を出した。それから「せっとこ、せっとこ」といい続けながら家に帰った。家に帰ると、母親、母親。「せっとこ」を拵えてたもれやといった。どうも母親は「せっとこ」の意味をよく飲みこめなかった。二人は高声になり言い合った。母はとうとうかんしゃくを起して、木の尻を持って、息子の額を打った。息子はおいおい泣いていたがしばらくすると、額に大きな瘤が出来た。母はそれを見て「それぁ汝(うな)余り解らねぇごどぬがすだす、なずぎさ団子のような瘤出はた」というと、そのとき息子は、やっと最初の団子を思い出して、その団子を拵えてもらった。
二十 剃刀
ある山寺の和尚は何時も塩引を買って来て隠しておき、それを剃刀で少しずつ切っては独りで食っていた。小さな小僧が自分も食べて見たいと思っていたので、あるとき堪りかねて「和尚様す、それは何というものですか」と尋ねると、和尚は「これか、これは剃刀というものだ」と教えた。
ある日檀家の用で小僧は和尚に連れられて行くと大きな橋にさしかかった。小僧はその橋を渡りながら珍しいものだから下を見ると川に鱒がたくさん浮いて泳いでいた。小僧は先に立って行く和尚に「あれあれ和尚様す、橋の下に剃刀がたくさんいますよ」、すると和尚は「見たこと、開いたこと、しゃべるもんでねぇ」といって、ずんずんそこを通り過ぎてしまった。
それから余程行って、和尚は日が照って頭が熱くなったから、小僧頭巾をよこせという。小僧は、さっき和尚様は袂から頭巾を落したからありませんといった。どうして黙っていたと和尚が言うと、小僧は、何でも和尚様は見たこと、きいたこと、しゃべるもんでねぇと教えたから黙っておったという。すると和尚は落ちたものは拾って歩くものだと教えた。
暫く行くと和尚は暑くて堪えられないから、笠をよこせと小僧にいった。「はい」といって小僧は後から笠をやると、笠の中に馬の糞が一杯入ってあった。和尚は馬糞を頭からかぶって、しかめ面をし、ひどく怒った。小僧、何で笠の中にこんなものを入れておいたとどなると、小僧は、それでも和尚様は落ちたものは拾って歩くもんだと教えたから拾って入れておいたのだといった。
二十一 燗酒
ある山寺に小僧が二人おった。夜になると、和尚は小僧共に早く寝ろ、早く寝ろといって、先に寝せてから炉にかんかんと火をおこし、戸棚から酒を出して燗をつけ、それから炙子(あぶりこ)をかけて餅を並べて炙った。その餅がよい程に炙れると手にとって、「ふうふぱたぱた、ふうふぱたぱた」と口で吹いて手で叩いた。また酒の燗がつくと、とくとくと杯についで、先ず一口飲んで見てから「よい燗、よい燗」といった。
二人の小僧は毎晩寝床の中で、それを聞いていた。一人の小僧が餅が好きであったし、他の一人は酒がすきであった。ある夜二人はひそかに相談して、これから一人は「ふうふぱたぱた」と呼んで貰い、一人は「よい欄、よい爛」と呼んで貰うことに翌朝和尚様の居間に行って頼んだ。和尚はそれは何の事やら分らなかったが、とにかく「よしよし」と言っておいた。
その日も夜になると、和尚はいつものように炉に炭をつぎ、戸棚から餅を出して炙り、酒を出して燗をした。二人の小僧は今か今かと待っていたら、和尚は餅が炙れたとみえて、一つとっては「ふうふぱたぱた」と吹いた。そのとき餅好きの小僧は「はい、和尚様何御用」といって跳ねて起きて来た。和尚は今餅を食べようと思って口に持っていこうとしているところへ、今朝「ふうふぱたぱた」と呼んでくれといわれた小僧が、急にあらわれた。和尚はやむなく、今この餅が炙れたから、これを「うな」に食わせべと思ってといって、手にした餅をその小僧に与えた。その後間もなく、「よい燗、よい燗」と呼ぶので、酒好きの小僧はやにわに飛出して来て、「はい、和尚様何の御用」とかしこまった。和尚は仕方なく、「うな」にこの酒飲ませべと思ってなといった。
二十二 粟ぶくと米ぶく
昔ある所に、粟ぶくと米ぶくという二人の娘があった。姉の粟ぶくは先妻の子で気立てが優しく、妹の米ぶくは後妻の子で余り性質がよくなかった。ままあっぱは何時でも、先妻の子の栗ぶくを憎んでひどく当っていた。
秋になって栗が熟したので、後家は二人の姉妹を山へ栗拾いにやった。「二人して栗ふるに行って来いでぁ。粟ぶくは姉なだす、先に立って拾うべす。米ぶくは妹なだす後に立って拾えといって粟ぶくにはぶずがれはぎご自分の子の米ぶくには新しいはぎごを持たせて山へ出してやった。姉の粟福は一生懸命に拾っても、はぎこのけつへ穴があいているから少しも溜らないが妹の米福は姉の落していったのを後から拾うので、少しも難儀をせずに栗を拾った。姉はそれを知らずに一心になって拾っていた。そこへ風がどうと吹いて来て栗の実をほろき落とす。その栗がころころと転んで、穴の中へはいっていった。またどうと吹いてぼたぼたと落ちて、また穴の中へ転んで行った。それが不思議なので、二人の娘はその穴へ入って見ると、中に家が一軒あって、山姥は日向で蚤取りをしていた。「このわらしゃどよく来たなや、俺さ蚤取りすてけろでぁ」といった。粟福は栗拾いをいいつけられたことをいうと、栗なら俺の拾ったのを欲しい位やるからというので、二人は山姥の蚤取りを手伝った。粟福は熱心に蚤を取る。妹の米福はいやいやながら取る振りをしていた。山姥は蚤を取って貰ったので大変悦んで栗を二人にくれ、粟福のぶっがれはぎごを新しいのに入れて与えた。そしてなお御礼に宝物の入ったつゞらをくれるといった。軽い葛籠がよいか重いのがよいか、どちらなり好み次第と言うので米福は欲を出して「俺には米福なだす重い葛籠けてくねぇ」といって重い方を貰った。粟福は「おら粟福なだす軽い方でもえます。」といって軽い方のつゞらを貰った。山姥は決して見るなと堅く言って聞かせた。
粟福は軽いのでちょこちょこ歩いて来たが、米福の方は重いので汗をたらしてうんうん唸って来た。途中で粟福につゞらを開いて中を見ようといった。けれども粟福は山姥のいった通り、家に帰ってから見るといって開けなかった。米福はそうすると、中に何がはいっているか見たくて耐らず、とうとう、つゞらを下ろして蓋を取った。そうすると中には牛の糞だの、骨からだの、しゃれこうべだの馬の骨だの、汚いものばかり入っていたので、さんざん怒って皆ぶんなげて帰ってきた。粟福のつゞらも汚いものが入っているから明けて見ろと言ったが、粟福はそれを聞かずにそのまま持って、帰って、こっそり夜になってから出して見ると、美しい帯だの、きれいな着物だのがたくさんあったので、そっとそれを隠しておいた。
秋祭りがきた。後家あっぱは、自分の娘の米福によい衣裳を着せて、二人で祭りを見に出かけた。粟福にはいど七くびり(麻糸七締め)、きすね(玄米)七臼、水を七さげ(十四桶)「この位の仕事をしておげでぁ」といいつけて出て行った。粟福も祭り見に行きたいのだが、あまり仕事が多いので悲しみながら働いていると村の友達が「粟福、お祭り見にあべでぁ」といって来た。こんなに仕事があって行かれないというと、「そんだら、俺もすける」という。そこへ後からも村の娘達が来て皆で手伝ったので、すぐにその仕事は終って一緒に皆と出かけることになった。
粟福は美しい着物を出して来た。それが余り美しいので、皆がたまげた。妹の米福は遠くから姉の姿を見て、母に粟福も来ているといったが、母はあれ程仕事をいいつけておいたから来るはずはないし、あんな綺麗な着物もないはずだから、よその娘に違いないといって本当にしなかった。粟福の方でも早く帰ってその美しい着物をたたんで取っておいて、元の悪い姿になって働いていたので、母は帰ってみて、米福にそらこの通り家にいるではないかといった。そこへ長者殿から粟福を稼に欲しいといって来た。継母は自分の娘の方を貰って欲しいので、米福は仕事も出来るし、「てんど」も良く美しくて髪を梳くにも「すわり、すわり」というが、粟福の方は厩の陰で、「ぐわりみり、ぐわりみり」とやるばがりと働くだけだと悪くいったが、それでもいいから粟福を貰いたいと長者殿はせめたてる。粟福には嫁にやるにしても何もくれてやれないと継母がいうと「おら何も貰わなくてもえます」といって、粟福は肌を洗って段段化粧したら、美しい好い娘になった。そうして山姥に貰った着物を出して着、長者殿から送って来た手箱、針箱、長持を持って美しく飾った馬に乗って嫁入りをした。
二十三 物を食わぬ女房
ある男が山に木伐りに行って、仲間の者共と俺は物を食わない女房を欲しいと話をした。すると、四、五日たってから、一人の見知らぬ女が男の家を訪れて来て、お前様は物を食わない女房を欲しいそうだが、俺は物を食わないから女房にして下さいといった。男は喜んでその女を女房にしておくと、なるほど物を食わない。男は夜昼一人で飯食うのも変なので、どうだ、お前も少し飯を食ってみないか、あんまり食わないでいては身体に障るべといっても「うんにぇ私は少すもくたぐねぇます。」といって食わなかった。
けれども、その女房がきてから、目に見えて米櫃の米が減るし、味噌桶には味噌がなくなった。はてなと不思議に思ってある日男は町に行くふりをして家を出、女房が裏に行っている間に雨戸から入って、まげに上がってかくれて見ていた。それとも知らぬ女は裏から出ると白米片馬をざんざんと担いで来て「はんぞう」にざわりとあけ、ざくざくととぎ大鍋に入れて炉にかけて「どがどが」火を燃した。それからまた味噌をひとたなき出して来て摺鉢に入れてがらがらと摺ってお汁をこしらえ、飯が焚けると「ひやげ」を出して来て、それに飯をもってトントンと打ち抜いて大きな握飯を拵え、それをずらりと大莚に並べた。汁はひやげに入れて冷やした。髪をほどくと女房の頭には大きな口があんぐりと開いていた。その口に莚から握飯を一つずつ手玉にとってドンドン投入れ、汁を「ひやげ」でざわりと注ぎ込んで、とうとう数多い握飯も汁も皆食べてしまった。終ると髪をば元通りに結んで、以前の女房になって、その辺を片付けて、また裏の方へ出て行った。
男はその隙にまげから下りて、西口からそっと出て、遠廻りして草鞋に泥などをつけて野に行って来たふりをして家に入った。翌朝女房に向って訳があって、お前に暇をやるから出て行けというと、女房はそれでは今まで働いた代りに何をくれるかというから、そこにある一駄入れの大桶をやるから出て行けという。女房はその大桶を横にして見ておったが、あれあれあんな虫こがいるのでとっておくれという。男は桶の中をまがって見ると、その拍子に女房は男の足をさらって桶に入れて、ちょいと担いでどんどん山に走って行った。
男はこれは大変なことになったと、「わなわな」ふるえて居ると女は山にかけ上がりながら、よい酒の肴を持って来たから出て来うと叫んで、柴立の中をがらがらと分けて行く。山の奥の方では「ほう」という声がある。男は桶の縁ががらがらと当るのに気がつき「ひょい」と木の枝に手をかけて桶から跳ね上がった。山女はこのことに気が付かず、がらがらと山を登って行って、よい酒の肴を持って来たといって桶を肩から下して見ると男が中にいないので、さては逃げられたと叫んで一緒にどんどん下りて来た。
男は木の枝のお陰で、桶から抜け出して山を走り下ったが、たちまち後からその者共が追いかけてくるので仕方なく菖蒲と蓬の生えている草むらの中に匿れた。山女らはこの草の中に男はいるけれども今日は此の蓬・菖蒲の中に手を入れると腕が腐れるから仕方がないと言って山奥に引返して行った。男はやっと草むらから出て、菖蒲と蓬とをたくさん持って頭からかぶり、腰に結び着けてきたので何事もなく家に帰った。家の屋根や入口にもその草を挿しておいた。その日は五月五日の節句の日であった。
二十四 馬鳥
昔は子供が十二・三になれば、山に馬を見つけるに行かなければならなかった。
ある家にかわいらしい十二歳ばかりの子供があった。その家の母はまま母であった。この母がこの子供に「今日は馬を見つけるに行ってこい。見つけることが出来なかったら、家に帰って来ても入れないぞ」と恐ろしい権まくでいうと、つき出す様にして山にやった。子供はいやだ、いやだといって行かなければ叱られるので、仕方なしに山に行った。深く山に入って行っても、自分の家の馬は見つからない。どこまで行っても、よその家の馬ばかり。そこで子供は馬のたづなを振って「うまぁ、おう。うまぁ、おう」とひっきりなしによんで歩くうちに日がくれて、真暗くなってしまった。
子供は深山で道に迷い、家に帰ると、母に叱られる恐ろしさで泣き出した。泣きながら「うまぁ、おう。うまぁ、おう。」とよんでいるうちに、その子供は、馬の口もっこをかけたような鳥になってしまった。
今でも、この鳥が、「馬おおう、馬おおう。」と深山の奥で泣いている。
この鳥がたくさん来ると世の中が悪いと言い恐ろしがっている。
二十五 三人のほら博士
昔、南部の国に一人のほら博士があったずおな。日光参詣に行ぐべどすて出がげだずおな。黒沢尻まで行ったどごろ、一人(ふとり)の旅人が来たずおな。
南部「じぇ、うなどこさ行(え)ぐ」、て言(へ)たずおな。
秋田「すたらばうなよ。」
南部「まんず、うなよ」
秋田「おりゃ、日光見物さ行ぐ」
南部「そが、俺も、いま、日光見物さ行ぐきなって出がげで来たどごだ」
秋田「へでぇ、一緒に行ぐべ」
南部「時に、うなどごの何とゆもんだ」
秋田「うにゃ、俺知らねえてが。秋田のほら博士では、おれの事だじえ。すたらは、うなどごの何でえ」
南部「南部のほら博士では俺のごどよ」
秋田「すたらば二人でほらふぎながら行ぐべすよ」また、少し行ぐど、今度は仙台の側道から一人の旅人が来た。
仙台「いや、お早よう。とぎに、うなだ二人でどごさえぐ」
秋田「おら二人は日光見物によ」
仙台「じゃ俺もそうだ。ときに、お前達(みぇだずぁ)どごだ」
南部「おら南部と秋田だ」
秋田「うなどごの何というものだ」
仙台「いや、仙台(しぇんでえ)のほら博士でば俺のごどだ」
南部「いや、おらも南部ど秋田のほら博士だ」
秋田「それやほら博士三人一度に日光参詣する事めったにあるもでねぇ。さあさ、えぐべぇぐべ」
南部「いや時に、この長(な)ぎぇ道中たんだむすむすど歩るったどごろで、さっぱりへんてつぁねぇ。何か一(ふと)ず面白(おもす)れほら話でも出すあて、勝ったやずを兄貴にすて背負(しょっ)た荷物を負げだやずにあずげ、向うの旅籠(はたご)賃も払わしぇるごどにすたらなじょだ」
秋田「うん、そりゃえがべ、さぁ出(だ)へ出へ南部」
南部「いや、おりゃ後(あど)がらだ」
仙台「すたらば、俺先ぎに出すべが」
南部「さぁ、さぁ、やれやれ」
仙台「俺あ先日(へどな)べごこを買って来たおな。さぁ飼(あずが)う飼うぜんぷ飼ったおな。何もかにも飼ったおな。とごろで仙台がら秋田南部さかげで寝てる位大(くりぇお)けくなったのよ」
秋田「うんにや、仙台。そんたにおけなべごあるってが」
仙台「あぁるてよ」
南部「どごにある」
仙台「おらほにある」
秋田「ほらでねぇが」
仙台「そよほらよ」
南部「仙台も相当(と)やった。俺二人なだおっつげねぇな」
秋田「今度(だ)南部だ」
南部「いやいやまだまだ、今度秋田だ」
秋田「すたら俺やる。岩手山がら鳥海山さまだがて田沢湖の水で顔(つら)洗らてる美人(えおなご)があるでぇ」
仙台「いや、それぁまたてぇすたおなごだな。化(ばげ)物でねぇがべが」
秋田「いや、それぁ当(あだ)りめぇの人(ふと)だ」
南部「またそれぁ本当が」
秋田「道理上ほらさ」
仙台「今度は秋田にやられだ。秋田一等賞(しょ)だな」
秋田「今度南部だ」
南部「いよいよ今度は俺の番だ。すたらばやるべ。南部は昔がら山国で、俺は僅か畠こすずげでいるどもな、その畠こさ豆蒔いだおな」
仙台「何(な)ぼばり蒔(めえ)だけぇ」
南部「種豆三百だん蒔だどごら、たった一本ほかおえねぇがった」
秋田「うにゃ南部。それで百姓間に合うてが」
南部「すたどもがすら、一本の豆の草をとるに七日もかがったじぇ」
仙台「うにゃ。たまげでかがったもんだなや。何たな豆だけえぁ」
南部「とでもとでも去年(ちょねん)の秋(あぎ)一枝おどすたどごら八百だんあるけでぁ」
秋田「いやいやこれはしぃんでんもんだなぁ。すたらばその豆からばなじよに仕末しゃ」
南部「すぇずば、太鼓(てぇご)の胴にすのよ」
仙台「何はりぁ」
南部「あだりめえの牛(べご)の皮よ」
秋田「そんたなおけな牛の皮あるてが」
南部「それぁ。へなだす仙台がら秋田と南部さかげで寝でる牛の皮よ」
仙台「いやいや南部。こんだはすっかりやられだ」
秋田「いやすたらば、そんたなおけな太鼓を誰(だりゃ)うずけぇな」
南部「そりぁ。へなだす、岩手山がら鳥海山さまだがて田沢湖で顔あらてる秋田の美人にうだへるのよ」
秋田「いやいや。こんどは南部にすっかりやられてすまた。南部はどすても兄貴だ」
そこで南部は兄貴となって、旅荷物を全部仙台と秋田に背負せてすまた。
いよいよ日光さつだ。参詣が終るど、
神主「三人のほら博士様方参詣した記念に何か一枚宛絵を描いて行ってくれませんか」
と註文があったとさ。そこで三人はめいめいに頭(あだま)をしぇねって描(けぇ)だ。終ってから較べで見るど、どれもこれもほでぇねぇものばり。ただ南部は丸こ一(ふと)つ。
そごで仙台は南部さ向って、
仙台「いや、南部しぇず何でぇ」
南部「ますて仙台、うなのは何でぇ」
仙台「けぇずが。見る通(と)り桜の満開さ大荒すの場面よ」
南部「えがにもその通りだ。その積(つむ)りで描ぇだべどもさっぱりその気持ぁ出はてねぇな。すぇずは、花びら散(つ)っても枝がちょきばてるそでぇねぇのが」
仙台「えがにもその通(と)りだ。そ描くのだったな」
南部「秋田、うな何描ぇだ」
秋田「この通り見でけろ。駿馬一足(いっそぐ)飛び」
南部「いかにもそだ。その積(つむ)りで描ぇだがもすれねぇども馬の一足飛びに手綱がたれてるてが」
秋田「いかにもそだ。そう描げばえがたな」
仙台と秋田は南部に欠点(あら)へわれだので、二人は南部にくちゃがる。
仙台「うな何描ぇだ。そんたな丸こただ一(ふと)つこが、おらのさくらべて見ろ、一体(いってえ)しぇずぁ何でぁ」
南部「けぇずぁ鍋のふたよ」
秋田「いがに鍋のふただて、そうゆうもんでねぇがべ。酒樽のかがみと間違うべぇでぁ」
南部「秋田でも仙台でも鍋のふたとっておぐずきなじょにすてる」
とへわれだ二人。いがにもなぁ。その通りだと南部のことばに感服すたどさ。
なお、第二編第二章第二節の大武丸と、同第三章第二節の安倍氏と本村に残る地名を参照されたい。
第十九節 歌人武田彩吉氏
作品抄
新雪の南部片富士の崇高さよわが佇(た)ちて見る心孤りに(歌碑)
夕されば美しき指かみながら窓の戸によりわれ待つといふ
朝がけて霰は降りけむ咲きほけし狐薊(あざみ)の葉にたまりをる
暮れなづむ須川の岳に凝る雲のさむざむとして北に動けり
雪に昏るる山越え来れば高枝と高枝がすれて音の寂しさ
午すぎて揺るる風見ゆ駅裏の炭骸崖の向日葵の花に
凍雲に寒き陽筋となりにけり羽後の境は雪降りて見ゆ
寄り添ひて枝の烏は動かざり流氷霧ふかき北上の川
没日遠き木山の谷の花わらび葉の青しもよ穂は老けにつつ
霙ふる木山の谷の花わらびこころ恋しくわれは見て佇つ
くれなゐを微かにのこす金線草(みづひき)の穂に没り際の陽はかがやけり
光堂垂木を落つる金箔の煌(きらら)ぐ今日を泌みて思へや
黒部峡谷見おろす直ち魂(たまき)消らふ白線の渓糸の如しも
啄木の恩人と称へられし平野喜平先生はわが恩師今は亡しはや
銭湯(ゆ)帰りとタオルぶらさげ肩聳やかしたる姿目に顕つ若き啄木
三山とふ岩手・早池峯・姫神のすがしく立てり和やかにこそ
湯の宿に枕ならべし畏さよ永久に思ひ出でて繁(しじ)に楽しからむを
祭文に操人形部落(むら)人(びと)と秋の夜長を悦に入り見し祖父の顔見ゆ
七夕の歌を父に書かせて笹竹につるせし短冊の想ひ出はるか
朝風に波うちなびく草の穂や羽後の境は虹あかりつつ
この朝明林檎の花の咲く果てや片富士の襞に心放つも
万丈の岩壁迫れる木野部の磯村戸毎に鳥賊は干されて
朝な朝な畳に光る老白髪われのか妻のかとも手にとりて愛し
そのかみに「おくの草桁」を名に負へる豪族をりしと語り継ぐはや
木の実汲み交はしつつ手製(てづくり)の楽器に踊り明かしけむ縄紋人あはれ
石桜図書館の軒下に蒲公英の花はほけて夏に入るはや
故郷の秋を偲べばまぼろしに機織る母見え黄なる灯(ひ)も見ゆ
暮れなづむ夕陽に佇てば駒ヶ岳の女岳の噴煙高く妖怪
今朝の朝げ書庫へ行かなと壁蔦の色濃き紅葉踏み惜しみつつ
北上の瀬鳴りさやかに聞えつつ天ゆく月は書庫の上に輝る
彩月洞小さき書庫を鎖ざしゐる鉄扉明るく若葉耀ふ
夕辣瀬逆波白くさやけさよ濁りは澄みたり北上川
武島繁太郎(本名武田彩吉)氏は、明治二十年三月十七日本村に生れる。同四十四年三月、岩手県師範学校本科卒業後、桜城、篠本寺田尋常小学校を経、大正八年篠木尋常高等小学校長。大正十二年岩手県立一関高等女学校教諭。沼宮内家政専修学校長、福岡実科高等女学校長、二戸郡教育部会長、福岡高等女学校長を歴任。昭和十九年三月、岩手県立杜陵中学校嘱託。同二十四年同高等学校講師。同二十六年四月、岩手高等学校、同中学校教諭。同四十二年四月以来、同校石桜図書館嘱託として六十有余年にわたり、本県教育界に貢献をした。昭和十七年八月高等官六等、正七位に叙せられ、同十九年一月、勲六等に叙せられ瑞宝章を受ける。永年教育に尽力された氏の人となりは温厚高潔、気品醇乎。子弟への愛情溢れ、余人ひとしく敬慕してやまず、その生涯にわたる情熱は厳しくまた美しい歌人としての道にもそそがれた。
それは明治三十七年四月、本村東林寺住職、晴山雪光師について和歌制作の導きを得て以来、師範学校在学中すでに同好の士と共に短歌活動に専念、やがて与謝野鉄幹主宰「明星」森鴎外指導の「スバル」に拠って制作に親しむ。大正十四年村野次郎主宰「香蘭」に入り同人となり、昭和十年北原白秋主宰「多摩」に参加して同人となり、白秋の高弟として岩手歌壇、中央歌壇に活躍をした。同二十八年木俣修主宰「形成」に参加し、同四十年白秋高弟拠点誌の松本千代二主宰「地平線」に参加して同人となる。
昭和二十二年より同四十六年に至る問、岩手県歌人クラブ会長に推され、「地平線」岩手歌会において後進を指導。同四十一年、日本歌人クラブ会員に推され、その間同二十七年十二月、第一歌集「花わらび」(四百五十首)を刊行し、同四十二年十月、第二歌集「おくの草桁」(四百五十首)を刊行した。同年五月二十一日には盛岡市愛宕山に、「武島繁太郎先生建設委員会」によって歌碑が建立された。氏の歌歴は岩手文壇において石川啄木と同世代として出発しその間日本近代文学研究の分野にも多大の業蹟を残し、とくに啄木研究史に大きく寄与し、また南部藩歌人山田吉風歌稿の発掘をはじめ、山田美妙の家系を明らかにし、それらの研究には後進に種々の道を拓き、岩手近代文学研究分野に幾多の後継者を生んでいる。明治・大正・昭和の三代にわたる岩手文壇の長老たる氏は昭和四十六年十月以降病臥され、十一月二十日八十四歳の天寿を全うされる。戒名繁翁歌仙清居士。菩提寺は大釜の東林寺である。